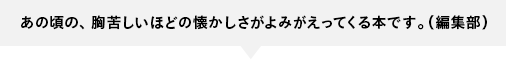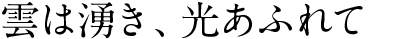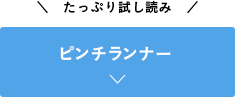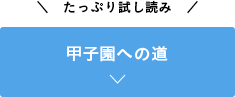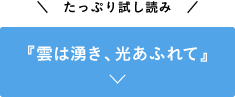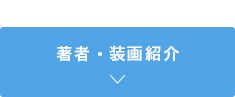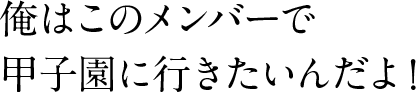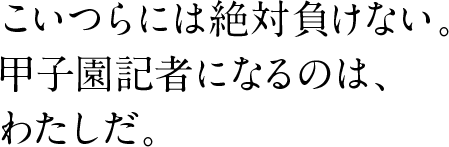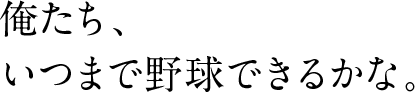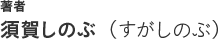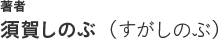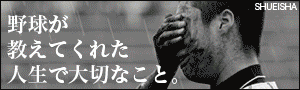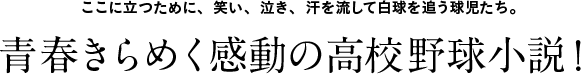
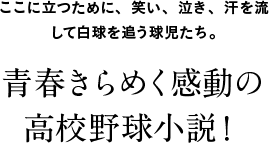

ピンチランナー
「おまえ、やる気あんのか」
おー、ドスきいてる。おっかないおっかない。
「あるよ。なかったら毎日足パンパンになるまで走ると思う?」
「だったらもっとちゃんとしてくれよ。おまえ、自分にどんだけでかい責任かかってるか、わかってんのか?」
あ、やばい。腹のあたりがムカムカする。抑えろ俺。大人になれ。
「おまえがそんなんじゃ、ベンチから外れた奴に申し訳ないだろ。ベンチ入りするっていうのは、全員の今までの練習に責任もつってことなんだぞ。なのに――」
「なんでおまえにそんなこと言われなきゃなんねーの」
益岡の声を遮って、勝手に口が動いた。ダメだ、腹の中が爆発したっぽい。
「そんなの、おまえが勝手に決めたことじゃん。俺は益岡専用のランナーなんだろ?おまえのためだけにいるんだろ?だったら、全員のぶんとか、おかしいじゃん」
「何言ってんだ。おまえ、試合に出るためにいるんだろ」
「でもそれって結局、益岡に利用されるだけみたいなもんだろ?」
俺が吐き捨てても、益岡は意味がわからないって顔をしたまんまだった。
「だいたいさあ、おかしいだろ。おまえが走れないから、後は頼む?代打で出たら必ず打つ?何それ。そのたった一打席のために、おまえよくベンチに入れるね。すっげえ頑張ってきて、フルで打って守れる奴らたくさんいるのにさ」
益岡の顔が、さっと青ざめる。ああ、いちおうそのへんの自覚はあるんだ?
「まあ、おまえは元々主将だったし、やっぱ要だったし、いてもいいと思うよ。けど俺はなんなの?おまえの代わりに走るためだけに、枠ひとつ潰すのってアリなの?吉川とかに悪くねえの?おまえはたしかにすごい奴だよ、でもそこまでやる権利あんのか」
益岡は、眉を寄せて、何度かまばたきをした。
「須藤、いやだったのか?」
「いやとかそういう話じゃねえよ!なんでわかんねえかな」
自分でもびっくりするぐらい荒っぽい声が出た。俺がびっくりしたぐらいだから、益岡のほうは目をまんまるにみひらいて固まっている。
「あのさ、故障したのはほんと気の毒だと思うよ。でも、なったもんはしょうがないだろ。ヘタしたら歩けなくなるかもまで言われたんだろ? なのになんでそんな必死に、しがみつくわけ。一試合に一打席出ることが、なんでそんなに大事なの? それで一点入ったからって、それが何?」
大きかった益岡の目が、だんだん細くなっていく。
性格そのままの、まっすぐあがった太い眉の間に、深い深い皺ができる。
「……本気で言ってんのか」
「本気だよ。そこまでして勝たなきゃなんねえもんなの?それより皆で頑張ったとか、そういうほうが大事なんじゃねえの?」
底光りするような目に気圧されそうになって、俺はますます声を張りあげた。
「前は完全に、おまえ一人のチームって感じだったよ。おまえがいるから甲子園行こうって盛り上がったんじゃん。全国行けば、おまえだってドラフト有利になるしさ。でも益岡、もう野球できないだろ? 悔しいけど、それが現実だろ。だったら何がなんでも甲子園に行く必要なんて、もうないじゃん。それより、もっと他に――」
「勝たなきゃ、意味がねえだろ!」
今度は益岡が声を荒らげて、遮った。
一瞬、心臓が縮こまった。
俺らもいつも喉かれるほど声出してるけど、こいつの声量はハンパない。益岡はなにもかもがデカいのだ。
なのに、なんで今こんなにちっこく見えるんだろう。
「三年間、ボロボロになるまでやってきたのは勝つためじゃねえのか。楽しく思い出作りするだけなら、ここまで練習する必要なんてないだろ。言ったはずだ、俺はこのメンバーで甲子園に行きたいんだよ!」
おー、ドスきいてる。おっかないおっかない。
「あるよ。なかったら毎日足パンパンになるまで走ると思う?」
「だったらもっとちゃんとしてくれよ。おまえ、自分にどんだけでかい責任かかってるか、わかってんのか?」
あ、やばい。腹のあたりがムカムカする。抑えろ俺。大人になれ。
「おまえがそんなんじゃ、ベンチから外れた奴に申し訳ないだろ。ベンチ入りするっていうのは、全員の今までの練習に責任もつってことなんだぞ。なのに――」
「なんでおまえにそんなこと言われなきゃなんねーの」
益岡の声を遮って、勝手に口が動いた。ダメだ、腹の中が爆発したっぽい。
「そんなの、おまえが勝手に決めたことじゃん。俺は益岡専用のランナーなんだろ?おまえのためだけにいるんだろ?だったら、全員のぶんとか、おかしいじゃん」
「何言ってんだ。おまえ、試合に出るためにいるんだろ」
「でもそれって結局、益岡に利用されるだけみたいなもんだろ?」
俺が吐き捨てても、益岡は意味がわからないって顔をしたまんまだった。
「だいたいさあ、おかしいだろ。おまえが走れないから、後は頼む?代打で出たら必ず打つ?何それ。そのたった一打席のために、おまえよくベンチに入れるね。すっげえ頑張ってきて、フルで打って守れる奴らたくさんいるのにさ」
益岡の顔が、さっと青ざめる。ああ、いちおうそのへんの自覚はあるんだ?
「まあ、おまえは元々主将だったし、やっぱ要だったし、いてもいいと思うよ。けど俺はなんなの?おまえの代わりに走るためだけに、枠ひとつ潰すのってアリなの?吉川とかに悪くねえの?おまえはたしかにすごい奴だよ、でもそこまでやる権利あんのか」
益岡は、眉を寄せて、何度かまばたきをした。
「須藤、いやだったのか?」
「いやとかそういう話じゃねえよ!なんでわかんねえかな」
自分でもびっくりするぐらい荒っぽい声が出た。俺がびっくりしたぐらいだから、益岡のほうは目をまんまるにみひらいて固まっている。
「あのさ、故障したのはほんと気の毒だと思うよ。でも、なったもんはしょうがないだろ。ヘタしたら歩けなくなるかもまで言われたんだろ? なのになんでそんな必死に、しがみつくわけ。一試合に一打席出ることが、なんでそんなに大事なの? それで一点入ったからって、それが何?」
大きかった益岡の目が、だんだん細くなっていく。
性格そのままの、まっすぐあがった太い眉の間に、深い深い皺ができる。
「……本気で言ってんのか」
「本気だよ。そこまでして勝たなきゃなんねえもんなの?それより皆で頑張ったとか、そういうほうが大事なんじゃねえの?」
底光りするような目に気圧されそうになって、俺はますます声を張りあげた。
「前は完全に、おまえ一人のチームって感じだったよ。おまえがいるから甲子園行こうって盛り上がったんじゃん。全国行けば、おまえだってドラフト有利になるしさ。でも益岡、もう野球できないだろ? 悔しいけど、それが現実だろ。だったら何がなんでも甲子園に行く必要なんて、もうないじゃん。それより、もっと他に――」
「勝たなきゃ、意味がねえだろ!」
今度は益岡が声を荒らげて、遮った。
一瞬、心臓が縮こまった。
俺らもいつも喉かれるほど声出してるけど、こいつの声量はハンパない。益岡はなにもかもがデカいのだ。
なのに、なんで今こんなにちっこく見えるんだろう。
「三年間、ボロボロになるまでやってきたのは勝つためじゃねえのか。楽しく思い出作りするだけなら、ここまで練習する必要なんてないだろ。言ったはずだ、俺はこのメンバーで甲子園に行きたいんだよ!」

甲子園への道
それからは、試合前にほとんどの人間が予想したであろう展開が待っていた。
月谷くんはつるべ打ちを喰らい、五回裏だけで四点を失った。そして六回に二点、七回に一点追加された時点で、コールドゲーム成立。7対0で東明勝利。
東明の木暮くんは、被安打2、奪三振11、四死球ゼロという完璧なピッチングだった。三ツ木の選手たちは、五回以降はまったく安打を打てなかったことになる。
それでも三ツ木の選手たちは、なんだか楽しそうだった。ベンチでは皆が声を張り上げ、最後まで元気に走り、バットを振り続けた。終わった後、ユニフォームは泥だらけだったけれど、泣いている選手はひとりも いなかった。みな笑顔で東明の選手と握手をし、気がつけば観客でいっぱいになっていた応援席に「ありがとうござっしたっ!」とお礼を述べていた。
王者相手に健闘した選手たちに、応援席だけではなく、バックネット裏や一塁側からも拍手がわき起こる。
不思議なものだ。誉れはまちがいなく勝者のものなのに、敗者に目が行く。自分が応援しているチームが負けたならともかく、そうでなくとも、どうしても心が向いてしまう。
おそらく、散るものを愛でる心理が強烈に働いてしまうこの光景こそが、高校野球というジャンルがもつ特殊性であり、最強の武器なんじゃないかと思う。
感傷に浸る間もなく、記者が一斉に移動する。誰もが一塁側のベンチ裏通路に向かう中、わたしは迷わず三塁側へと向かった。
大宮球場のベンチ裏通路は、薄暗い。テレビで見る甲子園のベンチ裏のあのスロープのような明るさはなく、ただただ、物悲しいのだ。夏の間、ここでは毎日、負けたチームの選手たちの泣き声でいっぱいになるんだろう。昨日は群馬の球場に行ったけれど、三年生が泣き崩れる姿は胸に詰まって、インタビューするわたしまで声が震えた。
だけど、歩いてくる三ツ木の選手は、やっぱり誰も泣いてない。あ、いや、主将マークをつけた子の目はちょっと赤い。やっぱり三年生は、平気じゃないよね。彼らは今日が、最後なんだ。
なのに、彼らを出迎える記者はわたしのほかにはいない。ちょっとびっくりだ。試合途中の記者席の雰囲気からは、三ツ木側にも殺到するんじゃないかと思ったけど、やっぱりみんな東明のほうに行ったんだ。五回からの展開で、前半の波乱はただのまぐれだったと判断されたのだろう。
後悔が頭をよぎる。たしかに、三ツ木なら東明の後だって話を聞ける。でも木暮くんたちには後から行っても話は聞けない。そりゃあ皆、まず東明に行くよね。
何やってるんだろう。きっとキャップに怒られる。
でもやっぱりわたしは――
「月谷くん!」
眼鏡をかけたひょろりとしたユニフォーム姿が現れて、とっさに呼びかけた。
右肩から大きなバッグをぶらさげた月谷くんは、びっくりしたように立ち止まって、わたしを見る。
マウンド上では不敵に見えた顔も、目を丸くしているとあどけない。彼も、木暮くんと同じ二年生だ。あと一年、熱い夏は残っている。
わたしは笑顔をつくり、足早に近づいた。
「蒼天新聞なんですが、お話聞かせていただいてもいいでしょうか?」
「えっと、俺ですか?」
眼鏡の奥の目を瞬かせ、月谷くんは困惑したようにあたりを見た。
「はい、月谷くんに。少しお時間いいでしょうか」
月谷くんはわたしの記者証をちらりと見下ろし、それから目を細めてわたしを見た。
「泉千納さん、ですか。蒼天には今年入社したばかりですか?」
え、と間抜けな声が出た。今年入ったなんてもちろん言ってないし、どこにも書いてない。
「そ、そうですけど……」
「なるほど。木暮のほうは人がいっぱいだし、新人じゃいい談話とれそうにないし、一発逆転を狙ってこっちに来てみたわけですね」
絶句したわたしを、月谷くんは笑顔で見ている。一見したところ、朴訥とした、人のいい笑顔だけど、それが急に怖く感じた。
月谷くんはつるべ打ちを喰らい、五回裏だけで四点を失った。そして六回に二点、七回に一点追加された時点で、コールドゲーム成立。7対0で東明勝利。
東明の木暮くんは、被安打2、奪三振11、四死球ゼロという完璧なピッチングだった。三ツ木の選手たちは、五回以降はまったく安打を打てなかったことになる。
それでも三ツ木の選手たちは、なんだか楽しそうだった。ベンチでは皆が声を張り上げ、最後まで元気に走り、バットを振り続けた。終わった後、ユニフォームは泥だらけだったけれど、泣いている選手はひとりも いなかった。みな笑顔で東明の選手と握手をし、気がつけば観客でいっぱいになっていた応援席に「ありがとうござっしたっ!」とお礼を述べていた。
王者相手に健闘した選手たちに、応援席だけではなく、バックネット裏や一塁側からも拍手がわき起こる。
不思議なものだ。誉れはまちがいなく勝者のものなのに、敗者に目が行く。自分が応援しているチームが負けたならともかく、そうでなくとも、どうしても心が向いてしまう。
おそらく、散るものを愛でる心理が強烈に働いてしまうこの光景こそが、高校野球というジャンルがもつ特殊性であり、最強の武器なんじゃないかと思う。
感傷に浸る間もなく、記者が一斉に移動する。誰もが一塁側のベンチ裏通路に向かう中、わたしは迷わず三塁側へと向かった。
大宮球場のベンチ裏通路は、薄暗い。テレビで見る甲子園のベンチ裏のあのスロープのような明るさはなく、ただただ、物悲しいのだ。夏の間、ここでは毎日、負けたチームの選手たちの泣き声でいっぱいになるんだろう。昨日は群馬の球場に行ったけれど、三年生が泣き崩れる姿は胸に詰まって、インタビューするわたしまで声が震えた。
だけど、歩いてくる三ツ木の選手は、やっぱり誰も泣いてない。あ、いや、主将マークをつけた子の目はちょっと赤い。やっぱり三年生は、平気じゃないよね。彼らは今日が、最後なんだ。
なのに、彼らを出迎える記者はわたしのほかにはいない。ちょっとびっくりだ。試合途中の記者席の雰囲気からは、三ツ木側にも殺到するんじゃないかと思ったけど、やっぱりみんな東明のほうに行ったんだ。五回からの展開で、前半の波乱はただのまぐれだったと判断されたのだろう。
後悔が頭をよぎる。たしかに、三ツ木なら東明の後だって話を聞ける。でも木暮くんたちには後から行っても話は聞けない。そりゃあ皆、まず東明に行くよね。
何やってるんだろう。きっとキャップに怒られる。
でもやっぱりわたしは――
「月谷くん!」
眼鏡をかけたひょろりとしたユニフォーム姿が現れて、とっさに呼びかけた。
右肩から大きなバッグをぶらさげた月谷くんは、びっくりしたように立ち止まって、わたしを見る。
マウンド上では不敵に見えた顔も、目を丸くしているとあどけない。彼も、木暮くんと同じ二年生だ。あと一年、熱い夏は残っている。
わたしは笑顔をつくり、足早に近づいた。
「蒼天新聞なんですが、お話聞かせていただいてもいいでしょうか?」
「えっと、俺ですか?」
眼鏡の奥の目を瞬かせ、月谷くんは困惑したようにあたりを見た。
「はい、月谷くんに。少しお時間いいでしょうか」
月谷くんはわたしの記者証をちらりと見下ろし、それから目を細めてわたしを見た。
「泉千納さん、ですか。蒼天には今年入社したばかりですか?」
え、と間抜けな声が出た。今年入ったなんてもちろん言ってないし、どこにも書いてない。
「そ、そうですけど……」
「なるほど。木暮のほうは人がいっぱいだし、新人じゃいい談話とれそうにないし、一発逆転を狙ってこっちに来てみたわけですね」
絶句したわたしを、月谷くんは笑顔で見ている。一見したところ、朴訥とした、人のいい笑顔だけど、それが急に怖く感じた。

『雲は湧き、光あふれて』
八月に入ってまもない日、甲子園にむけて練習に励む部員たちは、突然、監督の前に整列させられた。
いつもは色つやのいい丸々とした顔をどす黒く染め、監督は部員をひとりひとりゆっくり見回した。
「非常に残念なことを、伝えねばならない」
いかにも気がすすまないといった体で、彼は口を開いた。
「全国大会が、中止になった」
部員たちは、最初なんと言われたのかわからなかった。ただ、ぽかんと口を開け、監督を見つめることしかできなかった。
「上からのお達しだ。甲子園だけじゃない。年内は、秋の県大会も全て中止だ」
ここに至って彼らは、これがたちの悪い冗談などではない、まぎれもない現実なのだと知った。茫然としていた顔に、驚愕と怒り、絶望が広がる。
「国をあげて大事に立ち向かわねばならん今、舶来のスポーツなんぞをやらせるわけにはいかんそうだ。せっかく努力が実を結び、悲願の甲子園出場を果たしたというのに甚だ不本意だが……これもご時世ってやつだ。こらえてくれ」
そう言うと、監督は帽子を取り、深々と頭を下げた。
部員たちは絶句した。厳しい監督が自分たちに頭を下げるなど、考えられない光景だった。
監督はしばらくそのまま動かなかった。
動きを忘れ、木のように立ちつくす彼らを、真夏の太陽がじりじりと焦がしていく。静まりかえったグラウンドに、ただ蝉の声がうるさく鳴り響いていた。
やがて衝撃が去ると、激しい怒りが燎原の火のごとく広がった。
「なんだよそれ!なんでいまさら!」「信じられねえ……」「今になって中止にするなら、なんで県大会までやらせたんだよ」「こんなのひでえよ。ぬか喜びじゃねえか」
そこここで、憤激と嘆きの声があがった。泣いている者もいた。
「信じられない。こんなのって、ねえよ」
雄太のすぐ隣でも、林が号泣していた。
親友のその声も、地面に踞って泣く先輩の姿も、雄太にはまるで遠い出来事のように感じられた。これは、悪い夢だ。そうとしか思えなかった。
国の大事?わけがわからない。だったら甲子園だって、自分たちの一大事だ。
戦争なんて、国が勝手にはじめたことだ。そんなもののために、なぜこんな目に遭わなければならないのだろう。
自分はまだいい。どうせやめるつもりだったのだから。しかし林や他の者たちはそうではない。甲子園に出るために厳しい練習に耐え、ようやくその夢を手に入れたのに。
雄太はふと気になって、視線をさまよわせた。目当ての人物は、すぐに見つかった。
滝山は、険しい顔で地面を睨みつけていた。
他の選手のように泣いてはいなかったが、その横顔は明らかに烈しい怒りに張りつめている。彼にとっても、甲子園は大きなチャンスだったはずだ。こんなことで潰れるのは、やはり悔しいのだろう。
「皆、悔しいのはわかるが、それはどの学校も同じだ。気持ちを切り替えるしかない」
部員たちがひとしきり嘆くのを待ってから、湯浅主将が大きな声で言った。彼は事前に監督から話を聞いていたらしく、生徒の中では最も落ち着いていた。
「とにかくそういう事情なので、五年生は先日の県大会決勝が最後の公式戦ということになる。残念ではあるが、最後の試合を優勝で飾れたんだからな。それでよしとしよう」
日に灼けた顔に笑みを浮かべ、彼は励ますように仲間たちを見回した。
それでよしと思える人間などいるはずもなかったが、反論する声はあがらなかった。湯浅の人格のたまものだろう。
「今回のことに気落ちせず、新チームは俺たちのかわりに必ず来年に甲子園に行ってくれ。その時は、なにがあっても応援に駆けつける」
湯浅が、明るい声でそう締めくくった時だった。
「行けやしませんよ」
低い声でつぶやく者があった。
全ての視線が、声の主に集中する。
「来年も、公式戦はありませんよ。戦争が終わるまで、ずっと」
滝山は、鋭い目に反抗的な光を浮かべて、湯浅を見おろしていた。周囲の四年生は小声でたしなめていたが、滝山は睨むことをやめない。
「なのに、練習する意味あるんですか?野球部続ける意味、あるんですか」
「試合がないと決まったのは、今年だけだ。来年はまだわからん」
「あるわけないでしょう。去年より今年、今年より来年、どんどんひどくなっていく。今年ないなら来年、そしてその次だってあるわけがない」
吐き捨てる滝山を、湯浅は静かな表情で見つめた。
「試合がないなら、練習する意味はないのか?」
「当たり前です」
「よせ、滝山」
たまたま隣に立っていた雄太は、小声でたしなめた。しかし滝山は一顧だにせず続けた。
「投げる機会がないなら、俺もこのままやめます。続ける意味ないんで」
いつもは色つやのいい丸々とした顔をどす黒く染め、監督は部員をひとりひとりゆっくり見回した。
「非常に残念なことを、伝えねばならない」
いかにも気がすすまないといった体で、彼は口を開いた。
「全国大会が、中止になった」
部員たちは、最初なんと言われたのかわからなかった。ただ、ぽかんと口を開け、監督を見つめることしかできなかった。
「上からのお達しだ。甲子園だけじゃない。年内は、秋の県大会も全て中止だ」
ここに至って彼らは、これがたちの悪い冗談などではない、まぎれもない現実なのだと知った。茫然としていた顔に、驚愕と怒り、絶望が広がる。
「国をあげて大事に立ち向かわねばならん今、舶来のスポーツなんぞをやらせるわけにはいかんそうだ。せっかく努力が実を結び、悲願の甲子園出場を果たしたというのに甚だ不本意だが……これもご時世ってやつだ。こらえてくれ」
そう言うと、監督は帽子を取り、深々と頭を下げた。
部員たちは絶句した。厳しい監督が自分たちに頭を下げるなど、考えられない光景だった。
監督はしばらくそのまま動かなかった。
動きを忘れ、木のように立ちつくす彼らを、真夏の太陽がじりじりと焦がしていく。静まりかえったグラウンドに、ただ蝉の声がうるさく鳴り響いていた。
やがて衝撃が去ると、激しい怒りが燎原の火のごとく広がった。
「なんだよそれ!なんでいまさら!」「信じられねえ……」「今になって中止にするなら、なんで県大会までやらせたんだよ」「こんなのひでえよ。ぬか喜びじゃねえか」
そこここで、憤激と嘆きの声があがった。泣いている者もいた。
「信じられない。こんなのって、ねえよ」
雄太のすぐ隣でも、林が号泣していた。
親友のその声も、地面に踞って泣く先輩の姿も、雄太にはまるで遠い出来事のように感じられた。これは、悪い夢だ。そうとしか思えなかった。
国の大事?わけがわからない。だったら甲子園だって、自分たちの一大事だ。
戦争なんて、国が勝手にはじめたことだ。そんなもののために、なぜこんな目に遭わなければならないのだろう。
自分はまだいい。どうせやめるつもりだったのだから。しかし林や他の者たちはそうではない。甲子園に出るために厳しい練習に耐え、ようやくその夢を手に入れたのに。
雄太はふと気になって、視線をさまよわせた。目当ての人物は、すぐに見つかった。
滝山は、険しい顔で地面を睨みつけていた。
他の選手のように泣いてはいなかったが、その横顔は明らかに烈しい怒りに張りつめている。彼にとっても、甲子園は大きなチャンスだったはずだ。こんなことで潰れるのは、やはり悔しいのだろう。
「皆、悔しいのはわかるが、それはどの学校も同じだ。気持ちを切り替えるしかない」
部員たちがひとしきり嘆くのを待ってから、湯浅主将が大きな声で言った。彼は事前に監督から話を聞いていたらしく、生徒の中では最も落ち着いていた。
「とにかくそういう事情なので、五年生は先日の県大会決勝が最後の公式戦ということになる。残念ではあるが、最後の試合を優勝で飾れたんだからな。それでよしとしよう」
日に灼けた顔に笑みを浮かべ、彼は励ますように仲間たちを見回した。
それでよしと思える人間などいるはずもなかったが、反論する声はあがらなかった。湯浅の人格のたまものだろう。
「今回のことに気落ちせず、新チームは俺たちのかわりに必ず来年に甲子園に行ってくれ。その時は、なにがあっても応援に駆けつける」
湯浅が、明るい声でそう締めくくった時だった。
「行けやしませんよ」
低い声でつぶやく者があった。
全ての視線が、声の主に集中する。
「来年も、公式戦はありませんよ。戦争が終わるまで、ずっと」
滝山は、鋭い目に反抗的な光を浮かべて、湯浅を見おろしていた。周囲の四年生は小声でたしなめていたが、滝山は睨むことをやめない。
「なのに、練習する意味あるんですか?野球部続ける意味、あるんですか」
「試合がないと決まったのは、今年だけだ。来年はまだわからん」
「あるわけないでしょう。去年より今年、今年より来年、どんどんひどくなっていく。今年ないなら来年、そしてその次だってあるわけがない」
吐き捨てる滝山を、湯浅は静かな表情で見つめた。
「試合がないなら、練習する意味はないのか?」
「当たり前です」
「よせ、滝山」
たまたま隣に立っていた雄太は、小声でたしなめた。しかし滝山は一顧だにせず続けた。
「投げる機会がないなら、俺もこのままやめます。続ける意味ないんで」
「ピンチランナー」 雑誌Cobalt 2010年7月号
「甲子園への道」 書き下ろし
「『雲は湧き、光あふれて』」 雑誌Cobalt 2005年8月号
「甲子園への道」 書き下ろし
「『雲は湧き、光あふれて』」 雑誌Cobalt 2005年8月号
著者・装画紹介