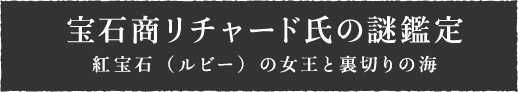

美貌の宝石商とともに過ごした正義の大学時代は、いよいよ終わりを告げようとしていた。卒業を間近に控えたある日、彼がリチャードに連れ出された先は――?
『スーツの話』
銀座の中央通りを七丁目から一丁目に向かうと、町の雰囲気の変化に驚く。ブルガリ、カルティエ、ルイ・ヴィトン、シャネル。そうそうたる高級ブランドの名前でしりとりができそうだ。クリスマス・シーズンどの店舗も電飾に趣向を凝らすので、そぞろ歩きが楽しい界隈だが、今は秋だ。この界隈で、俺に最もご縁のあるお店は、文房具を買いに行かされる老舗文具店一択だった。だったのだが。
「もう少しだけ腕をあげてください」
「はい」
「顎を少し引いて。ああ、いいですね」
「はあ。本当にこれで合ってますか」
「もちろんですよ。難しいかもしれませんが、どうぞリラックスしてくださいね」
通りを挟んだ、文具店のほぼお向かい。イギリス発祥のブランド紳士服店の二階に、どういうわけか俺はいた。バーカウンターと巨大な水槽まで存在する謎のジェントル空間の壁には、目立つ場所にしつけ糸がついたままの背広やパンツやチョッキの群れである。
オーダーメイドのための採寸をする場所だ。
何かの間違いじゃないだろうかという気分がまだ抜けない。ここは文具店じゃないのだろうか。一枚三十円のバニラ色の封筒を買いにくる場所ではないのか。あるいは季節を感じる絵入りの便箋とか、ペンとか。
「正義、緊張のしすぎです」
「……お前もだけど、中田さんも人が悪いよ」
バーカウンターにもたれたリチャードは、ひょっと肩をすくめて見せた。
今日は木曜日である。雑用を頼みたいとリチャードに呼び出され、エトランジェ前にやってきた俺は、緑のジャガーでこの店にやってきた。買い物に付き合わされるのだろうかと思っていると、運転席の男はいそいそと携帯端末をとりだし、俺のお父さんである中田さんからのビデオレターを見せてくれた。正義、卒業おめでとう、一緒にスーツを買いに行きたいけれどジャカルタだから、リチャードさんの力を借ります。オーダーメイドって最近はやってるらしいな、いいもの買うんだぞ、じゃあまたな。助手席で目をうるませる俺をリチャードは静かに見守ってくれたが、店舗に踏み込むと涙も引っ込んだ。
俺とあまり年頃の変わらない、若い店員さんは、イギリスのスーツとイタリアのスーツの違いなどを軽やかに語りながらすいすいとメジャーで俺の体を測り、これでもかという数の生地を見せてくれた。裏地も選べます。ポケットはどうなさいますか。目がくらくらし始めると、後ろからスーツの申し子のような男が助言をくれる。逃げ場がない。俺は本当にここでスーツを作るのだ。裏地を青にした、チャコールグレーのスーツを選ぶと、リチャードはすかさずタンザナイトのカフスがよく映えそうだと言ってくれた。もちろん俺も同じことを考えていた。
採寸を終えたお兄さんが、メモを作りに店の奥へ消えた頃、俺は深くため息をついた。
「……最近こういうのばっかりだ」
もらってばかりだと俺が言うと、リチャードはくっくっと喉を鳴らして笑った。リチャードの微笑には二種類あって、声をあげて笑う時には食い下がると一言何かもらえることが多い。無言の微笑の時には、どこかで『己を省みよ』と言われている気がしてちょっと焦るけれど、俺はどちらも好きだ。
鏡の前に立つ俺の隣にやってきて、リチャードはにこりと笑った。
「常に体の方が服より先に大きくなるとは限りません。たまには少し大きな服を買って、体が成長するのを待ってみるのも一興では?」
「それは『よく寝て牛乳を飲めよ』ってニュアンスの話じゃないよな」
お返事は微笑みだった。不思議だ。俺のすぐ左となりにリチャードの顔があるのに、鏡の中の微笑みは正面から俺を見ている。ダブルボタンの細身のシルエットのスーツに身を包んだ姿は、とびっきり上等な宝石のように、どこから見ても完璧で、隣でしゃちこばっている自分の姿がますますおかしい。
「なあリチャード、何だかスーツって、ジュエリーの地金に似てる気がするよ」
「指輪やピアスの、基盤部分のことですか?」
俺は頷く。地金とはジュエリーに宝石を留める土台になる金属パーツのことだ。金地金やらプラチナ地金やら、店の中では素材の名前を頭につけて呼ぶことが多い。石のついたアクセサリーを商うエトランジェにおいては、決して主役にはならない部品だ。でもそれがなければ石を身に着けるのは困難だし、素材や耐久性、デザイン性など、こだわりの現れる部分でもある。生かすも殺すも土台次第ですえと、俺の知っている京都のジュエリーデザイナーさんなら言うだろう。
逆も然りかもしれない。
「気合入れなきゃな。スーツに負けない中田正義にならなきゃ申し訳ない」
「個人的な見解ですが、石と地金がそれぞれに張り合っているジュエリーほど、見ていてくたびれるものもありません。重視すべきはハーモニーです。最高級素材の卵とミルクを使ったからといって、最高のプリンが生まれるとは限らないのと同じことでは」
「あ……」
確かに、高級食材は主張の強い品物が多いなと俺が応じると、全くその通りだと美貌の男は頷いた。どうやら最近そういうスイーツに当たったらしい。忙しくてなかなか時間がとれないが、そのうちまたプリンを作って献上しよう。高級スイーツ食べ放題の財布の持ち主であるにも関わらず、作れば作るだけいつまでも新鮮に喜んでくれるリチャードには、やっぱり人を喜ばせる才能があると思う。ありがたい存在だ。
「スーツもジュエリーも、持ち主のために存在する品物です。主導権のありかは最初から明確でしょう。戦うのではなく、心地よく乗りこなしなさい。そのためのオーダーメイドです」
「お前が今着てるその服も、『乗りこなしてる』感じ?」
「無論です。どこからが私なのか、もうわからないほどですよ」
そう言ってリチャードはさらりと自分のスーツを撫でた。いつか俺もそんなことを言ってみたい。俺たちは鏡ごしではなく直接ちらりと視線を交わした。店員のお兄さんが戻ってくると、再び採寸の始まりである。いい感じにリラックスしてますねと褒められ、俺は何だか気恥ずかしくなった。
「正義くん、おつかれさま! わっ、そのスーツとっても似合ってるねえ」
「ありがとう谷本さん。あれ、その振袖の柄、ひょっとして」
「現代柄って言われたんだけど、うん、ちょっとね」
「ビスマスの結晶っぽいよ!」
「わかってくれた?」
だよねえという顔をする彼女は、いつもより少しだけぱっちりした瞳の下に、ダンディな皺を浮かべて見せた。おかっぱの頭はいつも通りだが、クリーム色の袴に、謎の幾何学模様のプリントされた黄緑色と紺色の振袖を合わせている。キュートな上に個性派だ。レンタルだというが、こんなに彼女らしい振袖が存在していたことに感動する。
俺はといえば、やたらと体にフィットする、二つボタンのイギリスのスーツである。ちょっと恥ずかしいが、大学生男子などという生き物は多かれ少なかれ俺と同じ生き物で、男友達の服装にはあまり頓着しない。アパレル業界に就職した一人だけが、中田の着てるのいいスーツだなと言ってくれた。
笠場大学の卒業式。だたっぴろい講堂に集うのはほんの一瞬で、卒業証書を手に入れたらもう、思い思いの友達を講堂近くのスペースで撮りまくる連写パーティの始まりだ。
待ち合わせしていた中央図書館近くのスペースに、谷本さんは走ってきてくれた。
「正義くん本当におめでとう。これから大変かもだけど、正義くんなら絶対大丈夫だよ」
「ありがとう。頑張るよ。自分がそんなに大した人間だとは思えないけど……」
「そんなことないよ。正義くんの凄さ、私ちゃんと知ってる」
谷本さんも卒業おめでとうと、俺がちょっとだけふざけて頭をさげると、彼女は嬉しそうにふふふと笑った。彼女は教採に合格し、晴れてこの四月から中学校の理科の先生だ。学部二年の時に、俺に語ってくれた夢をかなえたのだ。かっこいい。かなうことならば彼女の授業を受けて勉強したい、と言ったら笑われたけれど、今は彼女の動画通信用アドレスも知っているので、もしかしたら本当に一度くらいは授業を傍聴させてもらえるかもしれない。俺の所在地が日本ではなくなっても。
「谷本さん、赴任校は……」
「岡山県。ビカリアの化石の勝田層群で有名だよね。正義くんに比べれば近所だよ」
あと数日で、俺の所在地は日本からスリランカにうつる。宝石商の見習いだ。ラフな格好で動き回ることが多くなるだろうと言われているので、しばらくきっとフォーマルは着おさめだ。
しょうこー、という声が遠くから聞こえてくる。谷本さんの友達のようだ。彼女も手をふって応じている。
「正義くんあのね、私この大学で、正義くんに会えて、すごくラッキーだったと思う。本当にありがとう。おかげで大学がずっと楽しかった」
「……それ全部、俺の台詞だよ。でも俺は谷本さんには迷惑ばかりかけて」
「そんなこと言うなら私だってそうだよ。私、いろいろなチャンスをもらった気がする。本当にありがとう」
がんばるねと微笑む彼女は本当に可愛い。俺たちはどちらも岡山には土地勘がないが、どんなところであっても彼女はきっと持ち前の強さでばりばりと道を切り拓いてゆくのだろう。そして休日には化石を掘りに勝田層群に出かけたりするのだろう。
「……これからも、俺で役に立てることがあったら言ってほしいな。何でもするよ。変な奴は飛行機に乗ってぶっとばしにいく」
「私も正義くんをいじめる人がいたら、クラックハンマーを持ってやっつけに行くからね。期待してて。あ、亜紀が言ってたけど、私にはスナイパーライフルの方がいい?」
「ど、どうかな」
俺たちはそれからしばらく目立たないベンチで話して、いよいよという時間になった時、体にだけは気を付けてねと言って、彼女は手を差し出してくれた。俺も頷き、手を握り返す。彼女の手は小さいが、とても力強い。
「体にだけは気を付けて。石のご加護がありますように」
「ありがとう。谷本さんにも」
俺たちは深々と頭を下げ、せっかくだからとお互いの写真を撮りあい、ほどほどに距離を置いた二人の記念撮影もすませてから、別れた。盛大にハグして号泣している学生もあちこちにいるが、彼女も俺もそういうタイプではないし、これが今生の別れになるとも思わない。これからもきっと会えるだろう。
だが学生として顔を合わせるのは、これが最後だ。
握手の後、俺の天使は本物の天使よりも朗らかに、じゃあねえと手を振ってくれた。
その後、友達という友達を探して、今までありがとうと言いまくるツアーを完遂した俺は、最後に一通、テキストを送った。リチャードではない。中田さんとひろみだ。
『無事に大学を卒業できました。今までありがとうございました。これからもお世話になります』
挨拶というよりも、改めての決意表明のような連絡になった。
ぱりっとしたスーツは、確かにフィット感抜群だが、まだ完全に馴染んでいるようには思えない。当然だろう。この前仕上がったばかりなのだ。ここからがスタートだ。着込めば着込むほど、俺の形になってくれるというのなら、どんどん俺好みに着こなしてゆこう。
大切なのはハーモニーだという。
まだまだよそゆきとしか思えないスーツを、お気に入りの石を撫でるような気持ちでさらりと撫でながら、俺は青空と桜の花びらのコントラストを目に焼き付けた。
「もう少しだけ腕をあげてください」
「はい」
「顎を少し引いて。ああ、いいですね」
「はあ。本当にこれで合ってますか」
「もちろんですよ。難しいかもしれませんが、どうぞリラックスしてくださいね」
通りを挟んだ、文具店のほぼお向かい。イギリス発祥のブランド紳士服店の二階に、どういうわけか俺はいた。バーカウンターと巨大な水槽まで存在する謎のジェントル空間の壁には、目立つ場所にしつけ糸がついたままの背広やパンツやチョッキの群れである。
オーダーメイドのための採寸をする場所だ。
何かの間違いじゃないだろうかという気分がまだ抜けない。ここは文具店じゃないのだろうか。一枚三十円のバニラ色の封筒を買いにくる場所ではないのか。あるいは季節を感じる絵入りの便箋とか、ペンとか。
「正義、緊張のしすぎです」
「……お前もだけど、中田さんも人が悪いよ」
バーカウンターにもたれたリチャードは、ひょっと肩をすくめて見せた。
今日は木曜日である。雑用を頼みたいとリチャードに呼び出され、エトランジェ前にやってきた俺は、緑のジャガーでこの店にやってきた。買い物に付き合わされるのだろうかと思っていると、運転席の男はいそいそと携帯端末をとりだし、俺のお父さんである中田さんからのビデオレターを見せてくれた。正義、卒業おめでとう、一緒にスーツを買いに行きたいけれどジャカルタだから、リチャードさんの力を借ります。オーダーメイドって最近はやってるらしいな、いいもの買うんだぞ、じゃあまたな。助手席で目をうるませる俺をリチャードは静かに見守ってくれたが、店舗に踏み込むと涙も引っ込んだ。
俺とあまり年頃の変わらない、若い店員さんは、イギリスのスーツとイタリアのスーツの違いなどを軽やかに語りながらすいすいとメジャーで俺の体を測り、これでもかという数の生地を見せてくれた。裏地も選べます。ポケットはどうなさいますか。目がくらくらし始めると、後ろからスーツの申し子のような男が助言をくれる。逃げ場がない。俺は本当にここでスーツを作るのだ。裏地を青にした、チャコールグレーのスーツを選ぶと、リチャードはすかさずタンザナイトのカフスがよく映えそうだと言ってくれた。もちろん俺も同じことを考えていた。
採寸を終えたお兄さんが、メモを作りに店の奥へ消えた頃、俺は深くため息をついた。
「……最近こういうのばっかりだ」
もらってばかりだと俺が言うと、リチャードはくっくっと喉を鳴らして笑った。リチャードの微笑には二種類あって、声をあげて笑う時には食い下がると一言何かもらえることが多い。無言の微笑の時には、どこかで『己を省みよ』と言われている気がしてちょっと焦るけれど、俺はどちらも好きだ。
鏡の前に立つ俺の隣にやってきて、リチャードはにこりと笑った。
「常に体の方が服より先に大きくなるとは限りません。たまには少し大きな服を買って、体が成長するのを待ってみるのも一興では?」
「それは『よく寝て牛乳を飲めよ』ってニュアンスの話じゃないよな」
お返事は微笑みだった。不思議だ。俺のすぐ左となりにリチャードの顔があるのに、鏡の中の微笑みは正面から俺を見ている。ダブルボタンの細身のシルエットのスーツに身を包んだ姿は、とびっきり上等な宝石のように、どこから見ても完璧で、隣でしゃちこばっている自分の姿がますますおかしい。
「なあリチャード、何だかスーツって、ジュエリーの地金に似てる気がするよ」
「指輪やピアスの、基盤部分のことですか?」
俺は頷く。地金とはジュエリーに宝石を留める土台になる金属パーツのことだ。金地金やらプラチナ地金やら、店の中では素材の名前を頭につけて呼ぶことが多い。石のついたアクセサリーを商うエトランジェにおいては、決して主役にはならない部品だ。でもそれがなければ石を身に着けるのは困難だし、素材や耐久性、デザイン性など、こだわりの現れる部分でもある。生かすも殺すも土台次第ですえと、俺の知っている京都のジュエリーデザイナーさんなら言うだろう。
逆も然りかもしれない。
「気合入れなきゃな。スーツに負けない中田正義にならなきゃ申し訳ない」
「個人的な見解ですが、石と地金がそれぞれに張り合っているジュエリーほど、見ていてくたびれるものもありません。重視すべきはハーモニーです。最高級素材の卵とミルクを使ったからといって、最高のプリンが生まれるとは限らないのと同じことでは」
「あ……」
確かに、高級食材は主張の強い品物が多いなと俺が応じると、全くその通りだと美貌の男は頷いた。どうやら最近そういうスイーツに当たったらしい。忙しくてなかなか時間がとれないが、そのうちまたプリンを作って献上しよう。高級スイーツ食べ放題の財布の持ち主であるにも関わらず、作れば作るだけいつまでも新鮮に喜んでくれるリチャードには、やっぱり人を喜ばせる才能があると思う。ありがたい存在だ。
「スーツもジュエリーも、持ち主のために存在する品物です。主導権のありかは最初から明確でしょう。戦うのではなく、心地よく乗りこなしなさい。そのためのオーダーメイドです」
「お前が今着てるその服も、『乗りこなしてる』感じ?」
「無論です。どこからが私なのか、もうわからないほどですよ」
そう言ってリチャードはさらりと自分のスーツを撫でた。いつか俺もそんなことを言ってみたい。俺たちは鏡ごしではなく直接ちらりと視線を交わした。店員のお兄さんが戻ってくると、再び採寸の始まりである。いい感じにリラックスしてますねと褒められ、俺は何だか気恥ずかしくなった。
「正義くん、おつかれさま! わっ、そのスーツとっても似合ってるねえ」
「ありがとう谷本さん。あれ、その振袖の柄、ひょっとして」
「現代柄って言われたんだけど、うん、ちょっとね」
「ビスマスの結晶っぽいよ!」
「わかってくれた?」
だよねえという顔をする彼女は、いつもより少しだけぱっちりした瞳の下に、ダンディな皺を浮かべて見せた。おかっぱの頭はいつも通りだが、クリーム色の袴に、謎の幾何学模様のプリントされた黄緑色と紺色の振袖を合わせている。キュートな上に個性派だ。レンタルだというが、こんなに彼女らしい振袖が存在していたことに感動する。
俺はといえば、やたらと体にフィットする、二つボタンのイギリスのスーツである。ちょっと恥ずかしいが、大学生男子などという生き物は多かれ少なかれ俺と同じ生き物で、男友達の服装にはあまり頓着しない。アパレル業界に就職した一人だけが、中田の着てるのいいスーツだなと言ってくれた。
笠場大学の卒業式。だたっぴろい講堂に集うのはほんの一瞬で、卒業証書を手に入れたらもう、思い思いの友達を講堂近くのスペースで撮りまくる連写パーティの始まりだ。
待ち合わせしていた中央図書館近くのスペースに、谷本さんは走ってきてくれた。
「正義くん本当におめでとう。これから大変かもだけど、正義くんなら絶対大丈夫だよ」
「ありがとう。頑張るよ。自分がそんなに大した人間だとは思えないけど……」
「そんなことないよ。正義くんの凄さ、私ちゃんと知ってる」
谷本さんも卒業おめでとうと、俺がちょっとだけふざけて頭をさげると、彼女は嬉しそうにふふふと笑った。彼女は教採に合格し、晴れてこの四月から中学校の理科の先生だ。学部二年の時に、俺に語ってくれた夢をかなえたのだ。かっこいい。かなうことならば彼女の授業を受けて勉強したい、と言ったら笑われたけれど、今は彼女の動画通信用アドレスも知っているので、もしかしたら本当に一度くらいは授業を傍聴させてもらえるかもしれない。俺の所在地が日本ではなくなっても。
「谷本さん、赴任校は……」
「岡山県。ビカリアの化石の勝田層群で有名だよね。正義くんに比べれば近所だよ」
あと数日で、俺の所在地は日本からスリランカにうつる。宝石商の見習いだ。ラフな格好で動き回ることが多くなるだろうと言われているので、しばらくきっとフォーマルは着おさめだ。
しょうこー、という声が遠くから聞こえてくる。谷本さんの友達のようだ。彼女も手をふって応じている。
「正義くんあのね、私この大学で、正義くんに会えて、すごくラッキーだったと思う。本当にありがとう。おかげで大学がずっと楽しかった」
「……それ全部、俺の台詞だよ。でも俺は谷本さんには迷惑ばかりかけて」
「そんなこと言うなら私だってそうだよ。私、いろいろなチャンスをもらった気がする。本当にありがとう」
がんばるねと微笑む彼女は本当に可愛い。俺たちはどちらも岡山には土地勘がないが、どんなところであっても彼女はきっと持ち前の強さでばりばりと道を切り拓いてゆくのだろう。そして休日には化石を掘りに勝田層群に出かけたりするのだろう。
「……これからも、俺で役に立てることがあったら言ってほしいな。何でもするよ。変な奴は飛行機に乗ってぶっとばしにいく」
「私も正義くんをいじめる人がいたら、クラックハンマーを持ってやっつけに行くからね。期待してて。あ、亜紀が言ってたけど、私にはスナイパーライフルの方がいい?」
「ど、どうかな」
俺たちはそれからしばらく目立たないベンチで話して、いよいよという時間になった時、体にだけは気を付けてねと言って、彼女は手を差し出してくれた。俺も頷き、手を握り返す。彼女の手は小さいが、とても力強い。
「体にだけは気を付けて。石のご加護がありますように」
「ありがとう。谷本さんにも」
俺たちは深々と頭を下げ、せっかくだからとお互いの写真を撮りあい、ほどほどに距離を置いた二人の記念撮影もすませてから、別れた。盛大にハグして号泣している学生もあちこちにいるが、彼女も俺もそういうタイプではないし、これが今生の別れになるとも思わない。これからもきっと会えるだろう。
だが学生として顔を合わせるのは、これが最後だ。
握手の後、俺の天使は本物の天使よりも朗らかに、じゃあねえと手を振ってくれた。
その後、友達という友達を探して、今までありがとうと言いまくるツアーを完遂した俺は、最後に一通、テキストを送った。リチャードではない。中田さんとひろみだ。
『無事に大学を卒業できました。今までありがとうございました。これからもお世話になります』
挨拶というよりも、改めての決意表明のような連絡になった。
ぱりっとしたスーツは、確かにフィット感抜群だが、まだ完全に馴染んでいるようには思えない。当然だろう。この前仕上がったばかりなのだ。ここからがスタートだ。着込めば着込むほど、俺の形になってくれるというのなら、どんどん俺好みに着こなしてゆこう。
大切なのはハーモニーだという。
まだまだよそゆきとしか思えないスーツを、お気に入りの石を撫でるような気持ちでさらりと撫でながら、俺は青空と桜の花びらのコントラストを目に焼き付けた。


