
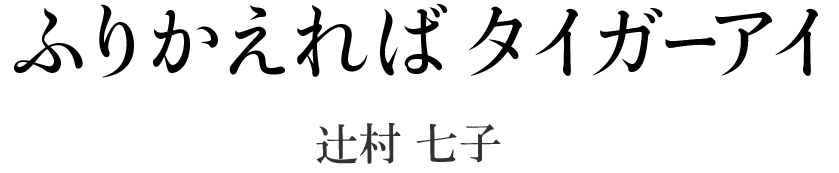
何故『目』が、魔よけになるのか。
タイガーアイという半貴石を、ブレスレットにしている男性がご来店したのは、うららかな五月の日曜日のことだった。高そうな腕時計と一緒に、数珠のようなものをつけているので、なんですかと尋ねたらタイガーアイだという。石の名前だ。彼がお買い上げになられたのは、ルベライトと呼ばれる赤い石のついたタイピンだったのだが、最後にちょっと面白いことを仰せになった。最後のお見送りの際、俺が下手に商売っけをだして、うちの店はいろいろなものを扱っているので、ブレスレットも準備できると思いますけどと申し上げたところ。
別にブレスレットが好きだから、これをつけているわけじゃないんだと、彼は笑った。
タイガーアイは第三の目だから、魔よけになるのだと。
商売をする人間にとって、もう一つ目があるということは、とても心強いことだから、この石を腕輪にしているので、別にダイヤや黄金の腕輪がほしいとは思っていないよと彼は言い、ほなな、と手を振って去っていった。彼の会社は大阪にあるという。海外雑貨の個人貿易をしているというバイヤーさんのはずだ。彼はなんだか、タイピンという品物よりも、銀座の不思議な店で買い物をしたというドラマをほしがっているように見えた。
結局『魔よけ』というのがどういうことなのかは、質問しそびれてしまった。
「なあリチャード、第三の目とか、魔よけって、目利きのことを言ってたのかな? 『変なものを掴まされませんように』とか」
ロイヤルミルクティーを嗜む美貌の店主は、今しがたそこで交わした会話の一部始終を伝えると、俺のことを白々と眺め、ぱちぱちとまばたきをした後、また無言でお茶に視線を落とした。おいしく飲んでいただけているようで、新米のお茶くみとしては嬉しい限りである。しかし今のリアクションはどうかと思う。眼差しにキャプションをつけるなら『ばかめ』あるいは『この大ばかめ』のどっちかだったと思う。
「……正義、あなたはタイガーアイという石のことをどのくらい知っていますか?」
「え?」
それは、ええと、茶色っぽい石で、『虎の目』という名前の石で――それだけだ。だってさっきそこで、見ただけなのだから。
美貌の店主は俺が言葉に詰まると、流麗な日本語で後を引き取っていった。
タイガーアイとは日本での呼び方で、英語圏ではタイガーズアイ。意味は虎の目。和名は虎目石。茶色っぽい石というのは不明瞭な形容で、黒茶色の部分と、縞状の金茶色の部分に分けられる石。名前の由来は、もちろんキャッツアイのように、シュッと一本線が走った姿からの命名だが、もともとは青石綿に石英が浸潤して出来上がった石であるらしい。石綿って。時々耳にするアスベストというあれなのかと俺が尋ねると、金髪の男は穏やかにうなずき、しかし最近日本で取り沙汰されているような健康被害をこうむる可能性は限りなく低いでしょうと補足した。まるで雑学王だ。金髪碧眼の男が、日本の社会問題までよくチェックしているというのは、何だか不思議な気がする。これも商売のためだろうか。
「……全然知らなかったよ。さっきのお客さんも、そういうこと全部知ってたのかなあ」
「鉱物学的なことにまでご興味があるかどうかはともかく、あの方はタイガーアイの特性を、あなた以上によく理解していたと思いますよ。彼は『目があること』ではなく『もう一つ目があること』と言っていたのでしょう。商売に携わる人間にとって、目利きというのは確かに必要な力ではありますが、それをブレスレットで補おうとする方は稀でしょう」
「じゃあ、魔よけっていうのは、目利きとは関係ない力ってことかあ」
「ノー。正義、あなたは……このくらいなら通じますか?」
そう言って美貌の店主は、珍しく英語で俺に話しかけた。九九パーセント日本語をしゃべる金髪碧眼の男という存在に慣れた俺の目は、一瞬「この人、外国語を話したな」と思ってしまった。明らかに逆である。
「……『彼は頭の後ろに目を持っている』?」
「グッフォーユ―。リスニングは得意だったのですね」
「そうでもないよ。今のは明らかに、聞きやすいように喋ってくれてただろ」
ともかく俺の聞き取りテストは正解だったらしい。慣用句だと思う。センター試験の英文法の点はそこそこよかった。頭の後ろに目がある。意味は多分。
「『抜け目がない』だっけ? あっ、それが『第三の目』?」
リチャードは軽く拍手して、俺の推理をほめてくれた。正解らしい。なるほど、なるほど。言われてみれば確かに。眼差しの中に若干『ここまで言ってやらなければわからないのか』という呆れの色が見える気もするが、それにしても整った顔立ちである。
「おわかりになったようですね。彼が必要としていたのは、抜け目のなさ、言い換えるのなら『土壇場で我に返る』『自己を客観視する能力』といったところでしょう。人間にはふたつしか目がなく、見える範囲はおのずと限られます。自分の頭の裏側が眺めることができる人間はいないでしょう。しかし勝負所に挑むような時には、己の姿をこそ客観視しなければ、足元をすくわれます。そういう時」
必要になるのは、一歩引いた視点だと、美貌の宝石商は言った。
それはつまり、エスパーのような透視能力などではなく、ちょっと待てよという一呼吸のことだろうか。問いかける前にリチャードはうんうんと大きく頷いてくれた。当たっているらしい。
「そういうのって、ああいうご商売をしてる人には、大切なことなのかなあ」
「すべての人間に大切なことだと思いますよ、正義」
「何か含みがあるよな、今の」
「穿ちすぎでは?」
飄々とした顔でとぼける美貌の男に、俺は再び名前を呼ばれた。せいぎ、とこの声に呼ばれるのには、正直まだあまり慣れていない。でも初めの一回目からずっと、全然嫌な気持ちはしない。テレビ局のアルバイトで『守衛さん』と呼ばれ続けることに辟易していたせいもあるだろうけれど、相手が俺のことを『俺』として見てくれているのがわかるからだ。
「はぁい、何でしょう店長」
彼の名前を覚えていますか? とリチャードは尋ねた。『彼』? タイガーアイのブレスレットのお客さまか。俺は『あの人』『あの人』と呼んでいたけれど、リチャードは彼の名前を覚えて呼んでいた。確か。
「麻野さん……だったな?」
「グッフォーユー。超能力者になる必要はありませんが、ここでのあなたは店員です。お客さまの居心地のよい空間の一部となるよう心がけていただけると、店主として嬉しく思います」
承知いたしました、と俺が頭を下げると、リチャード氏はよろしいと微笑んだ。かっちりと整った微笑みもまた息をのむ美しさだが、ぐっとこらえる。相手がいくら物分かりのいいお兄さんだとしても、思ったことを何でも言っていいなんてことはないのだ。
ふと気づいた。『第三の目』というのは、こういうことなのかもしれないと。自分自身がこうと思い定めていることを、ちょっと違うんじゃないかと声なき声で諫めてくれるような、『物の見方』そのもの。俺はタイガーアイのブレスレットが似合うような、伊達男ではないけれど、つけているような気分で頑張ってみることはできると思う。
「どうかしましたか?」
「いや……みんながタイガーアイの腕輪を、つけてるつもりで過ごしたら、世の中はもっと平和になるのかなって、ちらっと思った」
「同意します。逆に言えば、それほど己を客観視するということは困難なのです。全人類共通の、見果てぬ夢のようなものですね」
そう言ってリチャードはふわりと微笑んだ。ああ、本当にこの人間はきれいだ。いや、いやいや。タイガーアイを思い出そう。ちょっと待てよという気持ちを忘れずに。
「正義。どうしました?」
「……大丈夫だ。何でもない。それより……本当に俺、真面目に頑張るから、時々時々見とれてても、あんまり気にしないでくれる……か? 本当にきれいだからさ……」
これはもう不可抗力だと思う、と俺が言い訳がましく続けると、リチャード氏は青い瞳にしらじらとした色をのせ、お茶のカップを置くと、清々しいほどわざとらしく表情筋を使って笑った。
「わかりました。努力します。しかしあなたにも努力を求めます。美しいものに気を取られているうちに、魂を抜かれることもあると言いますからね」
そう言って、リチャードは表情を切り替えた。ふっと、作り笑いが仮面のような無表情にかわり、そこから徐々に妖艶な笑みに変わる。美しすぎておっかない顔だ。俺は少し体を引きつらせ、姿勢を正した。
「ラジャーです。気を付けます」
「『ラジャー』に『です』は不要では?」
「承知いたしましたあ!」
「……まあいいでしょう」
己を姿をかえりみる力。さしあたり、テレビ局の夜勤よりも随分割のいいこのアルバイトを続けるためには、必要不可欠なスキルだと思う。おいしいロイヤルミルクティーをいれる能力の次くらいに。


