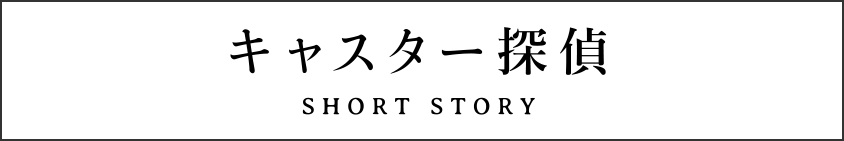
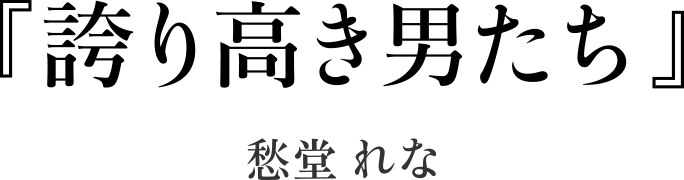
「藤田、お前、昨日はどこに行ってた?」
出庁早々、尋問よろしく問いかけてきた上司、斎藤警部補に藤田は、その勘の良さに内心舌を巻きつつ、答えを返した。
「竹之内さんのところです」
「愛キャスターの事務所だろうが」
誤魔化すな、と睨む斎藤の三白眼は、部下を始め、上司までをも竦ませるほどの迫力があるが、藤田はそう怖いと感じない。というのも彼の父親が警察OBで、長年SPとして第一線で活躍していた父の眼光の鋭さは並大抵のものではなかったために、ある意味慣れていたのだった。
もともと物怖じしない性格でもあり、また、斎藤の厳しさが理不尽なものではないとも納得しているので、たいして臆することなく相対することができている。
なので今回も斎藤が不機嫌極まりない口調で吐き捨て、じろ、と睨んできたにもかかわらず、藤田は、
「まあ、そうとも言いますね」
と笑って答え、傍で会話を聞いている同僚たちをひやひやさせていた。
「なにが『そうとも言う』だ。一体何をしに行った?」
斎藤がますます恐ろしげな顔で睨む。
「別に何も……竹之内さんに小説の感想を言いたかったのと、あとはまあ、世間話をしに、ですかね」
藤田が答えをぼかしたのは、『礼を言いに行った』と本当のことを言えば、斎藤の雷が落ちることがわかっていたからだった。
しかしそのせいで誤解を与えてしまったらしく、鬼の形相になった彼が凄んでくる。
「まさかと思うが、今捜査中の荻窪の事件に関する助言をもらいに行ったんじゃないだろうな?」
「まさか」
その発想はなかった、と藤田は驚いたあとに、そんなことを思いつくとは、とつい、まじまじと斎藤を見てしまった。
「なんだ」
斎藤が煩げに眉根を寄せ、問い返す。
「あの事件の捜査は行き詰まってますが、確かに愛キャスターの力を借りれば即解決かもしれませんね」
「馬鹿かお前は! 民間人に捜査情報を教えられるわけないだろうが!」
途端に斎藤の怒声が響き渡り、その場にいた全員――藤田を覗いては、だが――びくっと身体を震わせた。
「斎藤さんが自分で仰ったんじゃないですか。『頼みに行ったのか』と」
藤田の父の声もまた斎藤同様、否、それ以上に大きく響き渡る迫力のあるものだったので、その点でもまた慣れていた藤田が、何を言ってるんだか、と斎藤に言い返す。
「……っ」
確かにそのとおりであったため、斎藤が一瞬言葉に詰まる。その隙を藤田は逃すことなく、怒られるような真似を自分がするはずがないと主張し始めた。
「そりゃ、確かに愛さんに頼めば僕らが見落としていることにあっという間に気づき、事件解決――となるかもしれませんが、僕も刑事としてのプライドがありますから。余程の事でもない限り、相談になんて行きませんよ」
「実際、行ったじゃないか」
斎藤がここで突っ込みを入れる。
「あれは『余程のこと』だったんです」
胸を張った藤田の頭を、斎藤がバシッと叩いた。
「痛いなあ」
口を尖らせはしたが、言うほど痛くなかった頭を擦っていた藤田に、斎藤が厳しい顔で指示を出す。
「刑事としてのプライドがあるならとっとと聞き込みに行ってこい。何か事件に関するネタを拾ってくるまで戻ってくるなよ」
「わかりました! 行ってきます」
明るく返事をした藤田を見て、斎藤は一瞬、鼻白んだような顔になったが、すぐ、
「俺も行く」
そうぼそりと告げると、藤田の前に立ち歩き出した。
「今日は斎藤さんとペアですか?」
「そうだ」
「勉強させてもらいます」
「『勉強』なんて悠長なこと、言ってる暇はないぞ」
「確かにそうですね」
斎藤の言葉はいちいち厳しいが、やはり藤田が凹むことはない。というのも彼の父が――以下同文、であったためである。
「プライドといえば」
共に覆面パトカーに乗り込んだあと、ハンドルを握りながら藤田は、助手席でむっつりと黙り込む斎藤に向かい、一方的に話を始めた。
「愛さんの仕事に対するプライドには感じ入りました。傷口に塩は塗らないって、あれです。斎藤さんも感動しませんでしたか?」
「知るか」
吐き捨てる斎藤にかまわず、藤田は喋り続けた。
「愛さんも凄いなと思うんですけど、竹之内さんも凄いんですよ。愛さんのことは小説にしないんですって。それが竹之内さんのプライドだって。格好いいなと痺れましたよ、あの二人には。お互いを尊重している上で、それぞれプライド高い仕事をしているからこそ、名コンビになってるんでしょうね」
「……竹之内というのはあのボーズだよな」
と、ここで斎藤が藤田に問いかけてきた。
「そうです。ボーズじゃないですよ。年齢は愛さんと一緒で、ええと……30歳は越しているんじゃないかな」
「30か……見えないな」
斎藤が驚いた声を出す。珍しいな、と思いながらも藤田は、本人に斎藤がそれを言わないように、と一応釘を刺すことにした。
「竹之内さん、童顔なことを気にしているみたいですよ」
「知るか」
またも吐き捨てた斎藤だったが、会話をそこで終わらせることなく、ぽつ、と藤田に問うてくる。
「相方のことを小説にしないって? すればさぞ、売れるんじゃないのか?」
「売れるだろうし、愛さんも別に書いていいって言ってるそうなんですけど、それでもしないんですって。小説は一生の仕事にしたいから、愛さんの手を借りるようなことはしたくないそうです。安易な選択はしないって、あんなに可愛い顔して男前ですよね。かっこよすぎませんか? ますますファンになりましたよ」
「あのボーズがね……」
熱く語る藤田の横で、斎藤がぼそりと呟く。
「ボーズじゃないですって。竹之内誠人さんです。あ、そうだ。今度、竹之内さんの小説が載った雑誌、お貸ししますよ。きっと斎藤さんも一目置いて『ボーズ』なんて言わなくなりますよ」
「いらん」
「そう言わずに。きっとファンになりますって」
「いらんと言ってるだろうが」
不機嫌に言い捨てたあとに、斎藤がじろ、と藤田を睨む。
「他人のプライドはどうでもいい。お前のプライドを見せてもらうぞ。なんとしてでも今日中に容疑者を見つける。いいな」
「はい!」
身の引き締まる思いで返事をした藤田は、ハンドルを握りながら、ちらと斎藤を見やる。
彼の仕事に対する姿勢もまた、この上なく尊敬していると伝えたいのだが、伝えたほうが不機嫌になるとわかっているだけに口にできない。
尊敬できる人間が近くにこうもたくさんいるなんて、本当に自分は幸せ者だと心から思いながら藤田は、自分もまた刑事としてのプライドを保つべく、捜査に邁進しようという熱意を胸にハンドルを握り直したのだった。


