宝石商リチャード氏の謎鑑定 比翼のマグル・ガル 第三回
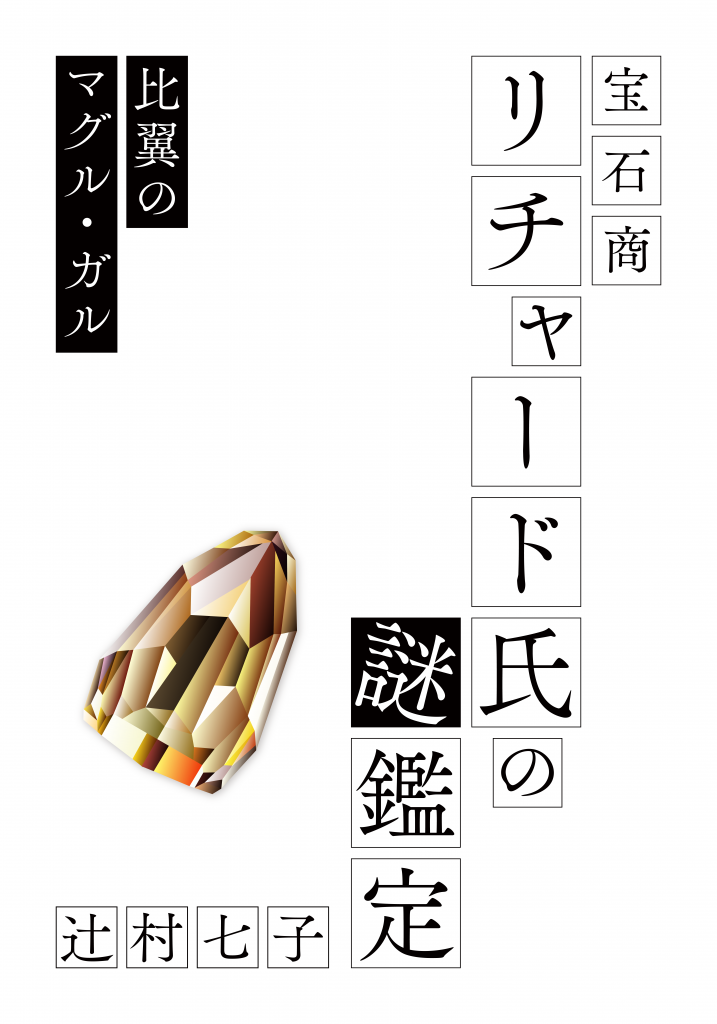
2 告白とペンダント(2)
土曜日はすぐにやってきた。みのるはその日朝から生きた心地がしなかった。なんなら金曜日の朝から緊張していた。悪いものでも食べたのかと良太にからかわれたが、みのるは決して秘密を打ち明けなかった。そんなことを真鈴が望んでいないことは明白だったからである。
「大丈夫、みのる? 眠れなかったの?」
金曜日、真鈴は普通の顔をしていた。普通に格好よくて、普通に急いで宿題をやっていて、普通に事務所の仕事のことを気にしていた。少なくともそういうふりをしていた。
本当のことを言えば、みのるは良太と二人でファストフード店で待っていたかった。片腕をひろげて脚を組んだポーズのキャラクター人形が座っているベンチで、良太と二人で真鈴を待ちたかった。そして店の中で何かあたたかいものを食べたかった。
だが今回は、おそらくみのる一人が、真鈴の許容範囲ギリギリである。
二人でわいわい言いながら真鈴を待つ姿を考えると、みのるは何故か、ひどく無礼なことをしているような気持ちになった。
土曜日の朝。今日は何もする気が起きないし、何をすることもできないという確信があったので、みのるは林くんの中華料理店に顔を出した。運が良ければ「手伝ってくれ」と言われ、配膳の手伝いくらいはすることができる。お駄賃はおいしい杏仁豆腐か中華蒸しパンで――『中田さん』の名前を出すと大量の中華総菜を持たされてしまうので、みのるは素知らぬ顔で仕事だけを手伝う術を身につけていた――みのるはそれを林くんと一緒に食べるのが好きだった。
家から山下公園の方向に歩き、ランチ時直前の福新酒家の門をくぐると。
「あっ……」
「おや。どうかしましたか」
見知った顔が立っていた。ツーブロックの髪。ポップスターのようなしゅっとした顔立ち。カンフーシューズ飛ばしの名人。
「ヒロシさん……じゃなくて、ヴィンス、さん?」
「はい。ヒロシでヴィンスです」
めちゃくちゃな自己紹介だったが、間違っていないことをみのるは知っていた。林くんの日本語の先生でもある『ヒロシ』のことを、正義とリチャードは『ヴィンス』と呼んだ。どういうことなのかと混乱するみのるに、ヒロシでありヴィンスである男は、どちらも自分の名前であって、なんならもう一つ自分には名前があると言ってくれた。香港出身の人間にはそう珍しいことでもないのだと。
以来みのるには、ちょっとした悩みが存在していた。
次に会った時には、彼を何と呼べばいいのか。
決断をする前にその時はやってきてしまった。みのるがあわあわしていると、ヒロシでありヴィンスである男はやれやれと言わんばかりに笑った。足元には黒いスーツケースが一つ、置かれている。背中にはリュックを背負っていて、どこかへ出かけるところであるようだった。
「どっちでも好きな名前にしてください。何なら文博でもいいですよ」
「あっ、あっ、三択になっちゃった……」
「じゃあ『ヴィンス』で。あの人たちと一緒にいるなら、その方がわかりやすいでしょうしね」
あの人たちとは正義とリチャードのことである。みのるは頷き、ヴィンスさんと呼んだ。はいなんでしょう、とヴィンスが答える。
「……ジェフリーさんは?」
「帰国したはずですよ。そのうちまた来るとか言っていましたが……しかし俺の顔を見ると、ジェフリーさんが浮かぶんですか? まずいですね、早急にアルゴリズムの改善が必要な思考です」
「す、すみません。失礼なことを申し上げたなら」
「冗談です。あの人に何か用事があるなら、リチャードに話をするのが一番早いと思いますからそうしてください。他には?」
「……どこへ行くんですか?」
「俺も帰国します」
「えっ」
アメリカ、とヴィンスが告げる。みのるは目をぱちぱちさせた。
「マリアンを……俺の奥さんをこれ以上一人にしておけません。今でも十分無茶だったんです。本人は『まだ日本にいた方がいいんじゃないの?』なんて言いますがね、いろいろ大変だし、寂しがっているのもわかってます。俺だって会いたいし」
「そういえばお子さんがいるんですよね」
「はい。めちゃめちゃ可愛いですよ。俺の日本での野暮用が済むまで会えなかったんですが」
「野暮用……?」
「こっちの話です。でも全部片付いたので」
そうですかとみのるは頷くことしかできなかった。
妻子を持っている知り合いができる。少し前のみのるなら、そんな知り合いができる可能性も考えなかった。だがヴィンスとは既に図書館で一緒に勉強し、カンフーシューズを飛ばしっこした仲である。仮面舞踏会では一緒に手を繋いで踊った。
「…………」
今ならば、何を尋ねても怒られない気がした。そしてチャンスは今しかない。みのるは勇気を振り絞った。
「あの……ヴィンスさんに質問したいことがあるんですけど」
「何でもどうぞ」
「奥さんの、マリアンさんと結婚した決め手って、何だったんですか?」
は? という形にヴィンスの口が動いた。みのるは死にたくなった。チャンスが今しかないとしても、何を質問してもいいということにはならない。
みのるは慌てて言い繕った。
「す、すみません! 変なことを言いました、気にしないでください!」
「臓器移植ですかね」
「……え?」
「臓器移植のドナー。はい、お答えしました。今度は俺の質問。どうしてそんなことを質問したんです?」
「えっ! ええっと」
みのるは再び慌てた。質問をしたら回答後に質問が返ってくる。当然の展開といえばそうだったが、あまりのスピード感だった。しかし「友達が一世一代の告白をしようとしているので恋愛について質問できそうな人に質問してみたかった」と正直に言うこともできない。だが適当な嘘をついてもすぐ見抜かれそうだった。
精一杯ぼかしながら、みのるは言えるだけのことを言った。
「友達が、恋愛していて…………それで質問したかったんです」
「友達が恋愛していると、どうして俺に『結婚の決め手』を質問することになるんですか」
「あの……結婚って……恋愛の最終進化形ですよね? だから……」
「別にそうは思いませんけど」
「あっ」
みのるの質問は、最後まで言いもしないうちに空中分解してしまった。
途方に暮れる顔をするみのるに、空いている料理店の椅子を促し、ヴィンスは向かいに腰掛けた。
「飛行機の時間まで余裕があります。その間でよければ話を聞きますよ」
「すみません……」
みのるが椅子に腰かけると、ヴィンスは首をかしげて問いかけてきた。
「恋愛の最終進化形って、結婚なんですか? 逆に教えてほしいんですが、どこでどういう分岐をたどったら結婚になるんですか?」
「それは……大人の方がよく知っているんじゃ……?」
「大人になるといろんな分岐が見えてくるので、逆にそういう『最終進化』に辿り着くばかりじゃなくなりますね。アナザールートが開放されまくっている状態というか」
「は、はあ」
「みのるさんが考えるのは? どういうシナリオなんですか」
シナリオ。そう言われるとみのるの頭は少し整理された。頭の中にあるすごろくのようなものを見せろと言われた気がしたのである。すごろくとは正月に正義とリチャードと遊んだ、マス目の上を自分のこまをすすめてゆくボードゲームのだった。
みのるの思い描いている盤上では『結婚』が『あがり』になる。すごろくの名前を『恋愛』という。
ぽつりぽつりとみのるは語った。たとえば人と人が出会って、恋に落ちて、付き合い始めて、ずっと一緒にいたいと思って、結婚する。それがみのるの思い描く恋愛の『進化』の過程だった。
ふーん、という顔をして聞いていたヴィンスは、うんうんと頷いた後、みのるを見た。
「じゃあ俺たちのパターンを説明しますね。俺とマリアンの出会いはマリアンの就職でした。俺の実家の住み込みのお手伝いさんになってくれたんです。その後いろいろなゴタゴタがあって、俺の親父が死んで、ジェフリーさんが俺に大学進学の金をくれて、その後にマリアンが病気になりました。俺はマリアンが好きだったので、臓器さえあればマリアンが助かるとわかってプロポーズしました。その時からマリアンが俺を好きだったかどうかは、その時には知りませんでしたね。どうでもよかったとも言います。ともかくマリアンに死んでほしくなかった。晴れて俺たちは結婚。俺は夫ドナーになって、マリアンの移植手術が成功、その後の仮面夫婦期間を経て、仲直りというか……まあ、ラブラブ? 今に至ります。おわり」
「………………」
みのるは開いた口がふさがらなくなり、慌てて手動で自分の顎をはたいて口を閉めた。
波瀾万丈のすごろくだった。
それも恋愛ドラマというよりは、サスペンスドラマである。
二人の結婚は恋愛の最終進化形ではなかった。少なくとも恋愛だけの結末ではなかった。いろいろな出来事がミルフィーユのように折り重なった末のもので、愛しているから結婚しましょう結婚しましたよかったねというタイプではなかった。
結婚の決め手は、考えるまでもなく臓器移植である。
恋愛ではなかった。
ぼうっとしているみのるに、ヴィンスは言葉を重ねた。
「これはほんの一例です。別に好き合っている同士だとしても、最終的に結婚する人ばかりではないです。いろいろなパターン、いろいろな考えがありますから。でも逆に、恋愛ってものを『最終進化』させたいと思っても、いろいろな理由で『結婚』に辿り着かない、あるいは辿り着けない人たちもいます」
「……いろいろなんですね」
「まあそうですね。話を脱線させまくってしまって申し訳ありません。最初の質問は何だったんですか? もう一度、改めて質問させてください」
みのるはしばらく考えた末、頭の中身をまとめようと試みた。この一年でみのるは何度も似たような状況に遭遇した記憶があった。大事なのは素早く口を開くことではなく、きちんと自分の考えをまとめておくことである。
しっかり時間をとった後、みのるはヴィンスの顔を見て、改めて質問した。
「人が……人を好きになって……一緒にいたいと思った時、うまくいく時と、いかない時があって……それは、どういう違いなんだろうと思いました。それで、奥さんと結婚した決め手を質問しました」
「失恋でもしましたか?」
「いいえっ! 違います……!」
「ふーん」
ヴィンスは頬杖をついた後、少し面白そうな顔をして笑った。
「理由はいろいろ考えられますけど、一番はタイミングじゃないですかね。あとは巡り合わせ」
「……タイミングと巡り合わせ」
「はい。ものすごく好きになれそうな人と巡り合ったとしても、その時に何年も付き合った恋人がいたら、恋人を替える人と替えない人がいるでしょう。こういうのがタイミングと巡り合わせ。ざっくり言えば運、ですかね」
「………………」
みのるは俯いてしまった。
タイミングと巡り合わせ。運。
いずれも努力ではどうにもならないものである。
つまり恋愛というのは努力した人が勝つゲームではないんだと、みのるは理解してしまった。街を少し歩けばいろいろな広告が目に入った。がんばって髪の毛をきれいにしましょう。スキンケアをしましょう。口のにおいを消しましょう。頭にもっと髪の毛を増やしましょう。やせましょう。それはどれも、広告を見た人に『もっと魅力的になるためにがんばりましょう』と働きかけるものだった。もちろんスキンケアは肌にいいかもしれなかったし、やせることは成人病予防になる。だがおそらく、それらの広告が言葉にせずアピールしているのは『がんばるといいことがありますよ』という論理だった。
だが、恋愛において、努力とは実を結ぶかどうかわからないものであると。
ヴィンスはそう言っているのだった。
みのるはつらくなった。真鈴はひたすら努力をしていた。モデルになるためだけではなく、正義に振り向いてもらうために、いろいろなことをがんばっていた。だがそれは、タイミングにも巡り合わせにも関係がない。それはどこか空を巡る星や潮の満ち引きを止めようとするような行為に思えた。
自分でもわからない理由で泣きそうになっていると、ヴィンスは少し困ったような顔で笑い、みのるの頬を撫でた。みのるはその顔にはっとした。目元がリチャードにそっくりで、手つきは何となく正義に似ていた。
「恋愛はタイミングで巡り合わせですけど、世の中の全てが恋愛ってわけじゃないですよ。努力や創意工夫で何とかなることもたくさんあります。いっぱいあります。それを忘れないでください」
「でも恋愛は、恋愛ですよね」
「それはそうですが、『恋愛』って言っても、全部が同じパターンとは限りませんから」
「……わかりました」
みのるは複雑な気持ちで頷いた。ヴィンスは手を動かし、くしゃくしゃとみのるの頭を撫でた後、立ち上がった。いよいよ店を出るらしい。
下ろしていたリュックと再び背負い、壁際のキャリーケースを手に取ったヴィンスは、最後にみのるを振り返った。
「言い忘れていました。よければ中田さんとリチャードに、俺から伝えてください。『ゴンヘイ』って」
「ごんへい……またねってことですか?」
「そのまま言えば伝わりますよ。それじゃあまた、どこかで」
最後に伊達に手を振って、大荷物のヴィンスは店を出て行った。最後までしゅっとしていて、ゲームに出てくるイケメンキャラのようで、格好よかった。
様子をうかがっていたと思しき林くんが出てきて、みのるの背中をばしんと叩く。
「どうしたみのる! ヴィンスに相談していただろう。何かあったのか。良太と喧嘩でもしたのか?」
「林くん……大丈夫。そういうのじゃないから」
「ははあ、お前ランチをたかりにきたな。こういうのを『たかり』というのもちゃんと覚えた。いいだろう、好きなのを食べさせてやる。麻婆丼と叉焼丼だったらどっちがいい?」
「叉焼丼だけど、何かお手伝いをさせてほしいな。ただで食べるのは気分が良くないし、何でもいいから何かしたい気分だから」
「お前は本当におひとよしだな。いいだろう、皿を洗わせてやる。阿爸!」
みのるは本当に皿洗いをさせてもらった。林くん曰く「三十分」のはずが、忙しいランチタイムが始まってそれどころではなくなり、結局みのるは二時までみっちり皿を洗い続けた。そして叉焼丼だったはずのものは、叉焼丼の中華総菜フルコース杏仁豆腐つきになり、みのるは林くんと二人できゃっきゃと騒ぎながら遅いランチを楽しんだ。
その間だけ、みのるは午後七時のことや、恋愛のことを忘れていられた。
冬の夜はあっという間に訪れ、午後五時にはもう日が暮れて、七時は深夜のように暗く、寒かった。
みのるは六時三十分からファストフード店で待つことに決めた。正義は銀座での仕事の後に直接マリンタワーに向かうらしい。福新酒家を出た後、一度みのるはマンションに戻ったが、正義もリチャードも仕事に出ているようで静かだった。
みのるは一人で宿題をし、六時過ぎにコートを着てマフラーをつけて家を出た。
巨大なものに立ち向かおうとしているのは真鈴であってみのるではないのに、みのるは緊張のあまり胃が痛かった。ということは真鈴はその何倍も緊張しているということで、みのるはたまらなくなった。自分が真鈴だったら七時になる直前にトイレに入って出てこられなくなりそうだった。
だが真鈴には、決してそんなことが起こらないことを、みのるは知っていた。
みのるの知っている真鈴は超人ではなかった。モデルで、颯爽としていて、格好いいものの、友達ができないと泣くこともある中学生の女の子だった。だが夢に向かって驀進するエネルギーを持ち、オムライス弁当やからあげ弁当を見ても「ほしい」とは言わずにブロッコリーを食べ続ける、巨大な自制心とガッツの持ち主でもある。
自分から挑んだ戦いに、挑む前から背を向けることなどありえない。
それがみのるの知る真鈴だった。
広いファストフート店の中で、みのるは祈るような気持ちで七時を待った。
【つづく】