宝石商リチャード氏の謎鑑定 比翼のマグル・ガル 第二回
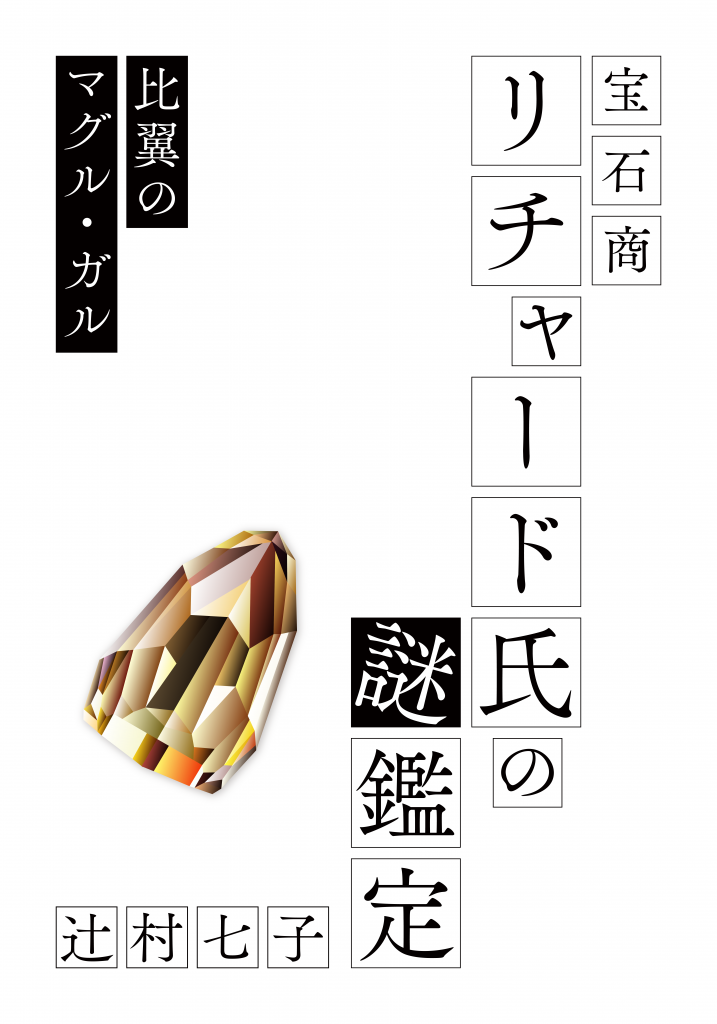
2 告白とペンダント(1)
お父さんの話は、病院のお母さんにはまだしばらく内密にしておくそうだった。気持ちの変化が大きく影響する病気なので、正義と担当医とが相談した結果、今すぐでなくてもいいでしょうという判断が下されたという。みのるは頷いた。お母さんにとってもみのるにとっても、『お父さん』は別に存在しなくても日常が成り立ってしまう類のパズルのピースだった。逆にいきなりはめこもうとすると、他のピースとの不調和が起こってしまいそうなほど。
「ゆらさんもだんだん回復しているよ。でも寒くなってきて、季節の変化もあるから、あまり無理をさせたくないって、先生が」
「そうですね……」
いつもと同じ朝食のダイニングで、みのるは無難に頷いた。リチャードはいつもと同じに、正義の隣でうとうとしている。
みのるはまだ、真鈴の頼みを正義に切り出せずにいた。何かが変わってしまう気がしたからである。
今まで通りの様子の真鈴の頼みだったなら、「どうせまた上手くいかないだろう」と思いながら、みのるは話を通してしまった気がした。いつもと同じように、真鈴が正義の情報を知りたがり、そのリサーチの結果何らかのアプローチをし、正義がそれをのらりくらりと笑ってかわす。
それだけのはずだったが。
今回はきっと、それだけでは終わらない気がした。何かが変わるはずだった。
その後に真鈴はみのるのことをどう思うか? みのるの最大の気がかりはそこだった。
真鈴は今まで通りにみのると友達付き合いを続けてくれるのか。スーパー親友と言ってくれるのか。そもそも真鈴がみのるに関心を寄せてくれたのは、銀座のダイヤモンド展示会での憧れがきっかけであったはずである。
もし何かが起こったら、真鈴はもう二人をスーパー親友とは思ってくれなくなるのではないか。
不安だった。
友達が遠くへ行ってしまうことではなく、本当は真鈴が、みのるや良太のことをそれほど大事には思ってはいないと突きつけられる可能性が怖かった。
「みのるくん、大丈夫?」
「えっ?」
正義はいつものようにみのるの顔を見ていた。
骨壺をどこかの寺に預けた後、正義はすぐにいつもの正義に戻り、みのるのことを気にかけてくれるようになった。それがただのポーズであったとしても、みのるはその逞しさに励まされた。いつか自分もこんな風になれるかもしれないという夢を、正義はみのるに見せてくれるのだった。だが真鈴にはおそらく別の夢を見せている。
正義は微かに首をかしげていた。
「何か俺に話したいことがある? 最近よく俺の顔を見てる気がするから、ちょっと気になってた」
正義はお見通しだった。
リチャードがうとうとしていることを確認してから、みのるはおずおずと喋った。
志岐さんが、正義さんにご用があるようです、二人で会いたいそうです、と。
途端にリチャードの目がぎんと開いたので、みのるはたじろいだ。正義が隣で笑っている。ジローとサブローが甘えてきたのをいなすのと同じ手つきで、正義はリチャードの背中を撫でた。眼差しはみのるを見たままである。
「そうなんだね。用件はもうわかってる?」
「……いえ…………………………」
みのるは精一杯の間を持たせ、いつもとは少し違うようですと、正義にだけ伝わるように頑張った。ぎんと目を開いたリチャードの目が、ふたたび眠そうに閉じてゆく。
正義はリチャードから手を離した。
「わかった。いつどこに行けばいいのか、志岐さんが指定してくれたらいいよ。そこに行く」
みのるは頷いた。
三人は言葉少なに朝食を済ませ、みのるは歩いて登校した。午前中の授業はみのるの好きな現代文と社会だった。先生に質問されたとしてもそれほど慌てずに済むので、気が楽な教科である。
昼休みがやってくる。
「みのるー! 今日のお前の弁当見せて。うは! オムライス弁当! すっげ、みっちみちに入ってる。全面オムライス」
「すごいでしょ。僕のリクエストなんだけど、正義さんは『何か手抜きみたいでつらい』って言うんだよね」
「デミグラスソース別添えのオムライスで手抜きとか、俺の母親に聞かせたら卒倒するぞ。真鈴は……いつものか」
「いつものって何。ちゃんと栄養バランスに気を配って、毎日違うものを食べてますけど」
「へえへえ。ブロッコリーとそのお友達だな」
「昨日とはフルーツが違うんですー」
みのるは真鈴と二人きりになるタイミングを作りたかった。だが良太がいる。都合よく良太がいきなりトイレに行ってくれたりしないかと思ったが、今日に限ってなかなかチャンスがなかった。
からあげと野菜炒めの入った弁当を七割ほど平らげたところで、良太はぽつりと呟いた。
「あのさー、俺たちいつまでこうやって三人で弁当食えるのかな」
「……え?」
「いきなり何言ってんの」
「いや、だってさ!」
冬が終わったら春が来て。
自動的に全員、二年生になってしまうのである。
クラス替えがあって、勉強の内容も変わって、少しずつ受験を意識しなければならなくなる。良太はそんなことをもごもごと喋った。つまり。
「今までと同じじゃなくなるだろう? 今日ふっと、そういうことを思ってさ」
「……いや、私たちみんな同じクラスってわけじゃないし、受験のことを考えさせられてるのは今でも同じじゃないの?」
「あ、そ、そうか。真鈴は別のクラスだった」
「期末テストも終わってないのに寝ぼけたこと言わないでほしいな、赤木クン。っていうかこの前教えてもらった数学の宿題、びっくりするくらい間違ってたんだけど」
「教えてもらっておいてその言いぐさはないと思うぜ……!」
良太と真鈴は楽しそうだった。みのるも二人のやりとりを聞いているのが楽しかった。だが時々真鈴が、真剣な瞳でみのるを見る。
無言の眼差しの意味が、みのるにはよくわかった。
良太が先に行くと言って去った後、みのるはようやく真鈴に話すことができた。
「どこでも、いつでもいいって。真鈴の指定した場所に行くって言ってくれた。決まったら僕に教えて。僕に言いたくないなら、手紙か何かに書いてくれたら、正義さんに渡す」
手紙の部分はみのるが勝手に付け加えたことだったが、正義には怒られない気がした。
真鈴はじっとみのるを見返した後、わかったとだけ告げた。
「それじゃあね」
「うん」
真鈴が去るのと同時に、みのるも良太の後を追いかけた。
午後の授業はみのるの苦手な理科と数学で、途中で眠くなってしまったが、お前らこれがわからないと高校で苦労するぞという声に励まされて何とか目を開けていた。
その日の夕方、自室で宿題をしていたみのるは、真鈴からメッセージを受け取った。良太との三人グループメールではなく、みのると真鈴、二人だけのやりとりである。
『土曜日の夜。夜七時にマリンタワーの下』
『場所や時間が合わないようだったら教えて。別の日にする』
みのるの心臓が、ひゅっと変な脈をうった。
今週の土曜日の七時に、真鈴は何かを決めようとしている。イエスかノーかで決まるものではなく、もっといろいろな広がりが含まれる何かを、自分だけではなく中田正義と。
わかった、ちょっと待ってて、とみのるは返事をした。
しばらくしてから再び真鈴のメッセージが入る。
『見世物じゃないから見にきてほしくないけど、見守っててほしい気持ちも正直ある』
どっちなんだ、とみのるは頭を抱えたくなった。
正直なところ、見たい気持ちが一割、見ていたくない気持ちが九割だった。見たい気持ちは、どうせ学校で顛末を聞くことになるので、真鈴が見ていいと言っているのなら全部自分で見ておいた方が気が楽かなと考えた結果だった。残りの九割はいたたまれなさと申し訳なさと恥ずかしさである。正直なところみのるは真鈴に決めてほしかったが、今まさに勇気を振り絞っている相手に甘えたことは言えない。
うんうんと唸った結果、みのるは一つのアイディアを絞り出した。
『僕が近くのファストフード店で待ってるのはどう?』
『全部終わったらこっちに来てくれたら、話を聞ける』
真鈴はしばらく返事を寄越さなかった。
その間にみのるは正義にメッセージを送った。土曜日の七時のマリンタワー。条件が合わないようだったら他の日や時間を考えるそうです。
先に返信を寄越したのは真鈴だった。
『みのる ほんと いいやつ』
『ファストフード店で待つコースでお願い』
『女の子の中にも君みたいな子がいたらいいのにって わりとガチで思う』
みのるはびっくりした。ただのアイディアをこんなに喜んでもらえるなんて不思議だったが、それ以上に真鈴の不安な気持ちが伝わってきてつらかった。
何よりみのるには、何が起こり、どんな結果になるのか、予想がついた。真鈴もきっとそうだと思った。にもかかわらず真鈴は正義と話がしたいという。変な話である。
だがみのるには、その気持ちも少しわかるような気がした。
神立屋敷でのタンゴ事件のことを考えると、みのるは今でも胸がきゅっとした。真鈴とリチャードが踊っている様子はまるで時代劇の侍同士の果たし合いだったし、その後にやってきた正義が手を取った相手も、真鈴ではなくリチャードだった。当然のように。少し怒ったように。
そういうことなのだと、みのるもそれなりに理解しているつもりだった。
真鈴がやろうとしていることは、既に一度切りつけられた部分を、もう一度切ってもらおうとするような行為に思えた。そんなことには意味がないと、みのるは思わなかったが、意味があるからといって切られる痛みが和らぐとは思えない。みのるはつらかった。友達がそういう目に遭いに行くのだと思うと胸がシクシクした。
何より『切る』側にいるのも、真鈴同様みのるの大事な人である。
どちらを向いてもつらい。
真鈴のメッセージを転送した正義からも、みのるにメッセージが入る。
『志岐さんの提案してくれた場所で大丈夫です、とお伝えください』
『ありがとう』
二番目のメッセージはみのるに宛てたものであるようだった。
みのるは無言で頷いた後、正義のメッセージをそのままコピペして真鈴に送った。
真鈴のメッセージは簡潔だった。
『了解』
みのるはハーッとため息をつき、耐えきれず背中からベッドに転がった。
土曜日になれば何かが決まる。
それが確定してしまった。
呻きながらベッドを転がり、それでもいたたまれなくなり、みのるはダイニングルームに出た。何でもいいから食べるものが欲しかった。食べている間は難しいことを考えずにいられるからである。
すると。
「あっ……」
「おや」
リビングにリチャードがいた。
いつ帰ってきたのか、みのるは気づかなかった。真鈴とのメールに気を取られている間に帰ってきたのだとしたら、よほど音を潜めていたに違いない。
リチャードはテーブルの上に、小さなビニールの小分け袋に入った宝石を広げ、検分しているようだった。
「おかえりなさいませ、みのるさま」
「リチャードさんも、おかえりなさい。あの……」
お腹が減っちゃって、とみのるは笑ってみせた。リチャードも微笑み返した。みのるは自分が下手な芝居をしている気分になった。
まごまごしている間に、リチャードは冷蔵庫を開け、シェパードパイとりんごのタルトであったらどちらの気分かと尋ねてくれた。とはいえじき夕食の時間である。みのるにはどちらも重すぎる気がした。
みのるが言い淀んでいると、では、とリチャードは告げた。
「正義のプリンにしましょうか」
「あっ、はい」
リチャードは冷蔵庫の中から、縁がやわらかく丸くなったガラスのカップを二つ、取り出した。中田正義謹製と時々正義がふざけるプリンは、言われるまでもなくリチャードの大好物である。幸せそうな顔をして大事に食べる姿を、みのるは既に何十回と目にしていた。だからこそ、冷蔵庫の中に並んでいても五個以上存在しない時には手を出さないことを、自分ルールで決めていた。
みのるの記憶が定かならば、今日のプリンは残り二個だった。
いいんですかと真剣な顔をすると、リチャードは楽しそうに笑った。
「もちろんです」
そしてリチャードは、台所のレンジの前に立った。リチャードがである。目の当たりにしたことこそなかったものの、味噌汁を沸騰させて床をびちゃびちゃにした事件と、ホットケーキが吹き飛んで壁に貼りついた事件はみのるも知っていた。そして正義の言うところによると、まだまだいろいろな『事件』がリチャードと台所の取り合わせには存在しているらしい。
「あの! 何かやりたいことがあるなら、僕にもできます!」
「ご心配なく。お茶をいれるだけです」
ロイヤルミルクティー、おいしいですよ、と。
リチャードは穏やかな声で言い、本当に何ごともなくお茶をいれてくれた。それでみのるは思い出した。
まだリチャードの名前すら知らず、神立屋敷に忍び込んだ日にも、みのるはこのお茶を飲ませてもらったことがあった。ロイヤルミルクティー自体は今までにも何度も振る舞ってもらっていた。だがあの夜のことを思い出したのは、今回が初めてである。
多分リチャードと二人きりでいるのと、この部屋の雰囲気のせいだ、とみのるは思った。
あの時の、得体のしれない幽霊のような、妖精のような雰囲気を、今のリチャードは再び纏っていた。
お茶とプリンを楽しみながら、みのるは時々リチャードを観察した。穏やかな曲線を描く金色の髪、長い睫毛にふちどられた淡い青色の瞳、所々にうすく血管が見え隠れするミルク色の肌、何だかそわそわしてしまうほどたおやかなカーブを描く唇。綺麗だった。正義が褒める言葉の通り、リチャードは美しい生き物だった。
その唇が動く。
「思い返せば長いものです。私と正義が出会ったのは、彼が大学二年生の時です。私はもう十年以上彼のプリンを食べ続けている計算になります」
リチャードはつん、つん、と銀色のスプーンでプリンを突いていた。三人でいる時であれば絶対にしないであろう、多少お行儀の悪い仕草である。みのるが目をぱちぱちさせると、唇が笑みの形にゆがむ。
「おかしいですね、いきなり思い出話など。自分でもそう思いますが、このお茶とプリンを見ていると、どうしても懐かしい気持ちになってしまうので」
「……正義さんも学生の時代があったんですね」
「ありましたとも。粗忽な学生でしたよ」
そこつ。どういう意味だろうとみのるが首をかしげていると、おっちょこちょいということですとリチャードが説明してくれた。信じられずにみのるが半笑いを浮かべると、リチャードは噴き出した。
「今の彼の姿からは想像もできませんか? そうですね……いろいろな例がありますが、彼の名誉にかかわる話ですし、私からご披露するのはやめておきましょう。ですが初めて出会った時から彼の優しさは変わっていません。それだけは確かなことです」
みのるが頷くと、リチャードは楽しそうに話し始めた。
二人が初めて出会ったのは十年前、東京の渋谷あたりだそうだった。かっこいいお店で出会ったのかなと思っていたらそうではなく、リチャードが迷惑な酔っ払いに絡まれたところを助けてもらったのだという。いきなり面白い出会い方をしているなというのがみのるの感想だった。その後ちょっとしたことを経て、正義がリチャードの店でアルバイトをすることになり、それが何年も続いた。正義の大学卒業後は、二人の関係はアルバイトと上司ではなく秘書と上司に変化し、二人で世界を飛び回る仕事を続けた末、時々はスリランカで休むという生活。
そんな中みのるに出会い、二人は日本に戻ってきたという。
みのるは少し、不思議な気分になった。二人は日本で偶然出会い、一緒に働くようになり、今は共同生活をしている。そこにみのるが加わっていることも不思議だったが、それ以前に、正義とリチャードが一緒に暮らし続けていることがふんわりと不思議だった。たとえ酔っ払いに襲われているところを助けてもらったからといって、人は単純にその人と一緒に暮らそうなどという気持ちになったりはしない。しばらく寝食を共にしたとしても、継続するかどうかはまた別の話である。
いろいろなことを積み重ねてきて、二人の生活がある。
全ての事柄を説明されたわけではなくても、それはみのるにもわかった。
それはどこか、何故みのるのお母さんは霧江ゆらで、お父さんが染野閑なのかと問うのに似ていた。
つたない言葉でそんなことを伝えると、リチャードは穏やかに微笑んだ。
「本当にその通りですね。思いもよらないような偶然が様々に積み重なり、文模様を描いた結果、私と正義はここでこうして暮らしている。そうはならない未来もあったでしょう。それはもう、たくさん、あったことでしょう。ですが私は……いえ、私たちはこの形を選んだのです。都度、望む形を選んできたように思います。その選択が十年分積み重なって、今ここにあるのです」
リチャードは微笑んでいた。
みのるは途方もない気分になった。十年分の選択。みのるは十四歳である。十年前は四歳だった。そこから過ごした十年間で、一体自分はどんな選択をしただろうと考えたが、正義とリチャードほどダイナミックな選択をしたようには思えなかった。お母さんと一緒に量販店に服を見に行った時、紺色と黄色の服どっちを選ぶか、大安売りになっているおかずのどちらを選ぶか、あるいは中学校に行くか休むかなどが関の山である。
「……大人になるのって、すごいことですね。自分で自分の人生を、作れるんですね。選択を繰り返して、好きな形にできる」
リチャードは微笑んだ。一口、ロイヤルミルクティーを飲み、静かに口を開く。
「確かに、成長は尊いものです。大きくなるという言葉が表しているように、背は伸び、以前に比べれば遠いところまで手が届くようになります。しかし選択を行い、自分自身の人生を形作るのは、何も大人の特権ではありません。子ども時代にもそうであるべきなのです。そして大人は、子どもが自分の望む選択をとれるよう、支え、見守る義務がある」
「………………」
義務。確かに福祉施設の人も、みのるに過去そんなことを言っていたような気がした。だが実際のところ、もし誰かが――というか中田正義のような人間が目の前に現れて「さあ、何でもしていいですよ」というようなことを言ってくれたとしても、みのるがいきなりばりばりと立派な選択ができるようになったわけではない。
確かに住む場所は変化し、万引きを考えるようなこともなくなり、お母さんは病院に入院して少しずつ体がよくなっているそうだったが、いきなりみのるが大発明をしたわけではないし、みのるが宝石商になったわけでもないし、みのるがお母さんを助けたわけでもない。
全ては大人の選択の結果であるように思えた。
みのるはただ、正義たち大人が動かしてくれるベルトコンベアーの上に、ぼーっと載っていただけである。
クラスの他の子たちも大多数はそうである気がした。もちろん良太も。
みのるの回りで唯一、自分の人生にまつわる選択をしているように思えるのは。
「みのるさま?」
「……友達のことを思い出してました。『自分の望む選択』をいっぱい決められる子で、すごく格好よくて、僕とは全然違います。だから、すごいなあって」
「みのるさまにとって、自分の望む選択をすることは『すごい』ことなのですね」
「そう思います」
「ではみのるさまも、十分に『すごい』ことになります」
「え?」
リチャードは少しだけ身を乗り出し、じっと上目遣いをするようにみのるを見ていた。青い瞳がほんの少し、細くなる。
「『今日も生きること』を、日々選択なさっている」
「………………」
「それはすごいことです。素晴らしく、パワフルなことですよ」
「そうなんでしょうか?」
「はい」
リチャードは微笑みながら、力強く頷いた。
変なことを言われたという気はあまりしなかったが、当たり前のことを褒められてしまったとは思った。
しかし少しだけ思い出の中に深く潜ると、みのるはその『当たり前』が確かに『選択』であった時期を思い出した。『しない』を選んだかもしれない自分の姿が蘇る。あまり思い出したくない、だが確かな黒い帯のような時間は、確かに記憶の中に存在した。
「…………」
そう考えると、確かに自分も大きな選択をしているのかもしれないと、みのるは思った。毎日、学校に行ったり。授業を受けたり。友達と話したり。お母さんのお見舞いに行きたくて行けなかったり。時々ハンバーグを作ったり。
その全てが選択であるのだとしたら、この世界には数えきれないほどの選択が溢れているに違いなかった。
リチャードと正義の間には、それが十年分積み重なっていて、その中で一度も、彼らは『一緒にいない』という選択をしなかった。
それもまた『素晴らしく、パワフル』なことであるように、みのるには思えた。
「みのるさま?」
「あっ、いいえ……」
何と言ったらいいのかわからずもだもだしているうちに、玄関扉の向こうに人の気配がした。すぐにオートロックの扉が開き、正義が姿を現す。
「ただいま! 遅くなってごめんね、渋滞につかまっちゃって」
「おかえりなさい、正義。待ちくたびれてみのるさまとプリンの会を開いていましたよ。残念ながらあなたのプリンは残っていません」
「そんな会があったのか? 参ったなあ、もっとたくさん作り置きしておけばよかった。最近バタバタしてたから、あと一つ二つだけだったんじゃないか。みのるくん、足りた?」
「足りました! おいしかったです!」
「私には『足りた?』と尋ねて下さらないのですか」
「二つでお前に十分だったはずがないだろ。質問しなくてもわかるよ」
リチャードがふんと鼻を鳴らすと、正義は楽しそうに笑った。
真鈴と約束をしていることなどおくびにも出さない。
冷凍されていた鶏肉のクリーム煮と、あたたかなオニオングラタンスープの食卓を囲みながら、みのるは正義とリチャードの顔をいつもより長く見つめていた。二人の間を行き交う優し気な表情や、話し声のトーン、相手の考えていることを読み合うゲームのような間、微笑みの深さなどを。
素敵だなと思う一方、みのるはどこかで少し寂しくなった。頭の中を、さらさらした黒い髪の残像がよぎっていった気がした。
【つづく】