宝石商リチャード氏の謎鑑定 比翼のマグル・ガル 第一回
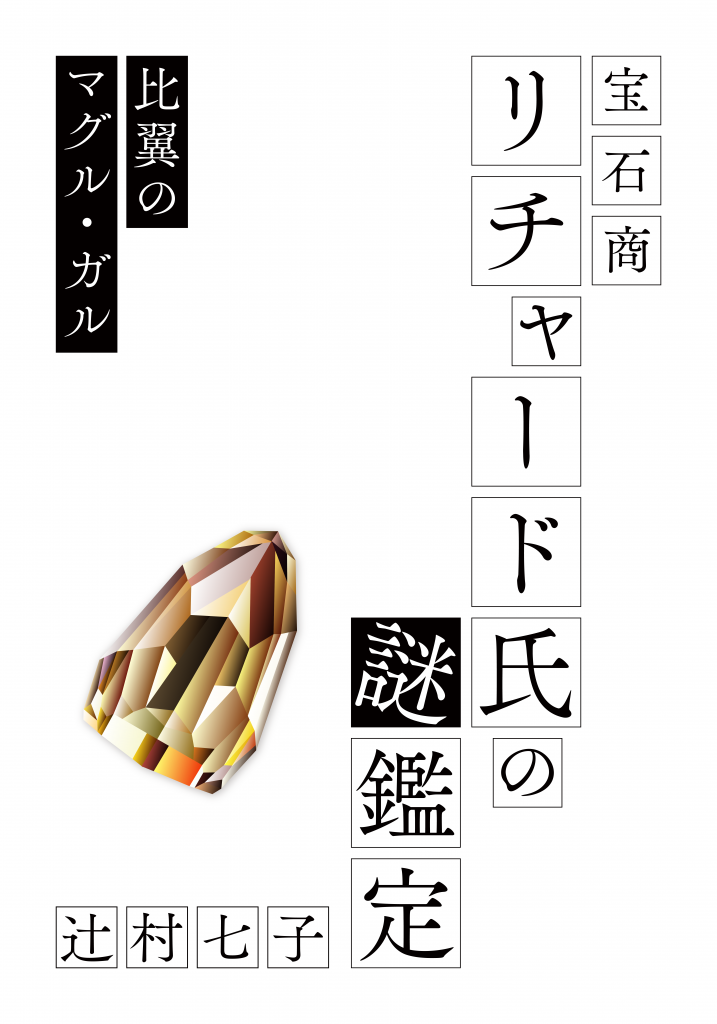
1 さよならとカフスボタン
東京駅にある東北新幹線のホームは、東海道新幹線のホームのすぐ近くを走っていた。何度か近くを通ったことがあるはずだったのに、みのるは路線がそこに存在していることすら知らなかった。
新横浜駅から東京までやってきて、盛岡行の緑色の新幹線に乗り換える。
学校は休んだ。
朝ごはん代わりの駅弁を何か買って、正義の隣の席で食べたが、みのるにはおいしさがよくわからなかった。味のことを考える余裕がなかったのである。
お父さんがいる。
盛岡にお父さんがいるのだと。
みのると正義はそう、伝えられたのだった。
最初はフランス語で話そうと言っていたジェフリー・クレアモントは、正義が「この話はみのるくんも一緒に聞いたほうがいいと思う」と言うと、改めて日本語で告げた。『染野閑の消息がわかった』と。
それがみのるの父の名前だった。
懐かしいはずの名前は、みのるの中でいつの間にか一行の記録のような存在になっていた。しばらく一緒に暮らしていた人の名前であるはずなのに、あまりにも遠い存在になりすぎていて、そもそも人の名前という感じがしない。そんな名前の何かがあったな、くらいの感覚になっていた。
しかし間違いなくその名前は、みのるの大切な、とても大切な人をさす名前だった。
三時間、窓の外の景色を無言で眺めているうちに、新幹線は盛岡に到着した。岩手県の県庁所在地、とみのるは頭の中で呟いた。社会の授業で暗記させられた地名である。何で今そんな遠いところにいるんだろうなどと考えている間に、みのるはきれいな駅舎の外に出た。東京より少しだけ、空気がひんやりしていた。
駅からタクシーに乗り、盛岡城跡と書かれた公園の脇を通り抜けて、目的地に到着する。大きな灰色の建物だった。
受付で正義が事情を話すと、すぐに案内の人が出てきた。
お待ちくださいと言って、どこかへ小走りに去ってゆく。
十五分ほどソファで待っていると、同じ人が戻ってきた。
「お待たせしました。こちらです」
大きな警察署の地下の空気は、駅の外よりもいっそう、ひんやりとしていた。
エレベーターで地下へ降り、長い廊下を歩き、みのると正義はがらんとした部屋に案内された。
他には何もない部屋の中に、布をかぶせられた何かが一つ、置かれている。布の下の物体はでこぼこしていた。
人間の体である。
案内をしてくれたのとは別の人がやってきて、正義とみのるの顔を見てから、よろしいですかと何故か確認をとった。どうぞと正義が促すと、そっと布を持ち上げる。男の人が寝ていた。
死んでいるのだった。
肩のあたりまで布をめくりあげられた男の人は、眼を閉じて眠っているようにも見えた。二人を案内してくれた警察官が言う。
「身分証明書のようなものはお持ちではなかったのですが、生前に話したという数人にうかがったところ、『しめのひさし』というお名前の確認がとれました。近隣の出身ではなく、関東地方からやってきたと話していたとも」
淡々とした言葉が、微かなドライアイスの煙と共にみのるの頬を撫でていった。耳から頭にうまく意味が入らない。それでも何を言われているのか、言葉としては理解できた。他にめぼしい情報はなく。親族の方と名乗り出る方もおらず。四日前の朝、公園の池で発見されました。酩酊中の溺水であったようです。第一発見者は早朝のランナー。
「こちらの男性は、お知り合いの方に間違いありませんか」
みのるはちらりと隣の正義を見た。正義は静かに、眼を閉じた男性の顔を眺め下ろしている。
正義が何と言うのか。
口が動く様子を、みのるは無言で見守った。
短い沈黙の後、正義は簡潔に喋った。
「はい。これは自分の父です。染野閑、本人に間違いありません」
正義がそう言った瞬間、みのるはどこか別の場所にいる自分が、暗い谷底に突き落とされたような気がした。
遺体は荼毘に付された。火葬という意味の言葉である。お坊さんが呼ばれ、お経の後に遺体は焼却炉に入れられ、骨になった。正義とみのるはお骨にも手を合わせ、箸で骨をつまんで小さな骨壺に移した。
全ての事は「これは本当に現実なのかな」「夢じゃないのかな」とぼんやり思っているうちに過ぎていった。
火葬場と葬儀場が一緒になった施設から出た時には日が暮れていて、二人は念のためとっておいた駅前のビジネスホテルにチェックインした。
正義とみのるは別部屋である。
プライバシーの問題があるからなどの言い訳はなく、正義はみのるに「ちょっとごめんね」と言い置いて、別の部屋を取ったのだった。一人になりたかったらしい。
みのるは多少混乱した。正義に見捨てられたとは思わなかったが、自分が誰かと一緒にいたいのか、それとも一人になりたいのか、それすらもわからない時、正義が勝手にそれを決めてしまったからである。いつもの正義ならそんなことはしない気がした。みのるにはよくわからなかった。何もかもがよくわからなかった。よくわからないままに時間が過ぎ、場所が変わり、いつの間にかみのるのお父さんは死んでいた。
死んでいた。
お父さんが。
既に骨になっていた。骨壺は正義の部屋にある。
死んでいるということはもう動かないということなので、もはやお父さんとお母さんが再会し「三人で暮らそうね」と言ってくれることもない。みのるのことを抱きしめてくれることもない。一緒に遊んだり海に行ったりすることもなければ、ごはんを一緒に食べることもないのだった。二度と、永遠に。
多分それは悲しいことなのだと、みのるは頭で理解し、少しだけ泣こうとも試みたが、うまくいかなかった。自分はかなりかわいそうな境遇になってしまったんだから涙を流すくらいは自然なことなのではとも思ったが、理詰めで考えてみても鼻水すら出ない。
みのるは自分自身の体が、遠い他人になったような心地になった。
ロボットを操縦しているような気持ちのまま、ホテルの狭いユニットバスに入り、歯を磨き、ベッドでぼんやりしていると、隣の部屋から声が聞こえてきた。
正義の声である。ホテルの壁は薄いようだった。
電話の声が聞こえてくる。相手はリチャードさんかな、とみのるは思った。
耳を澄ますまでもなく、声は耳に入った。正義はいつもより少しだけ声が大きく、もしかしたらお酒でも飲んでいるのかもしれなかった。非常に珍しいことである。
みのるは目を閉じ、正義の声に耳を傾けた。
「うん…………うん。本人だった。間違いなかったよ。火葬まで終わってる。戒名もつけてもらった。骨を持って帰る」
持って『帰る』、という言葉に、みのるは会話の相手がリチャードだと確信した。明日の朝の新幹線で帰るので、中学校の午後の授業には間に合うだろう、とも。ああそうだ明日も学校はあるんだ、とみのるはぼんやり考えた。お父さんが死んだことよりも、学校の風景や良太や真鈴の声の方が何百倍も現実味があった。
その後しばらく、正義は沈黙し。
もう電話は終わってしまったのだろうかとみのるが思い始めた頃、再び喋った。
「うん。よかったと思ってる」
みのるは目を見開いた。
『よかった』とは?
一体何が?
正義は実の父親の顔を認識していた。間違いありませんと言い、遺体の引き取り書類にサインまでした。だから本当に、正義は実の父親の死を目の当たりにしているのである。今日一日のうちに何かよかったことがあるとすれば、盛岡までやってきてきれいな景色を見られたことだけだった。少なくともみのるの感覚では、父親の死と比べておつりがくるようなものは一切ない。
それが『よかった』とは?
正義は喋りつづけた。
「うん。確かに……再会できなかったことはつらいと思う。でも………………会えたらそれだけでいいってものでもないだろう…………ああ、借金があったらしい。でも公的な場所から借りていたわけじゃなくて………………うん。俺はもう、何もしないよ」
みのるの心臓は嫌な早鐘をうちはじめた。
再会できなかったことはつらいと思う。でも会えたらそれだけでいいというものではない。
つまり正義は、みのるがお父さんに会えなかったことを、『よかった』と言っているのではないか。
みのるの頭はそう考え始めた。
正義はそれからも、みのるの仮定を裏付けるようなことをちらほらと喋った。どこかで死んでいる可能性があるとは思っていた。でもそれがここだとは思わなかった。どうして岩手に来たんだろうな。理由なんてないのかもしれない。それもよかったのかもしれない。会わずに済んだから。
どうやら正義は、みのるをお父さんに会わせたくなかったようだった。
みのるの心臓はいっそう早鐘をうちはじめた。わけがわからない。何故そんなことを言うのか。何故自分にお父さんを会わせたくなかったのか。正義は何を知っているのか。何を知っているつもりでいるというのか。みのるとお父さんの何を。
みのるは少しずつ、自分の心と体が重なり始めているのを感じた。ぐらぐらしたものが胸の奥にあって、それが溢れそうになっている。明日は朝早い新幹線に乗る予定である。もう眠らなければならない時間なのはわかっていた。だが目が冴えて仕方がない。
再びの長い沈黙の後、正義はぽつりと喋った。
「会いたい。すぐ会いたい」
みのるにはそれが、リチャードに対する声であることがわかった。本当に緊急性のある声ではなく、どこか甘えたような、大切な人によりかかるような声である。
回線はそのまま切れたようだった。
今日はきっと眠れないと思いながら、みのるはベッドにうつぶせになり、予想に反してすぐに眠りに落ちた。緊張していたのと体力を消耗したのとで、体が動かなくなったらしい。
朝になると、体は少し楽になっていた。
だが心は、勝手に晴れてはくれなかった。
ホテルでおにぎりと味噌汁の朝食をとり、二人は再び新幹線に乗った。今度は東京行きである。正義は往路にはなかった小さな紙袋を携えている。中に入っているのは骨壺だった。
新幹線の三人掛けの、窓側の席に荷物――骨壺も――を置き、みのるは席の真ん中に、正義は通路側に腰掛けた。二人とも買うのを忘れたので駅弁はない。みのるも正義も、少しずつ相手が平常モードではないことを理解していたが、だからといって相手を気遣う余裕はなかった。
正義は穏やかに喋った。
「ゆうべは、眠れた?」
「はい」
「そっか」
その後も正義は、何か当たり障りのないことを質問してくれたが、みのるは「はい」「はあ」以外の言葉で答えることができなかった。
正義とうまく口がきけなかった。
昨夜漏れ聞こえた電話の言葉が、巨大な骨のように喉の奥に引っかかっている。
よかったとは? どういうことなのか? みのるは新幹線の中でドカドカと足を踏み鳴らして暴れたかった。こっちはもう永遠にお父さんと会えないのに、正義は物心ついた後にも会えていたからいいようなものの、自分にはもう永久にお父さんと喋ったり微笑みかけてもらったりするチャンスはないのに、それが『よかった』とは一体どういうことなのか?
そんなに勝手なことを言う人だなんて思わなかった、と。
だが他でもない正義が、そんなことをするからには、何か大きな事情があるのであろうことも、みのるは朧に理解していた。全く意味のない意地悪である可能性などない。正義はそういう人間だった。
そうとわかっていても、怒りは消えない。
みのるが俯き、膝の上で手を握ったりほどいたりしていることに気付くと、正義はそれ以上話しかけようとはしなかった。
一つ目の駅を通過したあたりまで黙った後、ぽつりと問いかける。
「昨日、俺の電話の声が聞こえた? うるさかったかな」
「いいえ」
みのるはそれだけ言い、数秒後に後悔した。「聞こえませんでした」と言えばごまかせたかもしれなかったが、「いいえ」は駄目である。これで正義は自分が何に腹を立てているのかわかってしまったはずである。みのるは少し後悔し、同時にほんの少し、嬉しくもなった。正義が罪悪感を抱くかもしれない。
自分がそう思っていることに気づいた瞬間、みのるは慌てた。こんなによくしてもらっている人なのにそんなことを考えるなんておかしい、やめろ、なんならもう謝れ、と理性は怒鳴っていたが、みのるの感情の部分はスンとしたままそっぽを向いていた。ただただ正義に腹を立てていて、それ以外の感情が何も湧いてこない。仮に今すぐ正義が「ごめん」と言ってくれたとしても、みのるは自分が「気にしないでください」と言えるとは思わなかった。
途方もない怒り、あるいは怒りと混じり合った何か他の感情が、腹の底で煮えたぎっていた。もはやみのるの理性ではコントロール不可能なほどに。
正義はしばらく黙った後、ぽつりと呟いた。
「そういえば俺は……みのるくんに、自分の父親との話を全然しなかったね。でもそれは、偶然じゃなくて、あまり聞いてほしくなかったからなんだ」
「どうしてですか」
「楽しい話じゃなかったから。俺にとってはつらい思い出だった」
みのるは黙り込んだ。
ある程度は予想していたことだった。もしみのるのお父さんが聖人のような人で、とっても優しくて楽しくて素晴らしい人であったなら、正義はもっとお父さんの話をしてくれたであろうし、必死で探す素振りを見せたはずである。だがそうではなかった。本当にろくでもない人だったのだ、とみのるは思った。単なる自分の仮説との答え合わせだったので、そこまでの驚きはなかった。
だがろくでなしであろうが何であろうが、お父さんはお父さんである。そもそもみのるのお母さんも、なんならみのる自身でさえ、ある程度のろくでなしではあるだろうとみのるは思った。
染野閑は、みのるのたった一人のお父さんだったのである。
みのるの前ではそれだけが、たった一つ確実なことだった。
いよいよ強く拳を握りしめると、正義はそっと、その手を握ろうとした。
みのるはその手を撥ね退けた。
自分でもびっくりするような素早さだった。
正義は驚きもせず、かといってもう一度手を握ろうともせず、静かに喋った。
「……ごめん。俺のやったことは、かなり嫌な感じがするよな。俺がみのるくんの立場だったら、知っていることは全部話してほしいし、自分のお父さんの話なのに何を勝手に判断してるんだって怒ると思う」
その通りだった。だからそのことについて何か、何でもいいから何かを言ってほしかった。
だが。
「でも俺は、自分のやったことについて後悔していないんだ。完全な俺の勝手だけれど、よかったと思ってる」
正義の言葉はみのるの想像を超えていた。いつもの正義ではない人のようだった。みのるの口は勝手に動いた。
「ひどいです」
「俺もそう思う。ごめん」
ごめんと言いつつ、正義の声にはいつものような謝罪のニュアンスがなかった。自分のことを悪いと思っていない人が謝るとこんな感じの声になるのだと、みのるは生まれて初めて知った。
巨大な壁の前に立たされたような気分だった。
正義は持参した革鞄を開き、宝石箱を取り出した。リチャードや正義の仕事道具の中でよく見るサイズよりも少し大きく、かぱりと蓋を開けると、ジュエリーが二つ入っていた。
二つの青紫色の石。
何だろうとみのるが思うより先に、正義は解説した。
「カフスボタン。これはタンザナイトって石なんだ」
「タンザナイト……カフスボタン?」
「ワイシャツを着る時に、袖のところにつける飾り。フォーマルな場所で使う」
意味不明だった。そんなものが今出てくる理由も、袖のところにつける飾りがあることも、タンザナイトという名前も。この状況には全く何の関係もない。
仮に正義がこれを自分にくれると言い出したとしても、怒りは絶対に収まらないだろうし、勢い余って蓋を閉じてしまうかもしれないと思いつつ、みのるは目を閉じて首を横に振った。正義が優しくため息をつく。
「これは、俺の大事な人からのプレゼントなんだ」
「……リチャードさんですか?」
「リチャードは見立ててくれた人かな。贈ってくれたのは別の人」
「………………」
「俺にとってはお守りみたいなジュエリーなんだ」
お守り。
おかしな話だった。お守りというのは神社などで授けてもらうもので、それは受験や就職や安産など、何か強くお願いしたいことがある時に使うもので、そうでない時にはほとんど存在意義のないものであるように思われた。
それなのに何故、今、正義にお守りが必要になるのか?
正義はみのるを見ずに喋っていた。ただタンザナイトとやらのカフスを見て、ぽつりぽつりと喋る。
新幹線がトンネルに入る。
窓がちらりと目に入り、みのるは驚いた。
みのると正義が、よく似た表情をしているのである。
表情の薄い、どこかのっぺりとした、何かを必死で抑えているような顔を。
窓に映った顔には気づかず、正義は喋った。
「俺は……今日、ここに来るのが、とても怖かった。本当に怖かった。おとといはほとんど眠れなかったくらいだ。でもみのるくんが一緒にいてくれたから……俺は頑張れたと思う。何を頑張るんだって話だよな。でも本当に感謝してる。ありがとう。勝手なことをたくさん言ってごめん」
「…………いいえ……」
そういえばあの人は、正義のお父さんでもあったのだと、みのるは今更気づいた。
正義も昨日、お父さんを失ったのだった。お父さんの死体を見て、お父さんが死んだことを受け止めたのだった。
そうと思い出した瞬間、みのるが正義に向けていた怒りは、一斉に剣になって戻ってきた。自分は何て愚かなことを考えていたんだろうというレベルではない罪悪感と苦しみで、みのるの胸は爆発しそうになった。
正義はみのると同じなのだった。少し年が大きいだけで、同じ境遇なのだった。
みのるは盛岡行が決まってから初めて、泣きそうになった。ただその中に含まれている感情が、ただの正義に対する申し訳なさだけではないこともわかっていた。悲しかった。苦しかった。寂しかった。怒りもまだあった。何より心が疲れていた。
正義はそっと、宝石箱からカフスボタンを一つ、取り出し、みのるに差し出した。みのるが顔を上げると微笑む。
「あげないよ。でも握ってみるといいと思う。こういうものを握ると、心が落ち着くことがあるから」
そう言って、正義もカフスボタンを一つとり、右手に握った。
みのるも左手で手に取り、握る。ころっとしていた。
どちらからともなく、残った二つの手を、正義とみのるは無言で握り合った。
東京駅に到着すると、みのると正義は腹ぺこだった。正義は骨壺と鞄を携えたまま、東京駅をすたすたと歩く。
「早急に何か食べよう! 昔はこのあたりにおいしい葛切りを食べさせるお店があったんだけど、随分前になくなっちゃったからなあ。みのるくん、ラーメンとハンガーガーとお寿司だったらどれがいい?」
「はっ、ハンバーガーがいいです」
「決まりだ」
正義は迷わずに駅の中を歩き、アメリカ風のハンバーガーショップにみのるを連れていった。名物のバーガーが巨大で、ベーコンと卵とアボカドとトマトがいっぺんに食べられるという。当然のようにポテトの盛り合わせもついてくる。視覚が空腹感を連れてきた。みのるは目の色を変えてバーガーにかぶりつき、ポテトをぱくついた。写真を撮って良太に送ってあげたら羨ましがるだろうなと思いついたのは、皿が空っぽになった後だった。
「ごちそうさまでした……」
「ごちそうさまでした。あと一時間もしたら、リチャードが新横浜駅あたりに来るはずだ」
正義はにこりと笑った。盛岡行が決まってから久々に見る、『いつもの』正義の笑顔だった。お腹がいっぱいになったこともあり、みのるは久々に安心した。非日常の緊張感から少し解放されたような気がした。
きっと時間がかかるのだ、とみのるは思った。
お父さんが死んでしまったこと、正義がお父さんの話をしなくてよかったと思っていること、その他のいろいろなことを受け止めるのには、それなりに長い時間が。もしかしたら一か月や二か月ではなく、年単位の時間がかかるのかもしれなかった。お母さんの病気と同じように。
ぼんやりとした気分のまま、みのるは正義と共に東海道新幹線で新横浜駅まで向かい、リチャードの運転する青い4WDに乗り込んだ。正義は助手席に、みのるは後部座席に。車はぎゅんと加速し、みのるの中学へと走る。予定通り午後の授業には間に合いそうだった。
みのるは助手席の正義と運転席のリチャードの頭を眺めた。二人は何も言わなかったが、いつものようにあたたかな空気が漂っている。カーステレオからは小さな音量で何かのオペラが流れていた。正義の好きな音楽で、車が到着した時には既に再生されていた。囁くような声色の、細い女声である。みのるにはそれがリチャードの優しさの声のように思えた。
「それではみのるさま、どうぞお気を付けて」
「いってらっしゃい」
二人に見送られながら、みのるは校門をくぐり、いつもの教室に踏み込んだ。昼休みである。待ち構えていたように、良太が両腕を広げて笑う。弁当は食べ終わったようだった。
「おお、心の友よ!」
「何それ」
「アニメでガキ大将キャラがよく言ってるじゃん。『心の友よ!』って。いやもちろん俺は、お前の心の友だから言ったんだけどさ。でも心の友ってぶっちゃけ何だと思う?」
「わかんないのに言ったの?」
みのるは思わず笑ってしまった。良太も笑う。廊下には真鈴が立っていた。ほっとした顔で教室に踏み込んできて、良太の座っていた席にすとんと腰を下ろす。
「登校してくれてよかった。昨日いきなり『今日明日は学校にいけないかも』って連絡があったから、大怪我でもしたのかと思ってた。一応は元気そうだね。ほっとした」
真鈴はつややかな黒髪をかきあげ、大人っぽく笑ってみせた。教室の遠くの方で誰かがため息をつく。相変わらず真鈴は美しい少女で、大人びていて、格好よくて、特にそういうこととは関係なくみのると良太のスーパー親友だった。みのるが苦笑する。
「心配かけてごめん。いろいろあったけど、怪我や病気じゃないから大丈夫だよ」
「詳しく話さなくていいからね。君はいつも気を遣いすぎ」
「そうそう! まあ俺の予想だと、プロ野球観戦のために遠くに行ったって感じなんだけど」
「馬鹿すぎ。そんな理由じゃないのはわかってるでしょ」
「あのなあ真鈴、俺だってなあ、俺なりにみのるを励まそうと思ってだなあ!」
「そろそろ移動教室の準備をしないと間に合わないんじゃないの? それじゃあまたね」
真鈴はすたすたと大きな歩幅で教室を去ろうとし、最後に思い出したように振り返った。黒い髪が絹の帯のように揺れる。
「みのる」
みのるは少し驚いた。真鈴の声がいつもとは少し違うように聞こえたのである。
「……何?」
「今度、中田さんに会えるようにしてくれない?」
二人きりで、と。
みのるはため息をつきたくなった。また今までと似たようなことを続けるのかと、どんな言い回しながら真鈴を怒らせずに言えるだろうと思い、真鈴の目を見て、たじろいだ。
真鈴は真剣な瞳をしていた。
おどけたり、わくわくしたり、ときめいたりしているのではなく、刃のように真剣な瞳を。
冗談ではないのだと気づくのに、十分な眼差しだった。
みのるはただ頷き、真鈴に承諾の意を伝えた。真鈴もそれで理解したように微笑し、去ってゆく。良太だけが怪訝な顔をしていた。
「ん? どした、みのる?」
「…………何でもないよ」
みのるは小さく首を振り、ふたたび良太と話し始めた。実はさっき東京駅で大きなハンバーガーを食べたということ。それが顎が外れそうなくらい大きかったということ。ポテトもいっぱいついてきたこと。思った通り良太は画像を見せてくれとせがんだ。
いつもの場所、いつもの声、いつもの友達。
心のどこかに、癒えない傷の気配を感じながら、それでもみのるは笑った。大きな悲しい出来事があった直後だというのに、友達と笑うことができる自分を、みのるはそれほど嫌いではなかった。
【つづく】