宝石商リチャード氏の謎鑑定 再開のインコンパラブル 第三回
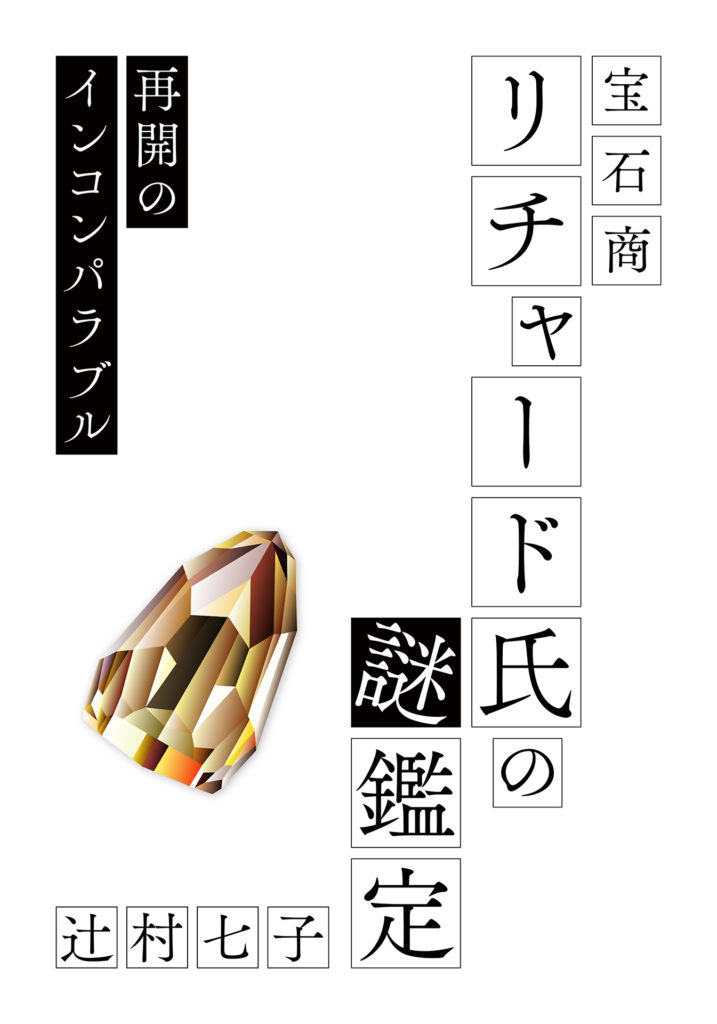
三話 タンゴ・コモ・ラーヴァ
十一月になってすぐの金曜日。みのるはリチャードから珍しい申し出を受けた。
神立屋敷が人手を募集しているという。
正義が前日から京都に出張している朝、ぱりっとスーツを着こなしたリチャードは、ジローとサブローを撫でてやりつつ、みのるに話を持ち掛けた。ヨアキムがまだ寝ているので、声は落としたトーンである。
「神立屋敷も片付いてきてはいるのですが、いらないものがいろいろと出てまいりまして。片付けのお駄賃とまでは申し上げませんが、よろしければお好きな方にお譲りしたいのです。とはいえフリーマーケットのようなことのできる場所でもありません」
なるほどとみのるは頷いた。とはいえそこで終わる話ならみのるに『人手を募集』などと言うはずもない。何となく話の成り行きを理解し、みのるは提案した。
「良太と真鈴に声をかけてみてもいいですか」
「願ってもないことでございます。片付けは来週の日曜日を予定しております」
来週の日曜日。偶然だろうか、とみのるは思った。その日も正義は出張で前日から留守にしている。
みのるが少し、訝しむような目を向けると、リチャードは首を傾げた。
「みのるさま?」
「あ、いえ、何でもないです。わかりました」
みのるが学校でその件を打ち明けると、良太は手を叩いて喜んだ。
「うひょー! あのお屋敷にまた入れるのサイコーだな! 仮面舞踏会の時のこと、俺今でも昨日のことみたいに思い出せるもん。多分一生忘れないな、あれは」
「他には誰が来るの? タヴィーも来る? 舞踏会で仲良しになった女の子のことだけど」
「わ、わからないけど、もしかしたら来るかも。でも正義さんはいない」
「なんだ……」
真鈴はがっかりした顔をしたが、でも諦めない、と言わんばかりに小さなガッツポーズを作った。
みのるはますます真鈴に申し訳ない気持ちが募った。
「……真鈴」
「何? みのる、顔が暗いよ。何かあったの。最近私と話す時、いつもそんな顔してる」
「お前がいつもブロッコリーばっか食べてるから心配なんじゃねーの? マジでもっと食べた方がいいって」
「栄養バランスは完全に管理してるの。事務所には栄養士さんもいるから、君たちよりよっぽど健康」
「だったらいいけどよお……」
みのるは何も言えず、適当に笑ってごまかした。真鈴は完全にはごまかされてくれなかったようだったが、それ以上追及もしなかった。
「じゃあ日曜日、二人とも参加だね。詳しい話が決まったらメッセージを送るから」
りょうかーい、と良太はおどけたポーズをとり、真鈴もにこりと笑って応じた。
日曜日。特に雑巾もほうきも持たず、『汚れてもいい服装』『荷物少なめ』の装備でやってきた三人が神立屋敷に入ると、広間の真ん中に誰かが仁王立ちをしていた。赤いバンダナをリボンのように頭に巻いた女性が、腕を組んで胸を張っている。
「よく来たな! これから始まるは掃除の饗宴! 心してかかるがいい!」
リチャードの元生徒だったという大学生、オクタヴィアである。三人とは仮面舞踏会で顔見知りだった。ラスボスのような口調で喋るオクタヴィアは、上下ともカーキ色のジャージ姿ではあったが、内側に着ているボウタイ付きブラウスが、何となく、というかかなり掃除には不似合いな高級品に見えた。リチャードの姿は見えない。
長い黒髪をアップスタイルにした真鈴は、オクタヴィアに寄りついてハグをした。
「タヴィー、久しぶり。元気だった?」
「マリリン! 元気だけど課題で死にそう。そっちも相変わらずだね。キム姉にダンス教えてもらったんだって?」
「そうなの。あ、キムさんとも知り合いなんだね」
「もちろんよ。そもそもあの人はリチャード先生の従兄の……おっと。この話はまだしないでおくわ、大人にはいろいろあるから」
「ふーん」
「ちょっと、誰かの口ぐせみたいなこと言わないで」
オクタヴィアは笑ったが、真鈴にはその冗談が通じないとわかると、ごめんなさいねと謝った。
広間の隅には、リチャードの言っていた『いらないもの』が並んでいた。年代物だがきれいに保存されているテディベア数体。大きなボトルの中に入った精緻な帆船の模型。毛足の長い糸で織られた手のひらサイズの敷物。ランプ。くるみ割り人形。
「うひょー! やべえ、この帆船ほしーわ。敷物系は母ちゃんが死ぬほどフィーバーしそう」
「これ全部、売ったら高いんじゃないの……ねえみのる、本当に私たちが来てよかったの」
「でも、リチャードさんがいいって言っていたから」
「お待ちしておりました」
いつものように二階から下りてくるのではなく、屋敷の給湯室側から出てきたリチャードは、スーツのズボンにワイシャツ、アームカバーに手袋という姿だった。これから掃除をしますという主張の強い服である。とはいえ相変わらず華麗な雰囲気を漂わせている。どうやったら掃除ファッションの中に気品が漂うのだろうと、みのるは頭をひねったがわからなかった。
「リチャードさーん! 久しぶりでっす」
「こんにちは。お招きいただきありがとうございます」
「良太さま、真鈴さま、ご無沙汰しております。こちらこそ、不躾な依頼をお聞き入れくださり、恐悦至極でございます」
挨拶を済ませると、リチャードは学校の先生のようにみのるたちにプリントを配った。時々正義が読んでいるミステリー小説の一ページ目のように、家の見取り図が描かれている。上からバツが書かれている部屋が幾つかと、マルが描かれている部屋が三つ。廊下にもマルが描かれている。
バツの部屋は立ち入り禁止、マルの部屋は入ってOKで掃除をしてほしい、とリチャードは説明し、その後みのるたちは分担を決めた。オクタヴィアは既に受け持ちの部屋が決まっているという。掃除の内容は埃とりとゴミ拾い程度でよし、どうしたらいいのかわからないものがあったり、トラブルが起きたりしたらすぐに知らせること。家にはもろい部分もあるので、必要な掃除道具は全て買い揃えてあるものだけを利用すること。
「それでは皆さま、よろしくお願いいたします。私は一階の掃除をしておりますので」
はーい、と四人は唱和した。
個々の部屋を分担して掃除、その後三人で廊下をするという段取りで、みのるたちはそれぞれ担当の部屋に入った。良太の呆れたような「うわー」という叫びが、みのるの、そして恐らくは真鈴の心境も代弁していた。
以前良太と神立屋敷に突入し、二階の天井裏に潜んだ際、部屋の広さはわかっていたつもりだったが、あの時には必死になっていて、部屋の中にどんな家具があるのか、壁紙がどんな風なのか等、細かいところを眺めている暇はなかった。
だが改めて観察すると。
淡い緑とピンクの小花柄の壁紙。やや色あせてはいるものの、細かな絵柄が幾重にも描き込まれていて、絵画のように繊細。
緩やかなカーブを描く濃い茶色の木材と、淡いグレーのクッションで構成された一人がけの椅子。そのセットとおぼしき同じ木、同じ布のソファ。鈍く輝く布で形作られた、大きな円柱形のクッション。
出窓にかかった二重のカーテン。カーテンを留めている金色の編み紐。そのライオンの尾のような房。
床板が若干、埃っぽいところを除けば、まるでお城の一室のようだった。
「こんなところ……本当に掃除していいのかな」
だから簡単な掃除でいいって言われてるでしょー、という真鈴の声が、壁ごしに返ってきた。古い家である。部屋と部屋のあいだの壁は薄いようだった。
ダラダラ掃除をしても意味がないので、みのるたちはリチャードに提案された通り、十五分のタイマーを二回セットした。三十分経過したら部屋の片付けがどれほど進んだのかを見て、残りの所要時間を考える。最初の十五分はあっという間に過ぎ、三十分もすぐに消し飛んでしまったが、ともかく作業は進んだ。
支給品の柔らかい布と羽ぼうきで受け持ちの部屋中を拭い、はたいて、ある程度きれいになったかなと思えたのは、一時間が過ぎた頃だった。廊下に出てきた良太は、うおーと唸りながら腰を叩いていた。
「腰がいてー! ひーっ、一生分掃除したー!」
「君の『一生分』短すぎ。ストレッチしたら? これから廊下の掃除もあるのよ」
「が、がんばるよ……」
三人がそれぞれの部屋から出てくると、誰かが階下でぱんぱんと手を叩いた。階段の上から顔を出すとオクタヴィアだった。
「みんなー! お茶の休憩の時間だよー! 手を洗って広間に戻ってきてー」
はーい、と答える良太を見て、小学生みたいと真鈴はぼやいた。三人はばたばたと洗面所に向かい、アンティークのような真鍮の蛇口から水を出して、泡石鹸できれいに手を洗った。
広間に入ると、いつものローテーブルではなく、仮面舞踏会の時に使われたのと同じ、やや背の高い大きいテーブルが引き出されていて、その上に五人分のケーキとロイヤルミルクティーのカップが置かれていた。オクタヴィアが準備してくれたらしい。
「さあどうぞ。お召し上がりになって。ランチはまだ先だけど、小休憩は必要でしょ」
「リチャードさんは……?」
「先生はあっちで電話中」
あっち、とオクタヴィアは管理人室に続く渡り廊下の方角を指さした。やっぱり二人とも仕事が忙しいから正義がいるいない等は関係なく、きっと今日しか選べなかったんだなと思い、みのるは少しほっとした。
掃除のためにそこらじゅうに散らばっている適当な椅子に座って、三人はオクタヴィアと共にケーキとお茶を楽しんだ。チョコレートケーキは甘さ控えめのタイプだったが、ロイヤルミルクティーは時々家でふるまってもらえるものと同じ、じんとしびれるような甘さで、バランスのいいおやつだった。
オクタヴィアは微笑み、三人を眺めてうっとりとした。
「懐かしいなあ。クリスマスパーティの準備をしてるみたい」
「タヴィー、クリスマスパーティが好きなの?」
「みんなでパーティの準備をするのが好きなの。寂しいのが嫌いだから」
「あ! わかる! 俺もみんなでわいわいする方が好き」
「あと、一応言っておくと、私、日本語で現地の人とこんなにおしゃべりするの、たぶん初めてなのよ。私の日本語の先生はみんな日本人じゃなかったから」
「リチャードさんも中田さんもそうだけどさあ、そんなにいっぱい色んな言葉を覚えてどうするんだろうな? 英語だけできれば何とかなるって、野口先生言ってたじゃん?」
「ああ、英世ね」
野口先生というのは一年の英語担当の先生である。もわっとしたヘアスタイルの男性で、苗字が野口なので、あだ名は真鈴が言った通り『英世』だった。
オクタヴィアは少し笑い、それはどうかなと呟いた。
「語学を勉強する理由って、リチャード先生みたいなところまで行くともう、想像が追いつかない感じはするけれど、誰しもみんな『外国で困らないようにするため』だけじゃないと私は思うな。日本語を勉強して一番面白かったのは、私みたいに英語やフランス語が母語の人とは、考え方が違うかもってわかる瞬間だった。みんな、頭の中で何か考える時も日本語で考えるでしょ? 私は英語かフランス語で考えるけど、絶対そのプロセスが違う」
みのるはオクタヴィアの言っていることが半分くらいしかわからなかった。良太は完全に『何言ってるのかわからない』モードの顔になっている。だが英語の得意な真鈴には通じるものがあるようで、うんうんと頷いていた。
オクタヴィアはハッとしたようで、おほんと咳払いをした。
「話をまとめるとね、言語学習には『自分じゃない誰かを理解したい』っていう、願いが含まれているような気がするの。それは自分の傍にいる大切な人かもしれないけれど、世界の裏側で暮らしている違う国の人かもしれない。私の出身地はスイスで、ここから飛行機で十時間以上かかるのよ。そんなところに生まれた人が、日本で友達を作ってケーキを食べてるんだから、本当に言葉って、すごいのよ」
「凄いのは言葉じゃなくてタヴィーの努力だと思うけどなあ」
「ありがとうマリリン。でもあなた、『努力は人間の最低条件』って、前に会った時に言ってなかった?」
良太はわざとらしく絶望的な声をあげ、椅子から転がり落ちて床に突っ伏した。俺は人間じゃなかったのかー、という呻き声に、真鈴とオクタヴィアが笑う。みのるはいたたまれなかったが、オクタヴィアは再び口を開いた。
「逆に言うなら、みんなちゃんと生きてるでしょ。それだけで努力してるのよ。ただまっすぐ立っている時にも体中の筋肉が緊張してるのと同じで、生きてるのって凄いことなんだから、胸を張った方がいいわよ」
そう告げるオクタヴィアの目に、みのるは透明な影のようなものを見た気がした。
生きているだけで、つらい。生きているのが嫌になってしまった。
日々そう思っていた頃の自分自身が、瞳の奥にいる気がした。
飛行機で十時間以上かかるようなところに住んでいた人に、どうしてそんな感覚を覚えるのだろうと、みのるが不思議な気持ちになった時。
音楽が聞こえ始めた。
ズンズン、ズンズン、というリズムと、アコーディオンのような甘い音色が特徴的な、異国情緒の漂うBGMである。
「あら?」
「なんか鳴ってるな」
「……タンゴね。これは『ラ・クンパルシータ』」
「真鈴、お前ほんと物知りなところとダメなところのギャップが激しいよな。アンモナイトも知らなかったのに」
「うっさい。昔のCMで流れてた曲でしょ。動画サイトで見たことある」
「お待たせいたしました」
管理人室の方角から、リチャードが戻ってきた。
胸には大きな金色の花のようなものを抱いている。らっぱだ、とみのるは最初思ったが、すぐに違うとわかった。吹き口にあたる部分が、箱にくっついているからである。音楽はそこから流れ出していた。
良太が声を上げた。
「わあー! リチャードさん、それ何ですか?」
「こちらは蓄音機という機械です。手巻き式ですので、電源に接続していなくても動きますが、ねじが切れると止まってしまいます。長くて一時間程度でしょうか。老朽化が進んでいる今、どの程度ねじが保つのか知りたいのです」
蓄音機の木箱の部分には、何か灰色の石っぽいものがはめ込まれていた。ダイヤモンドとは程通い、どちらかというと乾燥した粘土のような雰囲気だが、よくよく見るときれいな形が彫り込まれている。この蓄音機は一体幾らする品物なのかと、みのるは気が遠くなりかけたが、良太はただはしゃいでいた。
「何かすげーのが来たなあ! 真鈴、蓄音機って知ってる? 俺初めて見た」
「レコードをかける機械でしょ、知ってるよ、社長が好きでたまに聞いてる」
「俺レコードも知らねえ……」
「えっ……あなた、レコードを知らないの。ごめんちょっとショック」
「だ、大丈夫ですか、オクタヴィアさん。疲れたんですか……」
「そういうことじゃないの、ちょっとエイジのギャップを感じてね」
リチャードは蓄音機を空いている椅子の一つにぽんと置くと、手袋を外して胸ポケットに入れ、ケーキと紅茶に手を伸ばした。
みのるは奇妙に胸がざわざわした。ズンズン、というリズムのタンゴが流れ続けているせいかもしれなかった。椅子のない開けた場所で、真鈴はひとり、踊り始めた。
「あらマリリン、タンゴが踊れるの」
「ダンスは一通りやってるから。でも社交ダンスはほんの少しだけ」
「教えるわ。一緒に踊ってよ。タンゴは女同士でも男同士でも踊れるダンスよ」
そして真鈴はオクタヴィアの肩に手を置き、オクタヴィアは真鈴の腰を抱いた。せーの、という真鈴の合図で、四本の脚が動き始める。靴がステップを踏む。
掃除のための格好をしているのが惜しいほど、二人は颯爽とフロアを踊りまわった。途中でお茶とケーキを食べ終わったリチャードが、残りの椅子をきれいに広間の右と左に置き分ける。広間は舞踏のためのフロアになった。
タンゴが流れ続け、三曲ほど続いた頃、二人は息継ぎをするように停止し、それぞれ椅子に腰かけた。
「ふー! 楽しかった! タヴィー、上手だね。こういうのも勉強したの?」
「先生と中田さんがブエノスアイレスで同棲してた時、ちょっとだけお邪魔したのよ。その時お二人でよく踊ってたから、私も交ぜてもらって、三人で交代交代踊ったわ。ブエノスアイレスはいいわよ。きれいなところだし」
「……同棲って、同居のこと?」
「同居? 同居と同棲ってどう違うの?」
「友達とだったら同居、恋人となら同棲」
「え? じゃあ同棲でいいんじゃないの?」
みのるは一秒で心臓を握りつぶされた気がした。
タンゴは四曲目に差し掛かっていた。一体このレコードには何曲タンゴが収録されているのだろうと、みのるの頭は現状と著しく無関係なことを考え始めた。明らかな現実逃避だった。
真鈴は訝るような目をオクタヴィアに向け、オクタヴィアもしばらく似たような目をしていたが、ある瞬間に何かに気づいたように椅子から立ち上がり、両手で顔を覆った。
「……ごめんなさい」
困惑の顔をする真鈴に、オクタヴィアは弁解の言葉を重ねた。
「この前のパーティで、知ってると思ってた」
オクタヴィアはそれっきり真鈴を見て黙り込んだ。
真鈴は沈黙し、みるみるうちに青くなっていった。
みのるも黙り。
リチャードも黙っていた。
「え? え? みんな今、何の話してんの?」
良太はきょろきょろしながら黙り込んでいる面々を見ていたが、みのるは何も言えなかった。
真鈴は正義が好きで。
でも正義はリチャードが好きで。
それで二人はパートナーなので、他にそういう相手を作るつもりはないんだと。
真鈴は今それを、半分くらい知ったところなんだと。
そんなことをこの場所で口にできるほどみのるは恐れ知らずではなかった。
リチャードは立ち上がり、蓄音機に近づいていった。ズンズン、という音楽を止めようとしたらしい。
だがそれよりも早く、早足の真鈴が蓄音機に辿り着いた。
蹴り飛ばすのか、とみのるは思ったが、違った。
真鈴は蓄音機ではなく、針に手を伸ばしたリチャードに、自分の手を置いていた。
じっとリチャードの顔を見上げ、真鈴は低い声で告げた。
「……踊ってもらえますか?」
みのるはぞっとした。誰かのこんなに怖い声を聞いたことがなかった。脅すような声色というわけでもないのに背筋が粟立つ。どんな感情がこもっているのか、言葉で説明しろと言われてもできる気がしなかったが、ともかく何か、どろどろした黒い塊のような声だった。
リチャードはいつもと同じ、完璧な美貌の微笑みで応じた。
「喜んで」
新たなタンゴが始まった。
真鈴はリチャードの肩に手を置いた。オクタヴィアと真鈴で組んでいた時にはそれほど気にならなかったものの、成人男性のリチャードと組むと真鈴の小柄さが引き立つ。リチャードはそっと真鈴の腰に手を置き、リードした。
ステップを踏むたびに、真鈴はほとんど距離のない場所から、リチャードを突き刺すような眼差しで見つめた。
そういうことなんですか?
そういうことなんですか? と、問い詰めるように。
リチャードはその全てを涼やかな表情で受けていた。
まるで何も、問い詰められてなどいないかのように。
少し眺めているだけで、みのるにも明らかに二人の力量が違うことがわかった。真鈴のステップはどことなくぎこちないが、リチャードの足の運びは水のようになめらかで、火のように激しかった。それでいて上半身は揺るがず、唇には絶えず微笑みを湛えている。
五曲目のタンゴはすぐに終わり、六曲目が始まった。
二人の踊りは終わらなかった。
みのるの隣にやってきた良太が、ぼやくような口調で言った。
「真鈴、何で踊りまくってんの? そろそろ終わりにしてもらえばいいのに」
「……しないと思う」
「え? 何で?」
みのるにもわからなかった。だが真鈴は決して、自分から踊りをやめようとは言わない気がした。決して。
そしてリチャードも踊り続けていた。
みのるは急に怖くなった。リチャードはみのるの保護者の一人で、とても優しくて物知りでしっかりしていて、朝は時々寝坊するものの、それ以外の場所では完璧な存在である。みのるがそうと言わなくても疲れていると見て取れば、そろそろお休みになりませんかと言ってくれる相手だった。その完璧な常識人が、完璧な微笑みを浮かべながら、完璧なタンゴを踊り続けている。
それが怖かった。
六曲目のタンゴが終わろうとするとき、真鈴の脚が少しもつれた。リチャードが抱き起こそうとする前に、真鈴は自分で体勢を立て直した。
「まだ踊れるんで」
真鈴は踊る間、ずっとリチャードを睨みつけていた。瞳にこもる憎しみで人が殺せるのなら、真鈴はとっくにリチャードを殺していそうな気がした。だがその憎しみも疲れと共に徐々に薄れ、精一杯な頑張りばかりが前面に出てくるというのに。
リチャードの礼儀正しい表情は、いつまでも変わらなかった。
みのるは椅子から立ち上がった。
「みのる?」
「……音楽を、止める」
「え? 何で? 踊ってるのに?」
止めなければならないとみのるにはわかった。睨みつけられているリチャードが可哀そうだとは思わなかった。それは猫に爪を立てられている壁が可哀そうだというようなものである。
猫の爪が折れてしまう前に、何とかしなければならない。
みのるの中にある思いはそれだけだった。
蓄音機の止め方などみのるにはわからない。壊してしまうかもしれないと思うと怖かった。だが真鈴がこのまま壊れてゆくのを見るのはもっと怖かった。
何とかしなければ、とみのるが一歩踏み出した時。
誰かが蓄音機の後ろ、管理人室の側から広間に入ってきた。
最初に気づいたのはみのるだった。次に気づいたのは良太だった。三番目に真鈴が気づき、最後に気づいたのは背中を向ける姿勢で真鈴と踊っていたリチャードだった。
真鈴がステップを踏む前に、誰かがリチャードの手を取った。
バトンタッチ、とでも言うように。
「正義」
リチャードが呟いた時には、真鈴は正義の後ろにかばわれていた。
麗しい宝石商の手を取っているのは、今しがた広間に入ってきた中田正義だった。
停止されなかった蓄音機は、新しいタンゴを奏で始めた。
正義とリチャードは踊り始めた。
二人はオクタヴィアと真鈴のように打ち合わせをする必要などなく、ノータイムで静かに踊り始めた。真鈴と踊っていたリチャードのポーズは変わらないまま、正義がリチャードの腰に手を回している。
二人のステップは砕ける波のように素早く、たゆたう水のように穏やかだった。
くるくると回転しながら踊る二人の表情が、みのるには断片的に見て取れた。正義は怒っていた。何やってるんだ? とリチャードを問い詰めるような目をしている。他方リチャードは、何となく気まずそうに遠くを見ている。
ステップを介してコミュニケーションを取るように、二人の踊りは時に激しく、時におだやかになりつつ、絶え間なく続いた。
「すっげえなー……」
良太の呟き通り、『すごい』踊りだった。
真鈴はそれを棒立ちになって見ていた。肩で息をしているのを心配しオクタヴィアが後ろに立っているが、本人はまるで気づいていない様子で、踊る二人をただ見ている。
世界にただ、リチャードと正義の二人しかいないように、じっと。
「マリリン、ちょっとあっちで休んだら……?」
音楽が一区切りついた時、みのるははっとし、蓄音機に唯一ついているスイッチを押した。
音楽は終わり、リチャードと正義は踊るのをやめた。
「……志岐さんと何やってたんだ?」
「ダンスを」
「それはわかるけど」
正義の声は冷たかった。
リチャードが次に何か言う前に、真鈴が叫んだ。
「申し訳ありません! 私、急用を思い出したので、今日はこれで」
そう言うと真鈴は、広間に置いていた小さなリュックをひっつかみ、つかつかと屋敷を出て行った。おい真鈴、という良太の声にも振り返らない。オクタヴィアが追っていった。
「…………」
顔色の悪いリチャードに気づき、正義は眉根を寄せた。
「本当にどうしたんだ。何があった?」
リチャードは真鈴を追うかどうか迷ったようだったが、結局追わなかった。そして正義を見た。
「少し、話ができますか。二人で」
ぴりっとした表情を見せた正義の後ろで、みのると良太は顔を見合わせた。
同じ相手に何度も何度も何度も電話をかけることを鬼電と言ったりする。真鈴は電話の鬼になっていた。『ヨアキムさん』という最近登録したばかりの相手の表示には二桁の数字が表示されている。十五回この番号に電話をかけたという意味だった。一度も繋がらなかった。
神立屋敷から坂を下って元町に下りたものの、真鈴は行くところが思いつかなかった。とぼとぼ歩いて、山下公園のある方向に続く横断歩道を渡る。ぼうっとしていたせいか、何ということのない段差で、真鈴はつまづきそうになった。
あ、と思った時には、真鈴は前から歩いてきた相手に支えられていた。
「大丈夫ですか」
「……えっ! 嘘、リ」
チャード、まで言ったところで、真鈴は人違いであることに気付いた。青い瞳の持ち主は流暢な日本語を話し、金茶色の髪の毛にスーツ姿で、高そうな革靴をはいていたが、リチャードではない。横浜によくいる、ややハンサムなコーカソイド系の男性だった。アタッシェケースが似合いそうな風体だったが、何故か巨大なボストンバッグを提げている。
信号が点滅し始めた横断歩道をとりあえず渡りきり、真鈴は男性にお礼を言った。結局彼は回れ右をし、よろよろしている真鈴についてきてくれたのである。
「すみません、変な名前で呼んで。人違いでした」
「そんなのは構いません。でも本当に大丈夫ですか。顔が真っ白です」
それはそうだろう、と真鈴は思った。
今までの人生の中で、間違いなく一番、衝撃を受けていた。誰かに鉄パイプで後頭部を叩かれ続けているように頭が痛かった。
何も言わないでいたらこの人は通り過ぎていくかな、と真鈴が思っていると、男性は高そうなスーツで跪き、真鈴の顔を見て笑った。
「実は僕は、占い師の見習いなんですけど、そこの公園でちょっと占っていきますか」
真鈴の警戒アラートは黄色から赤に変わった。見ず知らずの男にこんなことを言われたら、百パーセント逃げるべきである。キャッチ、カラオケの勧誘、占いの呼び込み、どれも警戒のシンボルであると、母も社長も真鈴に教えてくれた。
だが真鈴は、自分を粗末にしたい気分だった。
「…………嫌なこと言われたら蹴っ飛ばしちゃいそうなメンタルなんですけど」
「別にそんなことを言うつもりはないですけど、蹴っ飛ばされても別に構わないですよ」
「気持ち悪い」
「今のは傷ついたなあ」
男性はいきなりボストンバッグを開け、中華風の布を取り出した。巨大な布で、スーツの男性が頭からすっぽりかぶることのできるローブだった。中から小学生の工作のような帽子を取り出し、折れている部分を直して頭にかぶる。
易者、と言ってもまあ通りそうなコスプレではあった。
「ね。本当に占い師セットを持ってるでしょう。ちょっとは信じてもらえましたか」
「山下公園のベンチでよければ付き合います」
「それはいいですね。僕は公園が大好きです。僕のパートナーの次くらいにね」
謎の占い師コスプレ男には恋人がいるようだった。へえ、と思った後、真鈴は自分の甘さに笑いそうになった。パートナーがいるというのは異性を安心させるための常套句である。信頼すべきではなかった。
パートナー。
自分で自分の胸を突き刺してしまったような痛みに耐えつつ、真鈴は海沿いの公園まで歩き、人出の多い花園のベンチを促した。
「ここでいいですか。じゃあ占ってください」
「かしこまりました、プリンセス。何を占いましょう」
「私の未来」
「未来の何を?」
「……そもそも未来があるかどうか」
占い師は真鈴の言っていることがよくわからないようだった。当然だと真鈴は笑った。真鈴自身よくわかっていないのである。
わかっているのは、目を開けているというのに、瞼を下ろしたように目の前が真っ暗だということ。
もう何もかもが黒く塗りつぶされていて、世界すら存在しないような気がした。
「もう……何か……全部……わからないから……」
真鈴は泣きたくなかった。見知らぬ男の前で泣く女というのは、その男によしよしと宥められたいと思っている女ということになり、相対的に弱い存在になる。真鈴は弱くなりたくなかった。強い人間でありたかった。英語の歌でよく歌われる『独立して光り輝く』『かっこいい方の意味のビッチ』でありたかった。そんな女は男の前でさめざめと泣いたりしない。
だが涙は勝手に出てきた。
真鈴は歯を食いしばり、怒りくるった鬼のような形相で、膝に顔をうずめた。隣から何かがスッと出てくる。淡いブルーの地に茶色のストライプが入ったハンカチだった。Jというイニシャルか何かが刺繍されている。真鈴はありがたくハンカチを広げ、顔面をがしがしと拭いた。
「ご婦人に泣かれるのは久しぶりだな。最後に泣かれたのは『ひどいわ、遊びだったのね』って、会ったこともない女性に抱きつかれた時かな」
「意味わかんない。何やらかしたんですか」
「カメラマンに雇われた俳優さんだったんですよ。そういう写真を撮るとセンセーショナルでしょ? 安い雑誌やタブロイド紙に売れるんです」
日本の話ではなさそうだった。真鈴にはタブロイド紙が何なのかよくわからなかったが、特に今教えてほしいことでもない。ハンカチではなをかんでも、占い師は特に嫌な顔はしなかった。
「……お兄さん、やくざですか?」
「どうして?」
「こんな高そうなハンカチではなをかんでも嫌な顔しなかったから。そういうの日本語だと、肝が据わってるって言うでしょ」
「ははは、それはいいですね。じゃあ僕は『やくざな占い師』ってことで。ちなみに僕のパートナーもよくハンカチではなをかみます」
「嫌な人……」
「そこが可愛いんですよ」
のろけ話のようだった。真鈴が無視すると、占い師は勝手に喋った。
「その人の未来の有無はね、占いではわからないんです」
「……何で?」
「どんな風にでもできることだから」
よくわからない言葉だった。真鈴が眉間に小さな皴を寄せると、占い師は立て板に水で喋った。
「いろいろな占いを勉強したんですが、あれってね、『大いなる存在があなたをどんな風に導こうとしているか』っていう、潮の流れを読み解こうとする試みなんですよ。もちろん潮の流れがあると仮定しての話ですが。でもぶっちゃけた話、ドーヴァー海峡やボスフォラス海峡を泳いで渡る人がいる以上、潮なんてそこまで絶対的なものじゃないですよね?」
「占いの概念に正面から喧嘩売るようなこと言ってますよ」
「そんなことはありません。占いの世界って深淵なんです。読み取り方次第でどんな風にでも判断可能、言うなれば究極の読書感想文ですよ」
「『読書感想文』って、日本以外の国にもあるんですか……?」
「僕の国にはありませんでしたけど、僕の家庭教師は宿題に出しましたね。その人は日本人でした」
「…………」
真鈴は次第にうすら寒い気持ちになってきた。そもそもコスプレ衣装を持っていたからといって、目の前の男が本当に占い師とは限らない。奇妙なことばかり言う日本語に堪能な男は、不気味な悪夢のような存在だった。
だが真鈴の気持ちを読んだように、自称占い師は真鈴に手を出すようにと促した。直接手に触ろうとはしないあたりに、真鈴はあるかないかの誠実さを感じた。
占い師は整った顔を輝かせ、華やかな笑みを浮かべた。
「すごいな! こんな手相は初めて見る。きらきら星が輝いてるような未来でいっぱいだ。星の光がまぶしすぎて見えない。あなたの未来は光に溢れてますよ」
「…………」
でもそれは未来が『あった』場合の話だ、と真鈴は思った。死にたいなと思っているわけではなかったが、何故世界が今も存在しているのか信じられないような感覚は消えなかった。自分がいるのが不自然に思えて仕方がなかった。圧縮袋に入れられた冬物の衣類のように、ぺしゃんこになって押し入れの隙間に放り込まれたかった。
真鈴が黙り込んでいるうちに、遠くで遊んでいた子どもたちが近くにやってきて、きゃーきゃーと叫びながら追いかけっこを始めた。楽しそうだった。
真鈴は目を伏せ耳を塞いだが、声は聞こえた。隣に座る占い師の声も。
「あの、僕が小さい頃一番ショックだったことの話をしてもいいですか」
「……短めでお願いします。私、今わりと余裕ないので、他人に同情できないです」
「自分は自分で好きになる人を決められないんだってわかった時でした。以上」
は? という顔を真鈴がすると、占い師はハンサムな顔に、悪く言えば多少うさんくさい、よく言えば親しみ深げな笑みを浮かべた。
「世界にはあるでしょう、『正解』ってものが。好きになる『べき』相手がいる。それはわかってる。品行方正でお金持ちでいい感じの人を選べばいい。でも僕の心が好きになるのはそういう相手じゃなかった。それどころか、どうやら将来的には自分の家族を傷つける可能性が高い相手ばかり。そう気づいた時には、けっこうショックでした」
「馬鹿みたいな話ですね。それ、つまり恋する相手を自分で選べないって言ってるんでしょ、そんなの当たり前じゃないですか。選べたら、選べたら、選べたら、もっと私だって、楽だった。楽だったのに!」
真鈴は叫ぶように言い、自分の拳で両膝を叩いた。賑やかな公園の中では目立ちもしない行為だったが、真鈴は自分で自分の動揺ぶりに驚いた。隣に座る占い師が涼しい顔をしているのが、真鈴は悔しかった。
「……何で私、こんなことになってるの。意味わかんない。もう一回キムさんに電話する」
「あー待って待って今はその人に電話するより占い師の話を聞いた方がいいって星が告げている」
「まだお昼ですけど、どこに星が見えるんですか」
「やだなあ! 『見えぬけれどもあるんだよ』って詩もあったでしょう、あれですよ」
「得意げな日本文学トリビアうざ……」
真鈴は自分が少しだけ元気になっていることに気づいた。誰かに話しかけてもらうと、それだけで多少は気が晴れるらしい。だから自分はこんなにヨアキムと電話したかったのだなと思ったが、相手が占い師になっても、多少は効果があるようだった。かといって説教をされたいとは思わない。でもちょっとくらいは励まされてもいい。
占い師はそのギリギリのラインを、多少の鬱陶しさと共に適えていた。
「選べるものと選べないものがある、って僕の友達のお母さんが言っていたらしいです。いい言葉じゃないですか。世の中そんなものばっかりですよ。選べないものの方が体感的には多いような気もしますけど」
「…………」
「逆に質問しますけど、誰が一番よさそうだろう、この案件かな、ってサブスクの配信映画みたいに選んだ相手に、泣くほど夢中になりますか?」
「無理」
それが答えです、と占い師は言わなかったが、そういうことだった。
真鈴は徐々に自分が平常運転に戻り始めているのを感じた。走り回る子どもたちの声が、数分前ほどには鬱陶しく感じなくなっている。
「だんだん頭が落ち着いてきました……自分が何にショックを受けてるのか分析したい気持ちになってきた……」
「おお、何と聡明なプリンセスだ」
「何を食べたら初対面の相手に『プリンセス』って言えるんですか? クレープシュゼットとか?」
「僕はフランス人じゃありませんよ。出身地はご想像にお任せします」
「普通に日本育ちの日本人っぽいですよね」
「日本人じゃないんだなー」
占い師は徐々に真鈴にバトンを預けようとしていた。話したいことがあるなら話してください、でも無理しないでね、と優しい声色で示している。
胡散臭いという気持ちは消えなかったが、真鈴は占い師を信じることにした。
「……好きな人がいた……いるんです。でもその人に付き合ってる人がいることを……知らなくて……しかも相手は私も知ってる人だったので、余計にショックで……そういう時どうしたらいいのかわからなくて混乱してます」
内心『あれ?』と真鈴は思った。あまりにも単純な悩みに思えたのである。そんなことよくあるじゃんと、自分で自分にツッコミをいれたくなるほどありふれたことである。ただそれが、男同士だったという部分には、多少の珍しさはあるかもしれないものの。
友達から相談されたとしたら「そうなんだ。つらかったね。でもよくある話だよ」としか言えない類の悩みに思えた。それを自分は、世界の終わりのように悲しみ、ショックを受けている。
真鈴は占い師に笑われる覚悟を決めたが、占い師は何も言わず、しばらくしてから「そうですか」と頷いた。それからまたしばらく黙り、庭園の花を眺めた後、呟くように告げた。
「それはアンラッキーでしたね。騙されたような気分になりましたか?」
「…………いいえ。ただ、自分が馬鹿みたいだなって思いました」
「どうして?」
「……好きになる意味のない人を好きになっちゃったから」
本当にその通りだった。
中田正義は自分のことを好きにならない。何故ならパートナーが既に存在するから。何故なら恐らくは恋愛の対象外だから。
それだけのことだった。
暗い目をする真鈴の隣で、占い師はあっけらかんとした声をあげた。
「好きになる意味のない人なんているんでしょうか? プリンセス、恋愛っていうのはつまるところ、自分自身の問題ですよ。そう思いませんか?」
「独り相撲を取ってるだけだって言いたいんですか」
「違います」
占い師ははっきりと言った。
真鈴が目を見開いていると、占い師は笑って、言葉を続けた。
「あなたは恋をしてる間、楽しくなかったですか? あの人にこうしたら好きになってもらえるかな、こうしたらどうかなって、考えるとうきうきしませんでしたか?」
「今そんなこと言われたくないです。ガチでつらいので」
「すみません。もちろん今すぐに『まあでもよかったな』って思うのは難しいと思いますよ。先々になってみるといい思い出になるなんて訳知り顔で言うつもりもないです。でも、あなたはそれを経験した。そしてそれを全身全霊で感じ取ってる。それはすごいことですよ」
「…………ちょっとよくわからないんですけど」
「あなたが生きてるのは、それだけですごいこと、って意味ですよ」
生きてるだけですごいこと。
ついさっき、オクタヴィアが言っていたのと同じことだった。
そういえば母も昔そんなことを言っていたなと、真鈴はぼんやりと思い出した。その頃の母は、今考えると父と離婚したばかりで、毎朝鏡の前で「生きてるだけで百点満点!」と自分の顔を見ては宣言していた。可愛い言葉だな、と幼かった真鈴は思ったが、今考えると少し不気味な習慣でもあった。毎日毎日毎日自分の顔を見て「百点満点!」と言うのである。
そうでもしないとやっていられなかったのかもしれなかった。
荒んだ目をする真鈴の隣で、占い師は言葉を続けた。
「好きになる意味のない相手なんかいません。絶対に成就しないことがわかっていたとしても、誰かを好きになることが無意味だなんて思わない」
「…………叶わなくても?」
「叶わなくても。それはね、プリンセス、自分の中に根を下ろして、次に好きになった誰かをより幸せにしてあげるための苗木になってくれますよ」
「『次』なんていらないんですけど」
「もちろん今はそうでしょう。でも『未来がある』場合は、いろいろな可能性がありますからね。ほら、たとえば僕だって素敵でしょう」
「鬱陶しくて胡散臭くて若干不審です」
「ううっ、青少年の鋭い言葉が胸を突き刺す。でもいいですよ、その調子です。弱ったところに付け込んでくる男なんてキモいだけですからね。プリンセスの判断はテン・アウト・オブ・テン、十点満点です」
「あなた……占い師っていうか、執事さんみたい」
「おえー、執事にはちょっと嫌な思い出がある……でもまあ大抵の人は『執事さん』っていうと素敵な人を想像するでしょうから、褒め言葉として受け取っておきますよ」
「そこまで褒めてもないです」
「辛辣ゥ!」
占い師はおどけた仕草で膝を叩いた。真鈴を楽しませようとしているところが、何となく執事さんっぽかったのだが、そこまでは言わないことにした。
執事っぽい占い師は、しっかりと真鈴の方を見て口を開いた。
「生きててください。そうするといろいろなことがあります。プリンセス、今はそれだけでいいですよ。そのうちまた、世界が楽しくなってきます」
「…………」
悔しいことに、占い師は今の真鈴が欲しがっているものを全部くれた。
お礼を言った方がいいのか、でもお礼を言ったところでセールスが始まったらどうしよう、と真鈴が考えていると、公園の遠くで音楽が聞こえ始めた。ヴァイオリンの音のようで、奏でているのは三拍子だった。
「そうか、ここは大道芸がOKなんだっけ……」
「横浜はそういうところが多いですよね。賑やかでいいところだと思いますよ」
「自分の故郷をウエメセで評価されるのって何かムカつきますね。占い師さん」
真鈴はベンチから立ち上がり、占い師の前にすたんと立った。
そして手を差し伸べた。
「ダンス、踊れますか」
占い師は少し驚いたようだったが、したり顔で微笑んだ。
「僕のワルツのデビューはウィーンですよ、プリンセス。ご安心ください」
「やっぱうざ」
外していたスーツのボタンを留め直し、占い師は真鈴に華麗に一礼した。やっぱりこの人はリチャードにちょっとだけ似ている、と真鈴は思ったが、彼とは違った。顔面の美貌の話ではなく。
雰囲気が、柔らかかった。
執事や貴族が存在するような、大きなダンスホールを想像しながら、真鈴は占い師と小さなダンスを踊った。占い師は神立屋敷のような広間がなくても、省スペースで地味に踊り、それでいて真鈴をぐいぐい振り回すようなことはしなかった。リードの力加減もダンスの先生のように絶妙である。この人本当にうまいんだな、と思った時、真鈴は気づいた。
笑っていた。
自分の口元が、少しだけ。
「……やっぱりダンスって、こうじゃないと」
「どういうことです?」
ヴァイオリンが二拍子のポップソングを奏で始めたので、真鈴はそっと占い師の腕をほどき、喋った。
「楽しくて、礼儀正しくて、ちょっと切ない感じ」
仮面舞踏会で習ったようにお辞儀すると、占い師もスーツの胸に手を当て一礼した。
そのダンスを、ハイヒールをはいた長身の人間が、遠くから眺めていた。
「蓄音機を彩る灰色の石、こちらが何なのかおわかりになりますか」
「リチャード」
「それほど頻繁に宝石商が扱う石ではございません。しかしラーヴァ、と言えばあなたはおわかりになるでしょう」
「リチャード」
「そう、こちらは火山の噴火と共に噴き出した溶岩が固まった、鉱物というより岩石の部類に入る石でございますね。ヴェスビオス火山のラーヴァ等が加工品としては有名ですので、この石もイタリア産である可能性が高い。まったくこの屋敷には、世界中のありとあらゆる宝物が詰まっている」
「リチャード、ちょっと聞いてくれ」
「しかし宝箱というものは、得てしてパンドラの箱にもなります。私はそれを開けてしまった」
神立屋敷の二階、中学生たちの手伝いに先んじて掃除され、通路が『開通』していたバルコニーは、横浜港を一望するスポットだった。内開きの扉を開けると、こもった屋敷の空気が冷たい外気と心地よく入れ替わる。
だがそこで繰り広げられている会話は、あまり心地よい類のものではなかった。
リチャードは隣に立つ正義を見て、静かに告げた。
「戯言として聞いていただきたいのですが、私はあなたの傍にいるべきではないかもしれません」
「いきなりすごい戯言が来たな」
正義が挑発するように茶化しても、リチャードは乗らず、静かに言葉を続けた。
「私の専属秘書をすると宣言した時、あなたは私にこう言ってくださった。『私のことを一番に考えてしまうから、それ以外の仕事をしている自分が想像できない』と。非常にありがたく、心尽くしに富んだオファーでした。しかし今になって、私はその恐ろしさが身に染みてきたところです」
「今回のこととは論点がずれてる気がするけど、最後まで聞くよ」
「私はあまりにも多くをあなたに期待し、望んでしまう。より直截に言うと、あなたが私以外の誰かのことにかかずらわっていると、あまり愉快ではいられなくなってしまう。おぞましいことです。嗤う気にもなれない」
「…………」
「失礼」
リチャードは取り乱した自分を恥じるように、正義に背を向け、バルコニーの汚れた手すりに摑まり、横浜の景色に正対した。港に入ってくる船が、ボーボーと汽笛の音を立てる。
汽笛の反響が消えた後、正義はリチャードの隣に立ち、同じように港の風景を眺め、口を開いた。
「ごめん。専属秘書の仕事と、中学生の弟の保護者、どっちもきちんとやってるつもりでいたんだけど、『つもり』だったみたいだ」
「あなたが謝ることではありません」
「でもやっぱり、俺の責任だよ」
「……私は仕事の話がしたいわけではない」
「ごめん。わかってる」
「何故そう何度も謝罪するのです」
「俺が逃げてるから」
フェイントのような短い汽笛が鳴り、二人の会話を邪魔した。
サイレンの音の余韻が、最後の一音すら消えた頃に、正義は言葉を重ねた。
「返事ができなかったんじゃなくて、返事から逃げたんだ」
「……いつの話をしているのです?」
「みのるくんの件の連絡をジェフリーさんからもらった時、二人でパリにいただろ」
しばらく二人で休暇を取りませんか、と。
提案したのはリチャードだった。
お前のことが大好きだから、もしかしたらこれから付き合ったりすることもあるかもな、という正義の呟きや、あなたと人生を共にすることが現実味を帯びてきました、というリチャードの言葉、一つ一つがいつの間にかうずたかく積み重なり、そろそろもう少し何か試してみようかという結論に、どちらからともなく達した結果だった。休暇を取りませんかとはつまり、上司と部下でもその他の何かでもなく、とにかく二人で一緒に過ごしませんかという申し出だった。面白そうだなあ、と言って正義も受けた。
どこで休暇を過ごそうかと二人であれこれ考えた結果、東京やイギリスの都市は外し、最終的にアムステルダムかパリの二択になり、アプリでくじを作った結果パリになった。
目的のある休暇ではない。
いきなり「さあ何かをしましょう」というわけでもない。
ただ、どちらかがどちらかの鞄を持ったりスケジュールを管理したりするのではなく、やることもなく、のんびりと過ごすための時間だった。
いつもとは違う関係性を作ってみようという、言うなれば打診である。
一緒にナイトクラブに遊びに出かけたり、気鋭のシェフのディナーを楽しんだり、時々手を繋いで歩いたりしているうち、リチャードは正義に問いかけた。
仕事は仕事と分けるとして、私とこの関係を続けてみる気はありませんか? と。
それが何を意味しているのか正義もある程度は理解した。
だが返事をする前に、ジェフリーから霧江みのるに関する情報が飛び込んできて、二人の休暇はやや繰り上げで終了となった。即日本に飛べたわけではなく、みのるの保護に必要になる根回しをするための、まとまった時間をとるための、仕事の片付けが必要だったのである。遊びの時間は終わった。
結果、回答はうやむやになっていた。
正義の顔をしばらく見つめた後、リチャードは微かに首を傾げた。
「やはり解せません。謝罪の必要などない。時をさかのぼれば、私たちの関係には教師と生徒のような側面もあったことでしょう。ですが今は違う。あなたは私と対等な一人の人間です。私にどのような回答をするのであれ、それを案じたり、過度に気に病んだりする必要はない」
「俺はお前の下僕をしてるつもりはないよ。何度も言うけど、俺がそうしたいからここにいる」
「その点は理解しているつもりです」
リチャードの語調は冷たくはなかったが、特に温かくもなかった。正義はしばらく目を閉じ、考えに浸った後、うっすらとした微笑みを浮かべてリチャードを見た。
「これは確認だけど、あの時パリで俺が『リチャード、俺の上司で友達で恋人にもなってほしい』って言ったら、なってくれた?」
「イエス、と答えるに吝かではなかったかと」
他の何と答えると? と詰問するようなきつい口調に、正義は少し苦笑した。リチャードが心外だという目をすると、正義はまた笑った。
今度の微笑みには、寂しさが満ちていた。
「…………でも、その先は?」
「『その先』?」
水を向けてきたリチャードに、正義はほのかに苦しげな表情を滲ませつつ、喋った。
「もし俺たちが恋人同士にもなったとして、その先は何が待ってると思う? 同性婚の法整備はゆっくりしか進まないし書面上の結婚はできないな、とかそういう話じゃないよ。恋愛の先には何があると思う?」
「広がりのある謎かけです。もう少し説明をしていただいても?」
正義は明朗な表情を作り、つまりだな、と言葉を継いだ。
「俺は…………怖いんだよ」
「私の全てを受け止めることが?」
「そうじゃない。いや、まだ受け止めてない部分があるなら、ダイビングキャッチしたいほど受け止めたいとは思ってるよ。これは絶対の本音だ。でも、その…………ああ、うぬぼれた言い方になるよ。許してくれるか?」
「どのようなことであっても」
リチャードが両腕を広げると、正義は息切れを起こしたように深く嘆息し、また深く息を吸った。そして顔を上げた。
「お前と会った時、俺は大学生だったよな。英語もろくに喋れなかった」
「無論記憶しております」
「専属秘書になるまでの間には就職活動と、いろいろ騒動があって、その間にも俺はまあまあ雑多なスキルを吸収したと思う。フランス語を習い始めたのもあの頃だろ。自転車の修理も自動車の整備もできるようになった」
「そのようです」
「それからは世界中を飛び回って、吸収できるだけの語学を身につけて、執事の学校に少し通って身のこなしを磨いたりして、空手の腕も磨いて昇段した。バリバリやれたな」
「存じ上げております」
「うん。それで、今は? 今の……いや、これからの俺は?」
正義はそこで言葉を打ち切った。
言わんとすることを受け取ったというように、リチャードは小さく頷いた。
「つまりあなたは、今後の自分自身に、過去の自分自身のような成長が見込めないであろうことを察知し、来たるべき未来におびえていると?」
「手加減しないで言うとそうなる」
「くだらない、と一笑に付すことは容易ですが、あなたの恐れにはもう少し別の側面も存在するようですね」
正義は頷いた。
「俺は…………お前と一緒にいる時に、どんどん成長する姿しか見せてない。たぶん俺の人生の一番いい時を、お前と一緒に過ごしたんだ。すごく楽しかった」
「何故過去形になるのです」
「………………日夜新しい語学とスキルを手に入れる、完璧な美貌のリチャードさんには想像もできないかもしれないけどな」
正義はゆっくり、言葉を選ぶように時間をかけ。
言葉を唇に乗せた。
「俺……白髪が一本生えたんだよ」
リチャードは黙り込んだ。
正義も黙った。
二秒後、リチャードは噴き出した。
「っく、くくく……」
「あー……」
「し、失礼。白髪……それはそれは……しかし、そのような……ふっ、ふふふ……失礼。お詫び申し上げます。しかし、そのようなことで……ふふ、ははは……」
「真面目に考えると笑いごとじゃないんだぞ。俺は成長してるけど、これからの俺の成長は、つまり、『老化』ってことで……これまでと同じくらい見ていて楽しいかって言われると、正直自信がないし、多分そこまでは楽しくないと思うし」
リチャードはますます笑った。口元に手を当て、体をくの字に曲げていたが、最後には堪えきれなくなりしゃがみこんだ。
正義は困った顔をし、ため息をついた。
「頼むよリチャード。白髪のことはただの、その、メタファーみたいなものとして受け取ってほしいんだけどさ」
「理解しているつもりです。ははは……」
リチャードはそれからもしばらく笑い続けたが、おほんおほんと何度か咳払いをし、よろよろしながら立ち上がった。ハンカチで目元を拭い、乱れたスーツを整える。
「大変失礼いたしました。お話をまとめると、こうでしょうか? あなたは私に、今以上の楽しみを提供できる自信がないと」
「うん。それと『恋愛』の概念についての俺の理解が、変に合致してる」
「概念。興味深い言葉です。是非お話を聞かせていただきましょう」
「恋愛の先って、どんな関係があると思う?」
リチャードは微かに首を傾げた。正義は再びバトンを受け取ったように喋り始めた。
「日本人はこういうことを『昭和っぽい』って言い方で形容することもあるけど、俺は恋愛の成就がゴールだとか、結婚できなかったら一人前じゃないとか、そういう風には全く思わないし、そんな考え方は乱暴だと思う。でも一つの、何て言うか、社会的な到達点みたいなものかもしれないと思うことはある」
「到達点」
「……そこから先に、どうやって進んだらいいのか、今以上にわからなくなるポイント、って言えばいいかな」
正義は惑星の軌道を描くように左右の人差し指をくるくると中空で回した。だがリチャードがそのジェスチャーに注目せず、正義のあまり芳しくない表情を見つめているのみだと悟ると、苦笑した。
「……俺はお前とずっと一緒にいたいんだ。『まだまだこれから一緒にいると楽しいことがある』って思ってほしい。将来の夢に『中田正義の隣にいること』って書いてほしいくらいにはそう願ってる。でも、俺は卑怯だから……恋愛したら、『もう先がない』ってお前に思われそうで、怖い」
言葉の後には空白のような沈黙が残った。
正義はそれ以上、何も言おうとしなかった。
遠くからポポポ、ポポポ、という穏やかな汽笛の音が聞こえる中、リチャードは口を開いた。
「残念です。中田正義」
「…………」
「あなたはデザートのアイスクリームを先延ばしにしておくことで、子どもに言うことを聞かせようとする愚かな保護者のような真似をしてしまいました」
「……ごほうびのアイスはもう溶けちゃったよ、ってこと?」
「違う。お忘れでしょうか? あなたが成長、あるいは老化しつつあるように、私もまた同じスピードで生きているのです。そして残り時間は無限ではない。あなたも、私も」
正義は静かにリチャードの言葉を受け止めた。
リチャードは静かな、力強いトーンで言葉を続けた。
「正義、どのみち命というものに『二回目』は、『先』はないのです。生まれてきた個体はいずれ生涯を全うして世を去ります。そのことを恐れるのは生き物として何らおかしなところのない感覚ですが、そこに私との関係性まで組み込もうとすることには無理があります。極論を言うなら、何もかも、始まれば終わりが来ます。永遠に続くものなどないのです」
「…………ダイヤモンドも?」
「ええ。ダイヤモンドも、永遠には輝きません。何故なら輝きとは、人の瞳の奥でこそまたたくものであるのですから」
世界一有名なダイヤモンドのキャッチフレーズを連想しつつ、正義はこわばった表情で微笑んだ。リチャードも微笑み返した。穏やかで、柔らかな顔で。
「であればこそ、私はあなたの傍にいたい。美しさという言葉が私ではなく他の誰か、何かを示すのに適した言葉になる日が訪れたとしても、その時あなたに私を『美しい』と言ってほしい。白髪や皴を持ったあなたの瞳にうつる私が、どんな姿をしているのか見てみたい」
「…………」
「いつの日かダイヤモンドが消し炭になったとしても、力強い炎を宿していた溶岩の流れが冷え固まり、脆い灰色のラーヴァになったとしても、あなたはそれを慈しむ。私にはその確信がある。何故なら私も、あなたというダイヤモンドの煌めきを、永久に瞳に留めておく自信があるから」
「…………俺、すぐに、つまんない男になるかもしれないぞ」
「ご心配なく。あなたには既に一生分以上楽しませていただきました。ここから先はボーナスタイムです」
「……はは」
今度は正義が笑う番だった。はは、はは、と静かに笑った後、さっきまでのリチャードと同じようにうずくまり、はははと笑い続ける。
震え始めた背中を、リチャードは優しく撫でた。
「正義。私があなたを好ましく思う理由は、私を絶えず慈しみ、楽しませてくれるからではない。あなたが目を見張るほどの速度で成長してゆく生き物であるから、好きというわけでもない。私はあなたが、あなたでいてくれることを愛している」
「…………」
「今までも、これからも」
「…………俺もだよ」
「知っています」
「……うん」
正義は大きなため息をつき、立ち上がった。もうどうしようもない、という諦めの唸り声には、喉に何かがからみついているような、微かな甘さがあり、リチャードがそれを感じ取った時、正義はズーとはなをすすった。
リチャードは涼しい顔で首を傾げた。
「どうかなさいましたか」
「いや、ちょっと目にゴミが入ってさ。気にしないでくれ。ああ……相変わらずきれいだな。世界で一番きれいで、時々泣きたくなる」
正義はリチャードとの距離を一歩詰め、頬に触れた。
そして襟元に額を押しつけ、ため息をついた。
「きれいだ。お前って存在が太陽みたいに輝いて、俺の人生を照らしてくれてる気がする」
「そろそろソーラーパネルを設置するとよいでしょう。あなたが私にそう言ってくださるのは三度目か、四度目です」
「ごめん」
「謝ることでは。太陽はあなたに褒められると機嫌がよくなりますので」
リチャードは肩をすくめた。
顔を上げた正義は、少し困った顔で笑った。
「お前と同じ時間を生きられることが、俺は本当に嬉しい。見えない残り時間がどんどん減ってるとしても、俺はその時間をお前と一緒に使えることがすごく嬉しいし、幸せだよ。ただ幸せすぎて怖くて、時々逃げたくなる。でも……もう逃げ場があんまりないんだよな」
「そのようです」
正義はリチャードの頬から手を離し、一歩退き、姿勢を正し、真っ直ぐに美しい顔を見た。
そして口を開いた。
「俺はお前の傍にいたい。これからもずっと傍にいたい。だから……傍にいてくれ。俺がボロくずになっても傍にいるって言ってくれ。嘘でいい」
「残念ながら、あなたにつくべき嘘の持ち合わせがありません」
二人はどちらからともなく互いの体に腕を回し、ハグを交わした。
きつく二秒ほど抱き合い、腕を離す。
うん、と頷いた正義は、再びリチャードの顔をまっすぐに見た。
「それはそれとして、志岐さんにはちゃんと謝ってくれ。俺も謝るから」
「無論です」
リチャードは深く嘆息し、右手で顔を覆った。
「私は何と言うことを……面目次第もない……」
「俺が悪かったんだよ。彼女の気持ちは何となくわかってたけど、飽きるかと思って放っておいたのが悪かった。でも何がどうなってあのタンゴになったんだ?」
「彼女に誘われて……あれは一種の決闘でしたが……踊っていれば何とかなるかと思っていましたが、思いのほか食らいつかれて、気づいた時には相手が中学生であることを忘れかけていました。愚かな……何と愚かなことを……」
ぶぶぶー、とリチャードの懐の中で何かが震えた。仕事用ではなく、私用に使っている携帯端末である。素早く取り出し確認し、リチャードはおやと呟いた。
「正義、奇妙なことが起こっているようです。ジェフからメッセージが……」
「ちょっと待った」
お揃いのように震え始めた端末を、正義も取り出し応答した。正義の通知は着信だった。
「はいもしもし。中田です。開帆病院さんですか。霧江さんのことで何か……?」
通話を聞いていた正義は、大きく目を見開いた。
途中で放り出されるような形で神立屋敷を後にしたみのると良太は、まず真鈴に連絡を取ろうと思ったが、電話もメッセージも全く通じないので諦め、次に真鈴の行きそうな場所を探した。だがどこにもいない。
一時間ほど探し回り、とりあえずどこかで休憩して作戦会議をしよう、そうしよう、という段取りになった頃、二人の端末に同時に連絡が入った。
真鈴である。
『私は大丈夫』
『心配しないで』
追加で送信されてきたのは、華やかなパンケーキ店のメニューだった。山盛りの生クリームに生フルーツのついたカロリーの塊のようなメニューである。真鈴らしくはなかったが、少なくとも元気な様子は伝わってきた。
良太は道の真ん中で昭和のコント番組のように尻もちをついて転げて、通行人に嫌な顔をされた。
「何だよお! こっちはガチで心配して歩き回ってたのにさー! パンケーキかよお! みのる、あいつスーパー親友から外す? もう外すか?」
「そんなことしたくないよ。よかった……」
みのるはため息をついた。真鈴がショックを受けていた理由を、みのるは良太に説明しなかったし、良太も尋ねようとはしなかった。そういうことは別に知らなくてもいいと思っているのかもしれなくて、みのるは良太のそういうところに、大人っぽく言うと『包容力』を感じた。
「…………」
あんなことから数時間で、真鈴がすぐ元気になるとは思えなかった。だがパンケーキがただの空元気だったとしても、少なくとも元気っぽいポーズを取ることくらいはできている。
それだけでもみのるは、ざわざわしていた心が少し落ち着くのを感じた。
「あいつもさ、いろいろあると思うけど、あんまり考えすぎないでほしいよな」
「……うん、そうだね」
「誰もあいつの敵じゃないんだからさ」
はっとするような言葉だった。
良太は尻をはたいて舗装された地面から立ち上がると、大人ぶった顔で頷いた。
「あいつ、何だか知らないけどリチャードさんに喧嘩売ってたじゃん? すごい怖い顔して。リチャードさんが真鈴に何したか知らないけど、たぶん誤解だと思うんだよな。俺そんなにリチャードさんのことよく知ってるわけじゃないけど、あの中田さんとすげー仲がいいわけじゃん? そんな人が中学生の女の子にひどいことするわけなくね? そんなやつだったら中田さん絶交してんじゃね? 俺何か間違ったこと言ってる?」
「たぶん、言ってないと思う」
「だろー?」
でもさ、と良太は言葉を続けた。でもさの後はなかなか続かなかったが、良太は決心したように喋った。
「仮にすげーいい人でも、時々心配しすぎたりすると変なこと言ったり、したりすることもあるじゃん。俺の姉ちゃんみたいに。でもみのるは俺の姉ちゃんのこと、けっこう許してくれてるだろ。俺とも絶交しないでくれてるし」
「……良太と絶交したら、学校に行くのが嫌になっちゃうよ」
「へへへ。いいこと言うじゃん。まあそれはともかく、お前のそういう『分けて考える』思考っていうの? 俺はそういうのが大人だなって思う」
「僕は……子どもだよ」
「んなことはわかってるよ、俺たち同い年なんだから。気持ちの話、気持ちの!」
「……ありがとう」
「いや別に感謝してほしいわけじゃねーけど、どうしてもって言うならポテトのLをおごらせてやってもいいよ」
「遠慮しとく」
「このお」
と、みのるはズボンの右ポケットの端末が震えていることに気づいた。着信である。発信者は『正義』。
「あっ」
みのるは慌てて通話ボタンを押した。
「正義さん、みのるです。あの、真鈴は、パンケーキのお店に行ったみたいで、あっ、あの、これは嘘や冗談じゃなくて」
『うん。その件は知ってる。俺の知り合いの人と偶然ばったり会って、しばらく一緒にいるって報告を受けてるから』
大丈夫みたい、とみのるは良太に手でOKのサインをした。正義も真鈴を探し回ってバタバタしていたらどうしようと思っていた矢先である。みのるもほっとした。
しかし、だとしたら何故電話がかかってきたのか。
『みのるくん、突然なんだけど、少し話をしてもいい?』
「話?」
うん、と正義は告げた。
『ゆらさんの、お母さんの病院から連絡があったんだ。みのるくんさえよければ』
みのるは目を見開き、一も二もなく頷いた。
【つづく】