宝石商リチャード氏の謎鑑定 再開のインコンパラブル 第四回
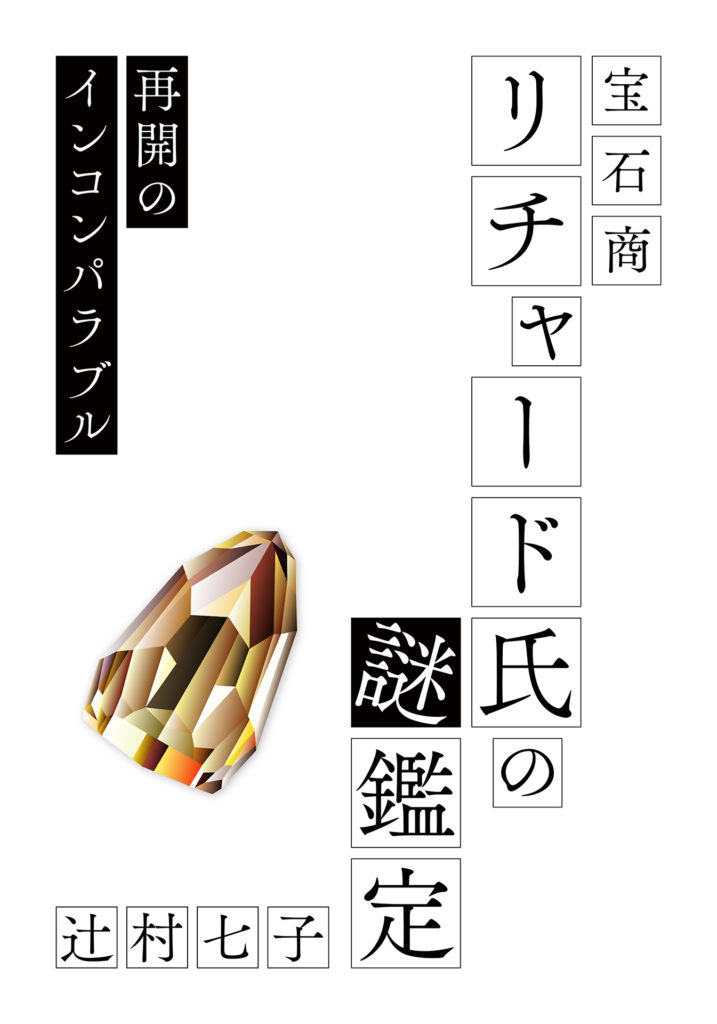
四話 再開のインコンパラブル
「……学校はどう?」
「楽しいよ。友達もいる」
そう、とお母さんは短く言った。そして再び、さっきまでと同じように、ずーっと黙り込んだ。
横浜市のオフィス街の一角に存在する、大きな総合病院の庭で、みのるは久しぶりにお母さんと会っていた。
正義からの電話は「ゆらさんがみのるくんに会いたいと言っている」という状況連絡で、その翌日、みのるは病院に向かった。
三十分ほど待たされた後、見たことのないパジャマとカーディガンを着たお母さんがやってきて、ちょっと引きつった笑顔でみのるに挨拶をした。
遠くから看護師さんが見守る中、二人は中庭のベンチで話をした。話というより、どちらかというとお母さんの呟きを聞き取るだけで、みのるが何か言っても聞こえていないような雰囲気ではあったが、みのるにはそれで十分だった。
お母さんがいる。自分の隣にお母さんの温度がある。
それだけで十分だった。
お母さんはぽつりぽつりと喋った。
「家に……戻りたいとは思ってる」
「うん」
「でも、今すぐは…………無理」
「うん」
「病院では……よくしてもらってる」
「うん」
「私……なんだか、疲れてたみたいで……」
「うん、そうなんだね」
「『ゆっくり休んでください』って、先生に……言われた」
「うん、うん」
「だから今……休んでる……」
みのるは頷きながらお母さんの話を聞いた。病院に行って、しばらく会えないと言われた時、みのるはお母さんがいっぱい点滴や医療器具のチューブに繋がれているところを想像し、身も凍るような思いを味わったが、今のお母さんは元気とは言えないまでも歩いている。パジャマ姿だが二本の足で立ってもいる。そしてみのるを見てくれている。
なんてありがたいんだろう、とみのるはこの世界にはいない誰かに、静かに感謝した。
みのるがにこにこしながらお母さんを見ていると、お母さんはみのるをじいっと見て、不意に言った。
「あんた……将来どうするの?」
「え?」
「将来……だから、中学校、卒業したら……」
たぶん高校に行く、とみのるは告げた。その次はとお母さんは言った。いつものようにお金の心配はしないんだなと、みのるは少し不思議な気分になったが、入院している間にお母さんにも心境の変化があったのかもしれなかった。
お母さんはしばらく、言葉を咀嚼するような時間をとったあと、また言った。
「その後は?」
「……その後?」
「あんた……何になるの? たとえば、警察官とか、お医者さんとか……」
「ああ」
お母さんはみのるの将来の職業を心配しているようだった。
「全然考えてない」
「……考えた方がいいよ」
「うん、そうだね」
「…………私、昔は、ファッションデザイナーになりたかった」
みのるは目をぱちくりさせた。ファッションデザイナー。どういう仕事なのか具体的には思い浮かばなかったが、華やかな響きである。ファッションというからには服をデザインする仕事なのだと思った。たとえば真鈴が着るような。
「別に……そんなに本気でなりたかったわけじゃないけど……でもあんたなら、なれるでしょ」
「ファッションデザイナー?」
「じゃなくて……『自分のなりたいもの』」
今ここでそんな話をするの? とみのるは言いたくなった。みのるの将来の夢の話など、中学校のホームルームの時間にちまちまとプリントに記入させられては提出する程度のよくある話である。今大切なのはお母さんと過ごす時間や、お母さんの病状や、お母さんの今後のことだった。
だがお母さんは、どうやら決心をして、その言葉を発したようだった。最初から震えがちだった手がもっと震えるようになってきていて、上半身もふらふらし始めていたが、それでもベンチを離れようとしない。
お母さんはどうしても、この話だけはしたいようだった。
みのるは慌てつつ、口を開いた。
「考える。その、ちゃんと考えてるよ。まだ決めてないけど、やりたいことは本当に、考えてる。大丈夫」
「………………そう」
それだけ言うとお母さんは振り向き、後ろの方で控えていた看護師さんを呼んだ。そろそろ戻りますという意味のようだった。お母さんは看護師さんに抱きかかえられるようにして歩いていったが、その途中で何か、微笑んで呟いた。
「やっぱり、外って、気持ちがいいわ」
お母さんは笑っていたが、みのるのことで笑っていたのではないようだった。
取り残されたみのるは、去っていったお母さんの残像を眺めるように同じ場所を見つめながら、ぼんやりと考えていた。
お母さんの様子は、家にいた頃よりも少し悪そうに見えた。
でも正義の「落ち着いてきている」という言葉を信じるならば、以前はもっとひどかったのかもしれない。つまりお母さんは、病院に入った後にぐんと具合が悪くなって、その後回復してきたようだった。
あるいは家にいる時はすごく我慢をしていて、それが病院でドバッと溢れ出した。
そっちの方がありそうな話だなとみのるは思った。今考えると信じられないほど散らかっていた部屋の真ん中で、お母さんは平気で床に寝転がっていた。でも今は、汚れた床ではなく病院の清潔なベッドで寝起きしている今のお母さんは、その時よりは大分調子がよくなっているという。
ならよかった、とみのるは思うことにした。
そして考えている途中に、ふと気づいた。
お母さんは元気になってきている。少なくとも話すことはちゃんとできているし、ごはんも食べている。意識がなかったということはない。それでも、正義の言っていた面会が延びに延びた理由は何だったのか。
もしかしたら。
お母さんは今日になるまで、みのるには会いたくなかったのかもしれなかった。
「…………」
だから何だ、とみのるは考えた。頭の中にプリントのようにパソコンの文字で打ち込まれた『だから何だ』という文字が浮かび上がってくるのを想像した。
お母さんがみのるに会いたくなかったからといって、だから何だというのだ、と。
お母さんが元気でいてくれて、みのるの将来を心配している。何より生きていてくれる。退院の「た」の字も出なかったとしても、それが何なのか。
これで十分じゃないか、とみのるは頷いた。
そして正義の待つ病院の出入り口へと急いだ。
お母さんとの面会のために、授業が終わった後すぐに正義の車で病院に向かったみのるは、良太からメッセージが入っていることに気づいた。『だいじょぶかー?』といういつものノリのメッセージの後ろに、珍しく長文が続いている。姉の秋穂のことだった。
『姉ちゃんが謝りたいんだってー』
『会いたいらしいけどめんどくね? 何回もお前呼び出すのも違う気がする』
『みのるさえよければだけど呼び出してくれたら姉ちゃん派遣するから』
『ちなみに手土産の菓子買ってたから会うとお得かも』
『よろ』
みのるは目をしぱしぱさせた。秋穂が何を考えてああいうことを言ったのか、正直なところまだよくわかってはいなかったが、今度はそれを謝りたいという。ちょっといろいろ面倒な人だなと思ったが、わざわざ会いに来て謝ってくれるというのなら、会ってもいいような気はした。また変なことを言われたら嫌だなとは思ったが、お菓子は魅力的である。
「みのるくん、どうかした?」
「あ……あの……」
みのるは迷った。この話を、蒸し返すような形で正義に打ち明けてもいいのか、正義を傷つけはしないか、そもそも神立屋敷で言うべきではないことを言ってしまった件を謝った方がいいのではないか等、いろいろな気持ちが交錯した。
しかし一番大きな気持ちは、自分も正義に謝らなければならないのではないかと言う思いだった。みのるは決断し、実行した。
できるだけ手短に、みのるは正義に何があったのかを説明した。神立屋敷で相談した件について、秋穂が今になって謝りたいと言ってきたこと。正義は何も言わず、最初から最後まで静かにみのるの話を聞いた後、深く頷いた。
「そうだったんだね。それで今日は、良太くんのお姉さんが来てくれるの?」
「……はい。謝りたいって」
「そっか」
その時俺も隣にいていいかな? と言われることをみのるは覚悟した。
だが正義はそうは言わなかった。かわりに微笑みながら喋った。
「それじゃあ、みのるくんの都合のいいところで降ろすよ。良太くんに電話したら? 特に急ぐ必要はないけど、どこにでも連れて行くから」
わかりましたと頷き、みのるは急いで良太にメッセージをした。『どこがいい?』『だからそれをお前が決めろって言ってんじゃん?』。みのるは考え、考え、結局前と同じファストフード店を指定した。その旨を正義にも伝えた。
前回同様、高校生のお姉さんと向き合うことを考え、みのるの中には緊張が走ったが、今回は何を言われるのかわかっている分、多少は気が楽だった。
もしかしたら秋穂も緊張しているのかな、と思った時。
「俺がこんなこと質問するのは卑怯かもしれないけど、みのるくんはどう思う?」
正義が口を開いた。
みのるはちょっと考えてから、質問を返した。
「……何をですか? 『きれい』って、言ってることについてですか?」
「うん」
みのるは正義の顔をちらっと見た。運転中の正義はもちろん前方だけを見ていたが、顔立ちは少し、緊張しているように見えた。
正義もこんな顔をすることがあるんだと思いながら、みのるは一度つばを飲み込み、思っていたことを言葉にした。
「……僕は……さっき、お母さんに会えて、すごく嬉しかったです。お母さんは……そんなに元気そうじゃなかったし、パジャマでしたけど、でも会えた時、すごく嬉しくて、世界で一番きれいなんじゃないかって思いました。キラキラして見えました。だから、あの、きれいとか、きれいじゃないとかって、そんなに……簡単な話じゃないんじゃないかなって、思います……うまくまとまらないんですけど」
変じゃないと思います、と。
その言葉だけは、みのるははっきりと言い切った。
こわばっていた正義の顔が、ほんの少し緩んだのを、みのるは確かに見た。
「そっか」
「はい」
「確かに、『きれい』も『変』も、人の心に関わる話だから……そんなに簡単じゃないよね。やっぱりみのるくんはすごいな。俺、中学の時、そんなことすらすら話せなかったよ」
「ぜ、絶対そんなことないと思います……!」
みのるが慌てると、正義は快活な笑みを浮かべ、そうかなあととぼけてみせた。車は横浜の街を走り続けた。
そして辿り着いたファストフード店で。
「みのるくん、ごめんなさい。私、ひどいことを言いました」
秋穂は敬語で、しかも起立していた。そしてファストフード店のテーブルに額がついてしまいそうなほど深くお辞儀をした。みのるもあわあわと頭を下げ返すと、秋穂側に腰掛けている良太がちょっと笑った。
「『ひどいことを言いました』って何だよ。そもそも姉ちゃんがそんなガチガチになってんの、ちょっとおもろい」
「良太……」
みのるが窘めると、良太はふざけた顔を作って詫びた。だが秋穂はその全てにノーリアクションで、腰掛けた後もみのるだけを見つめていた。
「あの……今回のことを、私、高校の先生に相談したんだけど……もちろんみのるくんの名前や、特定につながりそうな情報は出してないよ。ともかく話したんだけど……そうしたら、いつもすごく私に優しくしてくれる先生が冷たい声で『赤木さん、それは間違ってるかもしれない』って言って……」
みのるは少し不思議な気持ちがした。高校生の、しかも学級委員をしているような人も、しどろもどろになるようだった。高校一年生というのはみのるにしてみると三つ年上のとても大きな人に思えたが、それでも難しいことはたくさんあるらしい。
秋穂はしばらく考えてから、首を左右に振った。
「今のも違いますね。誰かに違うと言われたから、謝ろうと思ったわけじゃないです。あの……私、男の人が二人で暮らしてるのが変だと思ったわけじゃなくて、ただ……何て言うか……そういう環境にみのるくんがいることが、みのるくんにとって悪いことになるような気がして……ああぁ、謝りに来たのにまた同じことを言ってる。でもそれはただの『気がする』程度の、『私の不安』だったんです。みのるくんはそんなことを思ってないかもしれないのに、『きっとみのるくんも不安だろう』と思って、何か力になれないかと思って、この前あんなことを言ったんです。でも、ちゃんと考えてみたら、私の方がずっと『変』だったかもって思ったんです。もし誰かに『あんたのうちのお父さんとお母さんは変だから、行政に相談した方がいいよ』なんて言われたら、は? だし。そもそも失礼だし。あんた何様って思うし…………ううん、違う」
秋穂は最後に、全然違う声のトーンになり、違う、と繰り返した。良太とみのるは戸惑った。
秋穂は俯いた後、まっすぐみのるの顔を見て口を開いた。
「『思う』って便利な言葉ですね。それって感想文で済むから、何を言っても許してもらえそうだし、逃げられそう。でも私は……今、許してもらおうって思ってません。そういうことじゃなくて……『自分は間違ったことを言いました。それは違うことでした』って、みのるくんに言いたいの。それは私が『思った』結果じゃなくて、先生にアドバイスしてもらったりして『考えた』結果なの。それを……わざわざみのるくんを呼び出して、聴いてもらってる。最後にもう一回言います。本当に申し訳ありませんでした」
秋穂はもう一度、深々と頭を下げた。
みのるはもう秋穂に言いたいことがなかった。あの時つらかったみのるの気持ちを、秋穂がかなり理解してくれていることがわかったからである。泣きそうなほど反省している良太のお姉さんを、これ以上責めたり苦しめたりしたくなかった。しかし秋穂は黙っている。
みのるは少し考えた末、明るい調子で口を開いた。
「うちは……お父さんとお母さん、両方ともいませんけど、リチャードさんと正義さんがいてくれるので、すごく居心地がいいです。僕は困ってること、ありません。もちろんお母さんがいないと寂しいことはありますけど……お母さんも病院で頑張ってるので……」
うん、うん、と頷きながら秋穂は話を聞いてくれた。そして途中で何故か涙ぐみ、ううーっと呻きながら自分のハンカチで目元を拭っていた。そのたび良太がうひゃひゃと笑うので、みのるはだんだん秋穂が可哀そうになってきた。
「良太、家でもそんな風にお姉さんのこと笑ってるの……」
「逆、逆。姉ちゃんいつも俺に『もっと勉強しなさい』とか『もっとまじめにやりなさい』とか、そんなことばっか言ってんのに、今はめそめそしてんのが超面白いってだけ」
「弟、家に帰ったらお前が数学の宿題隠してることお母さんに言うから」
「ゲエーッ姉ちゃんいきなりいつものモードに戻るなよ」
「……秋穂さん、良太のことを『弟』って呼ぶんですか。面白いですね」
「そ、そうかな?」
「俺も時々『姉』って呼んでるよ」
「へえー!」
良太が買ってきたポテトをつまみながら、三人はそれぞれの家でのことを喋った。兄姉良太の三人構成の良太は、家の中では一番立場が弱いこと。よく喋る両親に一番似ているのは良太で、次に秋穂、最後に兄であること。秋穂は昔ガキ大将タイプで、良太と兄を従えていけすかない男子に喧嘩を売りに行っていたこと。
「とにかくうちはみんな元気なんだよ。元気だけは売るほどある」
「弟ッ。デリカシーがない」
「あっ。ごめんな、みのる」
「ううん。それ、すごくいいよ。すごくいいことだと思う」
「お前のお母さんも、すぐ元気になるといいな」
「すぐは難しいかもしれないけど、だんだん元気になると思うよ」
「また一緒に住めるようになるといいね。でもその時には、中田さんたちはどうするの?」
「……え?」
みのるは戸惑った。
そういえば、お母さんが戻ってきたら。
正義たちとの生活は、どうなるのだろう。
みのるはお母さんと自分が、正義とリチャードと一緒に生活しているところを想像しようとしたが、うまくいかなかった。もしお母さんが戻ってきたら、また児童福祉施設の人に様子を見に来てもらいつつ、二人で暮らし始めるような気がする。それは来年でも、もしかしたら再来年でもない可能性もあったが、いつかはきっとそうなりそうな未来である。
その時リチャードと正義はどこにいるのか?
賑やかに話を続ける良太と秋穂の間で、みのるは自分が、一人だけ時空のはざまに挟まれて、動けなくなったような気がした。
「ヨアキムさん? ヨアキムさーん?」
「どうしました、正義」
かくれんぼでもしているように、正義はヨアキムの名前を呼んでいた。マンションに帰宅したリチャードに、正義は厳しい表情をした。
「ヨアキムさんと連絡が取れない。置き手紙があった」
「……まさかとは思いますが」
「変なことは考えてないと思うよ。ただ『お世話になりました。次の場所に行きます』って」
正義はヨアキムの書き置きをリチャードに手渡した。飾り気のないメモ用紙に、署名と共に残された文章の最後には、日本風の顔文字が残されていた。ぺろりと舌を出しウインクする笑顔。リチャードはやや脱力した。
「……ここはホテルか何かだと思われていたのでしょうか」
「ヨアキムさんなりの気遣いだよ。『心配するな』って」
でも、と正義は言い淀んだ。みのるもヨアキムもいないマンションはやけに静かだった。
「結局、何で仲たがいをしたのかは教えてもらえないままだったな」
「別段彼らは仲たがいをしたわけではないのでは?」
「?」
「あなたの考えていたことと類似しているように思われます」
正義がリチャードに向き直ると、リチャードもまた、淡く灰色がかった青い瞳で正義を見つめた。
「結局のところ、物理的な距離を取ろうと、精神的な距離を置こうと、誰しも『自分自身』からは逃げられないのです」
「別にわかりやすいきっかけがあったわけじゃないのよ。ただ、いろいろなことが積もり積もって、スクラップブック百冊分くらいになっちゃったから、それでもう、耐えられないかもって思っただけ」
山手名物の洋館の一つ、ベーリックホールと呼ばれる英国貿易商の館は、五分ほど前まで降り続いていた小雨のせいか、人の気配がほとんどなかった。
丁寧に補修され、ワックスがけを施されたホールの床には、二十世紀初頭にこの屋敷に暮らしていた人々の姿をよみがえらせるように、ダイニングテーブルやソファが飾られている。ヨアキムはその間をゆっくりと歩きながら喋った。
「私の人生の基調色は、誰が何と言おうと黒。彩のない黒だよ。石の裏側に隠れて住んでる気持ち悪い虫みたいに、人の目につかないところでコソコソ生きてるのが信条だったの。そうすれば誰も……誰一人として、とは言えないけれど、そんなにたくさんの人の目につくことはないし、誰かに傷つけられたり傷つけたりすることも減る。そう思って、『明るいところには出ない』って決め事を実行、そういう人生を生きてきた」
ヨアキムは歩き続け、赤い絨毯の敷かれた階段をのぼった。一階の床に施された黒白のタイル模様がよく見える踊り場で止まり、床を見下ろす。
「でも最近、それが一変しちゃってね。『プリティ・ウーマン』って映画が昔あったでしょ? あれを地で行く話になっちゃったのよ。もっとわかりやすく言うとシンデレラ。まあ私は映画や童話に出てくるような可愛い女でも男でもないんだけど」
ため息をつき、ヨアキムは再び歩き始めた。音もなく赤い絨毯に足が沈む。
「ああいうフィクションを見るたびに、こういう感想を言う友達がいたっけ。『どうしてあんなに何でも持ってる男が、どこにでもいるような女に惚れるの? 意味わかんなくない?』って。まあそれはそうよ。理解できる感想。でも逆に考えてみたら? って私は言った記憶がある。別に運命の相手は、特別な相手じゃなくていいの。いつかどこかの街角でぶつかる誰かレベルの存在でいい。あの映画や童話は、そういう意味での『運命の人』との出会いを描いてるだけで、別にヒロインが特別だからうまくいったってタイプの話じゃないよって。つまり運。そういう意味での運命。私たちに運がないのと同じように、他の誰かには運がある。それだけの話」
どう? と言わんばかりにヨアキムが腕を広げると、はは、という笑い声が小さく洋館に響いた。ヨアキムは特に何も答えず、ただ薄い微笑みを唇に乗せた。
「だから私、運があるのには全然、慣れてないの」
今度は笑い声は起きなかった。
ヨアキムは歩き、踊り場から二階までの階段をのぼり切ると、また口を開いた。
「……舞い上がっていられたうちはよかったのよ。家族に紹介してもらえた時もよかった。私にもこの人のためにできることがあるんだって、心から思えた。でも人の心って移り気なのよねえ。私そこまでガッツがあるわけじゃないの。だんだん疲れてきたの。自分がパパラッチに追い回される価値のある存在になるなんて思ったこともなかったし、安っぽい新聞の一面に自分の顔が載るなんて想像したこともなかった。でも一番予想外だったのは、それでも私のことを好きだって言ってくれる人が存在する世界があるってこと」
「それって何か問題がある?」
「あるのよ、ダーリン。あるの」
ヨアキムは二階の階段の手すりに軽く掴まり、吹き抜け構造になっている一階を見下ろした。
金茶色の髪をしたスーツ姿の男は、両手をパンツのポケットに突っ込んで、ただヨアキムのことを見上げていた。ヨアキムは微笑んだ。
「あなた、私に何か言いたいことがあるんでしょ」
「まあね」
「かなり前から準備していたやつ」
「うん」
「申し訳ないんだけど、私はそれを受け取りたくない」
「まだ言いだしてもいないんだけど?」
「何となくわかる。戻れなくなるから無理」
「そんなポイントはもうずっと前に越えてると思うよ、僕たち」
「あなたにとってはそうかもしれないけど、私には別にそうじゃないの」
「ふーん。あ、これは昔雇ってた相手の口ぐせね」
「……こういうこと言われると堪えない? あなたは自分のことを『幾らでも冷酷になれる男』なんて言ってたけど、一度懐に入れた相手にはすごく甘いし、過保護になる。そういう相手に内側から胸を引っ掻かれるのは痛いんじゃないの」
「痛くないよ。ちょっと気持ちいいくらい」
「マゾヒストタイプだったっけ?」
「お好みで変化しまーす。もう諦めてよ。ストーカーみたいな男と深く付き合っちゃったそっちが悪い。それこそ運がなかった」
「冗談」
ヨアキムは吐き捨てるように告げたが、相手は何も答えなかった。沈黙の後、自分自身にしびれをきらしたようにヨアキムは口火を切った。
「私は、私はね、自分が生きてることを『いいこと』だなんて思いたくないの。私が生まれてこなければ、きっともっと幸せだった人がいるのよ。少なくとも五人はそういう人の顔が浮かぶ。でもあなたといると、『もしかしていいこともあったのかも?』って思いそうになる。自分のそういうところが、私は堪らなく嫌なの。そんなことをしても今まで私がボロボロにしてきた相手に対して、過去にさかのぼって贖罪ができるわけじゃないのに、自分だけのうのうと暮らすことを肯定するなんて、気持ちが悪くて吐き気がする。これは自罰的な感情なんかじゃなくてね、理性的に考えて導き出した結論」
階下の男は何も言わず、じっとヨアキムを見上げていた。
眼差しに促されるように、ヨアキムは再び口を開いた。
「……でも、できることなら、あなたの傍にいて、あなたが魘されてる夜に起こしてあげたいとも思う。あなたも私と同じ傷を持ってることを知ってるから。そういう生き方がしたいとも思う。それも本当の気持ち」
「ありがとう。じゃあやっぱり、僕の結論は変わらないな。あと、そういう気持ちを打ち明けてくれることが嬉しいよ」
「…………」
黙り込んだヨアキムに、ジェフリーは少し得意げな顔で微笑みかけた。
「意図してか否かはわからないけど、君、初めて会った頃は、ずっと僕に幼稚園の先生みたいに接してくれてたんだよ。あの時の僕は本当にボロボロで、自分でも気づかないうちに消耗してたから、それを君が察知して、ヨシヨシってあやしてくれてたんだと思う。でも幼稚園の先生と幼児とは恋愛しないよ。『できます』って言う大人がいたら逃げた方がいい。よね?」
「ん、そこは同意」
「ありがとう。そんなわけで僕はかなり回復させてもらって、まあその後も軽くボコボコにされたりなんなりして落ち込んでたけど、君のおかげで持ち直してきて今に至る。ヘンリーに任せていた仕事も、三分の二くらいは取り戻したし、今後はもっとやれるぞって希望にも満ち溢れてる。君もそれはわかってると思うけど、どう?」
「その認識で間違ってない」
「どうもね。だから今度は僕の番なんだよ」
ヨアキムは黙った。
ジェフリー・クレアモントは微笑みを浮かべ、腕を広げて二階を見上げた。
「弱気なことを考えたくなったんだよね? それを僕に見せたくなくて逃げた。いいよ、どんどん逃げてよ。僕にひどいことを言いたくなったりした? オーケーオーケー、好きなだけ言ってよ。だってそれは君が僕のことを『あ、この人そのくらいなら受け止めてくれるかも』って思い始めてくれた証拠でしょ? 僕はもう君にヨシヨシされるだけの存在じゃないよ。君のことも守ったりできる」
「そんなのは前からそうだったでしょ。私とあなたでは」
「メンタル面の話。地位とか財政とかじゃなくて。君はずっと僕を守ってた。おかげで僕は、文字通り命拾いした」
ヨアキムは言い返さなかった。
ジェフリーは微笑みながら言葉を続けた。
「うちの家系にはどうも、自分とは違うルーツの人に助けられる運命があるみたいなんだよね。リチャードにとっての中田くん然り、兄にとっての晴良くん然り、祖父にとってのレアおばあちゃん然り。だから僕の運命のパートナーや親友も日系やスリランカ系の人なのかな? って思ってたけど、そうじゃなかったな。まあ三人揃って日本人だったとしたら、智恵子の影響が偉大すぎるから、そこはちょうどよかったのかもしれないけど」
「私の血、だいぶさかのぼるとパキスタン系も入ってるらしいよ」
「中央アジアかあ、いいところだね。ああ失礼。世界を好きに切り分けたイギリス貴族の末裔がこんなことを言うのは不躾だ」
ジェフリーは芝居がかった仕草で首を傾げ、再びヨアキムを見上げた。
「僕は完璧な人間じゃない。どっちかって言うと悪辣で卑怯で、誰かと真心を通わせたりするのは苦手な方だ。でも君はそんな人間を助けちゃった。夜の海で溺れてる王子さまを助けてくれた人魚姫みたいに、僕のライフセーバーになってくれたんだよ。その時君はガッチリ罠にかかっちゃったんだな。一度くらいついたら放さないイギリス製のトラバサミに。だからもう諦めてほしい。このトラバサミはけっこう居心地がいいおうちにもなったりするし、時々はモーニングティーのサービスなんかもする」
薄い赤絨毯を踏みしめ、二人目の人間が階段をのぼった。足音は一組だけだった。ヨアキムは階段を見下ろす場所を離れようとしない。もともと小さな階段が一つしかない家なので、逃げ場がないだけではある。
だがヨアキムは、そこに立ったまま、まっすぐに目の前の人物を見つめていた。
ジェフリーは微笑んだ。
「今度は君に甘えてほしいな。幼稚園の先生はしたことがないけど、お兄ちゃん属性はあると思うから、好きなだけ甘えてほしい。君の気が済むまででろっでろに甘やかして、元に戻れなくなるまでとろけさせてあげる。そのくらいはさせてよ。少なくともあと五、六十年は」
「…………スパンが長い」
「そんなの。大英帝国の栄光と略奪の歴史に比べたら一瞬だ」
「あなたって本当に自分の国が嫌いなのねえ」
「イギリス自慢をするイギリス人なんかイギリス人じゃないよ」
ヨアキムは笑った。仕方ない、とでも言わんばかりの、どこか悲哀が滲む笑みだった。
ジェフリーは残りの階段を、二階に到達する一段前までのぼりきると、そこに膝をついた。ギギイー、という鈍い音が響き渡る。
そして懐から宝石箱を取り出し、ヨアキムの前で開いてみせた。
「……宝石」
「指輪だよ。返事はまだしてくれなくていい。でもこれは預かってくれないかな?」
箱の中のクッションに鎮座する指輪には、蒸留酒のような金色の石がセッティングされていた。カナリアイエローの石は、しかし光を反射すると七色に煌めく。
ダイアモンドであった。
それもとびきり大きな。
指につけたら骨が折れそうなサイズの石に、ヨアキムは再び呆れ混じりに微笑んだ。
「ゴルフボールくらいあるけど、本物の宝石なんだよね?」
「多分そうだと思うけど、違うかもしれないから噛んでみる? すごく大きな口を開いたら噛めるかも」
「金のコインじゃないんだから。いいから立って。そんなところに跪いてると後ろに倒れそうで怖い」
「じゃあ可及的速やかにお返事が欲しいなあ」
どんな返事でもいいよ、と。
ジェフリーが笑うと、ヨアキムは顔を背けた。
「……申し訳ないけど、返事ができない。私、今までの人生で経験したことのない嵐の中にいて、自分で自分のことがわからないの。何をするかもわからないよ。いきなり日本に逃げたんだから、次はスリランカかも」
「いいよ。どこにでも逃げなよ。どこまででも追いかけるから。もちろん安全にだけは注意してほしいけど」
「とりあえず立って」
「はいはい」
膝をはたいて立ち上がったジェフリーは、今度こそヨアキムと同じ二階の床に降り立った。ヨアキムは一歩退き、ジェフリーに触れるのを躊躇った。
「大丈夫?」
パートナーが尋ねる声に、ヨアキムは顔を伏せたまま喋った。
「あなたは…………あんなに、あんなにひどいことをSNSや新聞や雑誌にいっぱい書かれたのに、まだ私と一緒にいる方がいいって、本当に思ってくれるの? それってただの意地じゃないの? 心から五、六十年後の自分のことを考えてる?」
「考えてるよ。なんならお墓のことまで考えてる。その上で、君のことを放すなんてありえないって確信がある」
ヨアキムは俯いたまま顔を上げなかった。そうだなあ、と首を傾げ、ジェフリーは再び喋り始めた。
「君は、このダイヤの名前を知ってる? 今の形にリカットされる前の名前だけど」
「……ダイヤの『名前』?」
「うん。世界には幾つか名前を授けられたダイヤモンドがあるんだ。たとえば、もう分割されちゃったけれど英国王室の至宝カリナン。有名どころでは不幸を呼ぶホープ・ダイヤとか。このダイヤモンドは」
「ちょっと待って。あなたそんなものを家から持ち出してきたの」
「家っていうか会社だけど、それって何か問題がある? 文房具店で封筒を買うのと同じに、お金を出して買って、保管してもらっている我が家の持ち物だよ。兄の許可も取った。それで、このダイヤモンドの名前はね」
インコンパラブル。
ジェフリーはそう発音した。
ヨアキムが目をしばたたかせると、ダイヤモンドを差し出す男は笑った。
「意味は『比較できない』『比肩するもののない』。人間さ、誰かを好きになると、そういうことがよくわかるようになるよ。君の代わりなんか世界のどこにもいないんだ。いないんだよ、キム」
「…………」
「雑音はただの雑音。それで大切なことを見失うなんて愚かだよ。あー、メロドラマっぽい台詞は得意だから、あと千個くらい言えるけど、もっと試す?」
「……しばらくはいい」
「オーケー」
ジェフリーはヨアキムに抱きつこうとし、あっと気づいたような顔をして、上目遣いにご機嫌うかがいをした。ヨアキムは脱力したように笑い、自分からパートナーを抱き寄せた。
「…………あなたを嫌いになったから逃げたって言いたかった。でもできなかった。あーあ、ヨアキムさんも焼きが回っちゃったね」
「幾らでも言えばいいよ。『ふーん、でも僕は愛してるよ!』で解決だ」
「わかってないね。あなたにそんな言葉を聞かせたくないのよ」
「でも大してダメージは受けないよ?」
「あなたと一緒に暮らす間に、他人をサンドバッグ扱いしてヘラヘラしてるやつらを見過ぎたの。これ以上同類の真似をしたくない」
「……やっぱり僕は君が好きだなあ」
ジェフリーが柔らかく微笑むと、ヨアキムは対照的にへにょんと口を折り曲げた。
「うんと浪費をして『金目当てだったんだな』ってうんざりさせるプランもあったけど、あなたの従弟に『幾ら使ってもカードの限度額が来ないと思いますよ』って忠告されてやめた」
「試してみなよ。大体何とかなるよ」
「適当なノリでおぞましいことを言わないで」
ヨアキムがため息をついて歩き始めると、隣のジェフリーも続いた。常に開かれている洋館の入り口からは、声高くおしゃべりをする観光客が入ってきて、大きいねえ、きれいだねえ、と賑やかに言い交わしている。二人は階段を下り始めた。
「さっきの雨は止んだ?」
「だいぶ前に止んだよ。ねえ、逃亡者さんには申し訳ないんだけど、しばらく逃げるのは休憩にして、横浜の老舗ホテルで休憩しない? きれいなところでね、日本名物の瀟洒なデザート、プリンアラモード発祥の地らしいんだ。プリンアラモードの歴史って知ってる?」
「あなたね、私たちが何回この街でデートしたと思ってるの」
「覚えていてくれて嬉しいよ。でも歴史については初耳なんじゃない? その昔、第二次世界大戦後の進駐軍の話にまでさかのぼるんだけど……」
雨が止み、二人の去った山手の洋館には、穏やかな静けさが残った。
神立屋敷での出来事の後、真鈴は一日学校を休んだ。だが二日目からは登校してきた。みのると良太はいつものように突撃してゆき、大丈夫なのか、どこか具合が悪いところはないかと心配したが、真鈴もまた、いつものように女王然とした雰囲気で、
「しばらく放っておいてくれる?」
とだけ言った。二人の平民ならぬスーパー親友は、静かに従った。それが一番真鈴にいいと思ったからである。
「今日は進路のプリントの提出期限だよ。未提出の人は、今日中に、きっちり先生に出すように。忘れないようにね!」
進路指導のプリント、とみのるは呆然と呟いた。
全く何も記入できないまま、鞄のファイルの中で眠っている。先週はそれどころではなかった。あんた、将来どうするの、というお母さんの声が耳の中でこだまする。まるで世界がみのるに進路を決めろと迫っているような気がした。
朝のショートホームルームが終わると、良太は早々にトイレに行ってしまった。目を泳がせていたみのるは、ふと林くんに気づいた。林くんもみのるに気づき、手を上げた。
「ようみのる。どうしたんだ」
「林くん……」
みのるはよろよろと林くんに近づいていった。法廷通訳になりたいという林くん。将来の夢をきちんと思い描いている林くん。成績もアップした林くん。助けてほしかった。
「……僕も夢、見つけたいよ。お母さんにも『将来何になるの?』って言われたんだ。でも全然……思いつかないし、見つからなくて……どうしたらいいんだろう」
みのるが死にそうな顔で告げると、林くんは少し驚いたような顔をし、すぐに笑った。
「そんなことで悩んでいたのか! なあに、ひょっこり見つかるさ」
「ひょっこり?」
「そう、『ひょっこり』だ。ちなみにこの言葉はヒロシから習った。『ちなみに』もだな」
「ひょっこりってどういうこと?」
「そうだな、あー、もぐらが顔を出すみたいに……隠れているやつがいきなり顔を出すみたいに、ってことだ。そうだろう?」
「そうなんだ……」
「ははは! おいおい、俺がみのるに日本語を教えるんじゃあべこべだぞ」
「……じゃあ僕は林くんに中国語を教えなきゃだね」
「やってみろ、やってみろ!」
そのタイミングで良太がトイレから戻ってきて、三人はわいわいとゲームの話に突入することになった。みのるも何となく話を合わせたが、頭の中はプリントのことでいっぱいだった。
未来の自分。何がしたいか。どうなりたいか。
将来なんかずっと先だから放っておこう、とプリントが配られた日に良太は言った。できることならみのるもそうしたかった。でもそのうちきっと、お母さんとまた会う日がやってくる。それはとても嬉しいことだった。お母さんが少しずつ元気になっているところをきっと見られるはずである。
でもその時にまた、同じ質問をされたらと思うと、みのるは胸がきゅっとした。
え? あんた、まだ将来の夢がないの? お母さん心配だわ。
もたもたしてるうちに、すぐ大人になっちゃうわよ。
みのるはどうしたいの?
そんなことを言われても答えられず、がっかりした顔をさせてしまったら、もっとつらくなりそうだった。
ずんと落ち込んだみのるは、不意に肩を掴まれた。林くんである。
「お前、暗い。考え事しているな」
「う……うん」
「ヒロシから教わったことはまだある」
将来のことについてだ、と胸を張る林くんが、みのるには夏に中華街で目にした関羽さまのように見えた。堂々として、格好良く、いいことを言ってくれる大いなる存在に。
「未来のことって、誰かのために考えるものじゃない」
「……?」
「未来はな、みのる、自分のものなんだ。他の誰かの未来じゃない、お前の未来なんだよ」
「そ、それはそうだと思うけど」
「ヒロシに言われたのはそれだけだ。頑張れ。考えろ」
みのるはがくがくと頷き、良太はやれやれと言うように苦笑した。
「みのるはけっこう、つまんないことでも考えこむからなあ」
「……良太が考えなさすぎなんだよ」
「じゃー足して二で割ったらちょうどいいかもな!」
みのるは思わず笑ってしまった。そして少し、心の深呼吸ができた。
そもそも、慌てて探して、見つかるようなものとも思えない。
以前正義が言っていたように、答えがあるものでも、恐らくは、ない。
だったらもう、すみませんという気持ちで、書けるものを書くしかなかった。
みのるは机に戻り、シャープペンシルを握った。
「『自分のもの』……」
自分は何がしたいのか。
みのるの脳裏をよぎるのは、今までみのるのことを助けてくれた人たちの顔だった。一緒に住んで、食事も作ってくれたお母さん。今同じことをしてくれている正義。その正義に引き合わせてくれた児童相談所の人。正義と共にみのるにいろいろなことを教えてくれるリチャード。
みんな優しい人たちだった。
優しい人になりたいです、と書きかけて、みのるは考え直した。それは将来の夢というにはあまりにも漠然としていて、どっちかというと生活の目標のようなものに思えた。これは進路のアンケートである。
みのるはうんうんと考え、大丈夫かーという良太の声を聞き流しながら考え、考え。
何とか言葉を二行、絞り出した。
『好きな人たちを明るい気持ちにしてあげたい』
『そういう仕事がしたいです』
「…………」
見れば見るほど小学三年生くらいの作文に見えたが、今現在、みのるの全身全霊だった。
あまりに恥ずかしいので良太には見られないように裏返し、みのるは小走りで先生に提出にゆき、何でもないことをしたようなぶらぶらした歩調で席に戻った。椅子に座った時、みのるは小さくため息をついた。
林くんの『法廷通訳』や、真鈴の『世界で活躍するモデル』には、程遠いとしても。
自分にも小さな、将来の希望があるのだと、今のみのるは思えた。少なくともプリントに書いたのだから、全くないとは言えないはずである。お母さんに話すこともできそうだった。
続いてプリントを提出し、戻ってきた良太に、みのるはたまらず問いかけた。
「良太……最後の欄、何て書いた?」
「ああ? そんなの決まってるよ」
頑張ります! と良太は胸を張り、宣言した。みのるの反対側の隣の席の女子が、ぎょっとした顔をしたが、良太は気にしなかった。
「ああいうのはな、適当に『頑張ります!』って書いたらいいんだよ。先生はさ、言っちゃなんだけど一人で三十人分以上プリントを見るんだぞ。一枚一枚丁寧に読まないって」
みのるは肩の力ががっくりと抜けた。良太にとっては――そしてもしかしたらクラスの大多数にとっては、今回のプリントはその程度のものであるようだった。
自分は一体何をやっていたんだろう、恥ずかしい、と思いながらみのるは残りの時間をやりすごし、起立、礼、さようならー、という最後の挨拶を済ませて立ち上がった。今日は良太も家の用事があって、家族みんなで出かけるとかですぐ帰ってしまう。みのるも教室を早く出たかった。
そそくさと教室を出ようとすると。
「霧江」
川口先生がみのるを呼び止めた。
もう半年以上、みのるたちのクラス担任をしてくれている川口先生は、みのるの顔を見て、にっこり笑った。
「プリント見たぞ。いっぱい考えて書いてくれて、先生嬉しいよ。ありがとな」
さようならー、という生徒たちの声に応え、手を振って、先生は廊下を去っていった。
三十人分以上のプリントを読んでいるとしても、先生はけっこう、頑張って全員分のプリントを見てくれているようだった。
みのるは一応、いつもの階段でしばらく待った。だが案の定、真鈴はまた顔を出さなかった。とはいえ良太と二人で昼休みにクラスへ偵察に行った時には、宿題をしつつ周囲の女子とおしゃべりをしているのを目撃している。それほど深刻に心配することはないのかもしれなかった。
みのるは学校を後にし、受験の話をする三年生たちとすれ違い、塾のティッシュをくばっているスーツ姿の人たちを横目に見ながら、辿り慣れた帰路についた。
マンションに帰宅すると、当たり前のようにヨアキムがいた。ちょっと恥ずかしそうな、しかし晴れやかな顔をしている。何かいいことがあったのかな、とみのるが思っていると、ヨアキムはみのるに翻訳アプリの画面を見せた。
『突然ですが、私は他の国に逃げることにしました』
みのるが面食らうと、ヨアキムはおどけたポーズを取ってみせた。『逃げる』などと仰々しい言葉を使いつつ、そんなに深刻な話ではないらしい。しかし『戻る』ではなく『逃げる』である。よくわからなかった。
背後に控えているリチャードと正義に、みのるはただいまを伝えるかわりに質問した。
「ヨアキムさん、大丈夫だったんですか? 置き手紙があったって話だったのに……」
「うん。大丈夫だったみたいだよ。本当は一人で出て行くつもりだったみたいなんだけど、戻ってきてくれたし、さっきは食事もとったって」
「ダイジョウブ! アイムオーケー。ベリー・オーケー」
ベリー・オーケーなんて例文は教科書には出てこなかったな、と思いつつ、みのるは「アイム・グラッド」と答えた。みのるの数少ない手持ちの英語『よかったです』である。ヨアキムは微笑み、みのるの頭を撫でた。その後ろでリチャードと正義がどことなくやきもきした顔をしていた。
「みのるくん、そんなわけで今日はヨアキムさんのお見送りパーティ……になるんだけど」
「本人があまり盛大にはしてほしくないとのことでしたので、ホームパーティ風に」
その日の夕食は、みのるの感覚ではいつも通りだったが、ヨアキムにはジンジャーエールのかわりにビールが提供された。リチャードも正義もほぼ飲まないアルコール飲料である。最後にはプリンにフルーツを飾ったデザートが出てきて、みのるはようやく『ホームパーティ』の部分を味わった気がした。
ソファのヨアキムが脚を組んだ時、ちらりとアンクレットが光るのが見えた。ナワラタナ。星のお守り。メニー・フレンズ。宝石を集めること。
「……ヨアキムさん……あの」
「?」
昼間のアンケートに書いたことを、みのるはヨアキムに伝えたかった。だがそのままでは英語パワーが足りない。みのるはヨアキムに端末を借り、翻訳アプリに言葉を吹き込んだ。
「僕も、大切な宝石を、たくさん集めたいです。頑張ります」
声を聞いたリチャードと正義は、少し「おや」という顔をした。だがみのるは、まずはヨアキムに報告をしたかった。宝石の話をしてくれたダンサーで、気まぐれだが優しくて、これからすぐ立ち去ってしまうヨアキムに。
ヨアキムはしばらく、よくわからないような顔をしていたが、そのうち大きな瞳をさらに大きく見開き、長い睫毛をパチパチさせ、次の瞬間にはみのるをハグしていた。うわあ、香水だ、と思った時にはもう離れていたが、みのるは生まれて初めて『ハグ』というものをされた気がした。外国の人が挨拶でするという抱っこである。面妖な感触だった。
ヨアキムは何かをぺらぺらっと言い、リチャードが通訳してくれた。
「『あなたは成長したのですね、嬉しく思います』と言っています」
「成長……したんでしょうか?」
「はい。私もそう思います」
そうでもないだろうとみのるは思った。プリントに書いたことは『法廷通訳』などの立派な職業の名前ではなく、何となく小学生っぽい目標である。でも確かに、何かを書いたことは書いたのだった。
それを成長と誰かが思ってくれることが、みのるは嬉しかった。
そして寂しくなった。ヨアキムにはもう、少なくともしばらくは会えないのである。
質問したいことは、結局質問できないままだった。どうしてダンサーになったんですか。いつダンサーになろうと思いましたか。つらいことはありましたか。どんな時にやりがいを感じますか。
みのるの視線を感じたのか、ヨアキムは上機嫌な顔でみのるの頭を撫で、にっこり笑った。
「アスクミー・エニタイム。メイビー・ネクストタイム」
いつでも質問して。次の時でもいいよ、と。
ヨアキムはそう言ってくれたようだった。
「…………!」
みのるは真心を込めて、サンキューベリーマッチと返事をした。
リチャードと正義と一緒に、みのるは新横浜駅までヨアキムを送っていった。青い4WDは四人乗りになっても広々としている。夜の横浜の風景は眩い夜景でいっぱいで、きれいな反面、どことなく中身のない外側が光っているようで、少し寂しい感じがした。
新幹線の切符を買ったヨアキムは、最後にくるんと華麗に一回転し、前を向いて後ろ向きに歩くMJの真似をした後、みのるを指さし笑ってくれた。
「グッバーイ!」
ヨアキムは最後まで明るく面白く、みのるに優しい人だった。
だが夜のイベントはこれで終わらなかった。
みのるたち三人がマンションに戻ってくると、中に知らない人がいた。家の、中にである。
正義とリチャードは揃ってぎょっとし、みのるを後ろにかばったが、みのるはもう一段階驚いた。
家の中にいる誰かが、よくよく見ると知らない相手ではなかったからである。
「う、占い師さん……!」
「占い師? え? ……あっ、ジェフリーさん?」
「ジェフ、家に入る時には予め連絡しろとあれほど」
「ごめんごめん。誰もいなかったから仕方なくてさ。それにここ、忘れかけてるかもしれないけど、もとは僕の家だし」
怪しげな帽子とローブ姿ではなく、仕事に行くリチャードのような、しかしもう少しカジュアルな感じのする茶色のスーツ姿の男は、やはり占い師と同じ声で喋った。みのるが目をぱちぱちさせていると、スーツの男はにやっと笑って、小さく呟くように言った。
「サプライズ?」
「この人がジェフリーさん? この家の持ち主で、すごくいい人だっていう……?」
「えっ何それ。もっと聞かせて。みのるくんこんにちは。まだ挨拶してなかったけどジェフリー・クレアモントです。リチャードの従兄にあたります。おいしいアイスが食べたくない? アイスをあげるからその話をもっと聞かせてよ」
「ジェフ。それ以上言ったらあなたの鼻からアイスを詰め込む。それで、こちらには何の用事です」
リチャードの語調は厳しく、みのるは少し肌がぴりっとした。ジェフリーは何か気づいたようで、ごめんなさいと頭を下げた。リチャードにではなくみのるに。
「ごめんなさい。自分の家にいきなり知らない大人がいたら、ものすごく怖いよね。改めまして、霧江みのるくん、こんばんは。ジェフリーです。僕は普段はイギリスかアメリカで仕事をしているんだけど、諸事情で今は日本に滞在しています。ここに来た理由は、リチャードと中田くんとみのるくんにお礼を言いたかったのと、あと業務連絡」
「お礼?」
「僕の恋人がお世話になったみたいだから」
みのるはしばらく考えて、ああと納得した。ヨアキムのことである。
「で、でも……ヨアキムさん、『他の国に逃げる』って……」
「ああうん、そのあたりのことは聞いてる。楽しく安全にラグジュアリーに逃げてほしいな」
「それは『逃げる』なのでしょうか」
「キムが『逃げる』って言ってるんだから、それでいいんだよ」
そしてジェフリーはウインクをした。満足げな顔だった。
ヨアキムがジェフリーの恋人。ジェフリーはリチャードの家族。ということは将来的に、ヨアキムもリチャードの家族になるのかもしれなかった。賑やかな家族になりそうだな、とみのるは想像し、ちょっと楽しくなった。リチャードの家族になってくれるのなら、きっと本当に『ネクストタイム』がある。
ジェフリーは三人にもう一度、今度は深々と頭を下げた。
「本当にありがとうございました。キムのわがままに応えてくれて、放り出さないでくれて、優しく見守ってくれて。心からありがとう。今回は僕じゃない相手のところじゃないと意味がないみたいだったからハラハラしたけど、結果的には何とかなってよかった」
「そちらも大変ですね」
「君たちほどじゃないよ」
ジェフリーの言葉をリチャードと正義は適当に受け流した。そんなに大事な話でもなかったらしい、とみのるは思い、ほっと本音をこぼした。
「よかったです、ヨアキムさんに、また会えそうで……質問があったので……」
「質問?」
リチャードは怪訝な顔をした。それなら自分がかわりに尋ねようと言わんばかりの表情に、みのるは慌てて首を横に振った。
「あの……将来の希望のこと……ヨアキムさんにいろいろ聞いてみたくて」
「キムに? 将来の希望? 起業とか? オーケー、力になるよ」
「ジェフ」
よくわからないなりにみのるは苦笑し、何とかとんちんかんな誤解を解こうと思った。
「そうじゃなくて……僕の学校で、『将来のことを考えましょう』って課題があったので、ヨアキムさんにもいろいろ質問してみたくて……いつ夢を決めたのかとか、そういうことを」
「ああ、進路学習が始まったんだね」
正義はよく理解してくれたようだった。何ですかそれはという顔をするジェフリーに、後で話しますと告げ、正義はみのるに微笑みかけた。
「確かにヨアキムさんは、自分で自分の道を切り拓いてきた人だから、そういう質問をするのもすごく参考になると思うよ。でも、俺やリチャードに質問してくれてもいいからね」
「あっ……」
もっともな話だった。
だが近すぎて、質問するのが恥ずかしいし、申し訳ない。
そういう意味でヨアキムは、自分にとって質問をするのにちょうどいい距離にいてくれる人だったのだな、とみのるは改めて気づいた。
ジェフリーはしばらくみのるを見つめた後、楽しそうに笑った。
「ちなみに、君の将来の夢をうかがっても? 今のところの夢でいいよ。教えてくれないかな」
「ジェフ」
「だって気になるもん! ドロッセルマイヤーおじさん枠としては応援したいし」
「よくわからないたとえは慎んでください」
「あの……」
みのるはおずおずと答えた。『好きな人たちを明るい気持ちにしてあげたい。そういう仕事がしたい』。それはつまるところ。
「……優しい人に、なりたいです……」
そういうことになりそうだった。
三人の大人は顔を見合わせ、にっこりと微笑みを交わした後、交代交代にみのるの頭を撫でた。ジローとサブローもやってきて構ってくるので、みのるの手と顔はよだれでべちゃべちゃになった。
「そうかあ! すごい目標を立てたね。それはすごい。かなりすごい目標だよ」
「みのるさまは、私が同い年であった時にはまるで考えもできなかったことを、ご自分でお考えになっていたのですね。素晴らしいことです」
「うーん……身につまされる答えだったな……僕も今度企業買収に携わる時は、もうちょっとだけ手心を……おっと。今のは聞かなかったことにしてね」
最後にもう一度、正義がみのるの頭を撫でてくれた。ヨアキムのわしゃわしゃした豪快な撫で方とは違う、うんうんと頷くような撫で方と大きな手が、みのるは好きだった。
よくわからない横文字の飛び交う会話をジェフリーと交わした後、リチャードはおほんと咳払いをした。
「それでジェフ、業務連絡というのは?」
「ちょっとね。フランス語にしてもいい?」
ジェフリーは何かをぺらぺらと横文字で告げた。
途端にリチャードと正義の表情には緊張が走った。
自分はここにはいない方がいいのだろうと判断し、みのるは自主的に部屋に引っ込もうとした。こういう場面はお母さんと二人で暮らしている時にも、施設の人がやってきた際によくとっていた対応だった。
だが。
「ジェフリーさん、待ってください」
正義が日本語で喋った。
みのるが少し驚いた時、正義は言葉を続けた。
「この話はみのるくんも一緒に聞いた方がいいと思う」
今度はみのるが緊張する番だった。
ジェフリーは「本当に?」と尋ねるように正義の顔を見た。みのるの緊張は恐怖に変わった。何を言われるのかわからない。
それでも正義は力強く頷いた。
「お願いします」
ジェフリーはしばらく唇を尖らせていたが、最後にちらりとリチャードの表情を見た後、にこりと笑った。
「じゃあ手短に。染野閑の消息がわかった」
その名前の響きは、みのるの体を真っ二つに割るような衝撃をもたらした。
【おわり】