宝石商リチャード氏の謎鑑定 再開のインコンパラブル 第二回
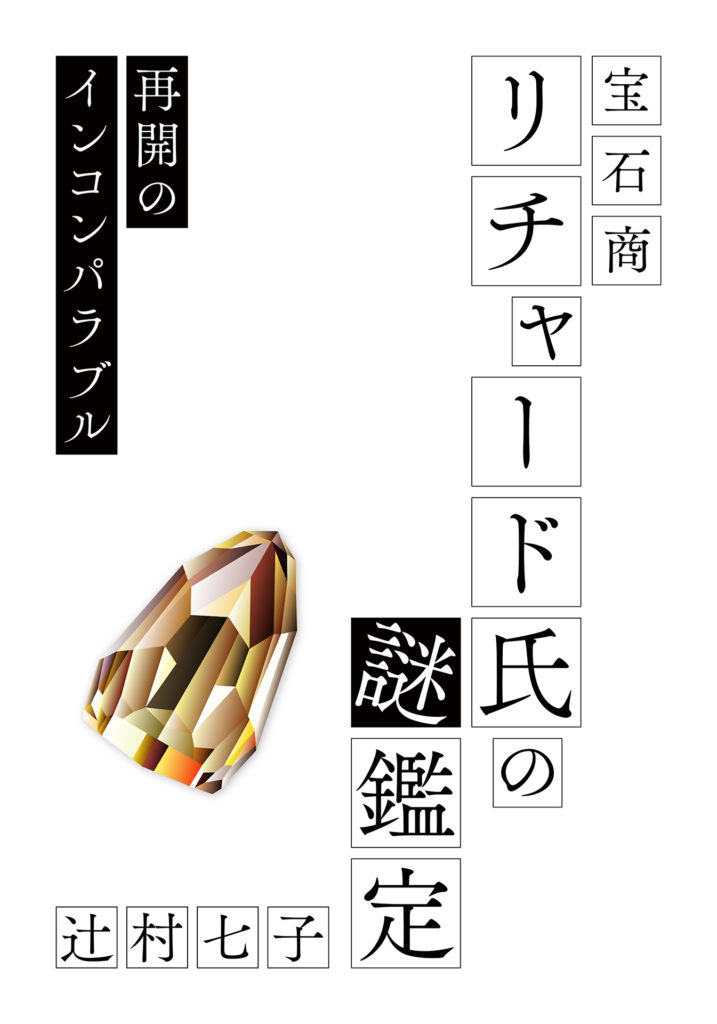
二話 ギターとマスターストーン
新しい開帆たよりには、一行目からよくわからないことが書かれていた。
『学習発表会が終わってクラスの団結力が増しました』と。
みのるは若干不思議な気分になった。団結力というのはどういうものなんだろうと考えても、うまく答えが出ない。良太に尋ねると、
「あれだよ。なんか、『みんなで頑張るぞ! 俺たちはひとつ!』って気持ちとか、そういうやつ」
そんな答えが返ってきた。しかし、じゃあ良太の中ではそういう気持ちがアップした感じがするのかと質問を重ねると、いや特にそんなことはねーよという答えと爆笑が返ってくる。なおのことわからなかった。謎である。先生もけっこう適当なことを書いているのかもしれなかった。
ヨアキムはまだマンションにおり、喧嘩別れした相手と仲直りしたという情報もない。
日々はゆっくりと過ぎていった。
移動教室の音楽の授業で、みのるたちは『世界の音楽』という単元に入り、ヨーロッパのいろいろな国の歌を聞いた。イギリスの『蛍の光』。フランスの『オー・シャンゼリゼ』。イタリアの『フニクリ・フニクラ』。みんな知ってる歌じゃん、と良太が笑い、それはあまりにも有名だからヨーロッパの歌が日本に伝わってきたからですよと先生に言われ、ちょっとクラスが受けていた。
みのるは少し、あれ、と思った。
正義がよく歌っている歌の雰囲気が、その中のどれかに、ちょっとだけ似ていたのである。
授業が終わると、クラスの中のピアノを習っている女の子が、休み時間中には触っていいことになっているピアノの前に座り、最近人気のアニメソングや、友達のリクエストの曲を弾き始めた。
みのるは今までその子に話しかけたことはなかったが、少しだけ勇気を出すことにした。
「ね……ねえ、この曲……多分知らないと思うけど……もしかして、知ってる?」
みのるは正義の『朝ごはんの歌』を、歌詞ぬきでハミングした。
ほかほかのあさごはん。できたてのあさごはん。
すると。
「それってこれ?」
いつの間にか後ろに立っていた先生が、クラスの女子の隣に立ち、鍵盤にそっと手を伸ばした。
みのるが鼻歌でうたったのと同じ旋律を、先生は一度で弾いてくれた。
「そ、それです……!」
「みのるくん、よくこんな曲を知ってるね。おうちの人の趣味?」
「えっ」
ということは、正義の朝ごはんの歌は、知名度のある歌なのか。
もっと教えてくださいという前に、キーンコーンカーンコーン、という予鈴が鳴った。先生は立ち上がり、はいはいとまだ音楽室にたむろする生徒たちを促した。
「次の授業に遅れますよ! みんな退室してください」
じゃあね、と先生はみのるに手を振ってくれた。出て行くしかなかった。
結局あの歌は何なのだろう、今度正義にちゃんと聞いてみよう、とみのるは思っていたが、その後の数学の授業が難しくて、疑問はいつの間にか雲散霧消していった。
放課後、良太は『オー・シャンゼリゼ』をふざけて歌いながら、配られたばかりのプリントをぴらぴらさせていた。
「このイベント何だっけ? 秋の遠足?」
お気楽な良太の台詞に、真鈴はハーッとため息をついた。
「小学校じゃないんだから、秋の遠足なんかないでしょ。芸術鑑賞会」
「芸術鑑賞会って何?」
「ギタリストが来るんだって。芸術家。っていうかミュージシャン」
みんなでギターを聞くんでしょ、と真鈴が言うと、良太は眉毛をうにょんと曲げた。
「なんか退屈そうだなー」
「それよりみのる、またキムさんと、っていうか中田さんと会えそうなチャンスはないの?キムさんはみのるの家にいるんでしょ。ダンスを教えてくれたお礼にクッキー焼いて持って行きたいんだけど。中田さんのいる日を教えてくれない?」
「あっそうそう! みのる、俺の姉ちゃんとも会ってやってくれよ。本当に会いたいんだって」
みのると真鈴は揃って良太を見た。
訳がわからない様子の良太は、え? と言って怪訝な顔をするだけだった。みのるの代わりに真鈴が質問してくれた。
「みのるに会いたい? って何で?」
「は? 何でって………………何でだろ?」
「そんなこともわからないまま使い走りをしてたわけ。何か理由があるんだとしても、私には全然思い当たらないし、その顔じゃみのるも同じでしょ。何でなの? 要件もわからないのにそんなこと言ってるわけじゃないでしょうね」
良太はばつの悪そうな顔をした。要件は本当にわからないし、見当もつかないらしい。
「ちょ、待ってろ。今姉ちゃんに連絡するから」
「あんたのお姉さんって高校生? 大学生?」
「高一だよ。学級委員。兄貴は受験でカリカリしてる高三」
「なんだ。じゃあ中田さんに勉強を習いたいとか、そういうことかもしれないね」
「違うと思うけど? 何か……微妙に怒ってるみたいだったし」
「『怒ってる』?」
みのるは急に不安になった。ヨアキムがやってきて急にお泊まりをさせてもらった日、もしかしたらみのるが何か失礼なことをしていて、ずっと怒っているのかもしれなかった。
真鈴は硬い顔をして、良太をねめつけるように見ていた。
「理解できないんだけど。高校生の女の人が、中学生の男の子に何を怒るっていうの? みのるは盗撮とかセクハラとか、間違ってもするタイプじゃないでしょ。うっかりみのるがお姉さんのお菓子を食べたとかだったら、みのるじゃなくて良太に言いそうだし」
「そりゃあそうだな」
みのるはますます不安になり、怖くなった。何か勘違いされているのかもしれないと思ったが、良太はいつものあっけらかんとした顔で、わからないと首を横に振るだけである。良太は嘆息した。
「お前らさー、俺の姉ちゃんを何だと思ってんだよ。しっかり者なんだぞ。俺のことだって意味もなく怒ったりしないよ。何かこだわってるみたいだったし、一度聞くだけ聞いてやってくれないかな?」
「あんたは自分のお姉さんの人間性を信頼してるわけね」
「信頼って何だよ。家族なんだから当たり前だろ」
真鈴はその言葉には答えず、みのるを見た。
「みのる、良太のお姉さんの呼び出しだけど、私も同席していい? いいよね。良太、許可取って。お姉さんにそれでもいいか質問して」
「え……面倒くさいから勝手についてくれば……」
「駄目。友達代表としてついていってもいいですかってちゃんと聞いて」
良太は面倒くさそうな顔をしながら、それでも姉にメッセージを投げた。
休み時間になっていたらしく、返事はすぐにあった。良太は首を横に振った。
「駄目だって。なんか、センシティブな話だからって」
ぞっとするような返事に、みのるは真鈴の顔を見た。真鈴は厳しい表情でみのるを見た。
「確認するけど、みのるは本当に、良太のお姉さんに変なことしてないんだよね」
「ぜ、絶対にしてない……! と思う……! で、でも……わからない……もしかしたら」
「そのくらいの認識ならまず平気でしょ。『もしかしたら』レベルのことで、女子は『センシティブ』なんて言葉は使わない」
「ほんとにぃ?」
「君のお姉さんが私と同じ感覚ならってこと! 一々補足させないで」
つまり良太のお姉さんは、それなりのレベルのことをみのるに言いたいようだった。
みのるは血の気が引き、足元がふらふらしてきた。見かねた良太が階段に座らせると、真鈴は苛立たし気に腕組みをし、そうだと大きな瞳を見開いた。
「今ここで話をしてもらうのはどう? どうせ高校生も昼休みでしょ。電話をかけて、マンツーマンで話をしてもらったら? 学級委員なんかしてる人なんだし、本当に何か言いたいことがあるなら、電話越しでだって言ってくれるんじゃないの。これだけ勿体ぶって待たせる方が失礼だと思う」
良太はしぶしぶ電話をかけた。
だが結局、良太の姉は電話に出ず、コールバックもしてこなかった。そのかわりメールが返ってきて、放課後に中学校の最寄りのファストフード店の二階で、みのるを待っているという。
「…………」
みのるは怖かった。あまりにも怖すぎた。良太と真鈴は、一も二もなくついてくると言った。一階で待っていればわからないからと。ありがたいことこの上ない申し出だった。
「…………」
放課後。ファストフード店二階に続く階段をのぼりながら、みのるは人生有数の緊張感を味わっていた。そもそも中学生だけでファストフード店に行くだけでも緊張するのに、ひとりで高校生に呼び出されるなど壮絶である。
良太の姉、赤木秋穂は、近くの高校の制服を着ていて、みのるを見つけるとすぐ立ち上がり、席へ促した。みのるは身を守る防具のようにシェイクを胸の前に持ったまま着席した。
「ごめんね、いきなり来てもらったりして。びっくりしたよね、友達のお姉ちゃんにこんな風に呼び出されるなんて」
「…………」
本当にその通りです、という気持ちが伝わったのか、秋穂は申し訳なさそうな顔をした。
だが「帰っていいよ」とは言わなかった。やっぱり本当に話したいことがあるようだった。
みのるが押し黙っていると、秋穂は深呼吸をした後、真面目な顔をした。さっきまでの笑顔の方がわざとらしかったので、秋穂も本当はとても緊張していたようだった。
「みのるくん、ごめんね。正直こんなこと私も言いたくなかったけど……やっぱり気になって」
「気になるって……どういうことですか」
「『きれい』の話」
みのるは目を見開いた。何の話かわからない。秋穂は説明してくれた。
「泊まりに来た時に、ちらっと言ってたよね。みのるくんは正義さんとリチャードさんと三人暮らしで、正義さんは毎日リチャードさんのことを『きれいだなあ』って褒めるって。これは本当?」
そういえばそんなことを言ったかな、とみのるは思い出を辿り、あやふやに頷いた。ともあれ真実ではある。
「本当ですけど……」
それがどうかしたんですかと、みのるは尋ねる代わりに秋穂を見つめた。秋穂は何か不吉な言葉を聞いたように黙りこみ、怖くなるほど何十秒も黙った後、切り出した。
「みのるくんって、お母さんとお父さんはどうしたの? 良太に聞いても『知らない』って言うの」
「……お母さん、入院してます。お父さんは……ちょっと。正義さんは、親戚です」
「じゃあリチャードさんはどういう人なの」
「正義さんの上司で、たぶん、友達です」
「上司で友達の人と、正義さんは同居してるの」
「そ、そう思います」
「それってどういう関係なの?」
みのるはしばらく、質問の意味がわからなかった。え? と問い返すこともできなかった。ただ秋穂が何も言わずに待っているので、何か言わなければならないことだけはわかった。
「ええっと、だから……上司で、友達……?」
「本当にそれだけなの」
「ちょっとわからないです……」
これって何なんですか? というのが、今みのるが一番尋ねたいことだった。初めてではないものの、まだ二度しか会ったことのない良太の姉に、どうしてこんな立ち入った質問をされるのかわからない。しかしそういうことを言葉にする方法もわからなかった。
泣きそうな気持ちで黙っていると、秋穂は何かを勘違いしたのか言葉を続けた。
「あのね、児童相談所って知ってる?」
知っているも何も、みのるには縁の深い場所だった。だが良太にもそんなことは話したことがない。秋穂も知っているはずがなかった。みのるは胸の内側をやすりがけされているような気がした。
秋穂は言葉を続けた。
「もしみのるくんが、正義さんたちと一緒に暮らすのが嫌だったり、怖いと思ったりすることがあったら、そこに行くと話を聞いてくれるの。もしよかったら、私が一緒に行ってもいいよ」
「嫌です」
はっきりとみのるは告げた。熱いものに触った時、ぱっと手を離すくらいの勢いで、喉から言葉が出た。
みのるは秋穂の顔をまっすぐ睨み、言葉が出てくるのに任せて喋った。
「僕は、正義さんとリチャードさんと一緒に暮らすのが、好きです。不満とか、ないです。本当にないです。あの……さよなら」
みのるは席を蹴立て、シェイクを置いたまま階段を駆け下りた。すかさず真鈴と良太がジュースを放り出して近づいてくる。
「みのる、どうだったの」
「うわ……お前すごい顔してるぞ」
息をするだけで精一杯になっていたみのるを、二人は店から連れ出し、道路を渡ったところにある海沿いの公園に連れだした。だが冷たい空気を吸っても、みのるの気分は晴れなかった。
何も言えずに固まっていると、そのうち良太が激昂した。
「俺、姉ちゃんに抗議してくる。ひでえよ。何してくれてんだよ、俺のスーパー親友によ」
再び道路を渡って店に戻ろうとする良太を、みのるは慌てて引き留めた。
「いいよ、いいよ! お姉さん、悪いことを言ったわけじゃないよ。ただ……」
何と言えばいいのかみのるにはわからなかった。いきなりぶたれたような衝撃だったのは確かである。だが秋穂にそんなつもりがないであろうことはわかっていた。とはいえわからないなりに、良太と真鈴はみのるが何か言わなければ納得しそうにない。みのるは言葉を絞り出した。
「……心配して、くれてたんだと思う」
「『心配』?」
「具体的にどういうことを言われたの。君の言える範囲で話して」
言える範囲のことなどなかった。
みのるはごめんと言って、二人の前からも去った。
みのるは神立屋敷への道のりを覚えていられなかった。毎日目にする通りである。毎度目に焼き付けるようなものではなかったが、それでも急にワープしたと言われても信じてしまいそうなほど、屋敷の前に立つまでの間の記憶がなかった。
朝に聞いた予定通りに動いているのなら、屋敷の中にはリチャードがいるはずである。
みのるは鍵を使って扉を開け、屋敷の中へと踏み込んだ。回数を重ねるごとに屋敷の中はきれいになっていて、今は扉の前に靴の泥を落とすためのマットが置かれていた。そのうち靴を脱いで入ることになるかもしれないと思った時、みのるは少しぞっとした。
その後は?
この屋敷が限界まできれいになった時、リチャードはまだここにいてくれるのか?
正義は?
大広間に踏み込むと、ソファの上に誰かが座っていた。リチャードではない。
大きな箱のようなものを抱きしめているのは、正義と同じくらいの年頃に見える男性だった。茶色い髪の毛を首の後ろで筆のように結っている。
「あ……」
みのるが立ちすくんだ時、男性もみのるに気づいて顔を上げた。人懐こそうな顔をしている男性は、にこっと笑った。
「お客さん? 待って。今リチャードさんを呼ぶから。リチャードさーん! 小学生か中学生くらいの男の子が来てるー!」
リチャードの知り合いなのだと思った時、みのるはほっとした。リチャードのお客さまだったらすぐに帰らなければならないと思ったところだったのである。今日はそれは嫌だった。
手袋を外しながら階段を下りてきたリチャードは、みのるの姿を認めると、すぐにいつもの柔和な微笑みを浮かべた。
「お待たせしました、みのるさま…………みのるさま?」
笑顔を見た時、みのるは崩れ落ちそうになった。泣きたかったが、さっき良太が自分のことを『スーパー親友』と言ってくれたのを思い出して耐えた。リチャードを心配させたくなかった。
とはいえ「ちょっとつまらないことがあったんですけど」というふりはできそうもない。みのるは吐き出すように、ファストフード店でのことを打ち明けた。具体的に何が嫌だったとは言えないのだが、ともかく嫌だったということを伝えたかった。お母さんにもこんなことは言ったことがないのにと思ったが、リチャードならそれを受け止めてくれそうな気がした。もちろん正義でも。
リチャードは跪く姿勢でみのるの話を聞いた後、ゆっくりと頷き、答えた。
「その方はみのるさまのことを『心配』していらしたのですね。正義が私のことをきれいだと褒めるから、と。そしてみのるさまは、その言葉がつらかったのですね」
「……そうです」
わかりました、とリチャードは頷き、音もなく立ち上がった。
「私は一本電話をいたします。みのるさま、大変申し訳ないのですが、そこで三分ほど待っていただけますか。下村さま、よろしければ」
「OK、ここにいる」
挙手した『下村さま』を見た時、みのるは初めて、彼が抱いているのが箱ではなくギターであることに気づいた。ぴかぴかの飴色のギターを、彼は宝物のような手つきで抱きしめていた。そして少し、つまびいた。
ららん、という明るい音が、広い屋敷に響き渡った。
驚くみのるに、男性は明るく微笑みかけた。
「みのるくん――って呼んでいいのかな。何か好きな歌はある? 最近の曲でも、昔の曲でもいいよ」
「と……くには……ないです」
「オーケー。じゃあハルヨシセレクトで。あ、『晴れ』に良い子の『良い』で『晴良』だよ。ちょっと歌うけど、びっくりしないでね」
下村晴良。この人は日本人の名前を持っているようだった。
晴良が弾き語り始めたのは、みのるにはわからない歌だった。アイウナなんとかと繰り返し、よその国っぽい雰囲気の旋律をポロポロと奏でてゆく。華やかなのに、どことなく寂しい感じも漂う曲だった。
みのるの胸に、何故かしっくりとはまる歌だった。
ちゃららん、と最後にギターをかきならし、晴良は曲を締めくくった。同時にリチャードが戻ってきた。
「お待たせいたしました。すぐに正義がここに来ますよ」
「えっ。でも今日は銀座の日なんじゃ」
「ちょうど近くにいたのです。ご心配なく。いい機会でもあります」
それが嘘でも本当でも、みのるはほっとしていた。リチャードと正義が揃うのである。二人がいてくれるのなら、怖いものはない気がした。
三十分後。
「みのるくん、ただいま! ケーキ買ってきた!」
「何故こんな時にケーキを……」
「こんな時だからこそ、だろ。晴良もいてくれるんだし」
神立屋敷の中には中田正義とチョコレートケーキの姿があった。首都高をとばして銀座から帰ってきたとするならもっと時間がかかる。本当にある程度は近くにいたんだと、みのるは少しほっとした。
正義はリチャードからことの次第を聞いた後、本当にそうだった? とみのるに確認をしてくれた。みのるは頷いた。二人とも微笑んではいなかったが、かといってそこまで厳しい表情というわけでもない。大人二人が赤木秋穂のところに怒鳴り込みにゆく姿など見たくはなかったので、みのるは少しほっとした。
ほっとした後、悲しくなった。
一体これはどういう気持ちなのか、みのる自身よくわからなかった。
待っていればリチャードと正義、どちらかが何か言ってくれるだろうとは思った。だがみのるは待てなかった。
「あの……正義さんとリチャードさんが一緒に暮らしているのって、そんなに変なことなんですか? 僕は、変なことだとは思ってなかったです。でも変なことなんですか? 心配されることですか?」
みのるはそれが知りたかった。それだけが知りたかった。
俺は外すね、と言って下村晴良は席を立った。食べかけだったチョコレートケーキの皿とフォークもちゃっかり持ってゆく。ギターはとりあえず置き去りだった。
リチャードはちらりと正義を見た。正義はバトンを受け取ったような顔をし、みのるに語りかけた。
「それをどう思うかは、個人の心の問題になると思う。たとえば『結婚してない男の人と女の人が一緒に暮らしているなんて変』とか、『血が繋がっていないのに一緒にいるなんて変』とか、『収入が全然違うのに一緒にいるなんて変』とか。いろんなパターンがあって、その全部は俺も想像ができないと思うな。でも」
正義は間を置いた。みのるが正義の顔を見つめ返すと、正義は微かに笑った。
「みのるくんはどう思う?」
みのるには正義の笑顔が寂しそうに見えた。
無性に悲しい気持ちをおさえながら、みのるは喋った。
「わからないです。それが……変なのか、変じゃないのか、さっきからずっと考えてるんですけど、僕にはよくわからないです。お母さんとずっと二人だったから、家に男の人がいたことがないし……でも、もし『変』だったとしても、僕は正義さんとリチャードさんと一緒にいたいです。児童相談所に行きたいとは、思ってないです」
「そっか」
正義は朝と同じように、さわやかに微笑んだ。
そして少しだけ、躊躇うようなそぶりを見せてから、呟くように口にした。
「ありがとう」
え? とみのるが思った時には、正義は既にいつもの笑顔に戻っていた。
「そうだなあ、俺とリチャードの関係をどう説明したらいいのか……ちょっと難しいんだよな。何年か前までは『上司と部下』『めっちゃいい友達』だったと思うんだけど、最近はそこに少しずつ、『いい感じのパートナー』っていう属性も加わってる」
「パートナー?」
「『これからの人生も一緒にやっていきたい相手』、くらいの意味かな」
みのるの胸はざわついた。それがどういう存在なのかはわからないし、あまり耳にしたことのない言葉である。もしかしたらそういうものを良太のお姉さんは『変』だと言ったのかもしれなかった。みのるは自分で自分が嫌になりそうだった。たとえ正義とリチャードの関係が『変』でもそうではなくても、みのるはその空間に自分も加えてもらいたいと思っている。それは確かである。
だが、それが、客観的な意味で変なのか、変ではないのか。
どうしても気になって仕方がなかった。
みのるの顔色が冴えないことに気づいたらしく、正義は穏やかに言葉を続けた。
「みのるくんは、あんまりそういうのは好きじゃない?」
「……わからないです。他にそういう人を見たことがないし……聞いたこともないので」
「うん、そうかもしれないよなあ」
「それは、変なことなんですか……? 変じゃないですよね……?」
「変じゃない!」
という声は、正義のものでもリチャードのものでもなかった。しかも壁の向こうから聞こえてきた。
戻ってきた下村晴良は、空っぽのお皿の上にフォークを乗せてしずしずと運んでいた。
「正義ごめんな。『外す』って言ったのに。でもこれは俺が言いたいから、今だけ首を突っ込ませてくれ。お前たちの関係は『変』じゃないよ。こういうのは自分では言いにくいことかもしれないから俺が言うけど、『変』じゃないし、それを『おかしい』って言う相手がいたら『どこがどうおかしいんですか?』って俺は逆に質問したい。『そっちの方がもしかしたら変な意見じゃありませんか?』って言いたい」
すぱん、すぱん、と歯切れのいい言葉で下村晴良は告げた。正義は少し呆れた顔をしていたが、嬉しそうでもあった。
「晴良、お前なあ……」
「これでも世界を股にかけている音楽家なのでね、えへん。言うことはハッキリ言わないと伝わらないぜ、アミーゴ。それじゃまた外すから!」
「いや……別にここにいてもいいよ」
「だめ、だめ! みのるくんが話しにくいだろ」
そう言って下村晴良は再退場しようとしたが、思い出したようにローテーブルの上に皿とフォークを置いて、陽気に手を振って出て行った。正義やリチャードに比べると、ちょっと子どもっぽいところのある、親しみやすい人であるようだった。
部屋が静かになった後、正義は再び話し始めた。
「誰かと一緒にいたいと思うことって、みのるくんはどう思う? 変なこと? 普通のこと?」
「ふ……普通だと思います」
「そっか。じゃあ、特別な誰かと一緒にいたいと思うことは?」
「ふ、普通……?」
「じゃあもう一つだけ質問。『普通』って何だと思う?」
「え?」
普通とは――とは?
説明する必要もないこと。そういうものだとみんなわかっていること。
こんな風に尋ねられることのない、何かとても、しっかりした柱のようなもの。
みのるの混乱を見て取ったように、正義は話すのをやめ、しばらく経ってからまた言葉を継いだ。
「うん、すごく難しいことを質問してるのはわかってる。ただこれは、何て言うか、いつか考えなきゃいけない宿題みたいなものだと俺は思ってる。今じゃなくても、いつかは考えないと、心がグラグラしちゃう問題」
「心がグラグラ……」
それはまさに今のみのるの状態そのものだった。何を考えたらいいのかもわからない。普通とは何かと質問されていることはわかるが、それ以前にリチャードと正義の関係が気になって仕方がなかった。
「たとえば……いや、たとえばじゃないな。実際の話、俺にとって特別な、ずっと一緒にいたい相手はリチャードなんだ。すごく尊敬してるし、一緒にいると楽しい。俺が何か助けになれるなら何でもしたいし、困ったことがあったら傍にいたい。そういう相手の近くにいることは、みのるくんの感覚だと……どうだろう? 『普通か』『変か』の二択だと極端だから、『どう思うか』とか、フワッとした感覚でもいい。何か思ったことがあったら教えて。これは正解や間違いのある話じゃないから」
正義は多弁だったが、自分でそうとわかっているようで、言葉と言葉の合間にいつもより長く時間をとってくれた。そして笑顔もさわやかだった。
だがみのるの考えは、まるでまとまらなかった。
特別な、傍にいたい相手。それはみのるにとってのお母さんのような存在なのかもしれなかった。だがそうではないかもしれなかった。
それはむしろ、真鈴にとっての正義のような存在なのかもしれなかった。
一緒にいて、笑ってほしいと望むような。
あるいは、手を繋いで歩きたいと夢見るような。
それが『普通か』、『変か』? 『どう思うか』?
「…………」
みのるは黙り込むしかなかった。何が何だかわからないにもほどがある。
しばらく正義の顔を見ることもできなくなりそうで、みのるは本当に、心底、困り果てた。
ソファに座ったまま、自分の膝のあたりを見てぼんやりしていると、誰かがそっとみのるの膝頭に触れた。
リチャードだった。
「みのるさま、突然の話で驚かせたことをまずお詫び申し上げます。その上で、是非見ていただきたいものがあるのです」
「…………?」
「こちらを」
リチャードが懐から取り出したのは、柔らかそうな黒い起毛の布包みだった。開くと輝く石が一つ入っている。ひょっとして、とみのるが思った時、リチャードは答えをくれた。
「ダイヤモンドです。ですがただのダイヤではございません。マスターストーン、と私が呼んでいるものです」
「マスターストーン……?」
何だか良太の好きそうな、ゲームアイテムのような名前である。リチャードは言葉を続けた。
「ダイヤモンド鑑定機関などにおいて設けられている、各グレードの基準となる石の意ですが、私にとってはこれがマスターストーンです。目を慣らし、この石と比べてどう見えるか、という判断を行う指標にしている存在です」
「目を……慣らす」
「その通りです。この宝石よりも輝いているか否か、透明か否か、石の中に汚れて見えるものがあるか否か。そういう時の基準、指標となってくれる石です」
基準。指標。その言葉からみのるが連想するのは、この状況では一つだけだった。
変なのか、変じゃないのか。
リチャードはあまり感情の滲まない顔で、静かに言葉を続けた。
「人が成長する中で少しずつわかってゆくこととは存じますが、世の中には『自分で決めるしかないこと』が多々ございます。『どのような本を好みとするか』『何を美しいとするか』、そしてさきほどみのるさまが仰せになった『何が変で、何が変ではないのか』も、そのようなことの一つと存じます」
「僕が決めなきゃいけないんですか? 何で……?」
「他の誰も、あなたが何をどう思うのか、決めてはくれないからです」
言葉の意味を呑み込むまで、しばらく時間がかかったが、みのるは多少、わかった気がした。
変なものは、変。自分にとって変なら、それは変。
きれいなものは、きれい。自分にとってきれいなら、それは美しい。
良太のお姉さんが二人で話したいと言った時、同席してもよいかと助け舟を出してくれた真鈴もまた、自分の『マスターストーン』を持っていたのだと、みのるは思った。そしてみのるを守ってくれた。
みのるが小さく頷くと、リチャードは微笑んだ。
「みのるさまは現在、ご自身のマスターストーンを育んでいる最中と存じます。それは人間が生きてゆく中で徐々に変化してゆくもので、いつになれば完成というものではございません。ある程度成長するまでの間には、そもそも指標となってくれる石が、自身の中に存在しないように感じることもあるかもしれません」
「あ、あります……」
今まさにそういう状態です、とは言わなくても伝わったらしく、リチャードは微笑んだ。
「慌てる必要はありません。しかしどうか、考えることをやめないでください。考えたくない、苦しいと思った時にまで、自分自身の心を追い込む必要はございません。ですがまた、『考える』という階段の前に戻ってきてください。そして一段ずつで構いません。階段をのぼってゆくことを諦めないでほしいのです。あなたの瞳が、あなたのマスターストーンとなってくれる日まで」
「そ、れって、いつですか……?」
「そのうち、そのうち」
明るい声は正義のものだった。
リチャードの隣にやってきた正義の顔は、いつもと同じ、みのるを勇気づけるような笑顔だった。そんなにすぐに『マスターストーン』が手に入るとは思えなかったが、それでもいつかは『そのうち』がやってくる。
そんな風に言ってくれている気がした。
二人が何を言おうとしているのか、完全に理解できた気はしなかった。胸の中にはまだもやもやしたものがある。だが何を質問しても、失礼になりそうで怖かった。他の誰よりも親身になってくれる二人を嫌な気持ちにさせたくはない。
好奇心よりも、『二人が好き』という気持ちが、みのるの中では勝った。
だが一つ、どうしても気になることもあった。
何か質問はあるかな、という顔をしている二人の前で、みのるは一つだけ、質問をすることにした。挙手をする。リチャードが促す。みのるは口を開いた。
「『いい感じのパートナー』って……二人とか、三人に増えることもありますか?」
リチャードと正義は顔を見合わせた。そして同時にみのるを見た。
「そうですね、これはあくまで私の主観的な判断によるものではありますが」
「ないなあ」
「正義」
「割り込んでごめん。でも俺は『ないなあ』って思ってるから」
「……まあ、私もそうは思っていますよ。未来は不確定なものではありますが」
正義はひょっと肩をすくめた。
いずれにせよ、二人一致で『ありません』ということだった。
みのるがそれ以上何も質問しようとしないとわかると、正義は広間の外に出てゆき、携帯端末をいじっていた下村晴良を連れて戻ってきた。端末にはピアノの鍵盤が表示されていて、下村が言うには作曲アプリだという。下村は音楽が大好きなようだった。
もう少しここにいたいけれど迷惑かな、とみのるがまごまごしていると、下村はぱんと手を打ち合わせた。
「よーし! 景気づけに何か一曲歌わせてもらってもいいかな。こういう時に音楽があると、ちょっといいだろ」
「明るい曲をお願いいたします」
「承知しました、リチャードさん。中田ぁ、何かリクエストある?」
「正義。俺の名前は正義な」
「昔のお返しだよ」
そして下村晴良は再びギターを抱き、チューニングを合わせるように弦をつまびき、さっきと同じ元気な旋律を奏で始めた。じゃらじゃらじゃらじゃら、という音の洪水に、ひょっとしてこれはダンスの曲なのかなとみのるは思った。ヨアキムがいたら教えてもらえるかもしれなかった。
「これは……うーん、みのるくんは多分見てないと思うんだけど、連作アニメの映画のテーマ曲なんだ。パートスリーの中に出てくるスペイン語バージョンで、パートワンの挿入歌のカバーになってる」
みのるはもちろんそのアニメ映画は見ていなかったが、歌はいいなと思った。どういう意味の歌なんですかと尋ねると、正義は簡単に答えてくれた。『僕は君の友達だよ』という、励ましの歌だと。
「…………」
変か変でないか問題は、みのるの中では既に少し遠くなっていた。
それよりもっと心配なことがある。
みのるの心の中は、スーパー親友の一人、真鈴への気がかりでいっぱいだった。
「ヘーイ、キムさん。いきなり呼び出してごめん。忙しかった?」
「全然よ、マリリン。あんたと話したかったとこ」
マリリンこと真鈴とヨアキムは、中華街にほど近いファミレス店でハイタッチをした。二人の会話が流暢な英語であることに気づき、近隣の席の人間が少し物見高い顔をしたが、二人がまるで気にしないでいると、次第に無視するようになった。
長い脚を組んでどっかとボックス席に腰掛けるヨアキムは、ブラックのレザーブーツにブラックジーンズ、ブラックのビスチェにもこもこした灰色のフェイクファージャケットという姿だった。真鈴は大うけし、それどこで買ったのと尋ね、「ユニクロとドンキ」という答えにさらに爆笑した。
「マリリン、ダンスの発表動画見たよ。サイコーだったじゃない」
「おかげさまで。みのるも入ってくりゃよかったんだけど」
「あははは。まあ、タイミングってものがあるからね」
二人はタッチパネルをつつき、真鈴はドリンクバーのみ、ヨアキムはフライドポテトを注文した。
「えー、キムさんポテトとか食べるの。それでそのスタイルは嘘でしょ」
「地道な運動と収支計算。って言ってわかる? 足し算引き算よ」
「それはわかる。でも私ティーンだから、太りやすくて嫌になる」
「そのくらいの年で極端なダイエットすると後々大変だよ。ちゃんと食べるもの食べて」
「年取ってる人みんなそう言うよね。他人事って感じでウザ」
「お口が悪いのも損だよ、ベイビーちゃん」
口をとがらせた真鈴を、ヨアキムは愛しむべきものを見るような目で見つめた。真鈴は笑い、狭いテーブルの上に身を乗り出して、ヨアキムとの距離を詰めた。
「キムさんさあ、中田さんとリチャードさんの友達なんでしょ?」
「まあね。私はまずリチャードの義理のお兄さんと知り合って、その縁で二人と知り合ったんだけど」
「二人のガールフレンドのこととかも詳しい?」
「……ガールフレンド?」
「私、中田さん狙ってるの。忙しすぎて恋人つくる時間もないって感じの人でしょ? 私でもチャンスあるかなって」
真鈴はわざとらしく体をくねくねさせ、夢見る少女のようなマイムをしてみせた。ヨアキムを笑わせようとしているようだった。
だがヨアキムは笑わず、静かな表情をしていた。
真鈴が怪訝な表情をすると、少し窘めるような口調で、ヨアキムは告げた。
「マリリン、もしあんたがあの男を狙ってる理由が、忙しすぎて恋人つくる時間もなさそうだからってだけなら、やめた方がいいと思う。あいつは見た目よりかなり面倒くさい男だよ」
「キムさんやっぱり詳しいんだ! 私そういう話が聞きたい」
ヨアキムは嘆息し、頬杖をついて天井を眺めた。
「キムさん?」
「ん、いろいろ考えてたとこ。一応聞いておくけど、脈はありそうなの?」
「今のところ何にもなーい。中田さんカタいっていうか、私のこと女として見てないっていうか」
「その言葉にホッとした。あのね、三十近い男がティーンの女の子を『女』として見てたら、そいつはただの変態よ。小児性愛者。大人に相談するか、警察に行った方がいい案件」
「極端だなあ、そうでもなくない? 恋愛に年齢は関係ないよ」
「若い子が言う分には、その理屈もギリOKなのよ、ギリで。でも年取った方がそれを言い出したら駄目。アウト。気を付けてよ、マリリン。あんたの人生ここからが長いんだから」
「『年の差がえぐいからやめろ』って言ってる?」
真鈴は少しだけ真剣な調子で言い返した。ヨアキムもその真剣さを受け取った。
ちゃかしているわけではない、と真鈴が理解するだけの時間をとった後、ヨアキムはテーブルの上で手を組んだ。
「マリリン、何で正義と付き合いたいの? 理由が気になる。どうして他の男の子じゃ駄目なのなんて野暮なことが聞きたいわけじゃなくてね、どういうことを考えて付き合ってほしいって思ってるのか、詳しいことが知りたい。ちゃんと教えて」
「何か今日のキムさん、大人っぽいね」
「私ねえ、これでも正義より年上なんですけど」
「でも、何ていうか『大人』感はないよ」
「そういうのは人によるの。年齢じゃなくて」
さあ話して、とヨアキムが腕を広げると、真鈴は微笑み、腕組みをした。考えていますというポーズだった。次第に真剣な顔になり、俯く。
顔を上げた時、真鈴は黒いカーテンを開けるように左右の耳に長い髪をかけた。
「私は、少なくとも年上趣味とかじゃないよ。あんなに年の離れた人好きになったのは初めてだし。っていうか私は、そんなにホイホイ誰でも好きになるタイプじゃないし」
「初恋じゃないんだ」
「現実味のある相手なら初恋。その前は雑誌の芸能人に憧れてるだけだった。そのうち自分はイケメンのモデルが好きなんじゃなくてモデルの世界に憧れてるんだって気づいたけど」
「…………」
「中田さんとのことは、すごく真剣に考えてる。そもそも好きになってもらえないかもしれないけど、もし中田さんが私と付き合って、将来結婚してくれたら、すごく幸せになれると思うから。かっこいいし、頭いいし、あと……優しいから。私のこと変な口調で『美人だね』とか『可愛いね』とか言わないから。だからあの人がいい」
ティロティロ、ティロティロ、というファミレスの入店音が、二人の背後で響いた。その後もしばらく真鈴は黙っていたが、ヨアキムが口を開かないのを見ると、「これで終わり」と肩をすくめた。
ヨアキムは静かに微笑み、コップを傾けた。
「真鈴の言ってることはわかるけど、不思議ね。褒めてくれない方がグッとくるなんて」
「大体私は美少女だから、ああこれは嫌味じゃなくて事実ね。日本だと私は『美少女』ってカテゴリにいれられて、きれいだねーとか可愛いねーとか、パンダみたいに指さして言われるの。そういう存在なわけ。でも中田さんはそういうことしなかった。私のことを、カテゴリなしの一人の人間として見てくれてる感じがする。そういうところが好き」
「じゃあ、これからもずっと正義には褒めてほしくない?」
「ううん! もし特別な人になれたら、『きれいだね』『可愛いね』っていっぱい言ってほしいな。うわ、恥ずかしー。日本語じゃ絶対こんなこと言えない」
「あんたの英語って本当に様になってるけど、いつどこで習ったの?」
「ニュージーランドに交換留学してたことがあるの。でも留学中より留学前の方が大変でさ、英会話の先生が鬼みたいに厳しくて、私ひとりだけビシバシしごかれて、でもおかげで現地では全然困らなかった。ああー、中田さんはどんな風に英語を習ったんだろうな。おうちがお金持ちっぽいから、やっぱり幼児教育で家庭教師とか付けてもらってたのかな」
想像の翼を羽ばたかせる真鈴の前で、ヨアキムはフライドポテトをつまみながら喋った。
「教えてくれてありがと。でも意外だった。結婚のことまで考えてたなんてね」
「付き合ってほしい相手がいたらそのくらい考えるでしょ? キムさんの恋人もそうじゃないの? いるならだけど」
「…………まあね。でも私にはそれがちょっと、つらかったかな」
「え?」
「何でもない。そう、マリリンは真剣なんだね。ガンバルをしてるんだ」
「そう。アイム・ガンバッテル」
ヨアキムの日本語を受け、真鈴もまたミックス言語で返事をした。
長い脚を組み直し、ヨアキムはロングカクテルのように、円柱形の水のコップを傾けた。
「『ガンバル』って日本語を初めて聞いた時には、何それ? って思ったな。『ワーキング・ハード』って意味らしいけど、目的語がないじゃない? 『何を』ガンバルのかしら、ってすごく疑問だった。スタイルを取り繕うだけじゃないの? なんて。でも、違うのよね」
「キムさんも日本語を勉強したことがあるんだ」
「ううん……知り合いの人がね、すごい日本語マスターだから、それで時々聞いてたの」
「その人は? どんな人?」
「うざいイケメン」
口を開け膝を叩いて大笑いする真鈴を、ヨアキムは慈しむように見守った。そして真鈴が笑い終わると、静かに口を開いた。
「『ガンバル』って悪いことじゃないのよね。何でも真剣に取り組んだら、ちゃんといいことがある。それは当たり前のことだよね。トライした記憶は、自分の財産になってくれるもの」
「そうそう。求めよさらば与えられんって言葉もあるしね。意志あるところに道あり、とか」
「真鈴、今から大切なことを言う」
ヨアキムはマリリンではなく『真鈴』と呼び、静かな声で続けた。
「あなたの好意を、正義がどう思うか私にはわからない。でも受け止めてくれない可能性もある」
「だから諦めろって?」
「違う。一番大切なのは、あなたが自分でその理由を確かめることだと、私は思う。諦めるならそれでもいいけれど、私だったら、まず確かめる」
「……キムさんはアメリカの人でしょ? アメリカにも『告白』の文化ってあるの?」
「私の知る限りあんまりないけど、あなたと正義が自然と一緒に出かけるようになるところは想像できないから」
好きです付き合ってください式の告白によって、恋人関係が成立する日本とは違い、他国では『何となく一緒に遊びに行っているうちにそういう関係になる』という不文律のようなものが存在する。まさかヨアキムが『告白』をすすめてくるとは思わなかった真鈴は、やや狼狽し、その後笑った。
「どしたの?」
「驚いたけど、何か、初めて背中を押してくれる人に会えて、ちょっと嬉しい」
「応援してるのとは少し違うよ。真鈴が自分で確かめた方がいいって、それだけのこと。結果がどうなるかもわからない。でも忘れないで。私はいつでも真鈴の味方だし、心はあなたの傍にいるから」
仰々しいほどのヨアキムの言葉に、真鈴の笑顔はすうっと消え、瞳が冷たい光を帯びた。
「…………中田さん、付き合ってる人がいるの?」
「何度も言うけど、自分で確かめた方がいい」
「ちょっと怖いんだけど」
「そりゃそうだよ。誰だって自分の秘密を誰かに打ち明ける時には怖い。でも真鈴は弱虫じゃないでしょ」
「当然」
啖呵を切ると、真鈴はドリンクバーのウーロン茶をごくごくと飲み干し、手の甲で軽く口を拭った。ヨアキムは笑い、はやし立てた。
「マリリン、世界に羽ばたくのも遠い日じゃないよ」
「キムさんさあ、前に話してた『喧嘩した相手』とはもう切れて、もっといい相手探せば? 山ほどいるんじゃない? キムさんめっちゃいい人だもん」
「あら、ありがと。でも残念なんだけど、この世にあの人以上の男がいる気が全然しないの」
「ちゃんと好きなんじゃん。じゃあもう仲直り一択だね」
ヨアキムは曖昧に笑い、残りのフライドポテトをかきあつめるようにつまんだ。追加の注文をするかどうか、季節のデザートを一つとって二人でシェアしようか等、二人はわいわい騒いだが、結局その後は何も注文せず、店を出た。
「じゃあねキムさん。私ガンバルから」
去ってゆく真鈴に、ヨアキムは大きく手を振った。夕暮れ時、海のにおいのする風が吹く。長い髪をなぶられたヨアキムは、軽く目を細め、呟いた。
「……確かに一択だけど、選択が『仲直り』とは限らないのよね」
良太の姉は、あれ以降連絡を取ってこようとはしなかった。良太曰く「ちゃんと異議申し立てをした」そうだったが、秋穂は特に何も言わなかったという。みのるは「そう」とだけ答え、良太に言伝を頼むようなことはしなかった。そもそも言えそうなことがない。
秋穂には秋穂の考えがあるのだろうし、自分には自分の考えがある。まとまっていなくても、自分の考えは、ちゃんとある。みのるはそう信じることにした。
のんびりしているうちに、秋の小イベントである芸術鑑賞会の日がやってきた。一年生から三年生までが勢ぞろいで体育館に並び、椅子に座ってステージを見る。ゲストが来ているのである。
壇上に人が現れた時、みのるは目玉が飛び出しそうになった。
気鋭のギタリスト、二十八歳、横浜市出身。
他でもないあの下村晴良が、開帆中学校の体育館にゲストとして降臨していた。
若いねー、可愛い雰囲気の人だねー、という声を聞きながら、みのるは目をぱちぱちさせることしかできなかった。
大切そうにギターを抱いた下村晴良は、もう一人のゲストを舞台袖から呼んだ。赤と黒のドレスをまとった、体格のいいお団子ヘアの女性が出てきて、ぺこりと頭を下げる。五十歳くらいの年齢に見えた。
「今回は特別に、横浜市のフラメンコバーのダンサー、モリエさんにも来ていただきました。モリエさん、よろしくお願いします」
モリエは画板をちょっと大きくしたくらいのサイズの板を持っていて、壇上の床にその板を置いた。下村晴良も一度舞台袖にひっこみ、木箱を持って戻ってくる。下村は脚を開いてその箱の上に座った。モリエは板の上に立つ。
二人は視線を交わし、音楽を始めた。
そこから先は音の洪水だった。ギターだけではない。下村は弦をかき鳴らしながら歌い、モリエは踊った。踊る靴から発される音は、まるで踏むことで悪魔をやりこめているような力強さだった。みのるの近くで誰かが小さく「ひえ」と呻いた。怖いほどの迫力である。
濁流のような音の世界が終わると、下村はにこっと笑って喋り始めた。
「今のは『マラゲーニャ』っていう曲です。『マラガの女性』で、『マラゲーニャ』。マラガはスペインの地名ですね。俺は大学のフラメンコ同好会でこの曲に出会って、ああー、フラメンコギターっていいなー、なんて思いました。思い出の曲です。それじゃあ次」
下村晴良は癒し系のMCをいれつつ、しかし強靭に情熱的に音楽を続けた。途中でモリエは休憩に入り、下村だけが音楽を続ける。それでもみのるには、目の前で踊る火のようなダンサーが見える気がした。ギターの音そのものが、目には見えないダンサーの姿になって踊っているような気がした。
鑑賞会のしおりに書かれていた五曲を弾き切ると、下村は微笑みながら立ち上がった。
そして最後の挨拶を始めた。
「……自分がフラメンコギターを極めるためにスペインに行くと決めたのは大学生の頃で、音楽をしようと思う人間にしては、そんなに早いことじゃありませんでした。プロを目指す人たちは、それこそ皆さんくらいの年の頃から、バリバリ活動している人も多いです。でも俺は最初からそういう風に考えていたわけじゃなくて、とにかく好きだから、めっちゃ好きだから、もっとフラメンコギターのことを知りたいと思って修業を決めました。もちろん俺のことを『変なやつ』っていう人もたくさんいました。でも、自分の信じる道を進んだおかげで、今俺はここで、ギターを弾いてます。そのことをとても嬉しく、誇りに思います。誇りに思うっていうのはちょっと難しい言葉になっちゃうな……何て言えばいいだろう。そう、嬉しくてハッピーだな、これでよかったな、って思ってます。だからもし、皆さんの中に『それは変だ』って言われることがあっても、頑張ろうって気持ちがある人がいたら、その人は無条件でアミーゴ、アミーガ、つまり俺の仲間です。今日は本当にありがとうございました。ムーチャス・グラシアス!」
その後みのるたちは拍手をし、先生に言われていた通り、しばらく拍手をやめなかった。そうすると「とてもよかったです」「アンコールしてください」という意味になるのだと。予想通り下村は戻ってきて、いやあ、と照れたように後ろ頭をかいた。モリエも一緒に戻ってきた。
「ありがとうございます。それじゃあ最後に一曲。これは俺の……っていうか、俺と友達のオリジナル曲で、本当はギターとピアノの二重奏なんですけど、今回はギターのソロバージョンでお送りします」
モリエとアイコンタクトを交わし、下村は再びギターを抱いた。
最後の一曲は、明るいとも暗いとも言い難い、不思議な雰囲気の曲だった。威嚇するような靴音は封印され、タタタ、タタタ、という軽やかな音だけが聴こえる。フラメンコには怒りや悲しみなどの激しい感情がいっぱい入っています、と下村はMCでさらりと伝えていたが、この曲にはそういう激しい感情の影は見当たらないように思えた。
下村は今度こそ名残惜しそうに舞台袖に引っ込んでゆき、芸術鑑賞会は終わった。
「思ってたより楽しかったねー」
「ギターってけっこうすごいんだね」
「でもあの人、何でフラメンコにはまったんだろう?」
「言ってたじゃん、大学で好きになったって。感想シート書かされるよ」
「そんなの『よかったです』でいいじゃん、めんどくさー」
ダレた空気で感想シートを書き終わると、その日の授業はそれで終わりだった。書き終わった人から帰ってよしというので、みのるは『よかったです』『ギターってすごいと思いました』など当たり障りのないことを書き、最後に『下村さんありがとうございました』とお礼を書き添えて、そそくさと教室を後にした。
閉鎖された屋上に続く階段には、案の定良太と真鈴がいた。
「みのる、おっそ!」
「お前真剣に感想書きすぎだろ」
「適当に書いたつもりだったんだけど……それに下村さん、正義さんの友達みたいだし」
「うっそ」
「ガチで?」
みのるはこの前の良太の姉の件は除外して、どうやら下村が正義の友達であること、リチャードとも知り合いであることを語った。良太と真鈴は一度驚くともうそれほどリアクションせず、「あの二人の顔の広さはやばい」という結論に達した。
良太の姉の一件以来、二人はみのるのことを心配していた。良太は一時的に秋穂と険悪になっていたらしいが、秋穂にフライドチキンをおごってもらったと楽しそうに話して以来、悪いムードが継続している様子はない。みのるとしては、このまま何となく話が消えてゆくことを願っていた。
下村さんとも今度もしかしたら会えるかもね、ギターすごかったね、という話をした後、またねと言って三人は別れた。
別れたのだが。
「みのる、ちょっと」
兄の友達とゲーム対決をする、と言って良太が急いで帰っていった後、みのるは校門近くで真鈴に呼び止められた。先に出て行って待ち構えていたようだった。
「話がある」
みのるは特に怖いとは思わなかった。相手は真鈴である。逆にみのるは真鈴が心配になった。思いつめた表情に見えたからである。
「真鈴、大丈夫? 最近ちょっと、顔がこわいよ」
「あ?」
「ごめん。こわいっていうか、真剣に見えるから……」
何か考えてることがあるのかなって、とみのるは言い添えた。心配されていることに気づいたらしく、真鈴は表情を柔らかくした。
「まあまあ考えてることはある、かな。でもこの前キムさんと話してね、励ましてもらったとこ」
「励ますって何を?」
真鈴は答えず、かわりに提案を投げかけてきた。
「今度、中田さんと二人で話したいことがあるんだけど、セッティングしてもらえない? 真剣な話だって伝えて」
「えっ……」
みのるは真鈴の言おうとしていることに想像がついた。真鈴にもみのるが気づいたことくらいはわかるはずである。そんなことを誰かに言うなんて恥ずかしいはずなのに、真鈴は静かにみのるを見ているだけだった。特にもじもじもせず、赤くもならず、堂々と。
真剣さのバトンを受け取ったように、みのるは頷いていた。
「わかった……やってみる。でも」
「『でも』じゃなくて、ちゃんとやって。スーパー親友の頼みだよ」
「…………すごく頑張る」
「はは。ありがとみのる。私も頑張るから」
真鈴は最後に少し恥ずかしそうに笑い、手を振って学校の駐車場の方向に歩いていった。お母さんが車で迎えに来るらしい。後ろ姿はいつもと同じように颯爽としていて、長い黒髪はサラサラと左右に揺れていた。
みのるはその時ふと思った。
下村晴良の最後の曲。明るくも暗くもないように聞こえた曲。
あの中にも、もしかしたら、フラメンコの中に含まれるという『激しい感情』が、いっぱい入っていたのかもしれないと。
真鈴の姿を見ている最中、みのるは何故かそんなことを考えてしまった。
みのるがおそるおそる家に帰り、宿題を仕上げると、案の定正義と一緒に下村晴良がやってきた。職員室の先生方との飲み会を早めに切り上げてきたのだという。
「あっちの飲み会も楽しそうではあったけどさ、俺としては正義の作った食事が食べたいんだよ。お前のメニューはプロ並みだから」
「日本食ってリクエストだったけど、いいのか。ここ日本だぞ。本格派の寿司も懐石もそこら中にあるだろ」
「わかってないなあ! お前の日本料理は、海外歴の長い日本人の『これ食べたい』ってツボを一撃で仕留めてくれるんだよ。俺はそういうかゆいところに手の届く料理がいいの。寿司屋でお好み焼きは食べられないし、懐石でタルタル唐揚げは出てこないだろ」
「わがままな息子を持つ親の気持ちがちょっとわかった気がするよ」
「アミーゴ! ジョキエロうまかもんー! ムーチャスおなか減ったー!」
「何語だ」
その日の献立はめちゃくちゃだった。ちらし寿司。めんたいこスパゲッティ。卵焼き。タコさんウィンナー。タルタルソースとパセリをかけた唐揚げ。ハンバーグオムライス・デミグラスソースがけ。エビチリ。麻婆豆腐。アジフライ。そうめんと薬味。様々なおにぎり。
「うひょーっ!」
情熱のギタリストであったはずの下村は、みのるより幼い子どものような顔をして、正義の準備した『日本食』ディナーに目を輝かせた。もしかしてこれは『お子様ランチ』の手加減なしバージョンなのかな、とみのるはちらりと思ったが、口にはしなかった。
「いっただっきまーす!」
「ゆっくり食べろよ。食事は逃げないから。そういえばお前、明日は?」
「明日はオフだけど移動日。関門海峡を越えて、明後日は俺の先生と福岡でライブ」
「忙しいやつだなあ」
「お前ほどじゃないよ。や、今は日本に定住してるんだっけ」
「久しぶりにな。腰を据えるのもいいもんだなーって思った」
「それで料理してくれるんだから最高だよ。また遊びに来てもいい?」
「来られるならな。ずっと公演の予定が詰まってるだろ。次はパレルモだっけ?」
「ローマ。その次がパレルモで、次がライプツィヒ」
「ドイツ語圏か。どうするんだよ」
「英語で乗り切る! 英検三級だけどな」
「……本当に困ったら、電話くれ。何とか力になるよ」
「だいじょぶだって、アミーゴ! 俺だって大人なんだから」
正義と下村晴良は本当によい友達同士であるようだった。二人はスーパー親友なんですねとみのるが言うと、二人はちょっと驚いた顔をした後、そうだね、そうだな、とうなずいてくれた。二人は同い年の二十八歳だという。
十年後くらい、二十三、四歳になった自分と良太を想像し、みのるは思考停止した。
全然何も浮かばなかった。そもそも良太の将来の夢も知らないし、自分の夢すらわからない。高校生になったら文系理系とコースが分かれるから、それまでにちゃんと決められるように、やりたいことをいろいろ考えておくといいぞと先生は言った。だがみんな適当に聞き流している。みのるも聞き流していたが。
何も浮かばないことを誤魔化しているだけなのかもしれなかった。
少なくとも真鈴はいろいろ考えている。二十代の真鈴は簡単に想像できた。大人になっていて、髪の毛の長さはそのままで、ちょっと化粧が濃くなって、モデルや女優として活躍していて、ひょっとしたらアメリカに住んでいる。かっこいい女性になっているはずだった。
そして真鈴は、その隣に中田正義がいることを夢見ている。
市内の実家に帰るという下村を見送った後、戻ってきた正義に、みのるは切り出した。
「正義さん……あの」
真鈴が、どうしても、二人で大事な話がしたいと言っている、と。
言いたかったが、みのるは言えなかった。
正義はいつもと同じ、どうしたの? という顔でみのるを覗き込んでいる。親しみ深い、みのるを信じてくれている顔で。
みのるはこの前、神立屋敷で聞いた話を思い出していた。
正義はリチャードと、パートナーで。
それはとても大事な相手であるという意味で。
他にパートナーが増えるということは、ないと断言した。
そういう人を、「付き合ってください」と誰かに告白されそうなシチュエーションに連れだそうとするのは、悪いことではないのか? 騙し討ちというものになるのでは?
「…………」
みのるは何も言えず、首を横に振った。
「何でも……ないです」
「そっか。思い出したらまた話してよ」
「はい」
みのるは風呂に入ってベッドに横になった後、勇気を出して真鈴に連絡した。
『ごめん。誘えなかった』
返事はすぐに入った。みのるの想像通り、真鈴は返事を心待ちにしていたようだった。
『わかった。ありがと。自分で誘う』
特に怒ったり悲しんだりしている様子のない、さっぱりきっぱりしたメッセージに、みのるは少し安堵した後、罪悪感に襲われた。真鈴には他にもっと言うべきことがあるかもしれないのに、何も言えないでいる自分が卑怯に思えた。
『ごめん』
いろいろな思いを込めて一言を送ると、真鈴は親指を立てたマークの絵文字を寄越した。気にしなくていいから、と言われた気がした時、みのるはいつもより強く、自分が友人たちに助けられているのだと感じた。
「こんにちは。ようこそ横浜中華街へ。一人ですか?」
夜の中華街の人ごみを歩いていたヨアキムは、流暢な英語で声をかけられ振り向いた。
「あらこんにちは、お兄さん。私、どこかであなたにお会いしたことあったっけ?」
「ないと思いますね」
赤い扉と、漢字で書かれた屋号とおぼしき看板の間に、切れ長の瞳のポップスターのような青年が立っていた。腰には薄汚れた白いエプロンをつけている。
「うちの中華料理はすごくうまいですよ。しかも安いです。寄っていきませんか」
「……じゃ、お邪魔させてもらおうかしら。少なくとも英語は通じるみたいだし。私はキム。あなたは?」
「バイト中の謎のナイスガイです」
「あらまあ」
自称謎のナイスガイを多少怪しみつつ、ヨアキムは繁盛している店の中に入った。英語メニューはなかったが、これとこれとこれがおいしいですというナイスガイの助言に従い注文すると、おいしそうなスープと粥と野菜炒めが出てきた。
一口食べ、ヨアキムは目を見開いた。
「私、この味とお料理を知ってる。よくみのるが運んできてくれるものと同じ」
「そりゃあそうでしょう。その子はうちの坊ちゃんの友達ですから。みのるくんを知ってるんですか?」
「居候先の可愛い子なのよ。まだ小さいのにすごく遠慮がちでね、頭のいい子よね」
「俺もそう思います。デザートは?」
「いただこうかしら」
つるりとした杏仁豆腐を食べた後、ヨアキムは勘定を払おうとしたが、謎のナイスガイはそれを手で留めた。ヨアキムは眉間に皺を寄せた。
「……もしかして、リチャードと正義にツケておけってこと?」
「そうじゃありません。うちの店のコースはまだ終わっていないので」
「もうお腹いっぱいで入らないわ」
「食べ物じゃありません。食後の占いです」
「?」
顔中のパーツというパーツで「?」の意を表するヨアキムに、謎のナイスガイは淡々と説明した。この店では営業努力として、従業員による占いが行われていること。占いの料金は飲食代にインクルーシブになっていること。素人のやることなので何を言われたとしても大目に見てほしいが、みんな真剣にやっていること。できれば協力してほしいこと。
ヨアキムは苦笑し、まあいいかなとひらひらと手を振った。
「このあたりで流行の占いは、手相って言うんでしょ? 手くらいなら貸してあげる」
ナイスガイは一礼し、それではと店の奥に消えた。どうやら占いをするスタッフがいるらしい。その後も店をうろうろ歩き回っていたが、どうも彼の探す相手はいないようだった。
心底呆れたとでも言うような深いため息を漏らし、青年は顔をしかめた。
「あいつ……本当に仕方ないやつだな……すみません。うちにはお抱えの占い師がいるんですが、今だけ消えているみたいで」
「あなたは? あなたはすごくお口が上手みたいだし、ナイスガイだから占いもナイスにしてくれそう」
「それはどうも」
青年はその後も店の内外をウロウロしていたが、本当に探し人はどこにもいないようだった。ヨアキムが笑い始めると、ナイスガイは肩をすくめた。
「本当に仕方がない。代わりに俺がちょっと見ましょう」
「お手柔らかにね。ひどい相が出てるでしょうから」
「人生経験のことを言ってます? 手相っていうのは新陳代謝と共にいくらかは変わってゆくものですから、いつどの段階でも同じ相が出るとは限らないんですよ」
「あらま、玄人風なことを言うのね」
ヨアキムの対面の席に腰掛けた青年は、大きな手を両手で捧げ持つと、うーん、うーん、とまるでやる気のない様子で唸った。そして告げた。
「えー……健康運、普通です」
「ちょっと。『普通』って何。笑わせないで」
「金運も普通」
「だから『普通』って何?」
「対人関係、普通。旅行運、すごく普通。妊娠出産運、普通」
「妊娠出産運って、そんな運気もあるの?」
「中華街の占いだと普通ですね。お産がうまくいくかどうかは、昔の人間には文字通り死活問題でしたから。ああ、恋愛運、大凶」
いきなりの託宣だった。
ヨアキムが目をしばたたかせても、青年は顔色を変えなかった。
「大凶です。何か問題でも?」
「何か問題でもって、そんなこと言われたらあるに決まってるでしょ。そこも『普通』でいいんじゃないの」
「でも、そう出てるんですよ。手相を説明しましょうか」
ここをこう、というよくわからない説明をヨアキムは聞き流したが、一番最後に言われた言葉は無視しなかった。
「今は恋人に関係した運がツイてないみたいですね。新しい人を探すといいって出てますよ。そういう感じですか?」
「……みのるから何か聞いてる?」
「まさかとは思いますけど、中学生男子に恋愛相談してるんですか。それもそれでどうかと思いますよ」
「してないっての。あてずっぽうでいい加減なこと言うとあなたを口説いちゃうわよ」
「すみません、既婚の子持ちなので、わりと命は惜しいです」
命なんか取らないよと、ヨアキムは笑ったが、青年は笑わなかった。しばらく大口を開いて笑い続けた後、長身の麗人は呟くように告げた。
「中学生男子には相談してないけど、中学生女子には多少相談したかなー。あの子にも言われたんだよね、『もっといい人探したら?』って。でもみんな勘違いしてるのよ。私は『良い人』が欲しいんじゃなくて、私の好きな人に、もっといい人を見つけてほしいの」
「はあ。面倒くさそうですね」
「そ。面倒くさいのよ。面倒くさい人生、面倒くさい性格、面倒くさい好み。私の人生面倒くさいことばっかり」
「聞くからに面倒くさい相手が寄ってきそうですね」
「まあ時々いるわ。私以上に面倒くさい男も」
ヨアキムは幸せそうに笑ったが、すぐに笑顔は引っ込んだ。
しばらくぼんやりするような時間があった後、ヨアキムは再び口を開いた。
「でもね、私の可愛いミスター面倒くさいは、本当にいい人なの。だからうんと幸せになってほしい。でも私と一緒にいると、面倒くさいが単純計算で二倍になるじゃない? 実際はそれどころじゃなくて何十倍にもなっちゃうんだけど……私はそれがもったいないのよ。私があげられるものがせいぜい杏仁豆腐一杯くらいだとしたら、あの人は中華料理店をまとめて十軒くらいくれるの」
「俺だったら杏仁豆腐の方がシンプルでいいですね……」
「もののたとえ」
窘めるようにヨアキムが告げると、よくわかりましたと男は頷いた。
そして告げた。
「要するにあなたは、逃げてるんですね」
「は?」
「好きな相手がいるのに、そこから逃げようとしてる。そういうのはアメリカ人がよく言うところの『天命から逃げる』ってことなんじゃないんですか。面倒くさい人生を送ってきたっていうからには、面倒くさい理屈はたくさんつけられるでしょう。でも自分が幸せになる道を選ばないのは、たとえそれが償えない罰を償いたいからとか何かそんな理由からだったとしても、人生からの逃避です。死ぬまで逃げ続けることになりますよ。俺はそれを知ってます」
「あらそう。あなた人を殺したことある?」
「あります。実の父親でした」
「…………冗談を言ってる?」
「死ぬのを待ってました。あいつが死なないと俺の人生は始まらなかったんで。病気の薬を買う金を自分のために使いこんで、晴れて父親は死にました。死に顔は今でも夢に見ます。苦しそうな顔でしたね」
ヨアキムは何も言わず、手のひらをテーブルの上に広げたままにしていたが、青年が言葉を打ち切ると手を握り、左手と重ねた。
「……それは『殺した』って言わない」
「俺の中では言うんです。じわじわ首を絞めたのと同じことなので」
「殺すっていうのは、もっと責任のあることで、あなたがやったのは自分の人生を生きるために仕方のなかったことじゃないの」
「文化の違いですかね。俺にとってはあれは殺人だったんです」
「…………いい人なのね」
「『いい人』はこんなことしゃあしゃあと話したりしなくないですか?」
「なんか、ごめんなさいね。面倒くさい話題を持ちかけちゃって」
「どういたしまして。俺も相当面倒くさい男なんで、そういうのは慣れっこですよ」
「本当に既婚の子持ちなの? シフトは何時まで? 一緒にカラオケ行かない?」
「何度も言いますが、わりと命は惜しいです」
ヨアキムはいたずらっぽく笑い、勘定を済ませた。ツケでいいですよと青年は言い張ったが、おいしかったから支払いたいと強弁するヨアキムに押し切られたのである。
それじゃあね、と手を振って出て行ったヨアキムは、夜の街を歩いていた時よりも幾らか元気な足取りになっていた。
店の奥からおずおずと出てきた、謎の帽子とローブ姿の『占い師』に、ヒロシことヴィンスは軽蔑の眼差しを向け、暗愚を責めるような嘆息を漏らした。
「遅。遅すぎです」
「さすがに出られないでしょ? こんなに人が多いところで修羅場をお見せできる? 無理だって」
「さすが面倒くさい男、幾らでも言い訳を思いつきますね」
「……否定はしないよ」
面目ない、とばかりに頭を下げる『占い師』の背中を、ヴィンスはぽんと叩いた。
「まあ、脈はまだ十分ありそうじゃないですか、占い師さん」
「うるさいよ。ああー、キムに君のこと紹介しなくてよかった。あとでパテックフィリップの時計をあげるね」
「いらないです。相変わらず言ってることとやってることが真逆ですよ」
「……君がやったことは殺人じゃないと思うけどね」
「あなたがやったことも大した裏切りじゃあないと思いますけど、こういうの『傷のなめ合い』っていうんですかね」
「今日はもう寝たい。ニューグランドに帰って寝たい」
「ホテルニューグランドに連泊して中華街でバイトしてる人間なんて珍獣ですね、珍獣」
「二回も言わなくていいから」
横浜を代表するホテルに宿泊する『占い師』は、厨房から呼ばれていそいそと戻っていった。任せられている数少ないタスクの一つ、皿洗いの人手が必要になったのである。
ヴィンスはその後ろ姿を見送り、呟いた。
「何でもかんでもあんたのせいになるほど、世の中単純じゃないよ」
そしてテーブルの客に呼ばれると、はあいと返事をして、追加の注文を取りに向かった。
みのるが風呂から上がったころ、ヨアキムはマンションに戻ってきた。いつものようにニコニコ笑っているが、どことなく疲れているような雰囲気なので、みのるは少し心配になった。リチャードと正義はそれぞれの部屋にこもって、別々の仕事を片付けている。
みのるが一度部屋に戻り、やらなくてもいい宿題の確認や明日の持ち物チェックをしてからリビングに戻ると、ヨアキムはソファに腰掛けて、いつものように端末を覗き込んでいた。手持ち無沙汰に端末をいじっているようでもあるが、表情はかなり深刻そうである。ヨアキムはみのるに気付かなかった。
少しだけまわりこむと、みのるには端末のディスプレイが見えた。
アルファベットの大きな見出しと、人間の写真。おそらく英語の新聞か雑誌。ショッキングな赤や黄色の吹き出しは、何となくSNSで多用されている強調のスタンプのようだった。カジュアルな雰囲気で、いろいろな人たちの記事が載っている。ヨアキムはスクロールをしてゆき、あるタイミングで指を止めた。
ヨアキム自身の写真が出てきたのである。
みのるは息をのんだ。写真の中のヨアキムは、かなり露出の多い格好をしていて、びかびか光るライトの下で脚を上げて踊っていた。その隣にまるで不釣り合いそうな、かっちりしたスーツ姿の男性の写真が並んでいる。みのるにはその人の顔をどこかで見たことがあるような気がしたが、少しリチャードに似ていること以外思い出せなかった。
みのるがぼんやりしていると、はっとしてヨアキムが顔を上げ、ディスプレイは暗くなった。
「ダイジョウブ?」
「……大丈夫です」
「ヨカッタ」
ヨアキムは微笑み、端末を持って自分の部屋へ入っていった。
部屋の扉がパタンと音を立てて閉じるまで、みのるはヨアキムの背中を見つめていた。上背のある、長い髪の持ち主の姿は、何だかいつになく寂しそうに、小さく見えた。
【つづく】