宝石商リチャード氏の謎鑑定 再開のインコンパラブル 第一回
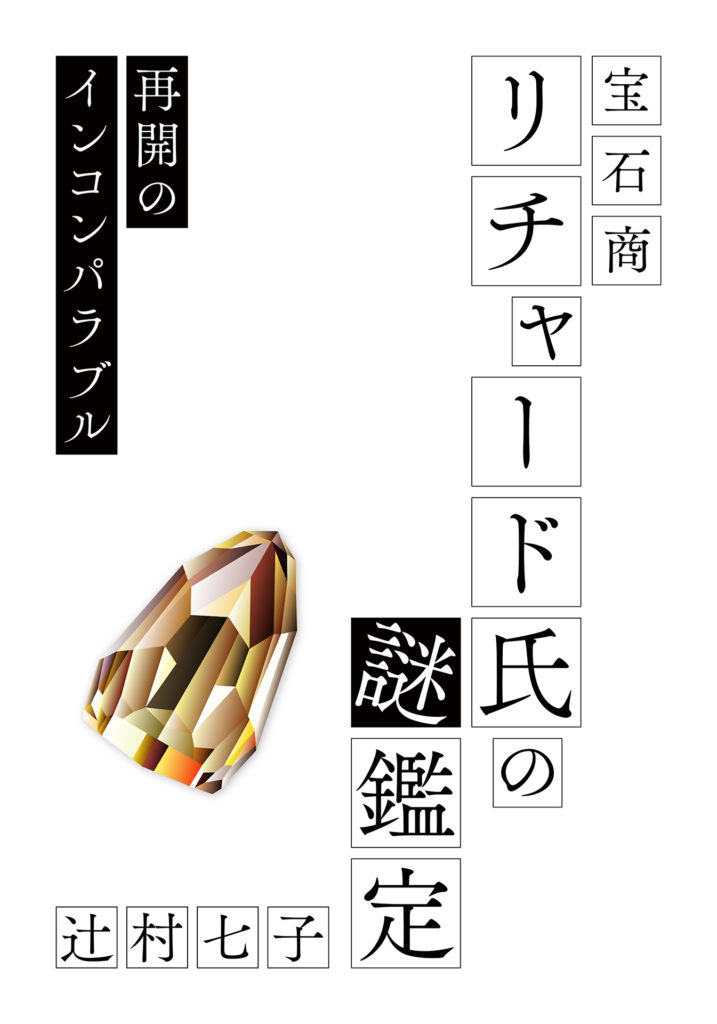
一話 ダンサーとナワラタナ
十月の終わり。みのるはスーパー親友こと赤木良太の住む家にお邪魔していた。赤木家は中田正義のマンションより部屋数が多かったが、一つ一つの部屋は狭い。こういうのが普通の家だなあと、何となく後ろめたいような気持ちになりながら、霧江みのるは良太のベッドに横たわっていた。
「しっかし、中田さんにしては急な話だよな。『お泊まりさせてもらえませんか』って」
「ごめんね、良太……」
「そういう意味じゃないって! 何があったんだろうって気になってるだけ」
「……僕も」
みのるは良太の顔から天井に視線を移した。良太の部屋の天井には大きな星座早見表が貼られていて、少しだけみのるの心をなごませた。春の星座。夏の星座。季節は既に秋である。お茶を出してくれて、何くれとみのるの家での話を聞いてくれた良太の姉も退出していて、みのるが気を遣うような相手はいなかった。
「…………」
中田正義が、みのる以上の優先度をつける、何らかの事件が起こっている。そしてそれは、入院しているみのるのお母さんにまつわることではない。お母さんに何かあった場合には必ずみのるにも伝えると、正義は約束してくれたからである。
何故か、みのるはそれが嬉しかった。
お母さんに事件が起こっていないから、ではなく、中田正義が自分以外のことに注力してくれているのが嬉しかった。もしこのまま、いつも正義に勉強を見てもらって、楽しいところに連れて行ってもらって、おいしい料理を作ってもらってという生活を続けていたら、みのるはどこかで自分がおかしくなりそうな気がした。
正義にも正義の生活があり、みのるとは関係のない部分がある。
そっちの方がいいな、とみのるは思った。
そして同時に、自分もまた、正義とは関係なく、自分自身の時間や空間を持たなければならないのかもしれないとも。
もしかしたらそれは、最近学校でよく耳にする『進路』というものと関係しているのかもしれなかった。
「イギー、リッキー、本当に、マジで、悪かったと思ってる。ごめんね。でも今回ばっかりはもうどうしようもなくて」
「事細かに説明していただこうとは思っておりません。驚愕したことについては否定しませんが」
広々とした山手のマンションの中に、複数の人種の人間が佇んでいた。
一人はソファに腰掛ける金髪のコーカソイド、リチャード・ラナシンハ・ドヴルピアン。
リチャードの背後でソファに手を置き前のめりに立つモンゴロイド、中田正義。
そして最後の一人が、どこの人種とも言い難い、うっすらとしたココア色の肌を持つ、ヨアキム・ベリマンだった。リチャードと対面のソファに腰掛けたヨアキムは、本当に申し訳ないという顔で、毛布をかぶって小さくなっていた。
本人曰く、身分は『逃亡者』である。
ヨアキムの登場は全くもって突然で、正義にもリチャードにも青天の霹靂だった。
何とかもう少し情報を分けあたえてもらおうと、正義は明るい声を出した。
「まあ、もともとここはジェフリーさんの家だし」
「ヨアキムさま、よろしければ彼に連絡をしても?」
「リチャード」
「やめて」
ヨアキムの声はいっそう低くなった。
リチャードはしばらく間を置いてから、ゆっくりとした口調で告げた。
「さきほどから厄介な男からのメッセージが届き続けています。『やあリッキー』『元気?』『ちょっと時間ある?』ほか。いつもの軽薄な調子ではありますが、矢継ぎ早な速度に若干の切迫感が滲んでいます。親愛なる逃亡者さま、よろしければあなたは一体何から逃げているのか教えていただいても? そうでなければ力になることもできません」
力になるという言葉に、ヨアキムははっとしたようだった。正義は表情を緩めた。
「俺もリチャードも、無条件にジェフリーさんサイドってわけじゃないんですよ。俺にとっては最初は、かなり『敵』寄りの人でしたし……いやそれはともかく」
リチャードの眼差しで、正義は言葉を打ち切った。
ヨアキムは黙ったまま、長い脚の膝あたりを見つめていた。禅寺の座禅で、自分の中に答えを探すように。
しばらくの沈黙の後、ヨアキムはリチャードと正義を見上げ、口を開いた。
「申し訳ないけれど、私たちの間には何も起こってないの。だから逃げてきたの」
怪訝な顔をする正義の隣で、リチャードは表情を変えなかった。ヨアキムは少しだけ微笑み、リチャードを見て喋った。
「まだ自分でも心の整理がついてないから、これ以上は言葉にして話せない。ごめんね二人とも。しばらく滞在させてもらえると助かる。もちろん無茶な話だったらすぐに出るから安心して。今ここで暖まらせてもらえただけで、随分体が楽になったし」
「好きなだけいてくださいよ! ただ……」
リチャードに先んじて口を開いた正義は、多少言い淀んでから、なぞかけをするような笑みを浮かべた。
「今、この家には他にもう一人、若い仲間がいるんですけど、そのことは知ってます?」
クウ、クウ、と鳴き声をあげる二匹の犬をヨアキムはおずおずと指さし、確認するように正義を見た。正義は苦笑し、首を横に振った。
急なお泊まり会の翌日。霧江みのるが正義のマンションに帰宅すると、『異人さん』がいた。長いアッシュグレイの髪。くっきりとした目鼻立ち。すらりとした長身。
「みのるくん、こちらヨアキムさん。ヨアキム・ベリマン。普段はアメリカとかフランスとかイギリスに住んでるんだけど、わけあってしばらくここにお泊まりする。日本語はほとんど喋れないけど、英語は通じるよ」
「ハロー」
みのるはびくりとした。初めて聞く『生の』『ハロー』である。リチャードや正義や、英語の授業にやってくるALTの先生の『ハロー』は、日本語しかわからない日本人の子どものために手加減してくれている言葉だとわかったが、ヨアキムの言葉にはそういう雰囲気がなかった。何より英語しか話せない。それは他に言語の選択肢がないということだった。つまりみのるが頑張るしかない。
付け焼き刃の言葉で、みのるは『ハロー』と『ナイストゥーミーチュー』と『マイネームイズみのる』を繰り出し、その後は地蔵のように黙った。ヨアキムは最初、みのるの英会話能力を過剰評価したらしく話しかけてきたが、一言も理解できないとわかると、ただ微笑むだけに切り替えた。ヨアキムが喋れる日本語は『ダイジョウブ』と『アリガトウ』だけで、みのるにはなんとなくそれが『イエス』と『ノー』の代用品に思えた。滞在中、ヨアキムの家事分担は免除されるが――ものすごく苦手らしい――かわりにジローとサブローの散歩などの世話を積極的に担当する。みのるはわかりましたと答え、特に質問はしなかった。謎が多すぎるとかえって何も質問できなくなるのは初めて正義と会った時と同じだなあと、みのるはしみじみと春を振り返った。
今まで通りの部屋に戻ると、あとから正義が追いかけてきて、みのるの前で膝をついた。
「みのるくん、さっきはああ言ったけど、無理をする必要はないよ。もしキムさんと一緒に暮らすのがしんどかったり、自分の居場所がなくなるような気がしたら、すぐに言ってほしい。俺たちもキムさんも、もう大人になって何年も経つから、どんな場所でもやっていけるよ」
「ぼ、僕は、大丈夫です。問題ありません」
「うーん……まあ、問題があるかないかも、だんだん見えてくるものかな」
「ヨアキムさんは、いつまでいるんですか?」
みのるがそう問いかけると、正義は少し困った顔をした。ああわからないんだとみのるは理解した。突然やってきたお客さんが、いつまでいるかわからない。そんなことはなかなか起こらない気がした。
リチャードと正義が、大変な苦労をしそうな話だった。
大丈夫ですか、と逆に気遣うような視線を向けると、正義はにこっと笑って立ち上がった。
「みのるくん、本当にありがとう。キムさんは面白い人だから、英語でお喋りしてみるといいよ」
「それは無理です……!」
「無理に喋れって意味じゃないよ。楽しくやれたらいいなって意味。それじゃあ」
正義はそう言って部屋を出て行った。
「…………」
みのるは自分の心が二つにわかれたような気がした。ひとつの心は『みのる以外の誰かのことを考えているのは正義にとってよいことだから、喜ぶべき』という感情で、もう一つは『ずっと自分だけを見てくれていた人がよそを見ているのは、少し寂しい』という、初めて感じる何かだった。
不思議な気持ちで天井を眺めている間に、朝はやってきた。
「おはようございます……」
ダイニングに出てゆくとヨアキムがいた。モーニン、という気だるそうな声が返ってくる。
朝に弱いといえばリチャードのことだと思っていたみのるは、ヨアキム襲来の翌日、上には上がいるという言葉の意味を理解した。寝起きのヨアキムは、初めて会った時のような化粧気が目元にも唇にもなく、もこもこしたフリースのジャケットを素肌の上にそのまま羽織っていた。正義とリチャードはいつも通りにしようと努めているようだったので、みのるもそうあるように努めた。
半分以上寝ていて、食べることもおぼつかないヨアキムを横目に、みのるはいつもと同じ時間に登校しようとして玄関を出た。
その後すぐ。
「みのるくん」
正義が玄関から出てきた。忘れ物でもしてしまったのだろうかと慌てるみのるに、正義はにこにこと声をかけた。
「今日の放課後、時間はある? 林くんのお父さんがお惣菜を分けてくれるんだって。受け取りに行ってくれるかな。ヨアキムさんの歓迎会も兼ねて、今夜は中華パーティにしようかと思って」
「あ……わかりました」
できることは全部自分でやってしまう正義には、珍しいオーダーだった。でもこういうところで頼ってもらえるのは嬉しいなと、みのるは少しだけうきうきした。
学校に到着すると、みのるは案の定待ち構えていた良太に質問を受けた。
「おはよーみのる。大丈夫か? お泊まり会は結局何だったんだ? 何かあった?」
「うん……」
説明が難しかったので、みのるは良太への返事を昼休みまで考え、現代文の授業のパラグラフ要約のようにまとめた。ヨアキムさんって人が家に来て、しばらく泊まることになった。リチャードさんと正義さんの友達で、いい人らしいんだけど、英語しか話せない。何で来たのかは知らない。以上。
良太はハアーッとわざとらしいため息をつき、ついでに伸びをした。
「面倒くさそうなことになってんなあ。お、真鈴じゃん」
「お邪魔さま。今日は何の話?」
隣のクラスの志岐真鈴は、良太とみのるの共通の友人で、キッズモデルをしている美少女である。腰まである黒髪を今日はゆるい三つ編みにしていて、現代文の小説に出てくる『むかしの女学生』のような雰囲気だった。体育のある日の定番スタイルである。
「真鈴。学習発表会の練習はもういいの?」
「朝練のこと? もうとっくに終わってるわよ。振り付けを覚えろって言われてるけど、あんなの一度踊ったら覚えちゃうし。ぶっちゃけダサいし」
夏休みを終え秋に突入した横浜市立開帆中学校は、文化祭ならぬ学習発表会を間近に控えていた。一年生はオブジェ制作、二年生はコーラス、三年生は演劇という、盛りだくさんなイベントである。生徒の保護者だけではなく、近隣の小学生も学校見学にやってくる。みのると良太のクラスは『ティラノサウルスのオブジェ』作りに邁進していたが、美術部所属の熱心な生徒たちの尽力でほとんど完成しており、二人は手持ち無沙汰になっていた。真鈴のクラスもまた、『赤い靴はいてた女の子のオブジェ』を切り絵で作ることになっているのだったが。
「ダンス部の助っ人に来てくれなんて言われたけど、正直個人差が大きすぎるのよね。学外のダンス教室に通ってる子は上手すぎるし、中学からダンスを始めた子はステップもわからないって言うし。顧問の先生の『ダンス』の認識はMJで止まってるし」
「エムジェーって?」
「『マイケル・ジャクソン』! ったく」
「みのる知ってる?」
「名前だけ……」
学習発表会では個別の演目を持つ部活動もあった。ダンス部もその一つで、ステージの上でダンスを披露する。部員の九割が女子というガールズグループのような部活動で、帰宅部の真鈴には全く縁のないもの、だったのだが。
クラスメイトの女子が、真鈴を誘ったのだという。
志岐さんダンスも上手なんだよね、事務所で練習してるんでしょ、だったらうちのグループに来てくれないかな、一人足りなくて決めポーズが映えないんだよね――と。
誘われたその日に、真鈴は良太とみのるに「もう困っちゃう」「ほんと困っちゃう」「でも頼られてるのに無視するのも感じ悪いし」「ほんと困る」を早口で連発し、迷っているというポーズを演出した。めちゃめちゃ嬉しそうじゃんと口にしてしまった良太は教科書で叩かれ、真鈴の百倍くらい真実味のある『ほんと困った』顔を作った。
とはいえ、真鈴に同じクラスの友達がいる。
体育祭前の嫌な出来事を経て、クラスの中での真鈴の立ち位置も少しずつ変化していることが、みのるは嬉しかった。良太や真鈴はみのるの大切な友達である。友達が楽しそうにしているのは嬉しかった。
でももし、良太や真鈴が、自分のことを全然気にせず、楽しそうなことをするようになったら?
初めてそんなことを考えた自分に、みのるはうろたえた。どうしてだろうと自問自答してもわからない、ただ脳裏に浮かんでしまった考えだった。正義がヨアキムを連れてきたからかな、とみのるは考え、自分の子どもっぽさに少し呆れた。
その日は長いホームルームで授業が終わる、特殊な時間割の日だった。
ホームルームではアンケートが配られた。
アンケートの内容は、入学から今までのことを思い出してみましょう、という一文で始まり、達成感を四段階で評価するというものだった。『学校の勉強』『学校の委員会活動』『おうちのお手伝い』『学校の外、たとえば家・近所での活動』など。すごくできたと思う、ややできたと思う、あまりできなかったと思う、ほとんどできなかったと思う。こういう項目にはつきものの、五段階評価でいう三段階め、『普通』がないことに、みのるは戸惑った。多少どちらかの選択肢を選ばなければならない。
ほとんどフィーリングでレのチェックをつけた後、みのるは最後の大きな記入欄に目を留めた。
『未来の自分を想像してみましょう。どんな人になって、何をしていますか?』
えっ、いきなりそんなことを言われても、というような質問だった。
「………………」
カリカリという周囲の机から聞こえる記入音が緊張感を煽る。みんなそんなにスラスラ書けることなのかと、みのるは頭が真っ白になった。
未来の自分。どうなりたいか。
考えたこともなかった。
クラスの八割がアンケートの記入を終えたとおぼしき頃、先生は笑って告げた。
「はい、お疲れさまでした。空欄なしに書けたかな? これは皆さんの進路にまつわるアンケートでもありますよ」
進路。将来どうするか。
みのるのイメージだと、それは将来入りたい学校や、つこうとする仕事のことだった。これのどこが進路や将来の話になっているのだろうと、みのるはもう一度アンケートを見直したが、わからなかった。提出前にまわりの三人の人にアドバイスのコメントをもらいましょうというワークは、全ての記入欄を埋める前に行ってよいようだったので、みのるは最後の欄が空白のプリントを持ってうろうろすることになった。
最初のコメントを、良太とは逆隣の席の女子にもらい、次に林くんにもらい――コメントは全部漢字だった――最後にみのるは良太の隣に戻った。
「おう! 待ってたぞ。じゃあ交換しよ」
みのるは良太とアンケートを交換した。良太は勉強やお手伝いの項目が『あまりできなかったと思う』で、最後の学校の外での活動の部分だけが『とてもできたと思う』になっていた。隣にある過去の具体的な活動を書く欄には『めっちゃゲーム』と書かれている。みのるは笑った。
「岡山まで行ったことも書けばよかったのに」
「あれもそうなのか? でも何か、俺だけ特別な体験してる感じが出てイヤじゃね? そういうことも書いていいのかな?」
いいんじゃないかなとみのるが頷くと、良太は『めっちゃゲーム』の下に、小さく『岡山で化石』と書いた。これで先生に伝わるんだろうかとみのるは思ったが、それ以上に気になることがあった。
「ねえ良太……何でこれが『進路にまつわるアンケート』なんだと思う? 未来のことなんか書いてないよ」
「知らねえー。先生に質問しなよ。ねえ先生!」
ちょうど机の間を巡回していた先生に、良太は元気よく質問した。ねえこれって進路にまつわるって言うけど、全然進路関係なくないですか? ただの振り返りじゃね?
先生は笑い、そうだねと頷いた。
「じゃあ逆に、赤木くんは、どういうことが進路に関係したアンケートになると思う?」
「え? それは…………」
将来どんな仕事につきたいか、ですか? という声がみのるの隣から聞こえた。授業中もよくハキハキと発言している、あまりみのるとは縁のない女子だった。うんそうだね、と先生は再び頷き、そこからは少し大きな声で喋った。みんなに話しかける時の声である。
「じゃあ、みんなは今いきなり、『将来どんな仕事につきたいですか?』って質問されて、答えられるかな。もちろん答えられる人もいるよね。小学校の頃から、将来の夢や希望はたくさん質問されてきたはずだ。でも、具体的にどうしたらその夢が叶えられるのか、そこまで考えている人はいるかな?」
クラスの中で手を上げたのは三人ほどだった。それも特に促されなくても手を挙げられるくらい自信満々なタイプの子たちである。やはりみのるは、そういう子と自分とは縁がないなと思った。授業中のワークならばともかく、昼休みにどんな話をすればいいのかなどは想像もつかない。
それでもみんな、みのると同じ年齢のはずだった。
不思議だな、と思って見ていると、先生がまた喋った。
「そういう将来のことはね、これまでのことを丁寧に見直してゆくと見えてくることがあります。昔の人はこれを『温故知新』と言いました。古いことを調べると、新しいことがわかるよというような意味です。林くん、これは何て発音する?」
先生は黒板に『温故知新』と書いた。林くんは嬉しそうに笑い、大声で発音した。
「ウェングーチーシン!」
クラスは一瞬、水を打ったように静かになった後、まばらな拍手が起こった。何人かは笑ったが、先生も拍手をしたのですぐに止んだ。
林くんは得意げに一礼した。
「林くん、ありがとう。これも不思議な話だけれど、この言葉も実はね、うんと昔に中国から入ってきた言葉なんだよ。それを日本でもずっと使っているから、同じ文字なのに、中国の読み方、日本の読み方、二つがあるんだ。でも意味はほとんど変わらない」
古いことを調べると、新しいことがわかる。
つまり、過去のことは未来に続いているのだと、先生は言いたいようだった。
どうしてそんなことが言えるんだろう、とみのるは暗い気持ちになった。みのるの昔のことといえば、お母さんと一緒に苦労してきたことばかりである。あれが未来に続いているのだとしたら、みのるは将来また苦労するぞと言われているような気がした。たとえお母さんと再び一緒に暮らせるようになるとしても、それは少し嫌だった。
「みんな、好きなことも嫌いなことも、得意なことも苦手なこともあるよね。そういうことを思い出しながら、アンケートにいろいろ書いてみましょう。先生も読むのが楽しみです」
最後にちょっといいことを言って、先生はまた黙り、クラスの中をうろうろ歩き始めた。
みのるはしばらく温故知新の気持ちになろうと思ったが、うまくいかなかったので、良太に尋ねることにした。
「ねえ……大体の人って、大人になったら仕事をしてるよね。あれって、いつどうやって決めてるんだと思う?」
「ああ? そんなの就職活動に決まってんじゃん。就活で仕事を決めるんだよ。しっかり就活しないとやりたい仕事に手が届かないって、兄ちゃんぼやいてるよ」
「で、でも、もうその時には『やりたい仕事』があるわけだよね? それはいつ決めてるの?」
「え? ……うーん……」
「昔のことを振り返ると、本当に決められるのかな?」
「いや……年収とかで決めてるんじゃねえの? やりたい仕事って、イコールほしい年収じゃねえの? そういうもんだろ?」
「うーん……」
そういえばヨアキムさんの年収はどのくらいなんだろう、とみのるは考えた。どんな仕事をしているのか、そもそも仕事をしているのか。
どうせ質問できるはずなどないと考えると、何故か次々に知りたいことが頭に浮かんでくるのが不可思議だった。
「……本当に、どうしてうちに来たのかな」
「あ? 誰が?」
「何でもない」
ホームルームの残り時間が十五分になり、アンケート用紙は後ろの席から前へ前へと回収されていったが、今日中に書ききれなかった人は持ち帰り、来週の今日、ホームルームはないが先生に提出すればよいという。未提出者の名前を控えた後、先生はうんと頷き、教卓の前に立った。
「書いてくれてありがとう。今日の授業はこれで終わりです。今日アンケートを書けなかった人、がっかりする必要なんかないからね。こういうことを考えるのには時間がかかるのが普通です。悩みながら書いてくれたらいいよ。それでは今日はこれで終わり。日直!」
きりーつ、きをつけー、れー、といういつもの号令で授業は終わった。
みのるは急いで林くんのところに行った。
「林くん」
「みのる。どうした」
「さっき……」
つらくなかった? と尋ねるように、心配する視線を向けると、林くんはニッと笑った。
「慣れた。あんなのしょっちゅうだ。笑うやつは特に深い意味もなく笑う。それだけだろ?」
「…………そうだけど」
「じゃあいい。友達もいるし」
それよりみのる、と林くんはヘッドロックをかけるようにみのるに組みつくと、廊下に連れ出し、懐から何か紙を取り出した。
「な、なに?」
「俺の小テストの成績だ。お前は見るべき」
林くんが取り出したテストは、まだ平均点には届かない点数の現代文テストだった。だが下の方に分数が書かれている。分母の数からして、クラスの中での順位のことのようだった。全ての科目の先生がこういうことをするわけではなかったが、現代文の先生はわりと順位をつけたがる方で、それが二十一と書かれていた。
クラス全員は三十名と少しである。つまり。
「俺はもう最下位じゃないぞ!」
「すごい! すごいよ林くん!」
「ありがとうみのる。父にもまだ見せてないけど、これはまずみのるか、中田さんに見せないといけないと思った。あとヒロシだな。本当に感謝してる。俺はたぶん中国に帰るけれど、すごくいい経験をしている。そう思うよ」
みのるが目を見開くと、林くんは逆にびっくりしたような顔をした。何だ、どうした、と言われ、みのるはおずおずと問い返した。
「……帰るの?」
「え? ああ。明日や明後日じゃないけれどな。中学校を卒業したらってこと」
何で? とみのるは尋ねたかったが、できなかった。それは聞いたらいけないこと、あるいは聞いても仕方がないことであるような気がした。代わりにみのるは別の質問を投げた。
「…………じゃあ、もう会えなくなるの」
「だから明日や明後日じゃないって! 日本にいなくても動画通話はできるだろ。でも、ははは。そんな風に言ってくれる朋友が日本にもいてくれるのは、すごく嬉しいな」
みのるはいきなり胸の内側にこがらしが吹き荒れたような気がした。そんな、友達に会えなくなるっていうのは、もっと先に起こるイベントなんじゃないか、と心が反論していて、気持ちの準備が全然できていなかった。
まごまごしているみのるに林くんは続けた。
「俺は、将来、通訳になろうと思っている。俺の言葉がみのるを助けた、本当にありがとうって、中田さんに言われた時、すごく嬉しかったんだ。だから法廷通訳になりたい。日本でトラブルに巻き込まれている中国人や、中国でトラブルに巻き込まれている日本人を、俺の力でどんどん助けるんだ。みのるも応援してくれ」
「……すごい……」
「すごいだろう! 自分で言うのは変だが、かなりすごい夢だと思ってる!」
もちろんみのるもそう思った。
そして急に、みのるは自分がちっぽけに思えた。ちっぽけで幼くて、どうしようもなく未熟な存在に。
「…………」
みのるは最後に、この話を正義や良太にしてもいいかと尋ね、もちろんだという返事をもらった後、林くんと別れた。
いつもの階段で待っていた良太に、みのるは林くんの『将来の夢』の話をした。
「ひょえー。すげー。法廷の? 通訳? って何?」
「言葉が通じないところでトラブルに巻き込まれた人を助ける係……みたいなもの?」
「すごすぎ。俺そんな仕事があることすら知らなかったんだけど」
「僕も知らなかったよ……」
でも林くんは知っていた。もしかしたら身近な人に、そういう通訳が必要になるトラブルが起こったのかもしれないと思うと、みのるは心配になったが、そこまで首を突っ込んでいいとは思えなかったので、みのるは言葉を飲み込んだ。
ハーッと良太は天井を見てため息をつき、思い出したように口を開いた。
「なあみのる、『将来』っていつ来んのかな?」
「えっ?」
「将来の夢、って言うだろ。でもそれって具体的に何歳からの夢なのかなって」
「……それは、ちょっと、わかんない」
「意味不明だよな。『将来』なんか先だよ。しばらく放っておこうぜ。それよりみのる、今日の放課後は俺んち来ない? 昨日の今日でなんだけど、姉ちゃんがお前の話、もっと聞きたいんだって。さては中田さん狙いだな」
ふざける良太に、みのるは手を合わせるポーズをとった。
「悪いけど今日の放課後は、中華街に行くから」
「へえ、珍しー。じゃあまた今度な。気を付けて行けよ」
「うん」
放課後。みのるはおなじみになった福新酒家への道のりをたどり、相変わらず歓迎してくれる林くんのお父さんから、大量のタッパーに入った多種多様な中華料理を受け取った。これが何、これが何、と林くんのお父さんは説明してくれ、みのるにはそれが少しでもわかることが嬉しかった。麻婆豆腐はマーポートウフだし、青椒肉絲はチンジャオロースである。
「シェシェ・ニー」
ありがとうございます、と林くんから習った言葉でお礼を言い、みのるは店を出て行こうとした。林くんのお父さんも店の奥に引っ込んでいった。
だが。
「そこなる少年」
店の中の誰かが、日本語で話しかけてきた。
営業時間ではないため客人のいない、がらんとした店の玄関脇、みのるの死角であった場所に。
地獄の閻魔さまのような、古めかしい中国風ローブをまとい、付け髭――でなければ野生のサンタクロースの可能性があるような――を装着し、瓶底眼鏡をかけ、ローブと同じ色の三角帽子をかぶった、男。
流暢な日本語を喋る男の目は、しかし青色だった。
この人は何なんだろう、と両手でタッパーの入った袋を持ちながら、みのるは眉間に皺を寄せた。男は笑った。
「君を占ってあげよう。僕は中華街名物の占い師。さあ、こっちへおいで」
「す、すみません、帰らなくちゃいけないので……」
「そんなこと言わず! ちょっとでいいから僕の占いを聞いてきなよ! いろいろ勉強してるんだから!」
無視して帰ろうとしたみのるの後ろで、誰かがカンカンという音を立てた。
振り向くと、おたまと中華鍋を持った男が立っていた。
「そこの不審者。占いをしないんだったら奥に入ってください。仕込みが終わってないんですよ」
「ヒロシさん……!」
「ああ、みのるさんですか。どうも。今日もバイト中のヒロシです。そこの占い師は、まあ見るからに不審なんですが、俺の腐れ縁非道仲間みたいなものなんで、それなりに信頼できますよ」
「『腐れ縁非道仲間』ってひどくない?」
「他に何て言ったらいいんですか? 『軽佻浮薄醜悪奸邪ストーカー』?」
「もっとひどいんだけど」
不審な占い師はヒロシの友人であるようだった。そして占いの勉強をしているという。
ちょっと付き合ってあげた方がいいのかな、と思い、みのるは料理の袋を空いているテーブルに置き、占い師の前に置かれていた椅子に座った。
閻魔さまスタイルの男はローブから大きな手を取り出し、みのるの手の甲を下にさせて左手で優しく握り、パーの形にした右手をその上でぐるぐると回した。胡散臭さの極みのような行為にみのるは焦ったが、ジェスチャーは思いのほか素早く終わった。
「見えてきた! 君には新たな希望の星が近くに存在している!」
「ああ……はあ……」
「察するに君は、若いのにたくさんの苦労をしてきた人だね。優しくて、他人にたくさん気を遣ってしまうから、心が疲れちゃうこともあるけど、それでも人に優しくしようとするのをやめない。世の中では少数派だけど、いるよねそういう人。僕は君を心から尊敬する」
「そ、そんなことないです……! それは僕の、あの、お兄さんみたいな人のことです」
「僕の義理の弟もそういうタイプだ。『兄弟』つながりで僕たちは似てるのかもね」
占い師ってこんなに自分のことを話すものかな、とみのるは少し不思議になったが、勉強中だというのでそういうこともあるのかなと思うことにした。何事にも不慣れなうちがあるものである。それからも占い師は、みのるのことをほとんど褒め殺しにするように、ああだろうこうだろうと告げた。誕生日くらい尋ねた方がいいのではないかとみのるは思ったが、口にしては失礼になるかと思って黙っていた。
しばらくの後、占い師は急に真剣な顔になり、みのるの手をそっと放した。
「さて、これが最後のお告げになるんだけど……君、もしかして最近、知らない人と出会ったりしなかった? 星が告げてる」
「ああ……あの、占い師さんと会ってます」
「そ、そうだね。でもその他にも、誰かそれっぽい人に出会わなかった? 『異国だなあ』って感じるような、『何なんだこの人』って思うような」
「あ」
みのるの頭には、眠そうなヨアキムの姿が浮かんできた。占い師はその幻影をつかんだように、そうそれ! と頷いた。みのるは怖くなったが、占い師は逆に、優しそうな、少し悲しそうな顔をした。
「……その人、元気? その人が元気だと、君の運勢は急上昇。そんなに元気じゃなくても悪いことにはならないけど、元気だと嬉しい。じゃなくて、君の運勢はグンと上昇する」
「ね、眠たそうでしたけど、元気だと思います」
「そっかあ」
よかった、と呟いた後、占い師は自分の発言を取り消そうとするようにあーあーと呻いた。よくわからないなりに、みのるは聞かなかったことにした。
ありがとうございましたとお辞儀をし、みのるは再び山手の長い階段を上ってマンションへと戻った。
リチャードも正義もまだ仕事中で、家にいたのはヨアキムだけだった。リビングの椅子に腰かけて、大きな携帯端末で何かを読んでいる。フリックしているのは、英語の新聞のような、雑誌のようなものだった。
おかえり、と告げるように、ヨアキムは笑顔でみのるに手を振った。みのるも振り返した。
中華料理一式を冷蔵庫に収納し、部屋で宿題を済ませてしまうと、みのるは手持無沙汰になった。思いのほか宿題が少なかったのである。こんなことなら良太の家に遊びに行った方がよかったかなと思いつつ、喉がかわいたみのるはおっかなびっくりリビングに顔を出した。
ヨアキムはまだ、深刻な顔でフリックを続けていた。
ひょっとして声をかけた方がいいのかもしれない、とみのるは思った。ヨアキムとお母さんとは全く違う存在だったが、思いつめた顔には見覚えがあった。お母さんがそういう顔をしている時は、大体何かつらいことを思い出している時で、みのるが声をかけない限り、いつまでも思い出の中に囚われているものだった。
「あ……あの」
みのるが声をかけると、ヨアキムは少し驚いた顔をした。今そこにみのるがいることに気づいたようだった。
何を言うべきか全く考えていなかったので、みのるは頭の中で今日の学校での日常会話をひっくり返し、英語っぽいトピックを探し、一つ、思いついた。
「あの……アイハブア・クエスチョン……」
MJって知ってますか? と。
『を知っていますか?』『は好きですか?』式の質問が、みのるには精一杯だった。三分くらい場がもてばいいなと思っていただけの質問だった。
だが効果はてきめんだった。
知ってる、知ってる、とヨアキムは全身でリアクションし、何故かすっくと立ちあがると、みのるの前で帽子を直すような仕草をした。そして足腰をちょっと不思議な角度にシャキシャキ曲げ、最後に。
前に歩いているような動きで、後ろに歩いた。
足は前に出しているのに、何故か体は後ろに五十センチほど進む。
「うわー……!」
みのるが拍手をすると、ヨアキムは芝居がかった仕草で頭を下げた。
そしてみのるに、新しい情報を与えた。
『私は、ダンサー』と。
みのるにもはっきり理解できる英語だった。
その時初めて、みのるは自分が今まで、英語を確かに勉強していたのだという心の震えのようなものを感じた。相手の言っていることが理解でき、かつ意思の疎通ができてしまうことが、とんでもない奇跡のように思えた。
みのるがガクガクと頷いた時、ポケットにいれたままだった端末が震えた。どうぞ、とヨアキムが促したので、みのるはおずおずと端末の画面を見た。
真鈴からのメッセージだった。
『みのる、三脚持ってる? 縦にスマホが挟めるやつ』
マンションには高さを調整できる黒い三脚が二つほどあった。正確に言えば中田正義の持ち物ではあったが、リチャード・正義・みのるが好きに使ってよい、輪ゴムやホッチキスのようなアイテムだったので、みのるは『あるよ』と返信した。即座にメッセージが帰ってくる。
『港の見える丘公園まで持って来てくれる? 悪いけど』
ああ真鈴は全然『無理』とか『何で?』とか言われることを想定していないな、とみのるは理解した。真鈴のそういうところがみのるは少し好きだった。クラスの女子がキャーキャーさわぎながら話題にしているよくわからない意味の『好き』ではなく、遠慮しないでものを言ってくれる友達として好きだった。
みのるはヨアキムに、簡単な英語で状況を説明した。『しなければならない』式の言い方をみのるは知らなかったので『私は公園に行きます』『友達が待っています』、そして三脚を納戸から取り出して『これを持って行きます』という三つの文章でしのいだ。ヨアキムは完璧に理解してくれたらしく、オーケーと長い指でサインしてくれた。
そしてまた、英文の表示された端末に目を落とし、暗い目をした。
みのるは思わず口にしていた。
「レッツゴー…………?」
一緒に行きませんか? と、もう少し何とか誘う言葉があったような気がしたが、みのるは思い出せなかった。
ヨアキムはアーモンド形の目を大きく見開き、長い睫毛をバチバチと動かした。いいの? と確かめるような目に、みのるは反射的に頷いた。
ヨアキムはちょっと外に出て、散歩か何かをした方がいい気がした。
もし嫌だったら無理しなくていいです、は何と言ったらいいのだろうと、みのるがうんうん唸っているうちに、ヨアキムはちょっと待ってとハンドサインした。そしてガツガツブオンブオンという音を立て、十分で化粧とヘアセットを終わらせて出てきた。ヨアキムは化粧がとても上手だった。
最後にヨアキムは、リビングの椅子の上に右足をでんと乗せ、ポケットから宝石のついた金色のチェーンを取り出し、装着した。チェーンにはペンダントのようなフックと、宝石が幾つか付いているようだった。みのるの見る限り、どれも違う色の石だった。
きれいだな、と思っているうち、ヨアキムは顔をあげ、みのるを見下ろしていた。
「レッツゴー!」
もしかしてちょっと困ったことになるかもしれない、と予感した時にはすでに遅かった。
港の見える丘公園まで、みのるの家からは十五分もあれば到着してしまう園内はバラ園と展望台に二分されていて、展望台の方はがらんとしているのであまり観光客が多くない。そこに女の子たちがジャージ姿で集っていた。結局真鈴は練習に付き合ったんだな、とみのるは笑った。
みのるとヨアキムを発見すると、真鈴は少しぎょっとしたようだったが、集団から出て、小走りにみのるに近づいてきた。はいこれと三脚を渡すと、真鈴はまずありがとうと言ってくれたが、次にすぐ尋ねた。
「こっちの人、誰?」
「ヨアキムさん」
「って誰」
「リチャードさんと正義さんの、友……達……?」
「ちょっとやめてよ。ほぼ『知らない大人』じゃない」
「で、でも、うちで寝泊まりしてるから!」
「君の家ってフリーダムすぎ」
ハロー、とヨアキムが陽気に手を振ると、真鈴もこなれた発音でハーイと返した。そして二人はみのるにはまだ聞き取れない速度で英会話をし、最終的に真鈴が何かに驚いていた。どうしたの、とみのるが水を向けると、真鈴は日本語で喋った。
「この人プロのダンサーなの? 何でそんな人が君の家にいるの?」
「えっと…………」
何もわからない、という言葉は無責任に思われた。どうしたらいいんだろう、と思っている間に、真鈴の後ろの集団が踊り始めた。音楽はない。公園の中で大きな音で音楽をかけるのは禁止されている。そのかわりにそれぞれの耳に入ったブルートゥースイヤホンが、同時に音楽を流している。
あれ何の曲なの? と尋ねたヨアキムに、真鈴は懐の端末を見せた。流行の韓国のガールズグループの曲のようである。へーえ、と言いながらヨアキムは少女たちを観察し、真鈴に何かの許可を求めた。真鈴は「みんなに聞いてくる」と日本語で答えた後、仲間たちのところにたっと駆け戻っていった。
女子の集団はしばらく何かを話し合っていたが、一分ほどで真鈴が両腕で、頭の上でマルを作った。
「OKだって! みのる、そこで録画用スマホと三脚、押さえててくれる? 風が強くてひっくり返りそうだから」
「ねえ、何がOKだったの……?」
「ヨアキムさんが『ダンスを見ていってもいい?』って言ったから、その件!」
「…………」
自分一人ではマンションに帰ることはできない。みのるは三脚の固定係を承諾した。
そこからの流れを、みのるは動画サイトの『定点観測動画』のように、固定のアングルから見守ることになった。
真鈴たちは無音の中でワンツーワンツーと声をかけあって踊っていた。上手だなあとみのるは思ったが、ヨアキムはそうは思わなかったようで、終始かたい表情をしていた。一曲分踊り切ったところで、ヨアキムは巨大な音を立てて拍手をし、グッド、グッド、と言い立ち上がった。
そして。
全く同じ振り付けを、より切れ味鋭く、楽しそうに、ダイナミックに踊った。
何かの間違いだとみのるは思った。ヨアキムはさっきここにみのるが連れてきただけの相手なので、真鈴たちのダンスを予習しておくことなど不可能である。一回ぽっきりの鑑賞であるはずだった。にも拘わらず振り付けは完璧で、何となれば完璧『以上』である。
どう? と言わんばかりに真鈴たちをヨアキムが見ると、女子たちはどよめきをあげて拍手をした。
「すっご」
「おわあ……」
「信じらんない!」
「レベル違いすぎて吐きそう」
優雅にお辞儀をするヨアキムに、女子たちはたかり、真鈴を通訳にしてあれこれと質問をしているようだった。どこから来たんですか。ダンサーってどんな踊りを踊ってたんですか。ヨアキムはその全てに適当に答えているようで、真鈴は苦しそうな顔をしながら「よくわからない」と応じていた。流れ作業のように、謎の麗人であるヨアキムはダンスの先生になった。
一時間ほど、みのるが録画担当者――時々真鈴が戻ってきて端末を回収し、メンバー全員で画面を覗き込んで「ここがずれてる」「ここがいい」などと話し合う時にだけ存在する――として座り込んでいるうちに、素人目に見ても、真鈴たちのダンスはめきめきと格好よくなっていった。みのるの隣で手を叩きながら英語で数を数えているヨアキムも、真剣なまなざしで監督している。
一時間ほど踊り続けた末、ダンスグループはヨアキムの前に来て頭を下げた。撤収の時間になったらしい。
「ヨアキムさん、ありがとうございました!」
「あのー、明日もまた来てくれますか?」
「真鈴、聞くだけ聞いて」
ヨアキムの返事は快い「オフコース」だった。女子たちはきゃっきゃと喜び、深々と頭を下げて去っていった。
「じゃあ、また明日」
運が良ければ、と。
真鈴は不思議な言葉を言い残し、みのるとヨアキムと別れを告げた。
結局三脚を貸すのではなく、持ってきて持って帰るだけになってしまったなと思いながら、みのるはヨアキムと家路をたどった。夕食は中華である。支度をする必要がないので気軽だった。
「ヨアキムさん、ダンスが好きなんですね」
みのるは女子たちを見習って、日本語でヨアキムに話しかけてみた。ヨアキムはわからないという顔をして肩をすくめたが、表情は明るかった。奇妙な結果になったものの一緒に外に出たのはよかったかもしれないと、みのるは胸を撫で下ろした。
リチャードと正義が帰ってくると、和やかに歓迎会が始まった。みのるも加わったが、あまりにも中華料理がおいしくて食べることに一生懸命になってしまったので、夕方の公園でのダンスレッスンの話を二人の保護者に打ち明けるのを忘れていた。明日の朝でいいかなと思っていたが、朝には二人が『空港まで常連さんの出迎えにゆく』とかでそれどころではなかった。
登校したみのるは、朝のホームルームより先にやってきた真鈴から、簡潔な報告を受けた。
「ヨアキムさんのレッスンの件だけど、受けるのは私だけになったから」
「え?」
「他のメンバーは参加しないの」
保護者に相談したんでしょ、と真鈴は適当ぶった口調で告げた。
そしてみのるは気づいた。
ヨアキムは外国人である。日本語を喋らない。みのるの保護者ではなく、保護者『の知り合い』という曖昧な立場でもある。そして。
男か女か、はっきりしない。
尋ねていいことなのかどうかわからないので、みのるはまだ尋ねられていなかったが、もし昨日の素敵なレッスンの話をガールズグループのメンバーが家族に自慢したら「で、その先生は女なの? 男なの?」と、基本情報の確認として聞き出されることは確実である。
その質問に答えられなかった以上、保護者たちの心象は、みのるにも想像できた。
みのるは何故か、自分が軽くぶたれたような衝撃に見舞われ、何も言えなくなった。ちゃんと自分がヨアキムに確認しておけばよかったというのとは違う、自分で自分に説明できない何かもやもやした感覚に襲われていて、真鈴にも理解してもらえる気がしなかった。
みのるが黙って、ごめんと告げると、真鈴はからっとした調子で首を傾げた。
「何で君が謝るの? 私は逆に『私だけこんなにトクをしていいのかな』って思ってるくらいだけど」
「真鈴は…………いいの?」
「何が?」
せっかく新しい女子の友達ができて嬉しそうだったのに、またこういう『個人行動』をしたら、折り合いが悪くなったりしないか。
言葉にできないまでも、うかがうような眼差しでみのるが伝えると、真鈴は笑った。
「あのね、そういう時に躊躇うような女子は、男の子ふたりと一緒に岡山旅行に行ったりしないから。うちのお母さんは、よく言えばそういうのに寛容なの。悪く言うなら放任主義」
「お父さんは?」
「言ってなかったっけ? お父さんはいないの。うち、シングル家庭」
みのるは目を見開いたまま、何も言えなくなってしまった。
いないって、生きてるの? 離婚したの? どういうこと? うちもいないんだよ。生死不明なんだ。お母さんはどうしてるの? つらいことはないの? 悩むことはないの?
みのるは何かが言いたくて、しかし喉の奥からシロナガスクジラを生もうとしているような巨大な喉のつっかえに見舞われ、結局何も言えなかった。言いたいことがありすぎた。真鈴は気を遣われていると思ったようで、それ以上は何も言わなかった。
「そういうわけで、ヨアキムさんには私だけ特訓してもらうから。今日は音楽をかけて踊りたいから、うちの事務所が貸りてるレッスン室を使う予定。予約が受理されたら、地図アプリで場所を送るから確認して。それじゃあ」
「うん」
ぼーっとしたまま一日の授業をやり過ごして帰宅すると、ヨアキムはぴかぴかのジャージに着替えていた。買ってきたものではなく、正義が時々街を走る時に着ているジャージで、足の長さが少し足りていなかったが、ともかくやる気満々という風情である。
みのるは申し訳ない気持ちになりながら、それでも何も言えなかった。保護者の許可が取れなかったので、ヨアキムさんは『あやしい人』だと思われたみたいで、真鈴以外の女の子たちは来ないことになったんです。ごめんなさい。どんな英語にすればいいのかわからなかったし、そもそも日本語でもこんなことは言えない気がした。
どうしたの? と話しかけてくるヨアキムに、みのるは首を横に振った。
そしてずっと気になっていたことを、思い切って尋ねようかと思った。
「ヨアキムさん、あの…………」
ヨアキムさんは男なんですか? 女なんですか? と、みのるは尋ねようとして、尋ねられなかった。今のところみのるにとって、『英語』とは大きすぎて使い方に四苦八苦している斧のようなものだった。うまくすれば切りたいと思っているものをスパンと切ることができる。だが一度扱いを誤れば、腕を落としてしまうかもしれない。自分だけではなく、言葉をかけた相手の。
結局何も言えず、みのるが頭を下げると、ヨアキムははーっとため息をついて、何かを携帯端末に話しかけた。そして次に、端末の画面をみのるに見せた。そこには日本語が書かれていた。翻訳アプリを通したのである。
『私は簡単に傷つきません。心配をしないでください。質問は何でも歓迎です。私はあなたが大好きです』
みのるは目を見張った。ヨアキムは強く、そしてリチャードや正義のように、優しい人であるようだった。
知りたいことはもちろんあった。性別のこと。ここにやってきた理由のこと。しかしそのどれもが、いい加減な気持ちで尋ねてはいけないことのような気がした。促すようにポーズを取ったヨアキムの右足で、宝石のついた鎖がきらりと光った。
考え、考え、考えた末、みのるの口をついたのは、
「これ……何ですか?」
これ、とみのるは宝石の鎖を指さした。
あまりにも無難すぎる質問だった。
一拍置いて、ヨアキムは笑い始め、もうよしてよという女子のように手をひらひらさせると、再び端末に話しかけた。
『これはナワラタナというものです。占星術的な意味があります。ラッキーを呼び寄せてくれると言われています』
「そ、そうなんですね! ありがとうございます」
みのるは自分自身の臆病さを軽蔑しながら、ヨアキムに頭を下げた。ナワラタナ。どこの国の言葉なのかもわからなかったが、ともかくみのるは質問をし、ヨアキムは答えてくれた。
みのるが沈黙していると、ヨアキムは再び、端末に英語で何かを話しかけ、みのるに端末を差し出した。少し待っていると日本語が表示される。
『あなたが私に質問しようとしたことは、恐らく私が何度も自分に質問してきたことと同じです。でも私はその答えを持っていません。だから答えることができないと思います。あなたの優しさに私はとても感動しました。ありがとうございます』
みのるは目を見開いた。そして気づいた。
きっと今までにも何十回と、もしかしたら何百回と、ヨアキムは同じ質問を受けてきたのかもしれなかった。見るからにそういう風貌をしているからである。リチャードを見た人間が『美しい』と反射的に思ってしまうのと同じように、ヨアキムを見た人間は『男と女どっちかな?』と思ってしまう。そして声をかける。あるいは質問する。あなたはきれいですね。あなたは男と女どっちですか? みのるはリチャードと二人で歩いている時に遭遇する、無遠慮な声の数々を思い出した。
嫌な声だった。
ヨアキムが『ありがとう』と言ってくれた理由に思い至り、みのるは首を横に振った。申し訳ない気持ちがした。だがヨアキムは笑い、続けて端末に声を吹き込んだ。
今度の日本語翻訳は、さっきより少しだけ短かった。
『あなたには私がここに来た理由を話します。私は恋人と大きな喧嘩をしました。恋人はとても良好な人です。私には良好すぎます。喧嘩別れできたらいいと思っています』
「え、え……?」
みのるは三十秒ほど考えて、考えるのをやめた。あまりにも大人なトピックすぎて、真鈴であってもわからないような気がして、自分についてゆけるとは到底思えなかったからである。恋人。喧嘩。良好すぎます。喧嘩別れできたらいい。あまりにも謎だった。
約束の時間が近づいてきたので、みのるは再び「レッツゴー」と言い、ヨアキムも「レッツゴー」と答えた。
真鈴が地図アプリで転送してくれたのは、みのるが行ったことのない雑居ビルの並んだ場所で、正義の家からの徒歩圏内にこんな場所があったことすらみのるは知らなかった。何でもない古いマンションのような建物の一室で真鈴が待っていて、中は鏡張りの大きな部屋になっていた。床はつるつるの板である。踊りやすそうだった。
「今日もよろしくお願いしまーす。みのるもせっかくだから一緒に踊ったら?」
「ぼ、僕はダンス部じゃないよ!」
「私だってダンス部じゃないよ。一人で踊るのって何か嫌じゃない? 体操服持ってないの?」
持ってきていた。
ヨアキムに「みのるは?」と翻訳アプリを介さず言われ、無視するのも気まずいので飾りのように持ってきただけの体操服が、みのるの鞄には入っていた。『霧江みのる』という名札が貼られていて、真鈴のスタイリッシュなジャージの隣に並んだら場違い感で消し飛びそうな服である。
とはいえ、あっち、と着替えブースを顎でしゃくられると、平民みのるとしては真鈴姫のいうことに従わなければならないような気持ちになり、最終的に拒否権はなかった。
「オーケー! レッツダンス!」
ヨアキムは真鈴だけではなく、みのるにも通じるように、平易な英語だけを使った。残りの会話は全てがボディランゲージである。ダンサーであるというヨアキムの体は、言葉がないのに雄弁だった。そして教え上手だった。港の見える丘公園で何回もダンスを見ていたことも加わり、みのるも何となく、イケている女の子たちの踊りの真似くらいまでは近づけるようになった。
ヨアキムはそのうち真鈴のことを「マリリン」と呼ぶようになった。真鈴もヨアキムを「キムさん」と呼ぶようになった。レッスンは三日続き、一日休みになり、また三日続いた。一週間が過ぎた。みのるの動きもそこそこは様になってきたような気がした。
みのるはその間に、ヨアキムとの距離が徐々に近づいてゆくのを感じた。
そして学習発表会の当日。
ヨアキムは学校に行こうとしなかった。
みのるが誘っても、笑顔で一言「ノー」と言うだけだった。
「えっ……登校は、自由なんですよ。大人も子どもも、誰でもフリーに入れるんです」
どうしてですかとみのるが驚くと、ヨアキムは肩をすくめるばかりだった。翻訳アプリをダウンロードした自分の端末をみのるが差し出しても、何を言おうともしない。
真鈴と喧嘩でもしたんですか? と尋ねると、ヨアキムは爆笑し、再びノーと告げた。
そしてみのるが心配そうな顔を崩そうとしないとみると、大きな手で頭を撫でてくれた。
「ドント・ウォリー」
心配しないで、と言われても、気になるものは気になった。
前日から泊まりの仕事が入ってしまった正義は、午後から学校に来てくれるという。リチャードも今日はねぼすけモードになる暇もなく、既に出かけた後である。
学習発表会のキャッチフレーズである『ウキウキ・ドキドキ』とは程遠い気持ちで、みのるは学校に向かった。それでも色紙や花紙でカラフルに飾り付けられた学校に到着すると、多少は気分が浮き立った。保護者たちがボランティアでバザーを開いていて、あげたてのコロッケが百円である。おいしかった。
「みのる! 真鈴の発表、前から三番目だってさ。ダンス部も大変だよな、あれだけ部員がいるのに、発表時間が二時間しかないんだから。もうあれ、何かスポーツみたいだよな」
ダンス部は開帆中学有数の大所帯であるものの、その他の部活動や団体にも公平にステージ発表時間を割くために、人数割の融通を利かせることはできない。そんなわけでダンス部に所属する無数のグループたちは、編集して短くした一曲を踊り切ったら即舞台袖に引っ込み、あとは客席から応援するという忙しい立ち回りを余儀なくされていた。しかも発表時間は朝一番の九時からである。
固唾をのんで見守る保護者たちの隙間に陣取り、みのると良太は真鈴の登場を待った。
踊らないの? と。
みのるは土壇場に真鈴から誘われていた。ガールズグループの曲ではあるけれど、別に男子が一人いてもいいんじゃない? せっかく練習したんだし、と。真鈴の申し出をみのるは丁重にお断りした。踊るだけならばまだしも、『その後』に起こるであろうことが怖すぎた。
真鈴は「そういう『ノイズ』は無視すればいいじゃん」と言ったが、みのるにはそんなことができる自信がなかったし、そもそも恥ずかしかった。
「お、始まるぞ」
三年生のヒップホップ風ダンスの後、流れ作業のように真鈴たちのダンスが始まった。舞台袖から飛び出してきたところからもう音楽が始まる。以前の段取りとはちょっと変わったようだった。おそらくは時間の関係で。
真鈴のダンスは抜きんでていた。ヨアキムに「ここはこう」と教わった部分を、真鈴はしっかり自分のものにして、他の誰よりも華麗に、キレキレに踊っていた。水晶の中に、一粒だけダイヤモンドが交じったように。
あれ、とみのるは思った。
スニーカーと、ピンクのジャージの裾の間の足首に、何かが輝いている。金色のチェーンと、キラキラ輝く石のようなもの。
どうして真鈴があれを、と思った時、後ろの座席の誰かがしゃべった。
「一人だけうますぎだろ。やっぱモデルは協調性がないなー」
周囲の男子がドッと笑った。だがみのるは聞かなかったことにした。
真鈴が踊っている。真鈴が格好いい。真鈴が友達と踊っている。
みのるにとって、それが一番大事なことだった。みのると同じく声を無視した良太にとっても、恐らくは。
フリーズと呼ばれる集団決めポーズの後、拍手に包まれて真鈴たちはダッシュで退場した。入れ替わりに上級生の男子グループが入ってきて、激しいロックミュージックと共に踊り始める。舞台の上を走り回るようなダンスだった。すぐに真鈴たちが客席の空いていた部分に戻ってくる。みのるたちと一列違いの後方だった。みのるがグッドというハンドサインをすると、真鈴は「当然」と口の形で応じ、つんと澄ました。
上級生のダンスが終わり、音楽が切れた時、声が聞こえた。
「そういえばあの人さあ」
公園に来てくれた人、と真鈴と同じダンスグループの女子が話しだすと、ああ、と誰かが受け合った。
「格好よかったけど、結局何だったんだろうね?」
「男の人だったのかな? 背がすごく高かったし」
「でも外人の女性モデルとかは百九十とか余裕であるじゃん?」
「珍しいもの見たねー。お客さんにいた?」
「いなかった、いなかった。いたら大騒ぎになったんじゃない?」
「確かにー」
きゃははは、という笑い声の後、みのるは真鈴の声を聞いた。
「……『人』は、『もの』じゃ、ないっつの」
低く押し殺したような声で、小さかったが、確かに聞こえた。
真鈴の言葉に、みのるは無言で、しかし力強く頷いた。
全ての公演が終わると照明がつき、客席の人々も寿司詰め状態だった会場から離脱可能になった。
みのるは人をかきわけ真鈴にたどりつき、ねえ、と声をかけた。
「お疲れさま。でも、そのアンクレット……? どうしたの」
「ああ、見えたの?」
真鈴は人波の邪魔にならないように壁際により、でんと右足を頭の高さまで持ち上げ、バレリーナの屈伸のように壁にもたせかけた。
きらきら輝くアンクレットには、カラフルで大きなビーズが九つ、はまっている。
「キムさんがつけてるのを見て、私もこういうのがほしいって言ったの。そうしたらこれは『アミュレット』だから、自分で自分のために作ってあげるといいよって言われてさ。柄でもなく手芸品店に行ってビーズ細工だよ。けっこう上手にできてない?」
「すごくいいよ! あと、そうだ、ダンスもよかったよ」
「当たり前。まずはそれを言うべき」
みのるが慌てると、真鈴はヨアキムのように口を開けて笑った。
出し物は午後の二時に全て終了した。いつもより少し早く下校できたので、みのるは一目散に帰宅した。ダンス部以外の人間による舞台の撮影は、SNSトラブルなどを考えて学校で一律禁止されていたが、部員および助っ人たちには、自分たちの踊った動画だけは配布される。みのるはそれを真鈴経由で受け取っていた。
大画面液晶テレビに映し出された、あまりぱっとしない中学校の舞台に、ヨアキムは声をあげて脚をばたばたさせた。
「ワオ! ワオ! ワンダフル!」
ダンス部の助っ人は大喜びで、画面の中の女子たちと一緒にブンブンと手を振ったり脚を動かしたりし、ライトがどうの、カメラがどうのと、みのるにも断片的には理解できる英語でぶつぶつと独り言を言っていた。
みのるは何だかそれが不思議だった。
確かにヨアキムに動画を見せたら喜んでくれるだろうとは思った。だがこんな風に、まるでハリウッドの大作映画を見ているようなテンションで大喜びするのは予想外だった。ヨアキムは『ダンサー』であり、素晴らしい身体能力の持ち主である。
だったらもう、こんなものは見慣れているんじゃないかとみのるは思った。
けげんな顔をしているみのるに気づくと、ヨアキムは何かを悟ったような顔をし、端末に話しかけた。英語の音声が日本語の文章に変換され、みのるの前に差し出される。
『私はあまり学校に通えなかったので、こういう催しをとても愛しく思います。見せてくれてありがとうございます』
「…………」
みのるは少し迷ってから、端末に言葉を吹き込んだ。
『どうしてあなたは、あまり学校に通えなかったんですか?』
震えてしまうような質問だった。だがヨアキムは、緊張しているみのるに微笑みかけ、ゆっくりと口を開いた。端末にではなく、みのる本人に。
「アンラッキー。ベリー・プアー。アンド・ビジー」
「……ぷあ……」
それは『貧しい』という意味の単語だった。ビジーは言うまでもなく、『忙しい』。子どもなのに忙しいというのはどういうことなのだろうと思ったが、みのるは少し前の自分の姿を想像し、理解した。公共料金の払い込みに行ったり。安いパンを売り出す時間に買いに行ったり。他にもいろいろ。
みのるは急に、ヨアキムといろいろなことを話したくなった。家が貧乏だとつらいですよね。でもいきなりお金持ちのお兄さんができて、いろいろと面倒を見てもらえることなんて本当にあるんでしょうか。これは何かの間違いじゃないんでしょうか。百歩譲って間違いではないとしても、僕はそんなありがたい幸運にふさわしい人間なんでしょうか。とても申し訳ない気持ちがして、時々逃げ出したくなることがあります。
だがみのるに、そんな言葉を英語にする能力はなかった。
みのるは急に、自分が死ぬほどもったいないことをしている気がして泣きたくなった。もし今まで、リチャードや正義に「英語を教えようか」と言われた時、学校の宿題だけで十分ですなどと言わずに、もっとたくさん習っていたら、ヨアキムとおしゃべりができたかもしれない。
みのるは絞り出すように告げた。
「アイウォントゥー・スタディ・イングリッシュ・モア……」
間違っていなければ『もっと英語を勉強したいです』という意味の文だった。本当なら『もっと英語を勉強しておけばよかったです』と言いたかったが、言い方がわからない。
こんなことしか言えない、とみのるが目を伏せると、ヨアキムは今度はわしわしと犬を撫でるようにみのるの頭を撫でた。そして歌うように告げた。
「ユーキャンドゥー・エニシング・ユーウォント。ユーキャンビー・エニワン・ユーウォント」
みのるがきょとんとしていると、ヨアキムは残りの言葉を端末に吹き込んだ。液晶画面に次々と日本語の文章が表示される。
『みのる、あなたのやりたいと思うことを、思う存分にやってください』
『それらはあなたの所有する宝石になります。それらは誰にも奪うことができません』
『たくさんの宝石を集め、育んでください。それらがあなたを形作ります』
宝石。
集め、育む宝石。
みのるはリチャードが見せてくれた、色とりどりの宝石の首飾りを思い出した。林くんのお父さんの珊瑚や、谷本先生が与えてくれた化石や、ヴェネツィアングラスの炎のようなガラスを。いくつかは『宝石』ではない気がしたが、みのるの中では不思議と同じカテゴリにおさまっていた。
あんなものを。
もし自分が集め、育んでゆけるなら。もし本当にそんなことができるのならば。
みのるの未来は、とても明るい気がした。
そんなのは無理だと、みのるは考えないことにした。もし本当に無理だったとしても、今そんなことを言ったら、せっかくいいことを言ってくれたヨアキムに失礼な気がした。
みのるは否定するかわりに尋ねた。
「ヨアキムさんの宝石は……何ですか……?」
今度のみのるは、端末の力を借りて質問した。ヨアキムは再び端末ではなく、直接みのるに告げることを選んだ。みのるにも理解できる単語、三つで。
ダンス。
言葉。
そして友達。
そう言ってヨアキムは、ほとんど何も入らないサイズではあるがビビッドでカラフルでかっこいいクラッチバッグを持ってきて、中から白い木綿の巾着袋を出した。
中にはダンスの練習中、いつも足首で輝いていたアンクレットが入っていた。
「あ、そういえば、真鈴がこれを真似してました。あみゅ……何とかだって」
「マリリン!」
ヨアキムは楽しそうに笑い、両手をわたわたと動かした。キュートとかチャーミングという言葉が続くので、ヨアキムが真鈴を気に入っていることがよくわかった。
みのるはおずおずとアンクレットを指さした。
「ナワラタナ……イズ……ワット……?」
ナワラタナって何なんですか? と。
ほうほうのていの英語で、みのるは疑問を投げかけた。ワットイズディス? ディスイズアペン、という例文は、実はあまり役に立たないんじゃないだろうかと、みのるはその時初めて思った。ペンと言われた後に、何と言葉を続ければいいのか書かれていないからである。
ヨアキムは少し迷ってから、端末に言葉を吹き込む代わりに、何かを検索したようだった。これ、と示されたのは、英語のたくさん並んだページである。うへえ、とみのるが顔をしかめると、ヨアキムは画面の右上の方の本のようなマークをタップした。英語が徐々に、徐々に、日本語に変換されてゆく。
一番上にはこう書かれていた。
『星のお守り ナワラタナ』
インドでは科学のひとつとされているヴェーダ占星術に基づき、一人一人の生まれた年月日、時間から、必要とされるナワラタナが割り出される。取り付けられる石は九つ。その全てに占星術的な意味があり、火星や水星などの惑星が割り当てられている。
ルビー、エメラルド、イエローサファイア、ピンクサファイアあるいは珊瑚、ブルーサファイア、真珠、ダイヤモンド、ガーネット、クリソベリル・キャッツアイ。
もちろんこれらは高価な宝石であるため、全ての人がナワラタナを身に着けることができるわけではない。同系色のより安価な石を組み合わせた『ナワラタナ』もまた、よく身に着けられている。自分自身の生まれにかかわるオンリーワンの宝飾品であるため、ナワラタナを手に入れた人は、とても大事にこの宝飾品をケアする。エトセトラ。
「星のお守り……お守りなんですね」
ヨアキムは頷いた。そして「バット」と続けた。でもね、の意味である。
同じ端末に、ヨアキムは今度は言葉を吹き込んだ。
『私はこのアンクレットが、星のお守りであるから大事であるとは思っていません。これは私がスリランカに行った時に、リチャード、およびセイギと作ったものです。大切なお土産です。その時に私は思いました。これは私にとって、守りの星ではなく、たくさんの友達の象徴なのだと』
「友達の象徴?」
メニー・フレンズ! とヨアキムは楽しそうに言った。そして九つの宝石を一つ一つ指さした。
たくさんの石。たくさんの友達。
ああそういうことかと理解した瞬間、みのるは頭の中の扉が開いたような気がした。自分がヨアキムと、英語以外話すことができない人と、こんなに難しい会話をしていることが、何かの嘘のように思えた。だが現実である。
ヨアキムは色とりどりの宝石を愛しそうに撫でつつ、ダイヤモンド――真鈴と出会った展示会のおかげで唯一みのるにもそれとわかる石を見つめながら、寂しそうな顔をした。
「ヨアキムさん?」
「…………」
ヨアキムは何も言わず首を横に振り、まだ少し寂しそうな顔で微笑んだ。
学習発表会の成功をねぎらってくれるリチャードと正義と共に、みのるとヨアキムはその日も愉快な食卓を囲んだ。今日も中華料理である。最近やけに中華が多いのは、林くんのお父さんがたびたびお惣菜を作ってくれるためである。そのたびみのるは中華街まで取りに行くことになり、あまり腕のよさそうではない謎の占い師と「あなたの隣人は元気か。元気なら運気急上昇」という謎のやりとりを繰り返していた。
その日も謎の占い師はヒロシに急かされつつ、みのると短い問答をし、最後にぎゅっと手を握ってくれた。嫌な人ではないし見かけほどあやしくもない、とみのるは理解し始めていたが、何のために何をしているのか、まるでわからないところだけがまだ少し怖かった。
中華料理の夕飯を食べ終わった後、みのるは正義にジローとサブローの散歩に招かれた。最近はすっかりヨアキムの担当になっていたが、久しぶりに正義が散歩をしたいと申し出たのである。みのるは運動靴をはいて正義と出かけた。ジローのリードを正義が、サブローのをみのるが持つ。
マンションが見えなくなった頃、正義は少し困ったような顔でみのるに微笑みかけた。
「調子がよさそうに見えるけど、どう? みのるくんは英語の上達がすごいね。ヨアキムさんといろいろおしゃべりできるみたいで、すごくびっくりしてる」
「そ、そんなことないです……ただ、単語であれこれ言ってるだけで」
「それでも考えが通じるのって、本当にすごいことだよ。中学生の時の俺だったら考えられないだろうなあ」
「そ、そんなこと……! あ、そうだ」
みのるはせっかくなので、ナワラタナについて尋ねることにした。はふはふ、と嬉しそうな息をするジローとサブローを時折撫でながら、正義は愉快そうに語った。
「『ナワ』はサンスクリット語で九つ、『ラトゥナ』は宝石って意味。スリランカには『ラトゥナプラ』っていう宝石の町もあるよ。そういうことで、九つの宝石をつけた占星術的なお守りなんだけど、ヨアキムさんが気に入ってくれてるみたいでよかった」
みのるは不意に、ダイヤモンドを見ていた時のヨアキムの顔を思い出した。
そしてその前に聞いていた、まるで意味のわからなかった言葉も。
「あの、ヨアキムさんが……大切な人と喧嘩して……喧嘩したまま別れた方がいい、って言ってたみたいなんですけど、何か誤解してるんじゃないかと思って。本当は何て言おうとしてたんだろうって考えてるんです。それとも、本当に……?」
みのるがそう告げると、正義はしばらく黙り込んだ。
何か言ってはいけないことを言ったのではなく、正義自身が驚いているからだと、みのるにもわかる、静かな動揺の表情だった。
ジローとサブローだけがご機嫌に歩き続ける中、正義は小さな深呼吸をするような間をとってから、みのるを見た。
「いろいろ事情があるってことだけ、俺は聞いてる。俺たちやみのるくんに迷惑はかけないって約束も、しばらく一緒に住むことにした時に交わしてる。でも、ヨアキムさんが本当に困ってる時には、俺は力になりたいと思ってる。もちろんリチャードもそうだと思う。あと、できれば、喧嘩したっていう『大切な人』の方にも」
知り合いの人らしい、とみのるは察した。ヨアキムが喧嘩したという相手と、正義とは。おそらくはリチャードとも。
もし自分なら、その人にさっさと「ここにヨアキムさんがいますよ」と連絡し、二人を会わせて、何とか仲直りに漕ぎつけるようにするのにな、とみのるは思った。その方が面倒がなさそうだからである。だが具体的に『何とか仲直りに漕ぎつけるようにする』とはどうすることなのか、と考え始めると、何だか嫌な気分になってきた。何も思いつかない。真鈴や良太とだったら、ファミレスかカラオケで仲直りパーティをするくらいで何とかなるかもしれなかったが、ことは大人の喧嘩である。
正義やリチャードにも、どうしたらいいのかわからないことはあるのかもしれなかった。
もしかしたら自分が思っているより、この社会とか世界とかいうものは大きいのかもしれないと思いながら、みのるは二匹の犬を連れて歩いた。それでも自分の隣を正義が歩いてくれることが、みのるは嬉しかった。
【つづく】