もののけ寺の白菊丸 第二回
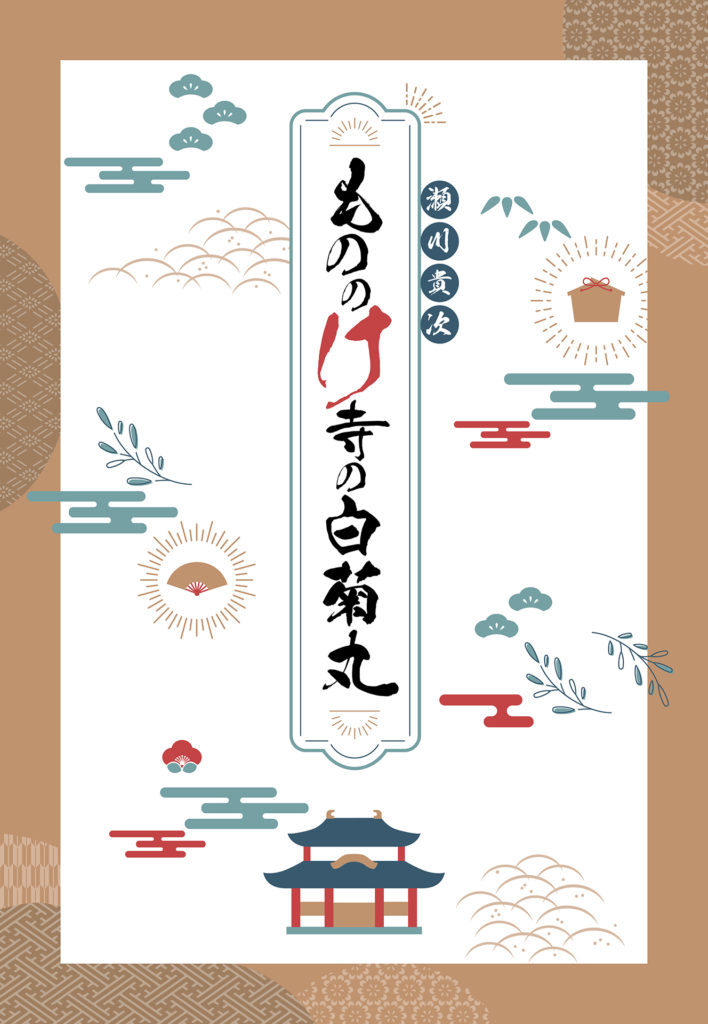
「では、白菊丸はわたしたちが勿径寺に連れて参りますので、乳母どのはここから都にお戻りなされませ」
定心に言われ、乳母は最初こそ拒んでいたが、ぐずぐずしていると再び賊の襲来があるやもしれないと諭され、涙を呑んで都に引き返していった。
白菊は定心とともに馬に乗せられ、山道を下っていく。手綱を握る我竜はずっと黙している。彼の背には、白菊の少ない荷物が負われていた。
寡黙な我竜とは対照的に、定心はよくしゃべった。
「聞いているかもしれないけれど、これから行く勿径寺には、きみのような公卿の子息たちが寺稚児として暮らしていてね。歳も同じくらいの子がほとんどだから、きっといい友になれると思うよ。というか、なってもらわないと寺が困るんだな」
あっはっはっ、と定心はよく笑う。帽子を頭からかぶって灰鼠色の頭髪は覆い隠しているものの、その陽気さまでは隠しきれない。尊いお坊さまだと聞き、想像していた和尚像とはまるで違う彼に、白菊丸は戸惑わずにいられなかったが、悪い気はしなかった。むしろ、気さくなかたで良かったと思った。
白菊は自分の本当の父親が誰か、一切、知らされていなかった。それを尋ねてはいけない雰囲気を、ずいぶんと早くから肌で感じ取っていたのだ。
養父母がいて、実母も乳母もいて、女房や家人たちに囲まれて、それでなんの不自由もなかったので、父親のことをあえて知ろうとはしなかった。大人になれば教えてもらえるだろうと漠然と思っていたし、知るのが少し怖くもあった。それが定心といると、父とはこのようなかたなのかもしれないと想像し、不思議とわくわくしてくる。
「疲れているかな? 馬に乗るのは怖くないかな?」
そう尋ねてくる定心に、
「いいえ、全然」
白菊がはきはきと応えると、定心はその大きな手で頭をわしゃわしゃとなでてくれた。
「そうか、そうか。優しげな見かけの割に、胆力があって結構、結構。これは武芸を教えて、僧兵にしたほうが勿径寺のためにもよかったりするのかな?」
どこまでが本気なのか、よくわからないことまで口にする。馬を牽く我竜が振り返って定心を睨みつけると、
「冗談だよ、冗談」
彼はからからと陽気に笑い飛ばした。
「勿径寺はね、小高い山の東斜面全体を敷地として、そのいたるところに数多の堂宇や塔が建てられ、数多くの僧侶たちが日々、仏道修行にいそしんでいるのだよ」
移動中、定心はそのように寺のことを語ってもくれた。
「寺では公卿の子息である上稚児を十名ほど、預かっている。きっと白菊ともすぐに仲良くなれると思うよ」
そうであればいいなと、白菊も心の底から願った。
寺に到着するや、白菊はさっそく、僧堂で寺稚児たちが絵の講義を受けているところに連れていかれた。
「講義中に悪いが、お邪魔するよ」
そう言いながら僧堂に入ってきた定心を、老齢の講師が笑顔で迎える。文机に向かっていた寺稚児たちもいっせいに振り返った。彼らの視線は当然ながら、新参者の白菊に集中していた。
「さあさあ、みんな、よく聞いておくれ。今日から、みなの仲間となる白菊丸だよ。仲良く頼むよ」
あっさりした紹介に困惑しながら白菊は頭を下げた。挨拶の言葉を事前に用意していたはずなのにそれが思い出せず、「白菊です……」と言うにとどまる。そのことがむしょうに恥ずかしく、顔が赤くなる。白菊は顔の赤みを隠すために、なおさら深く頭を下げた。
「では、あとはよろしく」
僧堂に白菊を残して定心は早々に退散していく。白菊は心細さをおぼえたが、みなの手前、和尚を引き止めるわけにもいかない。
あとを引き取った老講師が、「では、そこの空いた席に」と、着席するよう白菊を促す。指示された通り、白菊が席に着くと、老講師はおもむろに講義を再開させた。
「さて。では、今日は梅の絵を描いてもらおうかの。ちょうどいまは梅の盛り。勿径寺の寺内だけでも、あちらこちらに梅が咲いておる。あえて見ずとも、その花の風情、その香りは心のいずこかに刻まれているはず。それをそのまま、紙に写し取ってみなされや」
紙と筆、墨はすでに文机の上に用意されていた。白菊は墨を摩りながら、心に梅の花を思い浮かべる。
まだこの地に着いたばかりで、寺の梅はろくに見てもいない。だから、白菊が心に浮かべたのは、華山中納言の邸の庭に咲いた紅梅だった。旅立つ白菊を見送るように、梢に鶯がとまっていたさまも、はっきりと眼裏に映じてくる。
白菊はひと息ついて筆を手に取り、紅梅に鶯の絵を描いていった。
他の寺稚児たちも苦吟しながら、梅の絵を描いていく。老講師はゆっくりと文机の間を歩き、稚児たちの描く絵を覗きこむ。
その老講師の足が、ひときわ美麗な稚児の席の前で止まった。老講師は稚児の描く絵を眺めて、ほうとため息混じりの声を洩らした。
「さすがの腕前だのう」
垂髪の稚児はほんの少しだけ口角を上げて、「いえ、まだまだです」と謙遜する。
うむうむとうなずいて老講師は歩き出し、白菊の近くにまでやって来た。何かを言われることを期待したわけではなかったのに、老講師は白菊の前で足を止め、「これは……」と感嘆の声を洩らした。
「見事じゃ。梅はもちろんのこと、その鳥がなお素晴らしい」
てらいのない賞賛に、白菊はもとより、その場にいた寺稚児全員が驚きの表情を浮かべた。あの垂髪の稚児も、意外そうに目を見開いている。
「生き物を描く難しさをその歳ですでに乗り越えているとは。これは末が楽しみじゃのう」
老講師に褒められ、白菊も嬉しく感じた。と同時に、寺稚児たちの注視を浴びて、どういう顔をしていいものか、わからずに固まってしまう。中納言の邸では大人にばかり囲まれて、白菊自身と歳の近い子はほとんどいなかったのだ。
「ではでは、今日はここまで」
老講師は講義の終わりを宣言して、退室していった。そうすると、白菊の席のまわりに、自然と寺稚児たちが寄ってくる。新参のことが知りたくて、みな、うずうずしていたのだ。
「白菊、白菊と呼んでいいかな?」
「あ、はい」
「華山中納言さまの御子だと聞いたのだけれど」
「あ、はい……」
「本当に絵がうまいな。もう一度、見せてくれるかな」
「はい……」
「誰かに習ったのか?」
「いえ……」
矢継ぎ早に投げかけられる質問に、戸惑いながら対応しているため、どうしても言葉少なになる。それに、養父母の華山中納言のことも説明しづらい。中納言夫妻を本物の父母と思い、表向きにもそうしておくようにと、物心ついたときから言い含められていたので、ここでもそうしておくしかなかった。ましてや実母のことは、すでに話が通っている定心和尚以外、誰にも明かしてはならないのだ。
好奇心から白菊のまわりに集まってきた者たちの中に、あの垂髪の稚児は混ざっていなかった。彼は品のよい所作で文机の上の道具を片づけている最中で、そのそばには賢そうな顔立ちの稚児と、やけに体格のいい稚児が控えていた。さながら、本尊の左右に配される脇侍のごとくに。
白菊の視線が彼ら三人に向いていることに気づいた稚児が言う。
「気になるのか?」
白菊が否定も肯定もできずにいると、稚児たちは群れ雀のようにピイチクと勝手にしゃべり始めた。
「あのかたはな、朝廷で最も重きをおかれておられる内大臣さまの六番目の御子なのだよ」
「眉目秀麗、学問にも秀で、誠に非の打ちどころのないおかたで」
「その名も千手丸さまとおっしゃるのだ」
白菊の目が大きく見開かれた。千手の名を知った途端、母の言葉がありありと耳に甦ってきたからだ。
──あなたを授かったと知ったそのときから、母は千手観音さまに祈り続けてまいりました。
──きっとこれからも、観音さまがあなたを守り、導いてくださるでしょう。
もしかしたら、あそこにいる美麗な少年は、母が信奉する千手観音の化身なのかもしれない。そんな夢物語にも近い希望の明かりが、白菊の胸の奥底にふっと点る。
稚児たちはさらに続けた。
「そして、おそばに控えているふたりは、多聞に不動といって……」
「えっ?」
さらに驚き、思わず声をあげた白菊に、稚児たちは嬉しそうな顔をした。
「お、気づいたか」
「千手観音像の脇侍は不動明王像と毘沙門天像だものな」
「そして、毘沙門天は多聞天の別名でもある」
「偶然なのだろうけれど、面白い符号だろう?」
無邪気に面白がる稚児たちに、白菊も「え、ええ……」と曖昧に微笑んでうなずく。本当は、重なる偶然に宿命じみたものを感じ、胸がどきどきしていた。自分は来るべきところに来たのだと信じてもいいような気がしてくる。それは、中納言の邸の奥で隠れるように過ごしてきた彼にとって、まったく初めての感覚だった。
「千手……丸さま」
白菊が無意識に千手の名をつぶやいたそのとき、
「はいはい、すみません。お邪魔いたしますよー」
よく通る声で呼びかけながら、いがぐり頭の小僧が入室してきた。
寺稚児たちと年齢はそう変わらぬぐらいだろう。小柄だが、眉が太く、目に力があり、いかにも闊達そうな印象を受ける。彼は部屋を見廻し、
「白菊丸さまはおいでですか。ああ、あちらのかたですかね。はい、失礼、失礼」
白菊をみつけるや、稚児たちの間をひょいひょいとすり抜けて近づいてくる。公卿の子である上稚児たちに対して丁寧な言葉遣いをしているが、へりくだりすぎてもいない。
小僧は白菊の真正面に立ち、にっと歯を見せて笑った。
「知念と申します。白菊丸さまのお世話係を仰せつかりましたので、以後、お見知りおきを」
「あ、ああ……」
「では、お部屋にご案内しますので。ささ、参りましょう、参りましょう」
白菊の手を取り、有無を言わさずに引っ張っていく。白菊はされるがままだったが、知念の強引さを厭だとはこれっぽっちも感じていなかった。
小僧の知念に連れられて、新参の白菊が退室していく。その背中を、千手は無意識に目で追っていた。
「あ、絵を忘れていっているぞ」
稚児のひとりが、文机の上に残された白菊の絵を指さして言った。
「教えてやったほうが……」
が、彼らが立ち去った白菊を追おうとするより先に、千手が立ちあがった。
千手は黙って、白菊が使っていた文机に近づいていく。稚児たちは彼の雰囲気に圧されて、動きを止める。その間に千手は文机のそばまで来て、白菊が忘れていった絵を見下ろした。
紅梅と鶯の絵。それを目にするや、千手は小さく息を呑んだ。
「これは……」
墨一色で描かれていながら感じられる、紅梅のあでやかさ。それ以上に、梢の上の鶯へと千手の視線は吸い寄せられた。
小さな鳥の細い脚の緊張、冷たい空気を含んだ羽毛の膨らみ等、生き物の一瞬をこれほど巧みに捉えた描写を、千手はいままで目にしたことがなかった。どうしてこれを、本物の鶯を見もしないで描けたのかと驚嘆してしまう。
鶯の絵に見入っている千手の背後から、誰かが声をかけてきた。
「すみません、あの……千手丸さま」
振り返ると、小動物を思わせるつぶらな瞳が、まっすぐに千手をみつめていた。退室したはずの白菊だ。絵を置き忘れていたことに気づき、取りに戻ってきたのだろう。
白菊の視線の信じがたい純粋さに気圧され、千手はたじろいだ。と同時に、たじろいだ自分への怒りが、頭の芯からぶわりと噴き出す。
それは千手にとって初めて知る、どす黒い感情だった。
(なんだ、これは)
怒りに身を任せる以前に、驚きと困惑のほうが勝って千手は震えた。
次に、こんな負の感情をもたらしてくれた目の前の少年に、無性にいらだたしさをぶつけたくなった。
そもそも、中納言の庶子風情をどうして定心和尚は特別扱いするのか。わざわざ出迎えたり、世話係をつけたりと、これはやり過ぎではないのかと、不平不満はとめどなくわき起こってくる。感情の波の激しさに千手自身が追いついていかない。
それでも、千手は幼い怒りに身を任せるような真似だけはしなかった。寺いちばん優秀な稚児だと自他ともに認める矜持が、それを許さなかったのだ。
「千手でいいとも」
表向きは冷静に、そう返した千手の言葉に、まわりにいた他の稚児たちが「えっ」と声をあげる。
「千手さま、それは」とわざわざ言う者もいて、白菊も彼らが言わんとしていることにすぐ気づいた。
「……みなは『千手さま』とお呼びしているようですが」
千手は頭を左右に振った。白菊の絵から受けた動揺を悟られたくなくて、
「好きに呼べばいい」
いかにも面倒くさげな返事をして、その場から離れる。すかさず、多聞と不動が千手の脇についた。彼らはまさに千手観音像の脇侍となる二体の武神像さながら、こうなると誰も千手には近づけなかった。
白菊が寺に到着して早々のこの一件は、瞬く間に寺中に広まった。今度の新入りはどこか違う、との意見とともに。
老講師が白菊の絵の才をよそでも褒めちぎったせいもあろう。定心和尚が直々に出迎えたのも、与えた影響は大きかった。あの面倒くさがり屋の和尚さまが──との前置きをつけて、稚児たちのみならず、小僧や修行僧、講堂の講師たちや雑用の寺男、門番に至るまでもが、この話題を取りあげていたのだ。
「……と、言われているそうですよ」
大童子の我竜が、むっつりと仏頂面で報告するのを、当の定心は自室でごろごろと寝そべって聞いていた。頭にかぶった白い帽子からは、灰鼠色の前髪がちらりと覗いている。その前髪のせいか、それとも不謹慎なにやにや笑いのせいか、齢四十八にはとても見えない。
「そうなのか。みんな、仲良くしてくれているようで、よかったよかった」
「この話のどこが、よかったよかったなのですか」
定心の身のまわりの世話を長く務める我竜は、苦々しさを隠さず、遠慮もせずに和尚を睨みつける。
「新参者のくせに、来た早々にひとり部屋をあてがわれ、しかもお世話係までつけてもらえるなんて、分不相応だ。そんなふうに寺稚児たちに陰で言われるのが、聞こえてくるかのようですよ」
「言われているのか?」
「直接、聞いてはおりませんが、そのような話が出てもおかしくないかと。よくないことです」
我竜の苦言に定心は頓着せず、「言わせておけ、言わせておけ」とくり返し、ひらひらと手を振った。
「何もせずとも、多少の小競り合いはどうしたって起きることだから。幼い子たちはそうやって、ぶつかり合いながら成長してくれればいいよ。それより、もっと命に関わりそうな大きな危険に留意しなくてはね」
「命に関わる……ですか」
我竜のただでさえ生真面目な表情が、目を細めたことで、より厳しくなる。彼らが迎えに行かなかったら、白菊と乳母は峠の山道で賊に殺されていたかもしれなかったのだ。
「そのためにも知念をつけたのですが、あの者ひとりで対応できるかどうか……」
「できないだろうねえ」
本気で危惧しているのにあっさりといなされ、我竜は「定心さま!」と声を荒げた。
「おお、怖い、怖い。我竜はなんでもかんでも心配しすぎだよ」
「定心さまがお気楽すぎるのです」
「はいはい。気をつけましょうかね」
口ではそう言いつつ、定心の太平楽とした態度はいっこうに変わっていなかった。
──和尚と大童子がそんな会話を交わしている一方、寺稚児たちも寄ると触ると、新参の白菊の話題を口にしていた。そのほとんどが、あまり芳しくない方向へと流れていく。
「新参者のくせに、来た早々にひとり部屋をあてがわれ、しかもお世話係までつけてもらえるとはな。おかしくないか?」
ひとりがそう切り出せば、別の稚児たちも次に次に否定的な意見を述べ始める。
「中納言さまの子息だからかなぁ。でもなぁ、華山中納言さまはそれほどの権勢を誇っているわけでもなし……」
「わたしの父上も中納言で、しかも母上は正室だ。それでも、和尚さまに直接、出迎えていただけたりはなかったのに」
「あの千手さまにも、それはなかったはずだぞ。そもそも、和尚さまは筋金入りの面倒がり屋のはずだろう?」
なのに、なぜ。
明確な答えは出ない。だからこそ、もやもやとした感覚が、みなの心の底に澱のように溜まっていく。
白菊に絵画の才能があることも問題だった。それまで、一の絵上手は千手で間違いなかったのだ。千手はその完璧さから稚児たちからの支持も多く、当人が望むと望まないとに関係なく、偶像視されていた。その存在を脅かす邪魔な異分子として白菊が認定されたのだ。最初こそ、新入りへの物珍しさから浮かれていた稚児たちも、態度を変えるのは早かった。
「ここはひとつ、新参者に自分の立場をきっちり、わからせてやるべきかな……」
誰からともなく出た底意地の悪い提案に、異を唱える者はひとりとしていなかった。
ありがたい仏典や経文に関してだけでなく、絵画や和歌なども学んで、広い教養を身につけていく。白菊が勿径寺で指導された内容は、そのようなものだった。
それ自体は苦ではなく、立派な僧侶になるために必要なことなのだと思い、むしろ進んで学問に取り組んでいった。そんな白菊の前向きな姿勢は、講師陣から高く評価された。
白菊を質問責めにしていた稚児たちは、なぜか途端によそよそしくなった。が、白菊はまだ、いずれまた彼らとも自然に親しくなれるだろうと楽観視できた。それも同年代の知念が何かと世話を焼いてくれていたため、寂しさを感じずに済んでいたからに他ならなかった。
きっと、そのうち、みなとも仲良くなれるはず。あの千手さまとも、きっと。
そう、白菊は信じることにした。
でなければ、千手観音と同じ名を冠した少年にめぐり逢えるはずがない。これはきっと、御仏のお導きに相違あるまいと。
それでも、夜中にふっと目を醒ました折、母上さまはいまごろ、どうしておられるだろうかと考えずにはいられなかった。喪失感に胸が痛み、涙が目尻からあふれ、嗚咽が喉から洩れそうになる。その都度、白菊は夜具を頭から引きかぶり、寂しさを忘れて眠ろうと努力した。
そんなある日、白菊は講義のあとで数人の稚児たちから「ちょっといいだろうか」と声をかけられ、講堂の裏手に連れ出された。
ようやく、みんなと本当に仲良くなれるかもしれない。あの千手さまとも、いずれ。そんな期待を胸に、白菊はなんの警戒もせずに講堂裏についていく。稚児たちはそこで、白菊が思ってもなかった話をし出した。
「実はな、新参者の白菊は知らないだろうが、この勿径寺は他の寺院にはない重大な責務を担っているのだ」
「責務……ですか?」
そうとも、と稚児たちはそろってうなずく。みな、妙に肩肘張った、堅苦しい表情をしていた。
「始まりは勿径寺とは関係がないが。ここよりも都に近い、宇治のとある古寺の宝蔵に、いつの頃からか、力ある物の怪たちの死骸が納められるようになったのだよ」
「物の怪たちの死骸?」
「ああ。それもかの大悪鬼、酒呑童子の首に、九尾の狐の死骸。さらには、鈴鹿山を根城にしていた鬼の大嶽丸の首や、他にも世に知られていない珍しい宝の数々が、かの寺の宝蔵にて永年、守られ続けてきたのだ」
宝蔵とは文字通り、宝の蔵。寺院では主に経典などを納める場所だ。そこにまさか、物の怪の死骸が納められるとは。
いったい何を言い出すのだろうと白菊はいぶかしんだ。が、稚児たちは誰ひとりとして、表情をくずさない。語り手の稚児も生真面目な口調で語り続ける。
「ところが、都のすぐ近くで幾度となく戦乱が巻き起こり、宇治の古寺はそのあおりを受けて、ついには焼け落ちてしまった。このままでは、寺の宝蔵に封印された物の怪たちが復活し、世をさらなる混乱に陥れかねない。なので、都よりさらに遠い勿径寺が物の怪たちの死骸を引き取り、寺内に建立した宝蔵の奥深くに再び封印し直したと、そういうふうに伝わっている。そこで──」
いったん話を区切り、稚児はこふんと咳ばらいをしてから言った。
「勿径寺に新たに入ってきた者は、その胆力を鍛えるため、夜中にたったひとりで宝蔵に行かねばならないと、昔から定められているのだ」
「定め、ですか」
白菊は首を傾げた。
「そんな話は和尚さまからも知念からも一切、聞かされておりませんが」
まわりを囲む稚児たちの目が、あわただしく泳ぐ。語り手の稚児も急いで言葉を重ねた。
「それはきっと、寺に入ったばかりの白菊にそんな危うい真似はさせられないとの、和尚さまなりのご配慮だったのだろう。相手は物の怪。死骸とはいえ、なんらかの祟りを引き起こさないとも限らないわけで、和尚さまのお気持ちもわからないではない。だがな、われらはみんな、入山したての折にそのような試練を乗り越え、ここにいるわけだ。なぜ白菊だけが試練を受けないのかと、不満を溜めている者は少なくない」
「そうだったのですか……。みなさまがわたしによそよそしく振る舞われていたのは、わたしが試練を受けていないがためだったのですね」
「そうとも。そういうことだ」
語り手ばかりでなく、他の稚児たちもここぞとばかりに頭を縦に振った。単純な仲間はずれ、憧れの千手よりも絵の才があると見せつけてくれたことへのやっかみ、そんな幼い感情ゆえだったとは、誰も認めない。
物の怪と聞いて、白菊も怖じなかったわけではない。困ったことになったと困惑もした。が、稚児たちに受け容れてもらうきっかけになるやもと期待する気持ちも生じる。白菊の中で、後者のほうが次第に大きくなっていく。彼が覚悟を決めるのに、長い時間はかからなかった。
「わかりました。特別扱いはわたしも望みません。受けましょう、その試練を」
おおっと稚児たちが声をあげる。彼らはたちまち笑顔になり、口々に白菊の勇気を讃えた。
「よく言ってくれた。さすがは中納言さまの御子だ」
「それでこそ、われらの仲間」
「さっそく今夜、みなが寝静まった時刻に宝蔵に向かってもらおう」
「わかっていると思うが、和尚さまにも知念にも、このことは絶対に告げてはならないぞ」
くどいくらいに念押ししてくる稚児たちに、白菊はいちいちうなずき返した。
これでやっと彼らに受け容れてもらえる。そう思えば、うっとうしくは感じない。むしろ、気持ちは前向きになって、自然に浮かんでくる笑みを抑えることができずにいるくらいだった。
その夜、千手は自分に与えられた一室で文机に向かい、ひたすら絵を描いていた。
題材は鶯。小さな鶯が梅の梢にとまったところ、空を飛ぶところ、餌を探して地面の落ち葉をついばんでいるところ。さまざまな場面を描いており、どれも素晴らしい出来映えなのだが、千手の表情は晴れない。
描いては紙を文机からはたき落とし、描いてはまた紙を絵を飛ばす。部屋中に散らばる反故紙が増える一方で、それを不動がいちいち拾い集めている。
「夜もふけてきましたし、そろそろ休みませんか?」
不動がそう言っても、千手は無心で絵を描き続けている。不動は嘆息し、
「いい絵だと思いますが、何がお気に召さないのですか?」
と率直に問うた。いつも千手の身近にいる彼だからこそ、言えた質問だった。
千手は肩越しに不動を冷たく睨みつけ、視線以上に冷ややかな口調で告げた。
「この程度では駄目なのだ」
不動は肩をすくめて反故紙を拾い続ける。
体格のいい不動は、腕っぷしでは年上の修行僧にも負けていない。彼とやり合って勝てるのは、大童子の我竜くらいではないかとさえ言われている。
だからこそ、おのれの得意な分野で新参者に超えられた危機感は理解できないのだと、千手もそこは理解していた。
自分は誰よりも秀でていなくてはならない。いまは山里の古くさい寺院に預けられているが、それは単に幼いがゆえ。いずれは都に呼び戻されて、父や兄とともに栄光の階段をのぼっていく。あるいは出家して大寺院を任されるような身分になるかもしれない。いずれにしろ、中納言の庶子などに遅れをとってはいられないのだ。
千手がおのれに気合いを入れ、再び絵筆を走らせていると、もうひとりの取り巻きの多聞がさっと入室してきた。黙々と絵筆を走らせる千手とちらかった部屋を見やって、彼はあきれたふうに言う。
「まだやっておられるのですか」
「おう、言ってやってくれ、言ってやってくれ。根の詰めすぎはよろしくないと、いくらわたしが言っても、いっこうに聞き入れてくださらないのだ」
ぼやく不動に苦笑を投げかけ、多聞は千手の真後ろに寄り、「面白い話を聞いてまいりました」と声をかける。
そうか、と千手は気のない返事をして、絵筆を動かし続ける。多聞は何もかも心得た顔をして、静かに告げた。
「例の、白菊丸という新参の稚児なのですが」
千手の手がぴたりと止まった。不動は反故紙を拾い続けるふりをしながら、ちらちらと千手たちの様子をうかがっている。多聞は場の注意を充分ひきつけたことを確認してから、もったいぶった口調で言った。
「なんと、あやつは今上帝の落とし胤であると……」
「今上帝の?」
驚きの声をあげたのは不動だった。
「まさか。主上にはすでに、第一皇子であらせられる一の宮さまがおいでだぞ。しかも、つい最近、二の宮さまがお産まれになったばかりではないか」
「だからではないのか?」
素直に驚いてくれる不動を面白がりながら、多聞は言った。
「一の宮さまは御年五歳。いまだ幼く、しかもお身体の弱いかただと聞いている。このままでは、いつ主上の後継が絶えるかもわからない。なので、こたび、一の宮さまの母君である御息所さまが二度目のご出産を迎えられ、周囲からは大いに期待されていた。そして見事、第二皇子を産みまいらせ、御息所さまはご実家の氷野家から大絶賛されたそうだ」
娘を帝の後宮に入らせ、男児を産ませ、その子を次の帝に据える。そうして、新帝の外戚として母親の実家が権力を握る。古来より受け継がれてきた、わかりやすく確実な権力掌握の手段だ。
山里で暮らす寺稚児には必要もないはずの宮中の事情を、多聞はすらすらと述べていく。不動はううむとうなって腕組みをした。
「つまり、正室腹の男子がもうふたりもいるのだから、側室腹の第一子は不要だとみなされ、寺に厄介払いに出されたと、そういうことか」
多聞は不動のあけすけな表現を咎めもせず、逆に大きくうなずき返した。
「しかも、白菊はおそば仕えの女官が産んだ子らしい」
「女官? 正式な妃でさえないと? ああ、ならば都を追われるのも仕方がないな」
それまで黙っていた千手が、確認をとるようにつぶやく。
「新参者は帝の御落胤、か……」
多聞はうなずき、「そのようで」と返した。
「道理で、和尚さまがあいつをわざわざ出迎えなさるわけですよ」
と、不動は納得していたが、千手の表情はまだ疑わしげだ。
「いまの話は、どこまで確かなのか」
「さて、修行僧たちの噂話に過ぎないといえばそれまでですが、かなり信憑性は高いかと。主上に一の宮さまよりも年長の御子がおられるとの噂は、わたしも以前に耳にしたことがありましたから」
「多聞は頭だけでなく耳もいいのだな」
不動が真顔で褒め、多聞は自認するように薄く微笑む。
そんな話をしていた折、誰かがぺたぺたと素足で簀子縁を歩いてくる音が聞こえてきた。さっそく不動が反故紙を置いて、様子を見に簀子縁に出ていく。鉢合わせしたのは、小僧の知念だった。
「なんだ、知念か」
「どうも、不動さま」
格上の上稚児に、知念は一礼して言った。
「こちらに白菊さまはおいでではありませんか?」
「いるわけがないではないか」
即答する不動に、「ですよねえ」と知念は笑いかける。
「やれやれ。こんな夜ふけにどこに行かれたのか」
多聞が言う。
「月も出ているし、気晴らしにそのあたりを歩いているのかもしれない。寺に来たばかりの頃は、そういう気分になることもある」
「なるほど、それはそうかもしれませんね。では、お帰りを部屋で待つことにしましょうか。どうもみなさん、お邪魔をいたしました」
来たときと同じく、ぺたぺたと足音をさせて知念は去っていく。その音が完全に聞こえなくなってから、多聞が言った。
「そういえば……、昼間、講堂の裏で白菊が稚児たちに囲まれているのを見ましたよ」
ピンとくるものがあったのか、不動が濃い眉をひそめる。
「なんだ。さっそく新参いびりが始まったか?」
「おそらくは」
千手が小さくため息をついて立ちあがった。不動と多聞が異口同音に「どうされました?」と彼に訊く。
「疲れたので、少し外を歩いてくる」
不動が額面通りに受け取って「これからですか?」と驚く一方、多聞はにこりと笑って「では、お供いたしましょう」と申し出た。
「必要ない。それよりも、おまえたちは新参の白菊を捜すといい」
「白菊をですか? ほうっておけばよろしいではないですか」
いちいち驚く不動の広い肩を、まあまあと多聞が叩く。千手は淡々とした口調で言った。
「白菊がまこと主上の御落胤ならば、ほうってもおけまい。寺内には思いがけないところに急な崖があったりする。慣れない白菊が足を踏みはずして怪我でもしたら大ごとだ」
「なるほど。そういうことでしたらば、わたしと多聞で行ってまいりましょう。千手さまはどうか、お部屋で……」
みなまで言わせず、千手はしかめっ面で振り返った。
「言っただろう? わたしは気晴らしに外を歩きたいだけだ」
言いながら、千手はけだるそうに髪を後ろにかきやった。彼の長い髪は燈台の明かりを反射して、つやつやと烏の濡れ羽色に輝く。
困惑する不動に代わって、多聞がすまし顔で言った。
「では、わたしたちは稚児たちの誰かに、白菊に何を告げたか聞き出してみます。そのほうが、宛てもなく寺内を歩くより効率がよいですからね。何かわかりましたら、千手さまにご報告いたしますので、あまり遠くへは行かないでくださると助かります」
うむ、と千手がうなずく。
不動は勢いよく挙手をし、前のめり気味に言った。
「その聞き出し役、わたしがやろう」
「締めあげ役の間違いだろう」と多聞が訂正を入れる。
千手も多聞と同感だったが、そんな乱暴なことはやめろと不動に命じるつもりはさらさらなかった。
【つづく】