もののけ寺の白菊丸 最終回
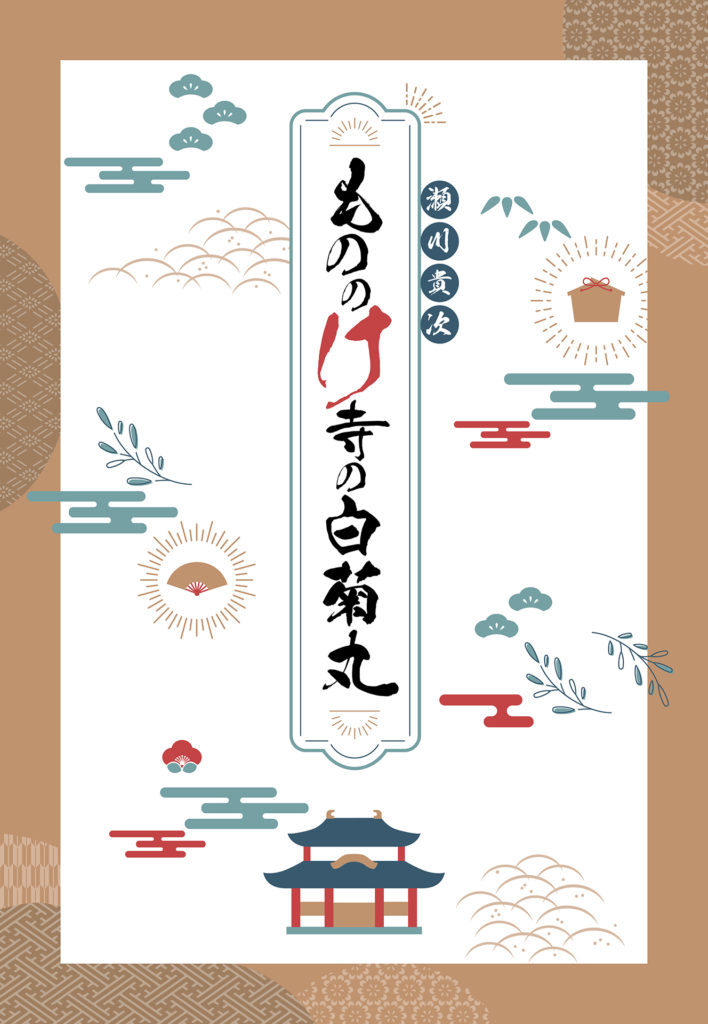
半分ほどに膨らんだ月が、山の斜面に転々と建つ堂宇の屋根を照らしている。
おかげで、案じていたよりも夜の寺内は明るい。これならば松明の類いがなくともどうにかなるなと思いつつ、白菊は宝蔵を目指し、緩やかな勾配の砂利道をひとり歩いていた。
勿径寺に新たに入った者は、胆力を鍛えるため、夜中にたったひとりで宝蔵に行かねばならない。その宝蔵には、古の物の怪たちの死骸が納められているらしい──
怖くないと言えば嘘になる。が、ここで尻込みしては寺稚児たちに受け容れてもらえまい。寺で修行を重ね、立派な僧侶となって母との再会を果たす。そのためには、こんな初手でつまずいてはいられないのだ。
涙に暮れながら別れた実母の切なげな顔を思い返せば、宵闇をおそれる暇さえ惜しい。ひと晩で片づく試練なら、さっさと片づけてしまおうと、白菊もすでに腹をくくっていた。
何も告げずに出てきてしまったので、知念には要らぬ心配をさせてしまうかもしれない。それだけは気がかりだったが、あとでよく説明しておくしか対処法は考えられなかった。
大丈夫、何も起こりはしない。生きた物の怪ならともかく、死骸が納められているのに過ぎないのなら、怖がる必要などそもそもないのだから……。
そんな理屈を並べながら白菊は歩み、ようやく宝蔵にたどり着いた。
瓦葺きの建物は古めかしく、観音堂や地蔵堂といった寺内の各所に点在する他の堂宇と見た目の違いはほとんどない。ここにそんな貴重な──危険な呪物が収蔵されているとは、にわかには信じがたい。それらしさを無理に探そうとするなら、扉にやけに大きな錠前がぶらさがっている点だろうか。
鍵は寺稚児のひとりから、すでに預かっていた。堂宇を管理する寺男のもとから、こっそり持ち出してきたらしい。これで宝蔵の中に入り、倉の奥に置かれている祭壇から何か行った証しになりそうなものを取ってくる。それが白菊に与えられた試練だった。
昔話でいうなら、即、仏罰が当たりそうな展開だ。ましてや、宝蔵に納められているのは物の怪の死骸。どんな祟りが及ぶか、知れたものではない。それでも、ここまで来た以上はやらなくてはならない。
息を詰めて、扉にかかった大きな錠に鍵を差す。いっそ、鍵が合わなければ言い訳もたつのにと思いながら鍵を廻すと、かちりと乾いた音がして錠がはずれた。白菊は唇を堅く結んで、宝蔵の扉をゆっくりとあけた。
中は真っ暗で、何も見えなかった。これでは祭壇がどこにあるのかも見分けがつかない。扉はあけたままにして、外から射しこむ光を頼りに奥へ進むしかあるまい。
扉に寄りかかり、目が闇に慣れるのを待ってから、白菊はそろりそろりと宝蔵の中へと歩を進めた。ところが、床板のわずかな段差にさっそくつまずき、転倒する。
前のめりに倒れた白菊は、右膝を床に思い切りぶつけてしまった。うわぁ……と小さく声をあげ、しばらくしてから、括り袴の裾をめくって膝に触ってみる。皮膚が少しめくれているのだろう、ざらざらとした感触が指先に伝わってきた。血も少し出ているようだ。
が、そんな大した傷でもない。これなら大丈夫と、白菊は自分に言い聞かせた。
「もっと注意深く進まないと……」
声に出してそう言いつつ、宝蔵の奥に向けて目を凝らす。そのとき、さっきまではなかったはずのモノが、白菊の目にとまった。
墨よりも黒い真の闇に閉ざされた中、白い霞がぼんやりと漂っている。それは最初、霧の塊のようにも見えた。
静かに揺らいでいる。煙のような靄をまとって。
宝蔵の中は空気がほとんど動いていない。なのに、それは常に微風を受けているかのごとく、細かく、あえかに蠢いている。
白菊の目が慣れてきたのか、それともそれが形を変えたのか。霧の塊のようだったそれは、次第に違うふうに見えてきた。
四足獣、と白菊は思った。真っ白くて長毛な。その繊細な体毛が、ひとではほとんど知覚できない空気の流れを捉えて立ちあがり、煙か湯気のようにゆらゆらと揺らいでいる。
ただし、なんの獣なのかは判別がつかない。細長い頭部に長い脚を見れば、鹿か馬のようでもある。が、大きな口の端からは鋭い牙が覗いている。非常に大型の狐のようにも見える。にしても、目があるべきところにそれが見当たらないのは奇妙だ。耳もない。それとも、堂内が暗すぎて白菊が視認できないだけなのか。
あれはもしや、宝蔵に封印された物の怪か。そう考えただけで、白菊は動けなくなってしまった。いや、下手に動くと、むこうの注意を引きつけてしまいかねない。
白菊が固まっていると、それは鼻先を高く上げ、くんくんと空気のにおいを嗅いでから、ため息のような声を洩らした。
「おや……。血の香りがするよ……」
女の声だ。若くはないだろうが、年をとりすぎてもいない。品があると同時に、なまめかしくさえ聞こえる。
「不思議と懐かしい香りだねえ」
そんなことをつぶやきながら、それは一歩一歩、白菊に近づいてきた。歩みに合わせ、逆立った白い体毛も細かく揺れている。
白菊が叫び出す前に、それは歩みを止めた。細長い顔の両脇に線状の切れこみが生じ、それが開いて一対の目となる。瞳の色は甘い糖蜜のようだ。やや小ぶりながら、耳も立つ。耳のほうは単に伏せていただけのようだ。
目と耳がつくと、それの印象はだいぶ狐に近くなった。もしや封印された九尾の狐なのだろうかと、白菊は焦る。ただし、それには尾がひとつしかない。形も狐よりは細く、猫の尾に似ている。なんにしろ、人語をしゃべる獣が普通の存在であるはずがなかった。
物の怪だ、と白菊は確信した。この寺が宝蔵に物の怪を封印しているという話は本当だったのだ。しかも死骸ではなく生きている。
正体不明の白い物の怪は、糖蜜色の瞳でじっと白菊を観察してから言った。
「今参の稚児か」
今参とは新参の意だ。
「こんな夜ふけに、こんなところへ幼い子がひとりで来るものではないぞ。鬼に喰われてしまうかもしれぬからのう」
諭すようなその口調は、別れてきた乳母を思わせた。そのせいだろう、恐怖の呪縛がほんの少しやわらぎ、白菊はかすれ声ながら相手に問いかけることができた。
「……おまえは鬼なのか?」
「さあ?」
物の怪は小首を傾げた。
「角は持っておらぬが」
「では、九尾の……」
「われが何者であったのか、もうすっかり忘れてしもうたよ」
その緩慢で優美とも言える動きに、なまめかしい声に、白菊はなぜか惹きつけられてしまう。おそろしくてたまらないのに、目が離せない。
物の怪は再びゆっくりと白菊に近づいてきた。一定の距離をおいて立ち止まり、大きな口が少し開いて、薄紅色の細長い舌をするりとのばしてくる。物の怪の舌先は、白菊の怪我をしたほうの膝小僧を舐めて、すぐに引っこんだ。白菊は驚き、めくりあげたままにしていた袴を急いで下ろした。
「なるほど」
白菊の血の味を口の中で転がした結果、物の怪は何かを察したようだった。
「おまえの血の香りと味は……、忘れていた遠い昔を思い出させてくれそうだ」
過ぎた過去を懐かしむように、物の怪は目を細めた。そうすると、白い体毛にまぎれてしまい、目の位置がまたわからなくなる。が、物の怪はすぐに目をあけ、白菊を見据えて言った。
「悪くない心地にさせてもらえた。礼をしよう。何が欲しい?」
「何がって……」
こういう妖しげなモノから授けられた品は、よからぬ事態を招きそうな予感がして、菊はためらった。が、ここに来た目的を果たさずに帰るのも気が引ける。
「祭壇の何かを……、ここに来た証しになるような物を持ち帰らないといけなくて」
くっ、と物の怪の喉が鳴った。くっ、くっ、と続けざまに鳴ることで、それが笑い声だとやっと白菊にもわかった。ただし、なぜ笑われているのかは、いまひとつ理解できない。
「そういう理由で来たわけか」
「理由?」
「誰かに言われたのだろう? 物の怪を封じる宝蔵にひとりで行って、証しになるような物を持ち帰ってこいと」
「……新参は必ず受けねばならない試練だそうだから」
くっくっくっと、物の怪がより声を高くして笑う。笑いすぎて涙が出てきたのか、それは前脚で猫のように顔をぬぐった。
「試練を受けに来た今参の稚児など、われはこれまで見たこともないぞ」
「えっ? それって……」
「つまりはそういうこと。謀られたのだよ」
「そんな……」
「いかにも寺稚児らしいな。幼い、幼い」
笑いながら、物の怪は白菊から離れ、宝蔵の奥へと移動した。その先に祭壇が設けられていることに、白菊は遅まきながら気がついた。
仏像の前に設けられる壇のように、燭台や香炉、花立てなどが置かれている。物の怪は前足を祭壇にかけると、香炉の蓋を咥え、白菊のもとに引き返してきた。咥えていた香炉の蓋を彼に渡し、
「これを証しにすればよい」
「……ありがとう」
ぺこりと頭を下げた白菊を、物の怪は目を細めてじっとみつめた。
糖蜜色の瞳から、その感情を読み取るのは難しい。逆立った長い毛は、依然、煙のように揺らぎ続けている。まるで霞の衣をまとっているようにも見えて、異形ではあるものの美しいと感じざるを得ない。
しかも、夜中に宝蔵に勝手に入ったことを責めもせず、証しの品まで渡してくれるとは。もしかして、これはいい物の怪なのかもと白菊が期待しつつ思っていると、
「おお、そうだ。知っているか? ここに封じられているのは、われのみではないのだぞ」
言われたと同時に、白菊の足裏に不気味な振動が伝わってきた。何かが宝蔵の真下で大きく身震いしたかのごとくに。
同じ振動を感じたのだろう、白い物の怪がにやりと笑う。
「鬼が起きてくる前に出ていったほうがいい。やつらはわれと違って、かなり粗暴であるからのう」
宝蔵には、九尾の狐の死骸だけではなく、源頼光に退治された酒呑童子、鈴鹿山で暴れた大嶽丸といった、おそろしい悪鬼の首も納められているという。稚児たちから聞いた話を思い出し、白菊は血相を変えた。
振り返ると、宝蔵の扉がゆっくりと閉まり出していた。足もとの振動はまだ続いている。もしかしたら、この振動の影響で扉が動き始めたのかもしれない。
閉じこめられる。その恐怖に衝き動かされて、白菊は走った。
あの扉が閉まったら、堂内は完全な暗闇となる。そんなところで鬼やら妖狐やら複数の物の怪に囲まれて、無事で済むはずがない。白い物の怪は直接、手出しをしてこなかったが、闇の中で豹変し、襲ってこないとも限らないのだ。
(早く、早く逃げなければ)
大した距離ではないに、気持ちばかりが逸って足がもつれる。扉の隙間は徐々に細くなり、そこから射しこむ月明かりは、もはや、ほんのわずかだ。
あともう少しで扉は完全に閉まる。ここは闇に包まれる。鬼が目醒める。そうなったら、おのれの命はきっとない──
絶望で胸がはちきれそうになる寸前、外から差し出された細い指が、閉まりかけていた扉の縁をつかんだ。ぐいっと扉を引きあけたその手の持ち主は、千手だった。
「千手さま……!」
千手は眉をひそめて、ぼそりと言った。
「やはり、ここだったか」
寺稚児たちを締めあげるまでもなく、新参者を怖がらせる手段として、何かと噂のある宝蔵を用いるのは常套だろうと判断し、千手はまっすぐここに来たのだった。そうとは明かさず、彼は白菊に素っ気なく言った。
「知念が捜している。帰るぞ」
くるりと背を向け、千手は歩き出す。
白菊は宝蔵の中を振り返ったが、堂内は真っ暗で、あの白い物の怪の姿はどこにも見当たらなかった。まるで最初からそんなものはいなかったかのように。
足もとの振動も、ぴたりと止まっている。白菊の手の中に残された香炉の蓋だけが、一連の出来事が夢まぼろしでなかったことの証拠だった。
「何をしている。ぐずぐずするな」
千手がいらだたしげに呼ぶ。白菊はあわてて扉を閉め、千手のもとに急いだ。
「千手さま、あの、あの……。わたしを助けに来てくださったのですね」
「助ける?」
千手は歩みを止め、しかめっ面をして振り返った。
「勘違いをするな。どうして、わたしが助けになど……」
「でも、こうして来てくださったではありませんか」
「それはおまえが今上帝の御落胤と聞いたからだ。でなかったら、誰がわざわざ──」
「今上帝の?」
まったく予期していなかったことを千手から聞かされ、白菊は衝撃を受けて硬直した。
「わたしが……、御落胤……」
唐突すぎて、最初は理解ができなかった。言葉の意味が頭に染み通っていくにつれて、白菊の身体はざわざわと震え始めた。
どうして、中納言夫妻が実の親であるかのように振る舞っていたのか。どうして、実母は中納言邸の奥深くで身を隠すように暮らしていたのか。そしてどうして、自分は寺に預けられることになったのか。
そのすべての答えが、千手から投げかけられたひと言の中にあった。
白菊自身も中納言の邸内でひっそりと育てられ、外の世界のことはほとんど知らされていなかった。それでも、今上帝に幼い第一皇子がいて、第二皇子が産まれたばかりという話は、女房たちがひそひそと噂していたので知っていた。勿径寺に行く話が出たのは、その直後だったような記憶もある。
自分が帝の子であったから。そう考えれば、さまざまなことに合点がいくのだ。
欠けていた部分が埋まって、ひとつの絵が完成したかのようだった。あるいは、濃く立ちこめていた霧が晴れて、行く手が唐突に見えてきたような。
もたらされた開放感は、白菊が初めて知る感覚だった。それまで囚われていたことにさえ気づいていなかった分、衝撃の大きさは計り知れない。
千手も白菊の反応がただならぬのを感じ取っていた。
「まさか、知らなかったのか?」
「はい……」
気まずい思いが千手の顔に広がる。こういうとき、何をどうすればいいのかと激しく動揺する千手に、白菊は目を潤ませながら言った。
「やはり、あなたは千手観音さまの化身……。わたしの運命の導き手だったのですね」
「……は?」
「母上さまに言われたのです。と。千手観音さまがわたしを守り、導いてくださると。その観音さまと同じ名を冠したあなたとこの勿径寺で出逢えたのは、もはやただの偶然とは思えません。千手さま、これはきっと運命の出逢いなのです。間違いなく運命です」
相当な熱量で運命だと連呼され、千手の端整な顔がぐぐっと変形した。目は大きく見開かれ、鼻孔は横に広がり、唇は左右非対称に歪む。その口から飛び出した言葉は、上品とはとても評しがたかった。
「な、何をたわけたことを言っているのだ、おまえは。おそろしさのあまり、どこかおかしくなったのか?」
「いいえ、いいえ」
首を横に振りながら、白菊は笑った。
「わたしがおかしくなったというのなら、それは喜びがあまりにも大きかったからですよ」「はああ?」
なんと罵倒されようとも、白菊の歓喜は消えない。遠い極楽にしかいないと思われていた観音の化身が、こんなにも身近にいたという驚きと喜びは、そうそう容易くしぼみはしないのだ。これまで胸をふさいでいた心細さが一気に解消してしまったのだから、無理もなかった。そうとは知らない千手が白菊を薄気味悪く感じるのも、これまた仕方なかった。
「わたしは嬉しいのです。本当ですよ。千手さま、千手さま」
「わかったから、へらへら笑っていないで早く部屋に戻れ。いつまでも、こんな物騒なところにいるんじゃない」
「はい。では、いっしょに参りましょう」
「おまえといっしょにだと?」
千手は口を極限にまで歪め、白菊に言い返そうとした。が、適した言葉がみつけられず、
「勝手にしろ」
短く言い放って、せかせかと走り出す。白菊も、千手の背中を追って走り出した。
千手が露骨に走る速度を上げても、白菊もめげずに彼を追っていく。むしろ、そうやって追うのが楽しくさえあった。膝小僧の痛みもなんのその、身体は翼を得たかのように軽い。心も軽い。
自分が誰だか、やっとわかったからだと、白菊は自覚していた。この寺に預けられたのは見捨てられたからではなく、千手観音の化身と出逢うためだったのだとも思えたから、なおさら。
いつまでも嘆いてはいられない。帝の御落胤という大きすぎるしがらみにはこだわらず、俗世とは違う世での成長を図ろう。そうしてこそ、なんの縛りもなく実母との再会も果たせるだろうから。
(ですよね、母上さま)
走る千手の表情が、せっかくの美貌が台無しになるほど必死になっているのも、白菊には見えていない。くすくすと笑う物の怪の声が近くで聞こえたような気もしたが、そこに厭な感じはまったくない。
傍目には、仲良しの稚児がふたり、月下で無心に追いかけっこに興じているような、そんな微笑ましい光景に見えていた。
【おわり】