もののけ寺の白菊丸 第一回
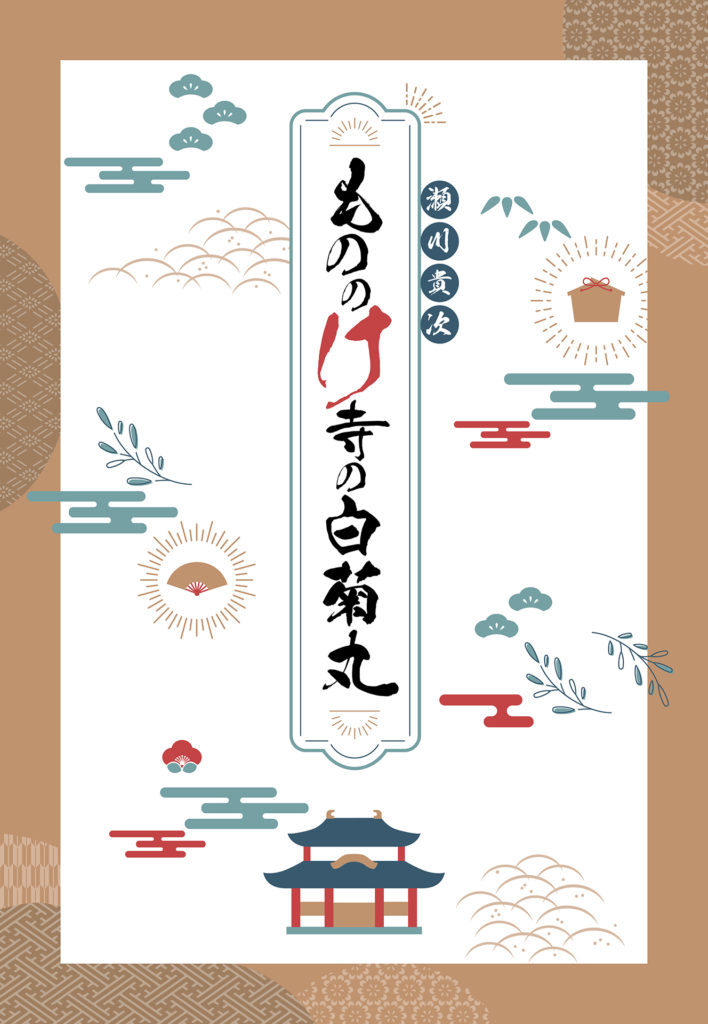
泣いてはいけない。
数えの十二歳になって間もない白菊は、そう自分に言い聞かせつつ、寝殿造りの奥の一室で実の母と向き合っていた。
元服前の白菊は長い髪を頭頂部でひとつに束ね、薄浅葱の水干に身を包んでいる。母は表を白、裏に赤を重ねた袿をまとっている。庭先に咲く紅梅の香りと相まって、若く美しい母は梅の花の精霊のようだ。
が、昼間だというのに陽の光が充分に届かず、室内は薄暗かった。母上さまのお顔をもっとよく見ておきたいのに、どうしてこんなに暗いのだろうと、白菊はもどかしく感じずにはいられない。
もどかしさが高じ、白菊の唇は真一文字に結ばれ、膝の上に置かれた小さな手はぐっと強く握られていた。わが子のその手に、母は白い手をそっと重ねて優しくささやく。
「白菊丸……。立派なお坊さまになるのですよ」
語尾が、それとわからぬほどながら震えている。母もまた、泣くのを懸命にこらえているのだ。
明日、白菊はこの邸を離れ、京の都のずっと南、大和国の寺に預けられる。そこで修行を重ね、ゆくゆくは僧侶となるように、彼の未来はすでに定められていた。それ自体には白菊も否やはない。だが、寺に入れば、もう母とは逢えなくなる。そのことが十二歳の少年の胸を重くふさいでいた。
なのに、母は思いも寄らないことを子に告げた。
「あなたが立派なお坊さまになれば、誰はばかることなく逢えますからね」
誰はばかることなく逢える。
その言葉は、悲嘆に暮れていた白菊の心にひとすじの光と温もりを投げかけた。
「また……逢えるのですか? 本当に?」
おそるおそる問い返す白菊に、母はうなずき返した。
「ええ、きっと」
白菊はもっと幼い時分から、実母の伯父夫婦を父上、母上と呼ぶようにしっかりと言い含められてきた。だからこそ、彼は実母をあえて「母上さま」と呼ぶ。育ての親たちも幼子なりの気遣いを汲み取って、呼称の使い分けを容認してくれていた。
こうして実母に「母上さま」と直接、呼びかけるのも、今日が最後になるのだと、白菊は覚悟していた。なのに、思いがけず「また逢える」と言われ、心が揺れる。目に涙が浮かんでくる。
わが子をみつめる母の目も、同じように涙に濡れていた。
「あなたを授かったと知ったそのときから、母は千手観音さまに祈り続けてまいりました。観音さまの御加護があったからこそ、あなたは無事に産まれてこれたのです。ですから、きっとこれからも、観音さまがあなたを守り、導いてくださるでしょう」
何も心配はいりませんよ、しっかり勉学に励むのですよ、と、母は言葉を重ねていく。白菊も母を安心させる言葉、決意の言葉を発しようと口を開いた。なのに、
「母上さま」
それだけしか言えない。呼吸を調え、再び試みるも、
「母上さま……」
やはり、そのあとが続かない。そればかりか涙で視界が霞んでいく。母の顔をもっとしっかり、みつめていたいのに。心に深く刻みこんでおきたいのに。
「母上さま……、母上さま……」
もどかしさは頂点に達し、白菊の目からは涙がとめどなくあふれてきた。母もこらえきれずに涙をこぼす。
紅梅の香りが微風に乗って漂う中、親子は身を寄せ合って静かにすすり泣いた。いくら泣いても涙は尽きそうになかった。
そして、翌朝──
まぶしい朝日の中、一台の牛車が簀子縁の階に寄せられた。「さあ、参りましょう」と、乳母が優しく白菊を促す。うなずいた白菊の白い頬に、もう昨夜の涙の痕はない。
見送りに立っているのは、親代わりになってくれていた中納言夫妻だけで、実母の姿はなかった。別れはすでに昨日のうちに済ませていたのだ。
「行って参ります。父上、母上」
幼いながら、すでに心を決めている白菊の健気さに、養父と養母も涙を禁じ得ない。
「達者でな、白菊」
「身体にはくれぐれも気をつけるのですよ」
はいと応え、養父たちに笑顔を見せて、白菊は牛車に乗りこんだ。
すでに車中で彼を待っていた乳母も、同行するのは寺の門前まで。物心ついたときから暮らしていた洛中のこの邸へも、もはや再び帰ってこれまい。庭に咲く紅梅も、もう見納めかと思いつつ、車中から見やると、小さな鶯が一羽、その梢にとまった。
あ、と思った次の瞬間には、鶯は梢を飛び立ち、もう姿が見えなくなる。
(あんな小さな鳥でさえ、おのれの好きな場所に飛んでいけるのに、引き替え自分は……)
弱気になりかける白菊の胸に、昨夜の実母の言葉が甦る。
──あなたが立派なお坊さまになれば、誰はばかることなく逢えますからね。
あの言葉は本当なのか、ただの気休めなのか。後者だとしても、いまは信じて前に進むしかない。
(母上さま……)
水干の広袖の中で、白菊は誰にもわからぬように拳を堅く握りしめていた。
小高い山の東側斜面に、小さな御堂がいくつも点在している。そのすべてが、勿径寺に属するものだった。
年が明けて、寺の境内ではそこかしこで梅の花が咲いていた。白、紅、薄紅と、色合いはさまざま、どの花もかぐわしい香りを放っている。
花だけが美しいわけではなかった。梅林をそぞろ歩いている寺稚児たちも、それぞれに美麗な装束をまとっている。所作も品よく、誰も彼もが育ちの良さをうかがわせた。
中でもひときわ目立っていたのが、十二歳の千手丸だった。
結わずに背中に流した髪は、早春の光をはじく艶やかな濡れ羽色。白い面は優美で、昔物語に登場する美姫のごとき風情を醸し出している。それでいて上背があり、いっそうの華やかさを彼に添えていた。薄紫の狩衣の着こなしも、完璧と言って差し支えない。
まわりの寺稚児たちも、彼にだけは「千手さま」「千手さま」と様付けで呼びかける。
「あれ、ご覧ください、千手さま」
寺稚児のひとりが、山裾を行く馬を指差した。有髪の大童子が手綱を引くその馬には、普通は襟巻きにする白い布を頭に巻いた僧侶がまたがっている。天台座主などの高僧にしかできないはずの、帽子と呼ばれる被りものを特別に許されているのは、勿径寺を総括する定心和尚だった。
寺稚児たちは山の上から、和尚さま、和尚さまと大声で呼びかけた。聞こえないのか、定心たちは振り返らずに馬を進めていく。
「どこに行かれるのでしょうね」
誰かが洩らした疑問に、誰かが応える。
「新参の稚児をお迎えに行かれると、修行僧たちが今朝がた話していたよ」
えっ、と驚きの声が寺稚児たちの間から起きた。
「定心さまが御自ら、お出迎えに?」
「よほどの家の出なのか?」
「それが華山中納言さまの庶出の子らしいぞ」
「中納言さま……。なるほど。公卿の子ではあるけれども、庶出か……」
微妙な空気が稚児たちの間に流れる。
貴族の中でも大臣、大納言、中納言、そして参議の高官たちは、公卿と称される上流貴族。ここにいる寺稚児たちは、そのほとんどが公卿の子だった。
上流貴族の子息とはいえ、四男、五男、六男ともなると持てあまされて、寺に預けられることは昔からよくあった。後継に空きが出れば、実家に呼び戻されることもある。でなければ彼らは将来、僧侶となり、俗界とはまた違う世界での栄達を目指すのだ。
新入りの話で沸く稚児たちの間で、千手は黙って、遠く定心和尚の後ろ姿をみつめていた。その細眉は、わずかながら不快そうにひそめられている。
三年前、千手がこの寺に迎えられた際、定心和尚とは寺内で対面した。わざわざ出迎えなどはされなかった。千手だけでなく、他の誰に対しても定心はそうだった。
(なのに、なぜ今回に限って……)
中納言よりも格上の大臣、大納言の子たちもそこにはいた。千手自身が内大臣の正室腹の子息なのだ。なのに格下の中納言の、それも庶子をなぜ特別に遇するのだろうかと不思議がるのは、当然のことだった。
常に千手の傍らにいる取り巻きのひとり、多聞が彼のいらだちに気づいて、さらりと言った。
「おそらく何か外出の御用があって、和尚さまはそのついでに出かけられたのでしょう」
寺稚児たちの中でもひときわ背が高く、がっしりとした体格の不動も言う。
「今日はふもとの里に市が立つ日ですからね。酒を求めに出られたのかもしれません。いや、きっとそうだな」
聡い多聞に、子供らしくないいかつい顔の不動がふたりして言うと、いかにもそれが真実であるかのように響く。千手は肩の力を抜いて、ふっと笑った。
「和尚さまの飲酒癖には困ったものだ」
いかにも、と多聞と不動が声をそろえ、ほかの寺稚児たちも笑いながらうなずく。
勿径寺の門前に建つ石柱には、『不許葷酒入山門』との文言が刻まれている。ニンニクなどのくさい野菜や酒を口にした者は、修行の妨げになるので寺に入ってはならない、との意味だ。だが、その戒めを勿径寺の長はまるで守っていなかった。
白菊と彼の乳母を乗せた牛車は、山中の細い道を進んでいた。
乳母は物見の窓から外ばかりを眺めていた。最初こそは、春の山々が連なる景色を珍しがっていたものの、それが延々続くと飽きてきて、
「見渡す限り、山、山、山と、山ばかり。里はまだなのですか」
もう何度目かになるかわからない問いを、徒歩で従う従者たちや牛飼い童に投げかける。従者も苦笑しつつ、律儀に応える。
「峠はとうに過ぎましたから、もう少ししたら里が見えてきますよ。そこまで来たら、勿径寺はすぐですから」
「すぐそこ、すぐそこと、いったい何度聞かされたやら」
長時間、牛車に揺られ続けた疲れもあって、乳母はかなり不機嫌だった。
白菊は都を離れてからというもの、ほとんど外の景色を見ていなかった。最初こそは、いつ戻ってこられるかわからない都の光景を記憶にとどめておこうと、物見の窓にかじりついていた。が、次第にひとの姿や家が消え、どんどん寂しくなっていく景色に、切なさに耐えきれなくなってしまったのだ。
かといって、外をまったく見ないでいると気持ちは自然と内向きになり、これまた別種の切なさ、母親恋しさがこみ上げてくる。どうにもならない憂鬱の袋小路に入りこんだ、そんな未熟な自分に白菊自身がいちばん辟易していた。
(いつまでも悲しがっていてはいけない。もう都には戻れないのだから、嘆く暇があるなら、その分、立派なお坊さまになるべく修行に励まないと……)
呪文のように言い聞かせているうちに、いつしか白菊はうつらうつらと船を漕いでいた。その微睡みが、突然、牛車がガクンと停車したことで破られる。
きゃっと小さな悲鳴をあげた乳母が、「何事ですか」と叱責の声をあげる。しかし、それに対する従者からの返答はない。
小さな物見の窓からでは事態が把握できず、乳母は牛車の前面の御簾を跳ねあげた。
「何事……」
問う声が宙ぶらりんになる。牛車の行く手を阻むように、数人の男たちが細い道に立ちふさがっていたからだ。
みな、ばさばさの髪に萎烏帽子、垢じみた筒袖を身につけ、見るからに怪しげな風体で、にやにやと笑っている。さらに悪いことに、肩に長槍をひっかけたり、垂らした手に抜き身の太刀を握っていたりと、不穏な空気はこの上ない。
乳母はひっ、と息を呑み、四つん這いになって牛車の奥へ後ずさった。白菊は眠気も何も吹き飛び、目を丸くして御簾越しに外の光景をみつめる。
従者たちも刀の柄に手をかけ、「何用だ」と語気荒く男たちに問いかけた。
「何用も何も、わかるだろ?」
唯一、筒袖ではなく古ぼけた直垂を身につけている男が、露骨に嘲るような口調で言った。
「そっちの数より、こっちの数のほうが多いからな。ほら、後ろを見てみろよ」
ざざざっと砂を蹴る音がして、牛車の後方に数名の男たちが現れる。数が増えたばかりでなく、完全に挟み撃ちにされてしまったのだ。
間違いない。山賊だ。
従者たちはそろって及び腰になり、牛飼い童もおびえて牛車の牛に身を寄せる。乳母は車中でうずくまって震えるばかり。白菊も何もできない。
山賊の頭目らしき直垂の男は、自分たちが優位であることを確信して、あはははと大声で笑った。
「おとなくしていれば手荒なことはしないとも。とりあえずは、そうだな、牛車に乗っておいでのかたの、きれいな装束を脱いで渡してもらおうか。風はまだまだ冷たいが、凍え死ぬほどでもなし。これくらいで済むなら安いものであろうよ」
この要求に、なんですってとつぶやきながら、乳母はわなわなと震え出した。しかし、白菊はため息ひとつつき、水干の襟についた組紐をほどき始める。
「し、白菊さま。そんな、そのようなことまでは」
「これでみなの命が助かるなら。乳母も、袿を一枚、渡してくれる?」
「えっ……」
「命あってのことだろう?」
「それは……、そうなのですが……」
乳母は哀しげな顔をしつつも、いちばん上に重ねた袿をしぶしぶ脱ぎ始めた。が、ふたりが脱ぎ終えるより先に、
「おやおや。これは」
妙にのんびりとしたつぶやきと穏やかに闊歩する馬の蹄の音が、道の向こうから聞こえてきた。
「変だね。わたしたちより先に出迎えが来ているよ」
そう言っているのは、白い帽子を頭に巻き、馬にまたがった僧侶であった。顔のほとんどを隠す帽子のおかげで、年齢は不詳だ。
馬の手綱を握って、徒歩で彼に付き従っているのは、十七、八とおぼしき大童子だ。もう元服してもおかしくない年齢なのに、童子のように髪をのばしたままにしているので、そう呼ばれる。その大童子の髪はやや短めで、後ろで結んだ分は小さく、子犬のしっぽのようでもあった。ただし、落ち着きはらった表情にかわいげなど微塵もない。
山賊たちはそろって不審そうに顔を歪め、僧侶と大童子を睨みつけた。
「なんだ、おまえたちは」
「ほう、わたしを知らぬのか」
にいっと僧侶が笑った。
「勿径寺の定心和尚、四十八歳」
名乗るだけでなく年齢までわざわざ表明するその間も、馬は闊歩し続け、距離を順調に詰めている。大童子の歩調と表情には、特に変化はない。ふたりとも、山賊たちをまったくおそれていないのだ。
牛車の中でうずくまっていた乳母が、ハッと顔を上げた。
「も、勿径寺の……」
白菊たちが向かっていた寺の名だ。
「お、お迎えですよ。白菊さまをお迎えに、勿径寺の和尚さまがわざわざ来てくださったのですよ。ああ、地獄で仏とはまさにこのことですわ」
乳母は両手を合わせ、無心に定心を拝み始めた。
白菊は何も言えず、何もできない。山賊に囲まれているところに来てくれたのはありがたかったが、あちらはふたりきり。それに引き替え、山賊たちは二十人以上はいる。多勢に無勢という言葉が、どうしても白菊の頭をよぎる。
そんな状況にあっても、勿径寺の定心和尚は飄々としていた。
「おまえたち、このあたりの輩ではないな」
定心がそう言った途端、山賊たちの顔がひきつった。
「うるさい坊主だ。叩き殺すぞ」
頭目が嚙みつくように吼えると、それに呼応して、長槍をかついだ男が前に進み出た。男は槍を頭上に掲げ、これ見よがしに振り廻し始める。回転する槍は風を切って、ぶんぶんと凶悪なうなりを発している。
大童子が馬を停めた。手綱を放し、代わりに腰に佩いた刀を抜く。鞘から放たれたそれは木剣だった。
山賊たちはそれを見て、げらげらと笑い出す。
「木剣だとよ。それ一本でどうするつもりだい」
牛車のまわりに自然と集まった従者たちは、一様に失意の表情を浮かべた。もう駄目だ、自分たちは助からないと、すっかり意気消沈している。
が、賊に笑われようと、従者たちに残念がられようと、大童子はひるまなかった。馬上の定心も、まだ微笑を浮かべている。
「我竜」
それが大童子の呼び名なのだろう。余裕さえ感じさせつつ、定心は言った。
「殺生はいけないよ。だからね、殺さないように──やっておしまいなさい」
その刹那、大童子の我竜が動いた。槍を振りまわしていた男の腹を木剣で突き、返す刀ですぐ隣にいた男の胸を打つ。ふたりはぎゃっと悲鳴をあげて吹き飛んだ。
何をしやがる、とわめきつつ、山賊たちが我竜に殺到する。我竜は黙々と木剣を振るい、賊たちを次々に薙ぎ倒していく。
白菊と乳母、従者たちはあっけにとられて、我竜の大立ちまわりを見守っていた。誰も彼も加勢はおろか、鬼神のごとき我竜の無双ぶりを目で追うのが精いっぱいだったのだ。
だからこそ、白菊も背後への警戒がおろそかになっていた。
突然、後面の御簾が落とされ、浅黒い腕が二本、にょきりと突き出てきた。山賊たちのひとりだ。男は白菊を捕まえ、彼を牛車の中から引きずりおろそうとする。
白菊さま、と乳母が悲鳴混じりの声をあげた。白菊もあらがったが相手の力は強く、十二歳の童ではとても振りほどけない。
「この餓鬼はいただいていくぞ!」
男が笑いながら宣言したそのとき、どすっと鈍い音がして、一瞬、牛車の屋根がたわんだ。馬上から跳躍した定心和尚が、牛車の屋根の上に飛び乗ったのだ。
定心はそこからさらに跳躍し、白菊を捕まえた山賊の顔面を蹴り飛ばした。
蹴りをまともに食らった山賊が吹き飛び、解放された白菊は定心がその手に抱き止める。
定心がきれいに着地したといっしょに、彼が頭に巻いていた帽子が肩に落ちた。僧侶ならば髪はきれいに剃りあげているはずが……、一寸(約三センチ)にも満たない程度ながら、彼には灰鼠色の毛髪が生えていた。
驚く白菊の視線で気づいたのだろう、「おっと」とつぶやき、定心は笑った。目尻と口もとに皺がぎゅっと寄って、なんとも愛嬌のある顔になる。
「驚いたかい? わたしは髪がね、すぐのびてしまうのだよ。これでも、今朝方、ちゃんと剃りあげていたのにねえ」
白菊を地面に下ろすと、定心は灰鼠色の前髪をさっと後ろにかきやった。
「うん。派手に動いて血のめぐりが良くなった分、髪の毛ののびも早いようだな」
白菊はぽかんと口をあけて、定心を見上げた。
勿径寺を預かる定心和尚は五十になるかならずと養父から聞いていたし、当人も四十八歳だと公言していた。が、もう十歳は若いのではないかと疑いたくなる。それに、たった半日で髪が一寸近くのびるなど、とても常人とは思えない。はったりではなく事実であるなら、定心和尚は僧侶ではなく神仙なのかもしれない。
それを言うなら、定心が連れてきた大童子のほうもすごかった。木剣一本だけで、槍や太刀をひっさげた山賊たちを次々に叩き伏せていくのだ。山賊側の攻撃はひとつとして彼に当たらず、逆に木剣で打ちのめされてしまう。そのさまを見て勇気づけられ、従者たちも武具を手に取り、山賊たちに反撃していく。
これでは勝ち目がないと判断したのだろう、
「まずいぞ、退け」
頭目がそう叫ぶや、山賊たちはその言葉を待っていたかのように、われ先に逃げ始めた。大童子の我竜も深追いはしない。従者たちは歓声をあげ、乳母も恐怖ではなく安堵から泣いている。
事態の急変に追いつけず呆然としている白菊の肩に、定心が手を置いた。
「もう大丈夫だよ、白菊丸」
深みのある声でそう言ってくれた定心を見上げて、白菊は細く長く息をついた。都を離れてからの緊張がやっとほどけていくのを感じていた。
【つづく】