「ゆきうさぎのお品書き 親子のための鯛茶漬け」(集英社オレンジ文庫7月刊)
「ゆきうさぎのお品書き 1」(YJCふんわりジャンプ)
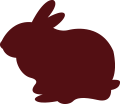

小料理屋「ゆきうさぎ」の先代女将だった祖母亡き後、無我夢中で店を切り盛りしてきた店主の大樹。祖母の初盆を前に、アルバイトの碧と交わす会話とは――?
最新刊『ゆきうさぎのお品書き 親子のための鯛茶漬け』に登場した
小料理屋「ゆきうさぎ」特製レシピがクッキング動画になりました。
ぜひ作ってみてくださいね。
七月二十日、十七時。
仕込みの途中で、ふいに外の空気が吸いたくなった。エプロンをはずして厨房から出た大樹(だいき)は、出入口の戸を開ける。
夏至は過ぎたが、まだ日は長い。昼間ほどではないものの、熱気がまとわりつき、どこからかヒグラシの鳴き声が聞こえてくる。
「……ん?」
軒下に、黒と白の毛並みが特徴的な一匹の猫が座っていた。今年のはじめから店の近辺をうろつくようになった大きな猫だ。
「なあ。その毛皮、暑くないか?」
声をかけても、猫はちらりと目を向けただけで、すぐに視線を戻してしまう。なんとなく「武蔵(むさし)」と名づけたその猫は、愛想はないが、そのつれなさが魅力でもあった。
(ばーちゃんもこういう猫、好きそうだな)
店の外壁に背中をあずけた大樹は、昨年の秋、八十歳でこの世を去った祖母のことを思い出した。
風邪をこじらせ肺炎で亡くなったが、それまではほぼ毎日、大樹と一緒に店に出て働いていた。いつもと同じように手間暇をかけて料理をつくり、店にやって来るお客と楽しそうに会話をしていたのだ。
『こんばんはー。また来ちゃったよ』
『女将さん、いつものください』
『ここに来て女将さんと話してると、嫌なこともけろっと忘れちゃうね』
『もうひとつの家みたいだよな』
「ゆきうさぎ」は多くの常連が心の拠りどころにしてくれている場所だけれど、それは祖母にも言えた。この店で働くことは、祖母にとっての生きがいでもあったから。
そんな先代女将のあとを継ぎ、店主となって約半年。なんとか経営を軌道に乗せようとしている自分の姿を、祖母はどこかで見守ってくれているのだろうか?
大きく息を吐き出したとき、こちらに近づいてくる車輪の音が聞こえてきた。
視界に入ったのは一台の自転車。乗っているのは見知った顔だ。ブレーキをかけて自転車を停めた人物は、またがっていたサドルから降りると明るく笑った。
「雪村(ゆきむら)さん、おはようございます!」
二カ月前に雇ったアルバイトの碧(あおい)は、「今日も暑いですね」と言いながら自転車を押して大樹の横を通り抜けた。所定の場所に停めてから戻ってくると、武蔵の姿を見てその前にしゃがみこむ。
「ね、武蔵。今日こそさわってもいい?」
そっと手を伸ばすが、すかさず威嚇されてしまい、碧はしょんぼりと肩を落とす。この猫が人になつくところがまったく想像できなかったので、今後もあまり変わらないような気がして苦笑する。
「あー……行っちゃった」
なおも気を引こうとする碧を無視して、武蔵は悠然と尻尾を揺らしながら通りの奥へと消えていった。立ち上がった碧は肩をすくめると、大樹のほうへ向き直る。
「またフラれちゃいました」
「まあ、気長にやれよ」
店内に入って仕込みの続きをはじめたとき、床をモップで磨いていた碧に「そういえば」と話しかけられる。
「昨日の夕ご飯、雪村さんから教わったばかりの生姜焼き、つくってみたんですよ」
「へえ。どうだった?」
「おいしかったです!」
碧はぱっと表情を輝かせた。
「父も褒めてくれたんですけど、ちょっとお肉がかたくなっちゃったんですよね。じっくり調味料につけこんだから、やわらかくなるはずって思ってたのに」
「あんまりつけ過ぎるのも逆効果だぞ。タレの塩気に水分が吸いとられるから、うちの店では十分くらいにしてる。それから火加減にも気をつけないと」
「う……」
碧の顔にははっきり「しまった」と書いてある。エプロンのポケットからメモ帳をとり出した彼女は、大樹から聞き出した注意点をしっかり書き留めた。
その姿はまるで、数年前の自分を見ているかのようだ。当時の大樹も、祖母から教えてもらった料理のレシピをメモにとり、何度も復習していた。なつかしくて微笑ましい気持ちになり、口の端が上がる。
「雪村さんに分けてもらったポテトサラダもすごくおいしかったですよ。あれ、どうやってつくるんですか?」
「前にも言っただろ。企業秘密」
「えー」
「俺だって、教わったのは先代が亡くなる直前くらいだったんだぞ。そう簡単には教えられないな」
でも、と大樹は続ける。
「いつかタマがうちの料理を完璧につくれるようになったら、考えようか」
かつての祖母に言われたことを、まさか自分が口にする日が来るとは。
「うーん。何年かかるかなぁ」
碧は途方に暮れた顔をしていたが、やがて奮起したようにこぶしを握る。
「でも、何事もコツコツ努力することが大事ですよね。料理の腕は頑張って上げていきます。とりあえずは生姜焼きから!」
「その前に掃除を終わらせてくれよ」
「あ、そうだ」
我に返ったように床を磨く姿を見つめていた大樹は、カウンターに目を移した。隅に飾ってあった写真立てに手を伸ばす。
来月は初盆。束の間こちらに戻って来るかもしれない祖母は、大樹が切り盛りするこの店を見て何を思うだろう。
―――ばーちゃん。これがいまの「ゆきうさぎ」だよ。
写真の中で微笑む祖母に、大樹は心の中で語りかけた。



