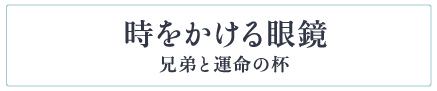

ある日「義理の母」の部屋へ呼び出されたキャスリーン姫。
待ち構えていたヴィクトリアが彼女に見せたものは、
きらびやかなドレスの数々で――?
待ち構えていたヴィクトリアが彼女に見せたものは、
きらびやかなドレスの数々で――?
『姫君の肖像』
「ヴィクトリア? ご用があるって?」
ノックの後、執務室の扉を開け、ぴょこんと首を覗かせたキャスリーンを、窓際の椅子に掛けて分厚い書物を読んでいたヴィクトリアは笑顔で差し招いた。
「うむ。今日はたっぷり時間が取れるゆえ、ようやく取りかかれると思うてな」
「ようやく取りかかれる? 何に?」
部屋の中に入ってきたキャスリーンは、不思議そうに首を傾げた。
ヴィクトリアは立ち上がると、本を椅子の上に置いて、自由になった手をパンと打ち鳴らした。
すぐに間続きの隣室から、侍女のマージョリーが駆けつける。
「マージョリー、支度はできたか?」
ヴィクトリアに忠実な侍女は、慎ましやかな笑顔で頷き、不思議そうに突っ立っているキャスリーンに、膝を軽く折って優雅に一礼した。
「姫様、ご用意ができました。奥方様のお支度の間のほうへ、お越し下さりませ」
キャスリーンは、小犬を思わせるつぶらな目をパチパチさせた。
「いったい何をするつもり?」
「まあ、見てみるがよい」
戸惑う少女の手を引いて、ヴィクトリアは含み笑いで隣室へ連れていく。
ヴィクトリアの執務室の隣には、彼女が来客と面会するために身支度を整えたり、執務の合間に休息したりするための部屋がある。
財政難のポートギース王国ゆえ、決して華美な部屋ではないが、ジョアン王心づくしの柔らかなベッドや座り心地のいい長椅子などが置かれ、十二分に快適な空間だ。
その仮眠用のベッドの上に、きらびやかなドレスが何着も広げてあるのを見つけて、キャスリーンは驚きの声を上げた。
「これって何? どういうこと?」
ヴィクトリアはベッドの横に立ち、ドレスを見回して、満足げに頷いた。
「良い選択だ、マージョリー。どれも、キャスリーンにはよう似合うであろう」
「……はい? 私に?」
キャスリーンは、ポカンとしたまま、歳の近い「義理の母」の美しい顔を見る。
「どうして私? これ全部、ヴィクトリアがお輿入れのときに、マーキスから持ってきた大事なドレスばかりでしょ?」
「さよう。その中から、そなたに似合いそうなものをマージョリーに選び出してもろうた。気に入ったものはあるか?」
ヴィクトリアの目的をはかりかねて、キャスリーンは怪訝そうにドレスを眺めた。
どれも、ヴィクトリアの持ち物としては比較的にシンプルな仕立ての、それでも十分に美しいものばかりだ。
中には、マーキスの海で採れた大粒の真珠を胸元に縫い付けた豪華なドレスまである。
手近にあるドレスに怖々触れ、その滑らかな布地の感触に驚嘆しつつ、キャスリーンはますますわからないといった様子でヴィクトリアの笑顔をまじまじと見た。
「何がなんだかわかんないわ」
するとヴィクトリアは、目についた一着を手に取り、キャスリーンの身体に当ててみながらあっさり答えた。
「腕のよい画家を招き、そなたの絵姿を描かせようと思うてな」
「絵姿!? 肖像画ってこと?」
「それもよいが、まずは書状に添えることができる小さなものを、幾枚か描かせようぞ」
「どうして急にそんなことを?」
そこまで言って、あることに思い当たり、キャスリーンは顔色を変えた。
「まさか、私をどこか適当なところにお嫁にやるつもり!? 絶対嫌よ!」
今にも地団駄を踏みそうなお転婆な王女を、ヴィクトリアはおっとりと窘める。
「さようななつもりはない。そなたがおらねば、私も我が君もつまらぬではないか」
「じゃあ、絵姿なんて描かせてどうするの?」
するとヴィクトリアは、悪戯な猫のような笑みを浮かべ、こう言った。
「実はな、そなたの絵姿を熱望する殿方が、お二人ほどおられるのだ」
「二人? 誰?」
「お一方は、アングレ王国のローレンス皇太子。文だけでは足りぬ、キャスリーン姫を想うよすがに絵姿を疾く送れと、我が君に矢の催促でな」
数ヶ月前、キャスリーンに「まずはお友達になりましょう」と言われ、後ろ髪を引かれる思いで帰国した男の顔を思い出したのか、ヴィクトリアはクスッと笑った。
キャスリーンも、大袈裟に顔をしかめてみせた。
「あの人、本当にあのアングレ王国の次の王様なのかしら。頼りないんだか頼れるんだか、さっぱりわからなかった。でも、私の絵姿をほしいなんて言ってくれてるんだ」
「うむ。ずいぶんとそなたにご執心だ。悪い話ではあるまい」
「まあ、ね。それで、もうひとりは?」
キャスリーンの問いかけに、ヴィクトリアはいっそう華やかに微笑み、答えた。
「ロデリック兄上だ。そう頻繁には会えぬゆえ、顔を忘れぬよう、現物を目の当たりにしたとき幻滅せぬ程度によう描けた絵姿を送れと仰せだ」
「……素直じゃなーい!」
血の繋がらない「伯父上」の暴言に、キャスリーンはリスのように頬を膨らませる。
「まことにな。可愛い姪に会えず寂しいと仰せになればよいものを」
「ホントだわ。でも……そういうことなら、ヴィクトリア」
「うむ?」
キャスリーンは、申し訳なさそうにもじもじしながらこう言った。
「せっかくこんなにたくさんドレスを出してくれたのに悪いけど、私、いつもの私で描いてほしい。いつも着てる服で、このポートギースの風景と一緒に描いてほしいの。それがきっと、いちばん私らしい。着飾った私は、私じゃないもの」
それを聞いて、ヴィクトリアは気を悪くした様子もなく頷いた。
「心得た。そなたならそう言うやもしれぬと思うておった。されど、一枚くらいは、着飾ったものも描かせておくがよい。何かの役に立つやもしれぬからな」
キャスリーンは、少し考えて頷く。
「それもそうね。わかった。じゃあ……どれにしようかな。ああ、ここにアスマがいたら、選んでもらうのに!」
残念そうにそう言いつつ、意外と楽しげにドレスを選び始めたキャスリーンを、ヴィクトリアは温かく見守っていた……。
ノックの後、執務室の扉を開け、ぴょこんと首を覗かせたキャスリーンを、窓際の椅子に掛けて分厚い書物を読んでいたヴィクトリアは笑顔で差し招いた。
「うむ。今日はたっぷり時間が取れるゆえ、ようやく取りかかれると思うてな」
「ようやく取りかかれる? 何に?」
部屋の中に入ってきたキャスリーンは、不思議そうに首を傾げた。
ヴィクトリアは立ち上がると、本を椅子の上に置いて、自由になった手をパンと打ち鳴らした。
すぐに間続きの隣室から、侍女のマージョリーが駆けつける。
「マージョリー、支度はできたか?」
ヴィクトリアに忠実な侍女は、慎ましやかな笑顔で頷き、不思議そうに突っ立っているキャスリーンに、膝を軽く折って優雅に一礼した。
「姫様、ご用意ができました。奥方様のお支度の間のほうへ、お越し下さりませ」
キャスリーンは、小犬を思わせるつぶらな目をパチパチさせた。
「いったい何をするつもり?」
「まあ、見てみるがよい」
戸惑う少女の手を引いて、ヴィクトリアは含み笑いで隣室へ連れていく。
ヴィクトリアの執務室の隣には、彼女が来客と面会するために身支度を整えたり、執務の合間に休息したりするための部屋がある。
財政難のポートギース王国ゆえ、決して華美な部屋ではないが、ジョアン王心づくしの柔らかなベッドや座り心地のいい長椅子などが置かれ、十二分に快適な空間だ。
その仮眠用のベッドの上に、きらびやかなドレスが何着も広げてあるのを見つけて、キャスリーンは驚きの声を上げた。
「これって何? どういうこと?」
ヴィクトリアはベッドの横に立ち、ドレスを見回して、満足げに頷いた。
「良い選択だ、マージョリー。どれも、キャスリーンにはよう似合うであろう」
「……はい? 私に?」
キャスリーンは、ポカンとしたまま、歳の近い「義理の母」の美しい顔を見る。
「どうして私? これ全部、ヴィクトリアがお輿入れのときに、マーキスから持ってきた大事なドレスばかりでしょ?」
「さよう。その中から、そなたに似合いそうなものをマージョリーに選び出してもろうた。気に入ったものはあるか?」
ヴィクトリアの目的をはかりかねて、キャスリーンは怪訝そうにドレスを眺めた。
どれも、ヴィクトリアの持ち物としては比較的にシンプルな仕立ての、それでも十分に美しいものばかりだ。
中には、マーキスの海で採れた大粒の真珠を胸元に縫い付けた豪華なドレスまである。
手近にあるドレスに怖々触れ、その滑らかな布地の感触に驚嘆しつつ、キャスリーンはますますわからないといった様子でヴィクトリアの笑顔をまじまじと見た。
「何がなんだかわかんないわ」
するとヴィクトリアは、目についた一着を手に取り、キャスリーンの身体に当ててみながらあっさり答えた。
「腕のよい画家を招き、そなたの絵姿を描かせようと思うてな」
「絵姿!? 肖像画ってこと?」
「それもよいが、まずは書状に添えることができる小さなものを、幾枚か描かせようぞ」
「どうして急にそんなことを?」
そこまで言って、あることに思い当たり、キャスリーンは顔色を変えた。
「まさか、私をどこか適当なところにお嫁にやるつもり!? 絶対嫌よ!」
今にも地団駄を踏みそうなお転婆な王女を、ヴィクトリアはおっとりと窘める。
「さようななつもりはない。そなたがおらねば、私も我が君もつまらぬではないか」
「じゃあ、絵姿なんて描かせてどうするの?」
するとヴィクトリアは、悪戯な猫のような笑みを浮かべ、こう言った。
「実はな、そなたの絵姿を熱望する殿方が、お二人ほどおられるのだ」
「二人? 誰?」
「お一方は、アングレ王国のローレンス皇太子。文だけでは足りぬ、キャスリーン姫を想うよすがに絵姿を疾く送れと、我が君に矢の催促でな」
数ヶ月前、キャスリーンに「まずはお友達になりましょう」と言われ、後ろ髪を引かれる思いで帰国した男の顔を思い出したのか、ヴィクトリアはクスッと笑った。
キャスリーンも、大袈裟に顔をしかめてみせた。
「あの人、本当にあのアングレ王国の次の王様なのかしら。頼りないんだか頼れるんだか、さっぱりわからなかった。でも、私の絵姿をほしいなんて言ってくれてるんだ」
「うむ。ずいぶんとそなたにご執心だ。悪い話ではあるまい」
「まあ、ね。それで、もうひとりは?」
キャスリーンの問いかけに、ヴィクトリアはいっそう華やかに微笑み、答えた。
「ロデリック兄上だ。そう頻繁には会えぬゆえ、顔を忘れぬよう、現物を目の当たりにしたとき幻滅せぬ程度によう描けた絵姿を送れと仰せだ」
「……素直じゃなーい!」
血の繋がらない「伯父上」の暴言に、キャスリーンはリスのように頬を膨らませる。
「まことにな。可愛い姪に会えず寂しいと仰せになればよいものを」
「ホントだわ。でも……そういうことなら、ヴィクトリア」
「うむ?」
キャスリーンは、申し訳なさそうにもじもじしながらこう言った。
「せっかくこんなにたくさんドレスを出してくれたのに悪いけど、私、いつもの私で描いてほしい。いつも着てる服で、このポートギースの風景と一緒に描いてほしいの。それがきっと、いちばん私らしい。着飾った私は、私じゃないもの」
それを聞いて、ヴィクトリアは気を悪くした様子もなく頷いた。
「心得た。そなたならそう言うやもしれぬと思うておった。されど、一枚くらいは、着飾ったものも描かせておくがよい。何かの役に立つやもしれぬからな」
キャスリーンは、少し考えて頷く。
「それもそうね。わかった。じゃあ……どれにしようかな。ああ、ここにアスマがいたら、選んでもらうのに!」
残念そうにそう言いつつ、意外と楽しげにドレスを選び始めたキャスリーンを、ヴィクトリアは温かく見守っていた……。


