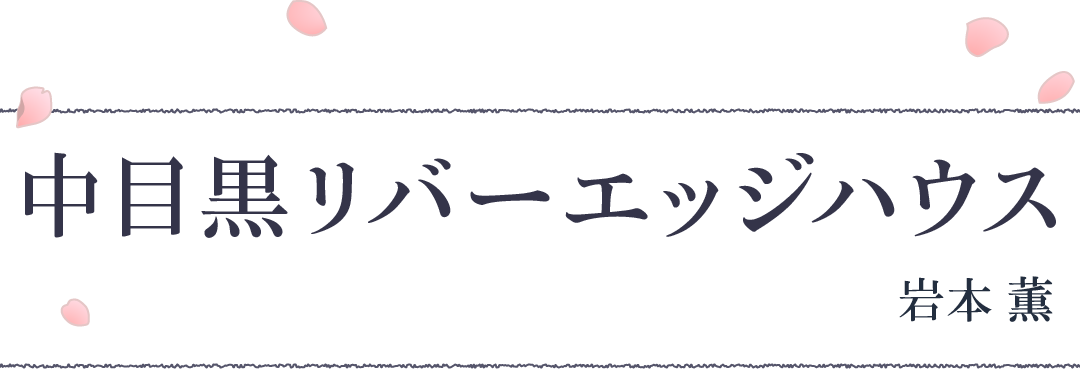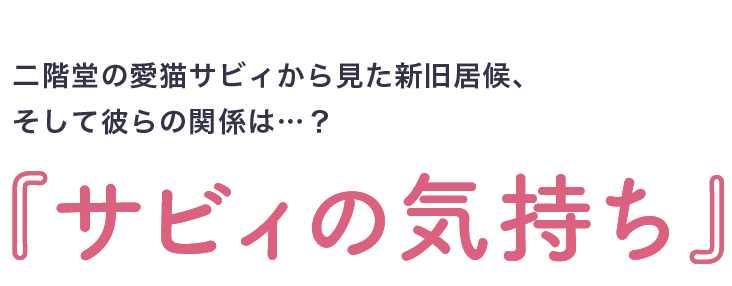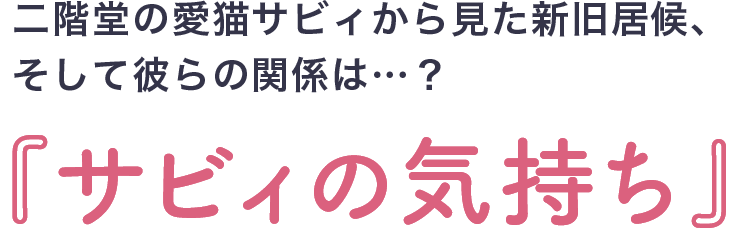「サビィ……サビィ、どこだい?」
これは主人の声。男性だけど、ソフトで穏やか。特に自分を呼ぶときは甘さが滲む。自分に対する愛情が感じられて、とても自尊心が充たされる。なので、主人が自分を探しているときは、素直に姿を見せることにしている。
お気に入りの書棚の上で昼寝をしていたサビィは、んーっと伸びをしてから、トンッと床に飛び降りた。自分を探している背の高い紳士にトトトトッと軽やかに歩み寄り、ぴかぴかに磨かれた革靴に頭を擦りつける。
「ナー……」
「あれ、いつの間に来たの?」
主人の整った貌──いろんな人間を見てきたけど、なかでもかなりきれいなほうだと思う──が、自分を見下ろした瞬間、くしゃりと相好を崩した。知っている。こういう表情を人間は〝デレデレ〟というのだ。
主人は人間界では〝社長〟という仕事で、それなりに偉いようなのだが、それとは別の肩書きも持っている。〝猫のお世話係〟という仕事で、よく「こっちのほうが本職だよ」と言っている。どうやら自分たち猫をケアするのが生きがいのようだ。
サビィ自身、まだ目も見えない子猫の時分に捨てられて、動物保護団体に保護されていたところを、主人に引き取ってもらった。
黒地に赤茶色、鼈甲色が混ざったさび猫の自分は、わかりやすいかわいらしさに乏しく、なかなか里親が見つからなかった。子猫仲間が次々ともらわれていき、ケージが空になっていくなか、ひとり取り残される心細さといったら……。
誰も自分を欲しがってくれない。家族に選んでくれない。
寂しくて、悲しくて、ケージの床に蹲るように丸まっていた。
そんなときだった。ふらりと現れた主人が、ケージのガラス越しに、蹲っている自分を覗き込んだのだ。不思議な色の、どこか哀しげな瞳と目が合った刹那、背中をびびっと電流のようなものが走った。このひとだ。このひとを待っていた!
尻尾をピンと立てて、必死に「ミー、ミー」と鳴いた。
お願い。わたしの家族になって!
懸命の訴えに耳を傾けていた主人が、やがて後ろを振り返り、スタッフに尋ねた。
「このコを抱いてみていい?」
「どうぞ。賢くていいコなんですけどねー。どうしてか引き取り手が現れないんです」
「そうなんだ。それは寂しいね」
「ミー……」
自分をそっと抱き上げた主人が、耳の後ろをつつきながら言った。
「だったら、うちのコになろうか」
そう申し出てくれたやさしい声は、いまでも忘れられない。
あとから知ったのだが、あのとき主人はとてもかわいがっていた猫を亡くしたばかりだったのだそうだ。その別れがあまりに辛くて、しばらく次の猫は飼わないつもりでいた。ところが。
「あの日は知人が運営している保護団体にたまたま顔を出したんだけど……きみと目が合った瞬間に、このコは僕の家族になる運命なんだって思ったんだ。そのために残っていたんだって。ね、サビィ?」
出会いのエピソードは主人のお気に入りで、何度か聞かされた。そのたび、「ナーン(わたしもそう思う)」と返事をするけれど、伝わっているかどうかは定かじゃない。猫は人間の言葉がわかるのに、人間は猫の言葉を理解しないのは、一方通行で不便だ。まあ、言葉を介さなくとも、気持ちは通じるけれど。
「ナーン」
ひさしぶりに出会いの記憶が蘇って甘えたくなった。
「ナーオ」
とっておきの甘え声を出したら、体を折った主人が後頭部から背中にかけて撫でてくれる。ソコが一番気持ちいいとわかってくれているのだ。無意識に耳がぴるるぴるると震え、ゴロゴロと喉が鳴った。マッサージをしながら、主人が甘やかすような声を出す。
「サビィは本当にいいコだね。今日はとっておきのおやつをあげようか」
おやつ!
その単語を耳にすると、普段はわりとフラットなテンションが跳ね上がり、ぴーんと耳が立った。
ごはんのカリカリも好きだが、おやつは特別だ。たまにしかもらえないレア感も相まって、ものすごく美味しいのだ!
キッチンに移動した主人が棚を開けておやつを取り出す。スティック状の袋をぴっと破き、シルバーのトレイの中にどろっとしたペーストを入れた。待ってましたとばかりに顔をトレイに突っ込む。今日はまぐろ味だ。
うんまい!
「美味しいかい?」
主人の質問に答える余裕もなく、夢中でペロペロしていたら、主室のほうからダンダンダンッと大きな音が聞こえてきた。この音は〝居候〟が階段を上ってくる音だ。足音がどんどん大きくなってきたかと思うと、ガチャッとドアが開く音が聞こえた。
「帰ったぞ!」
自分の帰還を知らしめるように、大声で叫ぶ。
主人が「……帰ってきた」とつぶやき、キッチンから離れた。
「勝った、勝った! 大勝ちだ!」
自慢げな声とガサガサとうるさい物音。勝ったというのはパチンコで、居候の〝仕事〟だ。
とにかく居候は声が大きくて、ガサツで、なにをするにも大きな音を立てる。優雅で物静かな主人とは正反対だ。居候がこの部屋に居候するようになって、それまでの静かな暮らしが一変した。物音だけじゃない。居候が脱ぎ散らかした衣類が床のあちこちに落ちていたり、食べ散らかした袋菓子のカスが散らばっていたり、ときには居候そのものがガーガーいびきをかいて床に転がっていたりする。とても邪魔だ。
主人も「脱ぎ散らかすな」「床で寝るな」と都度小言を口にするが、どこ吹く風と受け流す。居候のくせに図々しい。先住としては、後輩をきちんと躾けたいところだが、言葉が通じないのが難だ。
おやつを食べ終わり、口の周りをペロペロ舐め、ついでに毛繕いをしていたら、居候がズカズカとキッチンに入って来た。
主人も長身だが、居候はもっと大きくて、色も浅黒く、髪はぼさぼさ、髭まで生えていて、初めて見たときは恐ろしさのあまりに体がすくみ上がった。
──猫か。
それが、初めて自分を見た際の、居候の第一声。その声は主人と違って太くて低かった。甘さの欠片もないし、「猫か」って見たまんま。
反射的に毛を逆立て、シャーッと威嚇した自分を見下ろし、居候は不満げに「ふん」と鼻を鳴らした。
「こいつはなにを怒ってるんだ」
「おまえが大きくてびっくりしたんだろう。猫はデリケートなんだよ」
「デリケート? 臆病の間違いだろ? だから猫はいやなんだ。俺は断然犬派だ」
その上、全猫を敵に回すような暴言を放った。腹が立ったから、ぴゅっと逃げて、居候が帰るまで隠れていた(当時はまだ居候じゃなかった)。
……なんて、また昔を思い出してしまった。
「おいネコ、おまえのネコ缶も取ってきてやったぞ」
居候は自分を「おいネコ」と呼ぶ。名前で呼ぶのが小っ恥ずかしいのだそうだ。照れる年かと思うけれど。
「……ナー」
初めはその大きさが怖かったけれど、もう慣れた。
「ほら、来い」
デカい手が伸びてきて、ひょいっと抱き上げる。分厚い肩に前肢をかけ、居候の腕のなかにすっぽり収まった。抱っこに関してだけは、主人より居候に軍配が上がる。なんといっても安定感が抜群なのだ。
居候が主室に向かって歩き出す。ゆらゆらと揺り籠みたいで気持ちいい。居候の体温が高いせいか、徐々に眠くなる。
目を閉じてゴロゴロ喉を鳴らしていたら、ふたたび誰かが階段を上がってくる音が聞こえてきた。さっきよりは軽い足音。これは、アレだ。
ガチャッとドアが開くのと同時に、「宗方さん……いた!」と若い男の声が叫んだ。ここのところ、顔を出すようになった新参者だ。そんなに大きくないので怖くはない。それに猫好きらしく、その点は好印象。
だが、居候は新参者が苦手らしい。
「……なんだよ」
居候がげんなりした声を出す。
「今日は一緒に現場を見に行く約束してたじゃないですか!」
「あー、うるせー。なんでおまえはいっつも大声なんだよ」
「だって宗方さんが、約束破って消えちゃうから!」
「普段行かねー店がたまたま前通りかかったら新装開店だったんだよ」
「そんなの理由になりませんよ!」
若い男が詰め寄ってきたので、居候の腕からするっと抜け出し、トンッと床に下りた。
この二人が言い争いを始めると、長いし、うるさい。
「まあまあまあ、石岡くんもそうカリカリしないでさ。お茶でもどう? そろそろお茶の時間だよ」
仲裁役の主人が割って入り、なんとか場を収めようとしたが、
「こんなうるせーやつと茶なんか飲めるか!」
「こっちこそ願い下げです!」
と二人は一時休戦するつもりはないようだ。
毎回毎回、主人も大変だ。
そう思って横目で様子を窺ったら、二人の言い争いを見守るその顔は意外にも楽しそうだ。
人間とは不思議な生き物だ。
静かで穏やかだった生活に、居候が増えただけで充分猥雑なのに、さらに生きのいい新参者が参入してきて、ますます騒がしくなった。
自分は元の静かな生活が懐かしいが、どうやら主人はいまの生活がまんざらでもないらしい。
まあ、いいか。
主人が幸せなら、自分も幸せだし、居候の腹の上で貪る惰眠はなかなかのものだし。
サビィは騒がしい人間たちから離れ、お気に入りの書棚の上に上り、昼寝の続きを始めた。