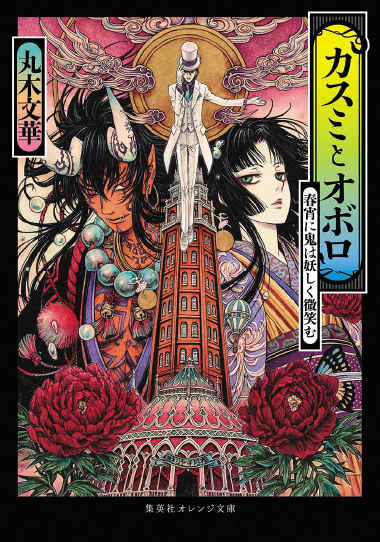梅雨も明けうだるような暑さが続く日々。
香澄は夕餉の後に湯を使い、さっぱりとした肌に青い浴衣をまとう。長い黒髪を器用にくるくると巻き上げかんざしで留め、細い首筋をあらわにするが、それでもすぐにうっすらと浮かぶ汗に閉口する。
こんな暑い夜には何もする気が起きないが、何分ちょっとした調べ物があるのですぐに寝ることもできない。手ぬぐいで汗を拭きつつ、香澄は重い足取りで父の書斎へと向かった。
目当てのものを探して視線をさまよわせていると、出窓にぽつんと忘れ去られたように置かれた一冊の冊子に気づく。何気なく近寄って手に取ってみるが、表紙には何も書かれていない。
パラパラと捲ってみれば、恐ろしく達筆な文字で何やらつらつらと書き連ねてある。日付が逐一記してあるので一見すると日記のようだが、その内容が奇妙だ。
『六月二十日 晴天 上野
久方ぶりの青空であったので実が動物園とやらに連れて行ってくれた。珍しき獣らがひしめき合いまことに面白き場所かな。獣らに鬼はなし。群がる子らにもろくなものなし。親に憑くものどもをひとつふたつつまみて喰らうがまだまだ青き味にて旨味が足りぬ。
夕餉は精養軒なる異国料理の店にて牛肉を煮込んだものを食す。美味い。どうやら富裕な者らの多き場所にて素晴らしく育った鬼どもがあふれる。興奮しきりで香澄に叱られ懸命に我慢しながら目立たぬよう注意を払いつつ喰らう。強欲な鬼どもの何とみずみずしき陰気よ。日々多量に取り憑いた人間の陰気をたらふく啜らねばこうも鮮やかな風合いは出せぬもの。喉越しも筆舌に尽くし難きなめらかさにて満足の極み。
六月二十三日 雨天 銀座
婆が鳩居堂に用ありとて我を伴う。銀座もなかなかに育った鬼ども多くあり馥郁たる香気に我覚えず打ち震える。……』
香澄は鼻白んだ顔で冊子を閉じる。どう見ても朧の日記だ。鬼の味、感想などが延々と述べられておりつまらぬことこの上ない。
そこへ折悪しく本人が入ってきて、香澄の手にあるものを見てあっと声を上げ乙女のように白い頬を火照らせる。
「なんとはしたなき娘じゃ! 我の秘密の日記を盗み見るとは!」
「一体何が秘密なんです。こんな場所に堂々と置いておくのが悪いんでしょう」
香澄はぷりぷり怒っている朧に日記を突き出し、冷たい眼差しで鬼を見やる。初めは威勢のよかった朧も、主人の無言の圧力に次第に怯み、いつしか機嫌を伺うような上目遣いになっている。
「それにしても……あなた、私のいない間に色々なところへ連れて行ってもらっているようですわね」
「う……、うむ。その、おぬしは学校やら稽古事やらで忙しいのでな。空腹に耐えかねたところを誘われれば、つい、な」
「あら。お兄様やお祖母様のせいにする気かしら」
「そ、そういうわけではないが……」
朧は基本的には主である香澄と一緒でなければ外出はできぬことになっている。外見は人間の少年にしか見えぬとて鬼は鬼。朧が何かしでかしそうになったとき、それを抑えられるのは香澄しかおらぬのである。
しかし坂之上家の者らも朧が平生行儀よく過ごしているので、危険な鬼神だということも忘れかけ、本当の家族を連れ歩くように外に伴うようになってしまったようだ。
お仕置きに真言でビシビシされるのではないかと怯えている朧を眺め、香澄は情けなさにため息を落とした。知らなかったことではあるが、どうやら問題もなかったようなのでここは大目に見てやるのが妥当だろう。何より、この家の権力者である祖母や兄の仕業とあっては香澄も怒るに怒れない。
「仕方ありませんわね。そんなにお腹が空いているのなら私に言えばいいのに。後でこうして露見してしまう方がお互いよくないことですわ」
「う、うむ……。これからは気をつける」
「もしも事前に報告できなかったとしても、その日のうちに私に伝えること。よろしいわね?」
香澄の仏心が意外だったのか、朧は大きな目を丸く瞠った後、ウンウンと何度も頷いた。
「それにしても、こんな日記つける意味があるんですの?」
「どういう意味じゃ。日記とは、こうして日常のことを記すものなのではないか。平安の世ですら日記は貴族の間で確立しておったぞ」
「だってあなたのこれは、鬼の味の感想が主じゃありませんか。どこそこで食べた鬼がどうだのこうだの……。あなたにとってそれは書き残しておかなければいけないほどのものなの?」
「当たり前じゃ!」
朧は先程の大人しさはどこへやら、憤慨した様子で捲し立てる。
「鬼の味は千差万別ぞ。人の食べ物とて同じじゃろう。甘い辛い、美味い不味いがあるじゃろう。鬼とて同じじゃ。またあの陰気が味わいたいと思ったとき、その鬼を喰ろうた場所へ赴くのがいちばんの近道じゃろうて」
「それじゃ、これは鬼の味を覚えておくための記録ということ?」
「まあ、そんなようなものじゃ。鬼を喰らわなかった日には書いてもおらぬのでな」
呆れるほどに食い意地の張った鬼である。ただ鬼が蓄えた陰気を自らの養分として摂取するだけでなく、味わいにも尋常ならざるこだわりがある様子だ。
「陰気の味などわかりませんけれど……あなたが普段必要もないのに食べている人間の食べ物よりも美味しいものなのかしら」
「比べられるものではないわ。まったく種類の違うものじゃからのう」
「あのね、朧。私、以前から聞いてみたいと思っていたんですけれど……」
急に改まった口調になった香澄に、朧はうん? と首を傾げる。
「あなた、牛肉や鶏肉、豚肉もよく食べますわよね」
「うむ。我は好き嫌いはないぞ」
「それで、牛肉などでは人間の肉のように中毒にはならないんですの?」
突拍子もない問いかけに、朧はぽかんとしている。
「私も鬼の家に生まれた者の知識として、鬼にとって人間の肉が麻薬と同じような作用をもたらすことは知っています。けれど、牛や豚ではそのようにはならないの?」
「おぬし、妙なことを訊くのう……」
どう答えたらよいものか、と悩ましげに唸る鬼に、香澄はそんなに難しいことを聞いたかしらと首を傾げる。
「獣は陰気を孕まぬ。ゆえに阿片のように我らを支配はせぬのじゃ。我らは人間から生まれる陰気を喰らい形を保つ。本来必要なものは陰気だけじゃが、肉を喰らう愚か者もおる。そうすると肉の味の虜となるのじゃ。喰らわずにはいられなくなるのよ。その原理は我にもわからぬ。肉ごと喰らう陰気でなければ満足できぬようになるのじゃろう」
「あなたは、その愚か者になったことはないということ?」
その問いかけに、朧は珍しく沈黙した。
一瞬、その表情は煙のように掻き消え、人形のように冷たい造作だけが瓜実顔の白い肌の上に際立っている。
香澄と朧は束の間、初めて見える者同士のように他人行儀に見つめ合った。
「おぬし、本当に聞きたかったことはそれか」
「さあ、どうかしら。別に答えられないことではないでしょう?」
「そう思うか」朧はいつものようにいじけた顔に戻り主を卑屈に見上げる。
「我が人を喰らったと言えば、おぬしは我を何とする」
「どうもしません。今のあなたが人を食べなければそれでいいわ」
「それならば、どうでもよいではないか。我とて初めからこの力を持っていたのではない。鬼として生じたばかりの頃の記憶はほとんどないのでな」
「阿片のように中毒になるほど食べはしなかった、ということね」
「まったく喰らわなんだやもしれぬ。まあ、何にせよ、今の鬼神たる我には人の肉など不要じゃ。喰らいたいとも思わぬのでな」
「あら、そう……。他の肉は食べたがるというのに、ふしぎなものね」
一般の人々の間には鬼は人を喰らうもの、という観念がある。古典を紐解けばそのような話は山ほどあるが、実際に鬼が人を喰らった数は少なく、ほとんどが流行り病や人による殺戮、誘拐などであり、理解できぬもの、口にできぬものをすべてあやかしの仕業と成した部分が濃厚であった。
だが、事実鬼は人の肉を欲することもある。朧のように力ある鬼神らはその行為を野蛮なものとして嫌っている様子だが、彼らにもなぜ人の肉が鬼にとって麻薬となるのかはわからぬようだ。
陰気の味にこだわり、人の食べ物ですら貪欲に欲しがる朧のような鬼が珍しいのかそうでないのか、香澄にはわからない。
「おお、香澄。我はひとつだけ嘘をついたぞ」
ふと、急に思い出したように朧がぽんと手を叩く。
「喰らいたいと思わぬ、ということじゃ。大昔に喰ってやりたかった者がおったわ」
「まあ。それは鬼神と称されるようになった後のお話?」
「ああ。我らにとって喰らうという行為はな、食欲の他に愛欲も含む。人を喰らうようになった鬼は、初めは道ならぬ恋ゆえに人を喰らったことがきっかけであった者もあると聞く」
「鬼が人を? そんなこともあるんですのね。それじゃ、あなたも人に恋をしたんですの?」
そう問いかけると、なぜか朧は得意気にふふんと鼻を鳴らす。
「長年生きていれば、そんなこともある。無論、我が妻、鈴鹿に出会う前の話じゃが」
ふうん、と気のない声で相槌を打ちながら、香澄は少し意外な心持ちで朧を眺める。こんな間抜けな鬼が、人などに恋情を覚えたことがあったというのか。いじらしい恋の話など、まったく似合いそうにない。
朧は真っ黒な瞳をキラキラさせて香澄を見つめている。
「嫉妬したか?」
「いいえ、別に」
「何じゃ、つまらんのう。もっとどんな女だったのとか根掘り葉掘り聞いてくれるかと」
「だって興味がありませんもの」
そもそも、この書斎へは調べ物をしに来たのである。いつまでも朧とお喋りをして時間を潰すわけにはいかない。
「その日記、見られたくないものなら自分の部屋に持って行きなさいな。ここに置いてあったら誰でも簡単に読んでしまいますわよ」
ぶつぶつと何やら不満げに呟いている朧を放って探しものを再開する。
それにしても、鬼ですら恋をしているというのに、年頃の娘のはずの自分にそういう経験がないとはどういういことなのだろう。ふしぎで仕方がないのと同時に、若干の歯がゆさ、悔しさも覚えて香澄の眉間に自然と皺が寄る。
「相変わらず冷たいおなごじゃ。我がとっておきの話をしたというのに」
「あなたが誰を食べたいと思っても私には関係ありませんもの」
「情の薄い娘じゃのう。もそっと欲を出してもよいのではないか」
香澄には食欲も愛欲も大したものはありはしない。鬼の身でありながら色々と旺盛な朧に呆れはするが羨望も抱くほどに。
「まあ、人でなくとも、いっそ喰らってしまえば我が物にできたのに、と思う者もおったがな」
去り際の朧のひと言は聞かなかったことにして、香澄は資料探しに没頭した。