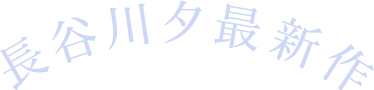
『どうか、天国に届きませんように』 発売記念
集英社オレンジ文庫から、長谷川夕の最新作『どうか、天国に届きませんように』が登場。
これを記念して、大反響を呼んだデビュー作『僕は君を殺せない』の未公開小説を初公開します!

SHORT STORY
『恋』
(『僕は君を殺せない』未公開小説)
『恋』
そのとき、彼はパンを食べていた。
ちなみにパンとはあたしがもっとも苦手とする食べ物の総称だ。むかしパン屋さんで買ったクロワッサンを食べたら奇妙な感触と味がしたので吐き出したら虫だった事件以来、あたしはパンが食べられなくなった。パンを食べているひとを見かけると、あたしはひどく不安になる。虫が混入していないかと、そしてそれをうっかり食べてしまわないかと、見ているこちらがはらはらして、目が離せない。
彼の様子をまじまじと観察してみる。どうやらあのクリームパンひとつが昼食らしい。校内の購買部で買ったのだろう。まるで餌だとでも思っているかのように、クリームパンを素早く飲み込んでいた。あの様子では虫が入っていようが入っていまいが、ろくに気づかなさそうだ。おかげでこちらがはらはらするのは一瞬で済んだ。パンを飲み下すあいだ、彼はずっと無表情だった。彼はいつだって無表情を徹底しており、愛想という言葉が辞書にない。
高校の中庭は晴れているが、風が強くざわめいて肌寒い。だからか、あたしたちしかいなかった。木の下に座っている彼とベンチに掛けてお弁当の包みをのんびりまとめているあたし。お互いに孤独でひとりぼっちずつ。一緒に食べていたわけではない。だが喋るには困らない距離だ。といって、これまで一言も会話していないのだが。
「麻野さん。予鈴鳴ったよ。戻らなくていいの」
彼がぼそりと呟いた。あたしは彼は言葉を発しない生き物だと認識していたので、いきなりのことに少し驚いた。
「あたしの名前、知ってるの?」
「……クラスメートだから」
そう。あたしたちはクラスメートだ。しかし今までのことを思うと、言い訳がましいのではなかろうか。彼はあたしの存在を意識しているはずだ。たとえば教室で、廊下で、帰り道で、道端で偶然を装ってすれ違ったりして、頻繁に存在と視線を感じる。気のせい……ではないと思う。視線には敏感なほうだ。あたしは警戒している。本能的にというのか、なんだか危険な香りを嗅ぎ取ったからだ。
「ふーん。そっち、名前なんだっけ?」
無関心を装って、あたしは訊ねた。
「……清瀬」
彼は答えた。もちろんあたしは彼の苗字を知っている。下の名前は誠という。あたしが彼の名を知っている理由は、クラスメートだからではない。
あたしがこれまでの人生で、もっとも憎んできた――仇敵だからだ。
初めて彼の名前を知ったのは、うんと小さなころだ。ママが教えてくれた。本当はちゃんと覚えているわけではないんだけど、ママくらいしか教えてくれるひとなんていないから、絶対にそうだ。そうに違いない。……でも彼の名前はいつの間にかあたしの心に刻み込まれていたから、生まれる前から知っていたのかもしれないと考えるときもある。そんなわけないのにね。
あたしのママは、自らを「正妻」だと、いつも主張していた。主張して言い聞かせていなければ、きっと自分がいちばんわからなくなってしまうから。
あたしのパパはとても気が多かった。あたしが小さなころから愛人と呼ばれるひとがたくさんいた。そもそも独身時代からたくさんの恋人がおり、ママは恋人たちのなかでもっとも美人だったから、パパと結婚できたんだって。ママの自慢のひとつだ。
ひとり娘のあたしは、パパが大嫌いだった。
基本的に仕事人間のパパが家に帰ってくるのは稀で、たまにしか会わない。だから他人同然で、会うときといえばいつだってお酒を飲んでいるにおいがして臭い。たまにやってくる臭いデブ。好きになれる要素がない。
あたしは生まれ落ちた瞬間からママにそっくりだったから、たまに会えば「綺麗」とか「将来は美人になる」と褒めそやされ、溺愛された。パパは会えば、あたしを抱き上げた。火を点けたら三日三晩燃えそうな、ぱんぱんに膨らんだ分厚い掌で抱き上げられるたび、あたしはその値踏みするみたいなパパの瞳に嫌悪感を覚えた。すごく気持ち悪くて、背筋がぞわぞわする。笑顔になんかとてもなれない。
会うたびに無愛想な子だと非難されたけれど、あたしだって好きで無愛想なわけではない。相手が相手だったのだ。人生で初めて嫌いになった人間、それがあたしにとってのパパすべてといえる。
だけどママはパパが大好きだった。とくべつだった。ときどき家に帰ってくると、いつでも大喜びで出迎えた。あたしは、パパを出迎えるときのママの様子を見るのは好きだ。楽しそうだからだ。普段では考えられないような馬鹿みたいなハイテンションで、はっきり申し上げて滑稽なのだけれど、目をきらきらと輝かせていて美しい。ひとりで静かに落ち込んでいる姿を見るより、ふたりで楽しそうな様子を見るほうがいい。
けれどママがパパを好きだと言えば言うほど、あたしはわからなくなっていく。だからあたしはママにこう訊ねたことがある。
「あんなののどこがいいの?」
我ながら父親に対する言葉ではないけれど、どうしても納得できなかったのだ。あたしの目に映るパパはせいぜい、明るくて陽気でポジティブかな……程度の魅力しかなかった。
あたしの疑問に対し、
「レイちゃん、言葉遣いを改めましょうね」
と、ママはまず冷静にたしなめた。それもそうだね。そしてママは、あたしの疑問にもちゃんとママなりの態度を提示してくれた。
「パパのどこを好きなのか、うまく説明ができないの」
ママは言った。ママは、パパに対しての感情や、男のひとの魅力について語ることが、他者の目にどう映るのかを知っていた。だから深く説明しなかったのだと思う。身振り手振りをまじえてどれほど力説したところで絶対に他人には正確に伝わらない、とよくよく承知していた。だからすべてをひっくるめて、
「レイちゃんもきっとわかるわ。いまに、大好きなひとができるから」
とママはあたしに、穏やかにそう言った。そして念を押した。
「運命ってこと」
まるで胸の痛みを堪えるみたいにぎゅっと両手を胸に抱き、そしてママはその痛みを味わうかのように、うっとりと微笑んだ。ママはじきに小学生になる娘がいる年齢であっても、恋に酔いしれる少女だった。「この恋だけはどうしようもないの」と笑ったときは、少し淋しそうにもみえた。恋はママに、希望と失望を同時に与えていた。あたしはそんなママを見て、哀しくなった。
パパがいないとき、ママはちゃんとしたひとだ。おっとりとした気質で、健気で、少々夢見がちなところはあるが、意思ははっきりとしている。それなのになぜ恋ひとつで変えられてしまうの? 運命? 他人に振り回されて感情に流されて溺れて、馬鹿みたい。でもママは自分自身の感情のどうしようもなさを、自分がもっとも理解している。どうしようもないから苦しいのだとわかっている。
あたしはよく、パパへの恋という一点に於いてひどく弱いママを、
「あたしが生まれてるってことは、パパもママがいちばんなんだね」
と励ました。すると、
「ありがとう。レイちゃんは、パパの次にいちばん大事よ」
だなんて言うから、なにもかも「仕方ないなあ」という気分になる。呆れながらも、あたしはママのそんな正直さが好きだった。だがこっそり、こう願うのだ。――見た目がいくら似ていても、あたしはママみたいにはなりませんように。
よりにもよってパパのようなはずれを引く運命が将来あたしの身にも訪れるのだったら、そんな日はアルマゲドンだ。世界なんて滅亡してしまえばいい。
あたしのパパ嫌いはどんどん加速していった。帰ってこないのはもちろん、女性を連れているのを見かけたりしてママが泣くたび、あたしはパパにも呆れたし、同時にママにも、何度も何度も悲しくなる。ママほどは、パパがママを愛していないのは、あたしの目にも明らかだった。ママとパパを同時に好きになることは、あたしにはむずかしい。
ママが本格的におかしくなったのは、いつだったっけ。はっきりとしたきっかけはわからない。緩やかに蝕まれていったというのだろうか。あたしが小学校にあがったくらいかな。あたしが幼稚園の頃はまだ、パパがいなくてもママは気丈に振舞っていたけれど、年を追うごとに、沈んでいる時間が長くなっていった。
じきにママは、パパを愛するあまり、パパを「調べる」ようになった。
叩けば埃が出てくるというよりは埃そのものであったパパからは、浮気の証拠が無限に溢れる。無尽蔵な発生源だ。ママはおかしくなっていく。それでも調べるのをやめない。調べて調べて調べ尽くす。浮気相手の女性はどんなひと? どんな生活? どんな家族構成?
ふつうのひとならば問い質したり別れたりするはずのところを、ママは調べるだけ調べて、悲しむ。そう。悲しむだけなのだ。
ママはパパのことが大好きすぎるので、とてもじゃないけれど離れるなんて選択肢はない。そしてたとえどれほど自分が傷つく結果となってもママはパパの情報をすべて知る必要があるらしい。理由は判然としない。どれほど止めても無駄だった。
そうしてママは、調査会社の優良顧客としての地位を確立していった。首を傾げざるをえないのだけれど、いつしか悲しむという不毛な行為が、ママを保たせていた。
とある子どもの存在を、あたしはそのころ知ったんだ。
あの日は雨が降っていて、朝から薄暗い日だった。いつまでも一定の調子で降りつづけている、六月の長雨だった。今日一日どんな不吉な出来事が起こったとしてもこんな天気ならば仕方ないと納得してしまうほど、陰鬱とした朝だった。
あたしはベッドから起きてきて、ママがいつも以上に塞いでいると気づいた。リビングで丸まって、嘆き悲しんでいる気配がしたのだ。そのときに偶然、ダイニングテーブルの上をみとめた。テーブルの上にはたくさんの書類がまき散らかされていた。
難しい内容の書類がばらばらになっていて、写真もたくさんある。ママがパパを調べて勝手に暗黒色に染まっているという経緯が、一目瞭然だった。傷つくとわかっているのに、どうしてやめられないんだろう。手放せば楽になれる。なのに、まるで一部を手放した途端にすべてから捨てられると恐れている。だから何もかも知りたくなり、なにも知らない状態ではいられない。
あたしはテーブルで足を止めて、一枚の写真を手にした。不意打ちのようにあたしの目を奪ったのは、うつくしい女の子の写真だった。ショートカットで服装もボーイッシュだけど、色白ですごくかわいらしい。
あたしの手にした写真には、「幸せな家族」が写っていた。
三人家族の写真だ。晴れている。どうやら遊園地に遊びに来たようで、入り口のところでキャラクターの着ぐるみと並んでいる。うちのママには及ばないにしても、女優さんみたいに綺麗で色白で小柄なお母さん。となりにはお父さん。このお父さんというのが端整な顔立ちをしており、なによりとっても優しそうだった。大人しそうで柔和な雰囲気をまとっていた。うちのパパと取り替えて欲しい。反射的にそう思った。
夫婦のあいだで子どもが笑っている。両親と手をつなぎ、すごく楽しそうにはしゃいでいる。この日、家族で遊園地に遊びに来るのを心から楽しみにしていたと見て取れる、しあわせそうで無邪気な笑顔だった。子どもは、顔の造作などはお母さんとそっくりだ。でも笑い方はお父さんとそっくりだ。
あたしには縁のない幸福。
「この子、誰?」
あたしはその場に立ち尽くしたまま、リビングのママへと訊ねた。ママは気だるげにこちらへと歩いてきた。あたしのすぐ傍に立ち、震える声で言った。
「パパの不倫相手と、子ども」
あたしは驚いて顔をあげる。
「まさかパパの子ども?」
「違うわよ」
ママは薄く笑った。あたしは写真に目を落とす。そうだよね、パパの子どものはずがない。この子はこの両親の子だ。こんなにも両親に似ているのだから。
ママはパパを調べ、この女性を調べ、女性の家族を調べたというわけだった。ママの「知りたい」にあたしも巻き込まれてしまった。ママと同様、あたしも傷ついた。自分たちと比較してしまって、どうしても傷ついた。
ママはあたしの手から写真を取った。細くて白い指先で、写真をふたつに裂いた。幸せな家族の肖像は、不仕合せな家族の手によって、びりびりに千切られる。その行為は、これ以上心ががらんと空虚にならないための自己防衛だった。
ママはしまいには他の写真や書類もどんどん破いていって、こらえきれなくなったみたいに笑いはじめた。あたしも一緒になって、一所懸命になって他の写真を破いた。最初こそ、あたしはいったい何をしているんだろう……と自分を不憫に思ったが、一心不乱に破くうちにどうでもよくなってきた。楽しくなってきた。あたしも笑った。笑ってやった。紙片を紙吹雪にしていつまでも遊んだ。
会ったこともこの目で見たこともない遠くにいる子ども。あたしはこんな子、ダイキライだ。ばかみたいな笑顔を浮かべている。正体不明な悔しさがわきあがってくる。現実が差し迫ると、溺れてしまったように息苦しい。だから叫び声をあげる代わりに、笑うのだ。
きっとこの日、この子は遊園地を楽しみにしていたんだ。写真の空は青空だった。晴れてよかったね。たくさん遊んで、そして家族で手をつないで家に帰ったはずだ。帰路も帰宅後も、また遊びに行こうとか、三人で仲良く話したでしょう。そして疲れて眠りに落ちる。その晩の夢は、どんな夢だった? あたたかい夢を見たのでしょう。
でもその母親は、別の男と不倫している。
そう考えて、あたしはやっと呼吸ができる。
家族なんて壊れている。写真が写しているのは虚像だ。幸せな家庭なんて世界中を探してもきっと存在しない。あたしにもこの子にも、辿り着ける未来なんかどこにもないんだ。
クリームパンの翌々日だったかの昼のことだ。
彼は野菜ジュースを飲んでいた。
相変わらず肌寒くてあたしと彼しかいない、高校の中庭での出来事である。以前よりも少しだけ座っている場所が近い。喋るには困らない距離だ。あたしは彼が吸っている野菜ジュースのパックを遠慮なく眺め、内容量を思いながら訊ねた。
「きょう、もしかしてそれだけなの?」
「うん」
彼の返事は素っ気無かった。あたしは信じがたかった。野菜ジュースのパックひとつ、どう見積もっても二百ミリリットルしかない。
あたしは少々身を乗り出して、もう一度訊ねる。
「おなか、すかないの?」
「食欲がわかない」
「だからって、そんなのじゃあ栄養失調になっちゃうよ」
彼の全身を検めると、あながち遠い未来でもない気がした。どうも細すぎるのだ。
高校で初対面となった彼は、むかし破いた写真そのままの、やたらめったら線の細い美人に成長していた。住んでいるところが離れていたはずだから、まさか同じ学校になるとは思わなかったので、あたしは心底驚いた。しかし驚きはそれだけではなかった。
初めて対面したとき――あたしはあのとき破いた写真の子どもが、実は男だったという事実に驚愕したのだ。写真のなかの美少女とまったく同じ顔がいるけれど、なぜ制服が男子生徒用なのか……当初、何の間違いかと思った。てっきり女の子だと……憎らしいことにいまではすっかり背が高くなっていて、とても女の子には見えない。それでも顔立ちは中性的で、雰囲気はどこまでも静寂で、美男子というよりも美人だといえた。笑顔はなかったが、相変わらず風が吹けば飛んでいってしまいそうな白さだ。
「ごはん、作ってあげようか」
あたしはそんな言葉を口にしていた。どうしてだったんだろう。自分の発言がどこからやって来たものなのかは不可解だが、彼の反応もいまとなっては奇妙だ。
「……うち、来る?」
そして、平素であれば男からの誘いなどというものを嫌悪して遠ざけてきたあたしが、その夕方には彼が暮らしているマンションを訪れていたのも不可解だ。
ごはん、作ってあげようか――なんて言っておきながら、実は料理というのは、もっとも自信がない家事だ。
あたしが幼いころからぎりぎりのところでおかしくなったりふつうだったりを繰り返していたママは、もともと不器用なのも手伝って、家事が少し難しい。そのためあたしは自然と家のことをするように育ち、家庭的とはいわないまでも、おおよその家事はできる。
たとえば掃除は大得意だ。失くしものや隠してあるものの在り処を探し出すのは、プロのトレジャーハンター級だと自負している。
しかし料理に関しては、あたしはママによく「大味」と評された。美味しいか美味しくないかはそのとき次第で、奇跡の一品が完成するときもあれば、どうしてこうなった……と頭を抱える怪事件ができあがったりもする。
料理のほうがあたしを嫌いでも、あたしのほうは料理が好きだ。一方通行の愛だ。ママがまったく料理をしなくなったから家庭料理の記憶はない。あたしはあたしの作るものがすべてで、それはそれは不確かで試行錯誤の日々だった。それがこの上なく楽しかったのだった。ときどき料理というより実験になってきて、つまり料理人ではなくマッドなサイエンティストだった。大量の失敗作を生み出しながらも、成功したときは達成感があった。料理についての記憶としては、正しいものでない気がする。
そんな一人遊び型の料理をしていたけれど、やはり食べてもらうのは嬉しい。そうだ、あの日といえば……ママがパパと旅行に出かけていたせいで、けっこう長い期間、あたしはひとりで生活していたんだった。
だからあたしはたぶん退屈だった。もしくは、寂しかったんだ。
「お邪魔します」
夕方、あたしは彼のマンションの部屋に足を踏み入れた。彼は一人暮らしをしているらしい。部屋のなかは薄暗く殺風景で、心細いほどしんと静かだった。
「どうぞ」
彼がドアを開けて、あたしを室内へ促し、あたしの後ろから入ってくる。
その日彼に食べさせたのは、ビーフシチューだ。
あたしのレパートリーではなかなか高品質を保っているメニューだ。学校帰りに慌てて食材を買い込み、牛肉と赤ワインと野菜とを仕込んだ。ほんとうのところせめて前日から仕込みたかったんだけど、圧力鍋の開発者にはお礼を言いたいと常々思っている。即席ながら、最高の出来だった。
そして彼はあたしの作った渾身のそれを食べ始めたのだが、クリームパンを食べていたときと何ら変わり映えしない無表情だった。
「美味しい」
いちおう、そのように呟いた。もちろんあたしは釈然としない。
そもそも彼からの賛辞を期待していたわけではない。彼がスタンディングオベーションで大絶賛、一瞬にして皿を空にし、すぐさまおかわりを要求するような豪儀な性格でないことはあたしも十分理解していた。
しかしそれにしたってリアクションが薄すぎる。あたしは拍子抜けしてしまった。だから自分でも食べてみた。口にした瞬間、あたしのほうが感動して咽び泣くところだった。最高の出来映えですよ。これは。これは本物のビーフシチューですよ。シェフを呼んでください。
彼はというと黙っていた。しばらく黙りこくって、どうも何らかを考えている様子だった。だが何を考えているのか口にしたりはせず、ただゆっくりと皿のビーフシチューを口にしつづけていた。彼の動作はとても淡々としていて、機械じみていた。その間、あたしは感動の涙をこらえて二回おかわりをした。美味い、もう一杯。
彼は一杯目を食べ終えるころ、ものすごく複雑そうな表情になっていた。たかが美味しいビーフシチューを食べて褒めるのに、なにをそれほど難しい顔をする必要があるのか、皆目見当もつかない。
「もう少しもらっていい?」
彼はそんなことを言った。
でもほんとうに美味しいと感じていたのかどうか、あたしにはわからない。
ところで、中庭でのやり取りの少し前の出来事だ。学校の裏庭を通り掛かったときだった。たまたま、あたしは彼が人といるところを見た。
彼は教室の中でも存在感が希薄で、友達らしき友達もいない……と思っていた。だがどうやらひとりだけ友達と呼べるひとがいる。それを知ったときのことだ。裏庭の倉庫の陰で、クラスメートとともにいた。最初にふたりでいるところを見かけたときは、少し驚いた。どうしてかって?
そのクラスメートというのが、クラスのリーダー格の人気者だったからだ。顔立ちが整っているだけでなく、底抜けに明るく、勉強もスポーツも万能。人当たりが良く、いつもみんなに囲まれて豪快に笑っている。確かクラス委員長だった気がする。
教室でもっとも地味な存在といちばん目立つ存在が友人関係というのが、取り合わせとして不思議だった。しかもふたりは、なかなか会話が弾んでいるらしい。通りがかったあたしに気づかず、親しげにしていた。
そのときだ。
「うわっ」
と、委員長が声をあげた。あたしが見ると、委員長は立ち上がって足下を見ていた。そこには虫か何かがいた。這ってきているのに気づかず、驚いたらしい。ああ、驚くよね……と同情した、次の瞬間のことだった。
いきなり粘着質な音がした。あたしは委員長の足下を凝視し、驚いた。虫を踏みつぶしたのだ。委員長、いくらなんでもそんな乱暴に踏みつぶすことないでしょうに。
「きたねー」
委員長は酷薄な笑みを浮かべながら、そう言った。それはそれは邪悪な表情だった。その瞬間、あたしが委員長に嫌悪感を抱いた。普段教室で見る顔との違いに、ショックを受けたのだった。委員長って、こういうひとだったんだ? 別に虫なんてそのへんの草むらにでも払っておけばいいだろうに、わざわざ踏みつぶす必要なんてある? 間違えて踏んでしまったとかでなく、わざとだなんて(余談だが委員長はこの先も虫やら小動物を虐げていて、あたしはなぜか彼の所業を目撃することが多かったため、あたしは委員長が嫌いになっていくのである)。
物静かな彼のほうはといえば、この一連のあいだ、特に何の言葉も発しなかった。虫を潰すまで、ふたりは楽しそうに会話していたようにあたしには見えていたが、委員長のちょっとした残虐な行動を見たあたしは、もしかして委員長がこの希薄な存在をいじめているのではないかと疑った。
でもそうではなかった。会話はごくふつうに次の話題に移った。しかしあたしは気づいていた。彼は、委員長の行動なんて別になんのこともない……というふりをしていると。彼が委員長の行動に少なからずショックを受けているその感情を、あたしはちゃんと感じた。彼の無表情に変化は生じていないけれど、虫の死骸から目をそらしたとき、瞳は些細に揺らぎ、無気力な色にはわずかに抵抗感が宿っていた。
そのときだ。長年の仇敵であった「清瀬 誠」は、もはや記憶のなかにある破り捨てたあの写真にしか存在していないのだと、あたしが気づいたのは。いま現在の彼は、あたしの知らない空白の時間に、生気をどこかへ置き去りにしてきていた。
殺生を目の当たりにしたときの彼の瞳には、委員長とはまた別の意味での嫌悪を含んでいたと思う。弱い者はそうなって然るべきだという侮蔑、諦念と嘲笑、しかしせめて痛みを知らないことを祈る、神様にでも縋るような気持ちだ。靴の下で踏みにじられた虫には痛覚がない。その事実が救いだった。
そしてあたしは興味を抱いた。いまの彼はどんなひとなんだろう? 変わってしまった現在の彼を知りたくなった。そして意識の端っこに彼を置いておくようになった。だから、彼のほうもあたしを観察している……という事実に気づいたのだった。
彼の部屋でときどき食事を作るようになって、数ヶ月が過ぎた。週に二、三回は行っている。晩御飯を作って、一緒に食べる。しかし彼の態度はどんな力作でも変化なかった。いつだって悲しいほど徹底した無表情だ。小さな声で「美味しい」とは言う。けれど、あたしが何を話しかけても相槌を打つのみで手応えがない。
料理に関してどころか、学校での出来事やバイト先の理不尽などを、あたしはママにいって聞かせるよりもずっと詳しく彼に話した。自分が憤ったことや笑ったことは大袈裟にして大爆笑を狙ったが、彼からの反応は推して知るべし。
けれどしばらくして、あたしに悪いと思ったのか、あたしがウケ狙いの話をしたときに彼はごく薄く笑うようになった。ただしあたしは彼がほんとうの意味で笑っていないとすぐに気づく。というか彼の場合は笑顔があんまりにも上っ面だから、あたしでなくて誰が見ても「笑ってないな」ってわかると思う。
それにあたしは彼の笑顔を写真の中で一度見たことがある。子どものころの無邪気なものではあったが、あれが彼の持つ本物の笑顔だ。ちょっとハードルが高いだろうか。
ある日、彼の部屋で晩ご飯を食べていた。夏になる前だ。窓の外では雨が降っていた。朝から降り続く長雨で世界は灰色一色に染まっており、何もかもが冴えない感じがして、憂鬱が色濃く澱んでいた。
あたしは向かい側の彼に訊ねた。
「ねえ、美味しい?」
訊ねてみたはいいものの、今日のごはんは美味しくない。特に鶏肉と茸のスープ。まず見た目からして失敗している。ぼけっとしていたら鶏肉をあらかた焦がした。トマトソースの赤でなんとなく誤魔化しているけれど、闇は隠しきれていない。つまりあたしは料理人ではなくマッドサイエンティストとしての腕を奮ってしまった。
それでも食卓の用意をして食べ始めたらなんとかなるんじゃないかと期待した。が、自分の判断力の低下を思い知っただけだった。なぜどこかで踏み止まり、やり直さなかったのか。
「美味しいよ」
彼は平気で嘘を吐いた。あたしは黙った。彼はあたしの視線に気づいた。どうやら聞こえていないと勘違いしたらしい。もう一度、少し大きめの声で言い直した。
「美味しいよ」
ふたたび平気な顔で嘘を吐いたのだった。
つまりだ。彼が美味しいといえばいうほど、美味しくできたときも美味しくできなかったときも大差ないということになる。あたしはそう結論づけ、にわかに怒りがこみ上げた。だって美味しいときは美味しくて、美味しくないときは美味しくないっていわれるほうが、いいじゃんか。
「ちゃんと味わってない」
あたしは不平を洩らした。あたしに気を遣って嘘を吐いてるのだったら、そんな気遣いなんかいらない。今日みたいにまずいものができあがったら、「まずい!」って真っ正直に文句を言い合えるほうが、ちゃんとふたりが関係している気がするでしょう?
彼は箸をすすめ、とにかく黙っていた。
あたしは詰問した。
「はっきり言いなさいよ。文句くらいあるでしょ」
彼は言葉と鶏肉をしばらく咀嚼していた。
「特にない」
でも黒いこげはちょっと避けている。食べてはいけないものだとはわかるらしい。だったらそれを言えばいいのだ。
「嘘じゃん」
「そうじゃない」
「何がそうじゃないの」
あたしが自分勝手な質問を繰り返すうちに、彼は困った顔になりはじめた。表情に乏しい彼にしては珍しい。どうやらこれが素顔だった。そして視線を泳がせる困惑しきった彼の瞳は、なかなか可愛らしかった。あたしは自分が原因だということも忘れて、もっと困らせてみたい衝動に駆られた。もっと彼の、いろんな表情をみてみたい。
そんな風に、ちょっとわくわくしてきたときだ。
「僕の食事に、何か文句があるのか」
彼は言った。しごく不機嫌そうに言ったので、あたしはその口調に驚いて目を丸くする。強い抵抗も、その内容も。
「は?」
訊ね返すと、彼は慌てた。ものすごい早口になった。
「レイちゃんのごはんは、なんでも美味しい」
そして小さくなった。
「……食べているんだから、邪魔しないでください」
彼は慌ててごはんをかきこんだ。スープの残りを飲むついでに、避けていたはずの黒いものも、つい一緒くたにして口に入れてしまっている。咽そうになって、けれどそのまま飲み込んだ。かなり狼狽していて、自分の言ったことを後悔しているのだとわかった。
そこでやっとあたしは気づいたのだ。ある事実に。数ヶ月も経ってやっと気づいたなんて、あたしは彼の何を見ていたんだろう?
あたしの作った料理を、彼はゆっくり食べていた。
その重要さに、ちゃんとした意味で気づいた。だってクリームパンなんて、虫が入っていたとしても気づかないほどの速度で、飲み込んでいたくせに。
彼なりに食事を味わっていたのだ。わかりづらいんだけど、間違いなかった。
彼は立ち上がった。
「片づけは僕がする……」
あたしを置き去りにして、彼はすべてを食べ終えた。テーブルの上に並んだ皿の、空っぽのものだけを彼が積んでいく。あたしの分はまだ残っている。
あたしは言葉を失くしたまま。
あたしはこんなの絶対に美味しいとは認められないし、事実としてぜんぜん美味しくない。それに、不味いものは不味いってはっきり指摘するほうがお互いのためではないか。良好な関係性というのは、言いたいことを何でも言い合えるものだ。……と思っていた。
でも少し、考えを改める。彼はそもそも、美味しいとか美味しくないとか、そのリングで戦っていなかったのだった。彼はあたしを尊重したのではない。性格がやさしいわけでもない。あたしがこうして作るだけで、本当にそれでいいって思っているらしい。そう伝わってきた。いつもおぼろげな彼にしては、はっきりとした意思だった。味なんて関係ないんだということだった。
……なんか、馬鹿みたいだ。あたし。一人相撲だ。自分が納得しきれなくたって、彼がそういうんだったら評価なんて預けてしまえばよかった。美味しいでいいのか。
いや、よくない。美味しくないってば。
あたしは決意する。次は絶対に失敗したくない。彼が真剣に食べるんだったら、あたしも真剣に作ってみるよ。いや、これまでも真剣に作っていたはずなんだけど。ふざけてなんかない。もう少しだけ成長してみたい。
あたしくらいしか彼に食べ物を用意しない。どうせあたしだって、彼くらいしか食べてくれるひとがいない。
あたしたちは恋人同士じゃない。
ただのクラスメートであり、たまたまお互いのタイミングが合ったから、向かい合わせで晩ごはんを食べていただけだ。そこに必然なんてない。だから何ヶ月もふたりきりで食事をしていたけれど、なんの接触もなかった。それなのに、わずかに心が触れたかと思えば、いきなり何もかもを飛び越えるようなことになるから不思議だ。
彼のとなりで目覚めたとき、真夜中だった。一日中降りつづいた長雨の音が、いまは聞こえなくなっていた。こんな日はどんな悪い出来事が起きたって仕方ないと思うほど陰鬱な一日だったけれど、夜が更けたら晴れてきた。
あたしはそうっと上半身を起こして、すぐ横の窓に掛かるカーテンに指を差し入れて、少しだけ隙間を作る。かぼそい月明かりが洩れる。午前二時の深い藍色の世界で、輪郭の淡い半月がぽかんと浮かんでいる。色彩はたった二種類だけで、やたら澄んでいて、あたしの目に鮮やかに映る。月が永遠みたいにまばゆく光る。上空を渡る風の遠い音、夜の色が涼しくて、まっさらな気分だった。
そうして彼の寝息に耳を澄ませていたら、熱かった身体が冷えてきて、ふしぎでたまらない気分になる。憎悪っていったい何なんだろう。あたしはあたしの家庭不和の原因だった家族を、写真の美少女を、憎んでいた。だから雨の朝、写真をびりびりに破いていたら、楽しくなった。幸せなんて、あたしにもこの子にも辿り着けないんだって。
けれどあたしは今、あのとき足元に散らばった破いた写真の残骸を、心のなかで一片ずつ繋ぎ合わせようとしている。
だってあの子の笑顔が思い出せなくなってしまったんだ。
かつて写真に映っていた笑顔はどこかへ消えて、彼は空気に溶けるように薄い影となっている。別人みたい。蝋燭の火でも吹き消すように、いつかふっと消えてしまうかもしれない。心がひとりぼっちのまま、どこかへ遠ざかってしまう。
振り返って屈んで、こちらに背を向けて眠っている後ろ頭の髪を手櫛で梳いてみる。かいた汗はもう乾いて、柔らかい毛だった。そんなことをしていたら彼は起きた。喉を鳴らして整えて、訝しげにこちらを仰ぐ。眠たげだ。
「レイちゃん?」
彼の声が低く響いた。なつかしい気持ちになる。昔からそんな風に呼ばれていたみたい。
「うん」
ここにいるよっていう意味を込めてあたしが頷くと、彼はあたしを引き寄せた。あっという間に腕のなかに抱きこまれる。肩がすっかり冷えていて、大きな掌に包まれて温かい。
あたしは少し体勢を整え、彼の胸に頬を寄せる。お互いに気持ちがいい具合を模索しながら、ずれてしまった上掛けを羽織りなおした。あたしたちはやっと、もうちょっと近づいて抱き合う。
あたしは彼の背中に腕を回して、指先や、鼻や、額で彼の肌をなぞる。できるだけ優しく触れる。なんだか傷だらけで、疲れはてた鳥に似ていて、可哀相だから。
鋭利なもので刺された痕も、煙草を押しつけられたらしい火傷も、古傷、濃い痣、薄い痣、たくさんある。けっこう新しいものもある。
どうしてこんなにも傷つけられているの?
でも何も訊かなかった。見て見ぬふりをしよう。たぶんいま、この鳥は飛べない。だから鼓動だけに耳を傾ける。飛べなくても、生きている音は確かだ。
彼のことが知りたい。でもほんとうに知りたいのは彼の過去じゃない。どうして傷ついているのかじゃない。かといって事情を知りたくないわけでもない。でもそれを説明させたら、思い出すことによって彼がもう一度傷ついてしまうでしょう。だから、この傷はどう手当てしたら癒えるのかな。そんなことを静かに、ただ闇雲に考えていた。
この状況が幸せかどうかはこの際置いておいて、ここはあたしたちが辿り着いた未来だといえるだろうか。激しい水流に揉まれてやっとの思いで漂着した岸辺だろうか。この、これから先に続いていく道がどういうところかまったく見えない、手探りの、現実のただなかは。
あたしの耳元で彼が静かに呟いた。
「少しだけ、このまま」
じゃあ、あたしはこのままでいてあげるよ。君がそう願うのなら、そのとおりにしてあげる。望むことをしてあげる。そうだ、美味しいものを作ってあげよう。他にもして欲しいことがあるんだったらどんどん言えばいい。あたしでできるのならばなんだって叶えてあげるから。
たとえ見たことも聞いたこともない料理をリクエストされたって、あたしなりに一所懸命作ろう。もちろん、きっと最初は上手く作れない。家庭料理ではなく化学実験かもしれない。けれどもしかしたらカレーから肉じゃがみたいに新しいメニューが爆誕する可能性もあるから、それはまた一興ってことで許してほしい。
何かの約束みたいに、あたしの指を彼の指に絡ませる。そうして、ともすれば夢のように消えてしまいそうに遠い彼を、こうしてちゃんと現実に掴まえておこう。じゃないと、ここにいるのにどこにもいない感じがするもの。
触れた指先から体温が伝わってきて、このままでいさせてほしい。急に。無性に。神様、このひとがいいです。そんな風に。息が詰まる。熱がこみあげてくる。あたしの胸に疼痛が広がっていく。それらはあたしに甘い心地など一切もたらさず、ひたすらに辛い気持ちだ。なのになぜかずっと味わっていたい。息なんかできなくなってもいい。
たとえ馬鹿みたいになったとしても、泣きたいくらい哀しくなったとしても、この身が滅びてしまっても、後戻りはしない。できない。どうなったって構わない。
<了>
ちなみにパンとはあたしがもっとも苦手とする食べ物の総称だ。むかしパン屋さんで買ったクロワッサンを食べたら奇妙な感触と味がしたので吐き出したら虫だった事件以来、あたしはパンが食べられなくなった。パンを食べているひとを見かけると、あたしはひどく不安になる。虫が混入していないかと、そしてそれをうっかり食べてしまわないかと、見ているこちらがはらはらして、目が離せない。
彼の様子をまじまじと観察してみる。どうやらあのクリームパンひとつが昼食らしい。校内の購買部で買ったのだろう。まるで餌だとでも思っているかのように、クリームパンを素早く飲み込んでいた。あの様子では虫が入っていようが入っていまいが、ろくに気づかなさそうだ。おかげでこちらがはらはらするのは一瞬で済んだ。パンを飲み下すあいだ、彼はずっと無表情だった。彼はいつだって無表情を徹底しており、愛想という言葉が辞書にない。
高校の中庭は晴れているが、風が強くざわめいて肌寒い。だからか、あたしたちしかいなかった。木の下に座っている彼とベンチに掛けてお弁当の包みをのんびりまとめているあたし。お互いに孤独でひとりぼっちずつ。一緒に食べていたわけではない。だが喋るには困らない距離だ。といって、これまで一言も会話していないのだが。
「麻野さん。予鈴鳴ったよ。戻らなくていいの」
彼がぼそりと呟いた。あたしは彼は言葉を発しない生き物だと認識していたので、いきなりのことに少し驚いた。
「あたしの名前、知ってるの?」
「……クラスメートだから」
そう。あたしたちはクラスメートだ。しかし今までのことを思うと、言い訳がましいのではなかろうか。彼はあたしの存在を意識しているはずだ。たとえば教室で、廊下で、帰り道で、道端で偶然を装ってすれ違ったりして、頻繁に存在と視線を感じる。気のせい……ではないと思う。視線には敏感なほうだ。あたしは警戒している。本能的にというのか、なんだか危険な香りを嗅ぎ取ったからだ。
「ふーん。そっち、名前なんだっけ?」
無関心を装って、あたしは訊ねた。
「……清瀬」
彼は答えた。もちろんあたしは彼の苗字を知っている。下の名前は誠という。あたしが彼の名を知っている理由は、クラスメートだからではない。
あたしがこれまでの人生で、もっとも憎んできた――仇敵だからだ。
初めて彼の名前を知ったのは、うんと小さなころだ。ママが教えてくれた。本当はちゃんと覚えているわけではないんだけど、ママくらいしか教えてくれるひとなんていないから、絶対にそうだ。そうに違いない。……でも彼の名前はいつの間にかあたしの心に刻み込まれていたから、生まれる前から知っていたのかもしれないと考えるときもある。そんなわけないのにね。
あたしのママは、自らを「正妻」だと、いつも主張していた。主張して言い聞かせていなければ、きっと自分がいちばんわからなくなってしまうから。
あたしのパパはとても気が多かった。あたしが小さなころから愛人と呼ばれるひとがたくさんいた。そもそも独身時代からたくさんの恋人がおり、ママは恋人たちのなかでもっとも美人だったから、パパと結婚できたんだって。ママの自慢のひとつだ。
ひとり娘のあたしは、パパが大嫌いだった。
基本的に仕事人間のパパが家に帰ってくるのは稀で、たまにしか会わない。だから他人同然で、会うときといえばいつだってお酒を飲んでいるにおいがして臭い。たまにやってくる臭いデブ。好きになれる要素がない。
あたしは生まれ落ちた瞬間からママにそっくりだったから、たまに会えば「綺麗」とか「将来は美人になる」と褒めそやされ、溺愛された。パパは会えば、あたしを抱き上げた。火を点けたら三日三晩燃えそうな、ぱんぱんに膨らんだ分厚い掌で抱き上げられるたび、あたしはその値踏みするみたいなパパの瞳に嫌悪感を覚えた。すごく気持ち悪くて、背筋がぞわぞわする。笑顔になんかとてもなれない。
会うたびに無愛想な子だと非難されたけれど、あたしだって好きで無愛想なわけではない。相手が相手だったのだ。人生で初めて嫌いになった人間、それがあたしにとってのパパすべてといえる。
だけどママはパパが大好きだった。とくべつだった。ときどき家に帰ってくると、いつでも大喜びで出迎えた。あたしは、パパを出迎えるときのママの様子を見るのは好きだ。楽しそうだからだ。普段では考えられないような馬鹿みたいなハイテンションで、はっきり申し上げて滑稽なのだけれど、目をきらきらと輝かせていて美しい。ひとりで静かに落ち込んでいる姿を見るより、ふたりで楽しそうな様子を見るほうがいい。
けれどママがパパを好きだと言えば言うほど、あたしはわからなくなっていく。だからあたしはママにこう訊ねたことがある。
「あんなののどこがいいの?」
我ながら父親に対する言葉ではないけれど、どうしても納得できなかったのだ。あたしの目に映るパパはせいぜい、明るくて陽気でポジティブかな……程度の魅力しかなかった。
あたしの疑問に対し、
「レイちゃん、言葉遣いを改めましょうね」
と、ママはまず冷静にたしなめた。それもそうだね。そしてママは、あたしの疑問にもちゃんとママなりの態度を提示してくれた。
「パパのどこを好きなのか、うまく説明ができないの」
ママは言った。ママは、パパに対しての感情や、男のひとの魅力について語ることが、他者の目にどう映るのかを知っていた。だから深く説明しなかったのだと思う。身振り手振りをまじえてどれほど力説したところで絶対に他人には正確に伝わらない、とよくよく承知していた。だからすべてをひっくるめて、
「レイちゃんもきっとわかるわ。いまに、大好きなひとができるから」
とママはあたしに、穏やかにそう言った。そして念を押した。
「運命ってこと」
まるで胸の痛みを堪えるみたいにぎゅっと両手を胸に抱き、そしてママはその痛みを味わうかのように、うっとりと微笑んだ。ママはじきに小学生になる娘がいる年齢であっても、恋に酔いしれる少女だった。「この恋だけはどうしようもないの」と笑ったときは、少し淋しそうにもみえた。恋はママに、希望と失望を同時に与えていた。あたしはそんなママを見て、哀しくなった。
パパがいないとき、ママはちゃんとしたひとだ。おっとりとした気質で、健気で、少々夢見がちなところはあるが、意思ははっきりとしている。それなのになぜ恋ひとつで変えられてしまうの? 運命? 他人に振り回されて感情に流されて溺れて、馬鹿みたい。でもママは自分自身の感情のどうしようもなさを、自分がもっとも理解している。どうしようもないから苦しいのだとわかっている。
あたしはよく、パパへの恋という一点に於いてひどく弱いママを、
「あたしが生まれてるってことは、パパもママがいちばんなんだね」
と励ました。すると、
「ありがとう。レイちゃんは、パパの次にいちばん大事よ」
だなんて言うから、なにもかも「仕方ないなあ」という気分になる。呆れながらも、あたしはママのそんな正直さが好きだった。だがこっそり、こう願うのだ。――見た目がいくら似ていても、あたしはママみたいにはなりませんように。
よりにもよってパパのようなはずれを引く運命が将来あたしの身にも訪れるのだったら、そんな日はアルマゲドンだ。世界なんて滅亡してしまえばいい。
あたしのパパ嫌いはどんどん加速していった。帰ってこないのはもちろん、女性を連れているのを見かけたりしてママが泣くたび、あたしはパパにも呆れたし、同時にママにも、何度も何度も悲しくなる。ママほどは、パパがママを愛していないのは、あたしの目にも明らかだった。ママとパパを同時に好きになることは、あたしにはむずかしい。
ママが本格的におかしくなったのは、いつだったっけ。はっきりとしたきっかけはわからない。緩やかに蝕まれていったというのだろうか。あたしが小学校にあがったくらいかな。あたしが幼稚園の頃はまだ、パパがいなくてもママは気丈に振舞っていたけれど、年を追うごとに、沈んでいる時間が長くなっていった。
じきにママは、パパを愛するあまり、パパを「調べる」ようになった。
叩けば埃が出てくるというよりは埃そのものであったパパからは、浮気の証拠が無限に溢れる。無尽蔵な発生源だ。ママはおかしくなっていく。それでも調べるのをやめない。調べて調べて調べ尽くす。浮気相手の女性はどんなひと? どんな生活? どんな家族構成?
ふつうのひとならば問い質したり別れたりするはずのところを、ママは調べるだけ調べて、悲しむ。そう。悲しむだけなのだ。
ママはパパのことが大好きすぎるので、とてもじゃないけれど離れるなんて選択肢はない。そしてたとえどれほど自分が傷つく結果となってもママはパパの情報をすべて知る必要があるらしい。理由は判然としない。どれほど止めても無駄だった。
そうしてママは、調査会社の優良顧客としての地位を確立していった。首を傾げざるをえないのだけれど、いつしか悲しむという不毛な行為が、ママを保たせていた。
とある子どもの存在を、あたしはそのころ知ったんだ。
あの日は雨が降っていて、朝から薄暗い日だった。いつまでも一定の調子で降りつづけている、六月の長雨だった。今日一日どんな不吉な出来事が起こったとしてもこんな天気ならば仕方ないと納得してしまうほど、陰鬱とした朝だった。
あたしはベッドから起きてきて、ママがいつも以上に塞いでいると気づいた。リビングで丸まって、嘆き悲しんでいる気配がしたのだ。そのときに偶然、ダイニングテーブルの上をみとめた。テーブルの上にはたくさんの書類がまき散らかされていた。
難しい内容の書類がばらばらになっていて、写真もたくさんある。ママがパパを調べて勝手に暗黒色に染まっているという経緯が、一目瞭然だった。傷つくとわかっているのに、どうしてやめられないんだろう。手放せば楽になれる。なのに、まるで一部を手放した途端にすべてから捨てられると恐れている。だから何もかも知りたくなり、なにも知らない状態ではいられない。
あたしはテーブルで足を止めて、一枚の写真を手にした。不意打ちのようにあたしの目を奪ったのは、うつくしい女の子の写真だった。ショートカットで服装もボーイッシュだけど、色白ですごくかわいらしい。
あたしの手にした写真には、「幸せな家族」が写っていた。
三人家族の写真だ。晴れている。どうやら遊園地に遊びに来たようで、入り口のところでキャラクターの着ぐるみと並んでいる。うちのママには及ばないにしても、女優さんみたいに綺麗で色白で小柄なお母さん。となりにはお父さん。このお父さんというのが端整な顔立ちをしており、なによりとっても優しそうだった。大人しそうで柔和な雰囲気をまとっていた。うちのパパと取り替えて欲しい。反射的にそう思った。
夫婦のあいだで子どもが笑っている。両親と手をつなぎ、すごく楽しそうにはしゃいでいる。この日、家族で遊園地に遊びに来るのを心から楽しみにしていたと見て取れる、しあわせそうで無邪気な笑顔だった。子どもは、顔の造作などはお母さんとそっくりだ。でも笑い方はお父さんとそっくりだ。
あたしには縁のない幸福。
「この子、誰?」
あたしはその場に立ち尽くしたまま、リビングのママへと訊ねた。ママは気だるげにこちらへと歩いてきた。あたしのすぐ傍に立ち、震える声で言った。
「パパの不倫相手と、子ども」
あたしは驚いて顔をあげる。
「まさかパパの子ども?」
「違うわよ」
ママは薄く笑った。あたしは写真に目を落とす。そうだよね、パパの子どものはずがない。この子はこの両親の子だ。こんなにも両親に似ているのだから。
ママはパパを調べ、この女性を調べ、女性の家族を調べたというわけだった。ママの「知りたい」にあたしも巻き込まれてしまった。ママと同様、あたしも傷ついた。自分たちと比較してしまって、どうしても傷ついた。
ママはあたしの手から写真を取った。細くて白い指先で、写真をふたつに裂いた。幸せな家族の肖像は、不仕合せな家族の手によって、びりびりに千切られる。その行為は、これ以上心ががらんと空虚にならないための自己防衛だった。
ママはしまいには他の写真や書類もどんどん破いていって、こらえきれなくなったみたいに笑いはじめた。あたしも一緒になって、一所懸命になって他の写真を破いた。最初こそ、あたしはいったい何をしているんだろう……と自分を不憫に思ったが、一心不乱に破くうちにどうでもよくなってきた。楽しくなってきた。あたしも笑った。笑ってやった。紙片を紙吹雪にしていつまでも遊んだ。
会ったこともこの目で見たこともない遠くにいる子ども。あたしはこんな子、ダイキライだ。ばかみたいな笑顔を浮かべている。正体不明な悔しさがわきあがってくる。現実が差し迫ると、溺れてしまったように息苦しい。だから叫び声をあげる代わりに、笑うのだ。
きっとこの日、この子は遊園地を楽しみにしていたんだ。写真の空は青空だった。晴れてよかったね。たくさん遊んで、そして家族で手をつないで家に帰ったはずだ。帰路も帰宅後も、また遊びに行こうとか、三人で仲良く話したでしょう。そして疲れて眠りに落ちる。その晩の夢は、どんな夢だった? あたたかい夢を見たのでしょう。
でもその母親は、別の男と不倫している。
そう考えて、あたしはやっと呼吸ができる。
家族なんて壊れている。写真が写しているのは虚像だ。幸せな家庭なんて世界中を探してもきっと存在しない。あたしにもこの子にも、辿り着ける未来なんかどこにもないんだ。
クリームパンの翌々日だったかの昼のことだ。
彼は野菜ジュースを飲んでいた。
相変わらず肌寒くてあたしと彼しかいない、高校の中庭での出来事である。以前よりも少しだけ座っている場所が近い。喋るには困らない距離だ。あたしは彼が吸っている野菜ジュースのパックを遠慮なく眺め、内容量を思いながら訊ねた。
「きょう、もしかしてそれだけなの?」
「うん」
彼の返事は素っ気無かった。あたしは信じがたかった。野菜ジュースのパックひとつ、どう見積もっても二百ミリリットルしかない。
あたしは少々身を乗り出して、もう一度訊ねる。
「おなか、すかないの?」
「食欲がわかない」
「だからって、そんなのじゃあ栄養失調になっちゃうよ」
彼の全身を検めると、あながち遠い未来でもない気がした。どうも細すぎるのだ。
高校で初対面となった彼は、むかし破いた写真そのままの、やたらめったら線の細い美人に成長していた。住んでいるところが離れていたはずだから、まさか同じ学校になるとは思わなかったので、あたしは心底驚いた。しかし驚きはそれだけではなかった。
初めて対面したとき――あたしはあのとき破いた写真の子どもが、実は男だったという事実に驚愕したのだ。写真のなかの美少女とまったく同じ顔がいるけれど、なぜ制服が男子生徒用なのか……当初、何の間違いかと思った。てっきり女の子だと……憎らしいことにいまではすっかり背が高くなっていて、とても女の子には見えない。それでも顔立ちは中性的で、雰囲気はどこまでも静寂で、美男子というよりも美人だといえた。笑顔はなかったが、相変わらず風が吹けば飛んでいってしまいそうな白さだ。
「ごはん、作ってあげようか」
あたしはそんな言葉を口にしていた。どうしてだったんだろう。自分の発言がどこからやって来たものなのかは不可解だが、彼の反応もいまとなっては奇妙だ。
「……うち、来る?」
そして、平素であれば男からの誘いなどというものを嫌悪して遠ざけてきたあたしが、その夕方には彼が暮らしているマンションを訪れていたのも不可解だ。
ごはん、作ってあげようか――なんて言っておきながら、実は料理というのは、もっとも自信がない家事だ。
あたしが幼いころからぎりぎりのところでおかしくなったりふつうだったりを繰り返していたママは、もともと不器用なのも手伝って、家事が少し難しい。そのためあたしは自然と家のことをするように育ち、家庭的とはいわないまでも、おおよその家事はできる。
たとえば掃除は大得意だ。失くしものや隠してあるものの在り処を探し出すのは、プロのトレジャーハンター級だと自負している。
しかし料理に関しては、あたしはママによく「大味」と評された。美味しいか美味しくないかはそのとき次第で、奇跡の一品が完成するときもあれば、どうしてこうなった……と頭を抱える怪事件ができあがったりもする。
料理のほうがあたしを嫌いでも、あたしのほうは料理が好きだ。一方通行の愛だ。ママがまったく料理をしなくなったから家庭料理の記憶はない。あたしはあたしの作るものがすべてで、それはそれは不確かで試行錯誤の日々だった。それがこの上なく楽しかったのだった。ときどき料理というより実験になってきて、つまり料理人ではなくマッドなサイエンティストだった。大量の失敗作を生み出しながらも、成功したときは達成感があった。料理についての記憶としては、正しいものでない気がする。
そんな一人遊び型の料理をしていたけれど、やはり食べてもらうのは嬉しい。そうだ、あの日といえば……ママがパパと旅行に出かけていたせいで、けっこう長い期間、あたしはひとりで生活していたんだった。
だからあたしはたぶん退屈だった。もしくは、寂しかったんだ。
「お邪魔します」
夕方、あたしは彼のマンションの部屋に足を踏み入れた。彼は一人暮らしをしているらしい。部屋のなかは薄暗く殺風景で、心細いほどしんと静かだった。
「どうぞ」
彼がドアを開けて、あたしを室内へ促し、あたしの後ろから入ってくる。
その日彼に食べさせたのは、ビーフシチューだ。
あたしのレパートリーではなかなか高品質を保っているメニューだ。学校帰りに慌てて食材を買い込み、牛肉と赤ワインと野菜とを仕込んだ。ほんとうのところせめて前日から仕込みたかったんだけど、圧力鍋の開発者にはお礼を言いたいと常々思っている。即席ながら、最高の出来だった。
そして彼はあたしの作った渾身のそれを食べ始めたのだが、クリームパンを食べていたときと何ら変わり映えしない無表情だった。
「美味しい」
いちおう、そのように呟いた。もちろんあたしは釈然としない。
そもそも彼からの賛辞を期待していたわけではない。彼がスタンディングオベーションで大絶賛、一瞬にして皿を空にし、すぐさまおかわりを要求するような豪儀な性格でないことはあたしも十分理解していた。
しかしそれにしたってリアクションが薄すぎる。あたしは拍子抜けしてしまった。だから自分でも食べてみた。口にした瞬間、あたしのほうが感動して咽び泣くところだった。最高の出来映えですよ。これは。これは本物のビーフシチューですよ。シェフを呼んでください。
彼はというと黙っていた。しばらく黙りこくって、どうも何らかを考えている様子だった。だが何を考えているのか口にしたりはせず、ただゆっくりと皿のビーフシチューを口にしつづけていた。彼の動作はとても淡々としていて、機械じみていた。その間、あたしは感動の涙をこらえて二回おかわりをした。美味い、もう一杯。
彼は一杯目を食べ終えるころ、ものすごく複雑そうな表情になっていた。たかが美味しいビーフシチューを食べて褒めるのに、なにをそれほど難しい顔をする必要があるのか、皆目見当もつかない。
「もう少しもらっていい?」
彼はそんなことを言った。
でもほんとうに美味しいと感じていたのかどうか、あたしにはわからない。
ところで、中庭でのやり取りの少し前の出来事だ。学校の裏庭を通り掛かったときだった。たまたま、あたしは彼が人といるところを見た。
彼は教室の中でも存在感が希薄で、友達らしき友達もいない……と思っていた。だがどうやらひとりだけ友達と呼べるひとがいる。それを知ったときのことだ。裏庭の倉庫の陰で、クラスメートとともにいた。最初にふたりでいるところを見かけたときは、少し驚いた。どうしてかって?
そのクラスメートというのが、クラスのリーダー格の人気者だったからだ。顔立ちが整っているだけでなく、底抜けに明るく、勉強もスポーツも万能。人当たりが良く、いつもみんなに囲まれて豪快に笑っている。確かクラス委員長だった気がする。
教室でもっとも地味な存在といちばん目立つ存在が友人関係というのが、取り合わせとして不思議だった。しかもふたりは、なかなか会話が弾んでいるらしい。通りがかったあたしに気づかず、親しげにしていた。
そのときだ。
「うわっ」
と、委員長が声をあげた。あたしが見ると、委員長は立ち上がって足下を見ていた。そこには虫か何かがいた。這ってきているのに気づかず、驚いたらしい。ああ、驚くよね……と同情した、次の瞬間のことだった。
いきなり粘着質な音がした。あたしは委員長の足下を凝視し、驚いた。虫を踏みつぶしたのだ。委員長、いくらなんでもそんな乱暴に踏みつぶすことないでしょうに。
「きたねー」
委員長は酷薄な笑みを浮かべながら、そう言った。それはそれは邪悪な表情だった。その瞬間、あたしが委員長に嫌悪感を抱いた。普段教室で見る顔との違いに、ショックを受けたのだった。委員長って、こういうひとだったんだ? 別に虫なんてそのへんの草むらにでも払っておけばいいだろうに、わざわざ踏みつぶす必要なんてある? 間違えて踏んでしまったとかでなく、わざとだなんて(余談だが委員長はこの先も虫やら小動物を虐げていて、あたしはなぜか彼の所業を目撃することが多かったため、あたしは委員長が嫌いになっていくのである)。
物静かな彼のほうはといえば、この一連のあいだ、特に何の言葉も発しなかった。虫を潰すまで、ふたりは楽しそうに会話していたようにあたしには見えていたが、委員長のちょっとした残虐な行動を見たあたしは、もしかして委員長がこの希薄な存在をいじめているのではないかと疑った。
でもそうではなかった。会話はごくふつうに次の話題に移った。しかしあたしは気づいていた。彼は、委員長の行動なんて別になんのこともない……というふりをしていると。彼が委員長の行動に少なからずショックを受けているその感情を、あたしはちゃんと感じた。彼の無表情に変化は生じていないけれど、虫の死骸から目をそらしたとき、瞳は些細に揺らぎ、無気力な色にはわずかに抵抗感が宿っていた。
そのときだ。長年の仇敵であった「清瀬 誠」は、もはや記憶のなかにある破り捨てたあの写真にしか存在していないのだと、あたしが気づいたのは。いま現在の彼は、あたしの知らない空白の時間に、生気をどこかへ置き去りにしてきていた。
殺生を目の当たりにしたときの彼の瞳には、委員長とはまた別の意味での嫌悪を含んでいたと思う。弱い者はそうなって然るべきだという侮蔑、諦念と嘲笑、しかしせめて痛みを知らないことを祈る、神様にでも縋るような気持ちだ。靴の下で踏みにじられた虫には痛覚がない。その事実が救いだった。
そしてあたしは興味を抱いた。いまの彼はどんなひとなんだろう? 変わってしまった現在の彼を知りたくなった。そして意識の端っこに彼を置いておくようになった。だから、彼のほうもあたしを観察している……という事実に気づいたのだった。
彼の部屋でときどき食事を作るようになって、数ヶ月が過ぎた。週に二、三回は行っている。晩御飯を作って、一緒に食べる。しかし彼の態度はどんな力作でも変化なかった。いつだって悲しいほど徹底した無表情だ。小さな声で「美味しい」とは言う。けれど、あたしが何を話しかけても相槌を打つのみで手応えがない。
料理に関してどころか、学校での出来事やバイト先の理不尽などを、あたしはママにいって聞かせるよりもずっと詳しく彼に話した。自分が憤ったことや笑ったことは大袈裟にして大爆笑を狙ったが、彼からの反応は推して知るべし。
けれどしばらくして、あたしに悪いと思ったのか、あたしがウケ狙いの話をしたときに彼はごく薄く笑うようになった。ただしあたしは彼がほんとうの意味で笑っていないとすぐに気づく。というか彼の場合は笑顔があんまりにも上っ面だから、あたしでなくて誰が見ても「笑ってないな」ってわかると思う。
それにあたしは彼の笑顔を写真の中で一度見たことがある。子どものころの無邪気なものではあったが、あれが彼の持つ本物の笑顔だ。ちょっとハードルが高いだろうか。
ある日、彼の部屋で晩ご飯を食べていた。夏になる前だ。窓の外では雨が降っていた。朝から降り続く長雨で世界は灰色一色に染まっており、何もかもが冴えない感じがして、憂鬱が色濃く澱んでいた。
あたしは向かい側の彼に訊ねた。
「ねえ、美味しい?」
訊ねてみたはいいものの、今日のごはんは美味しくない。特に鶏肉と茸のスープ。まず見た目からして失敗している。ぼけっとしていたら鶏肉をあらかた焦がした。トマトソースの赤でなんとなく誤魔化しているけれど、闇は隠しきれていない。つまりあたしは料理人ではなくマッドサイエンティストとしての腕を奮ってしまった。
それでも食卓の用意をして食べ始めたらなんとかなるんじゃないかと期待した。が、自分の判断力の低下を思い知っただけだった。なぜどこかで踏み止まり、やり直さなかったのか。
「美味しいよ」
彼は平気で嘘を吐いた。あたしは黙った。彼はあたしの視線に気づいた。どうやら聞こえていないと勘違いしたらしい。もう一度、少し大きめの声で言い直した。
「美味しいよ」
ふたたび平気な顔で嘘を吐いたのだった。
つまりだ。彼が美味しいといえばいうほど、美味しくできたときも美味しくできなかったときも大差ないということになる。あたしはそう結論づけ、にわかに怒りがこみ上げた。だって美味しいときは美味しくて、美味しくないときは美味しくないっていわれるほうが、いいじゃんか。
「ちゃんと味わってない」
あたしは不平を洩らした。あたしに気を遣って嘘を吐いてるのだったら、そんな気遣いなんかいらない。今日みたいにまずいものができあがったら、「まずい!」って真っ正直に文句を言い合えるほうが、ちゃんとふたりが関係している気がするでしょう?
彼は箸をすすめ、とにかく黙っていた。
あたしは詰問した。
「はっきり言いなさいよ。文句くらいあるでしょ」
彼は言葉と鶏肉をしばらく咀嚼していた。
「特にない」
でも黒いこげはちょっと避けている。食べてはいけないものだとはわかるらしい。だったらそれを言えばいいのだ。
「嘘じゃん」
「そうじゃない」
「何がそうじゃないの」
あたしが自分勝手な質問を繰り返すうちに、彼は困った顔になりはじめた。表情に乏しい彼にしては珍しい。どうやらこれが素顔だった。そして視線を泳がせる困惑しきった彼の瞳は、なかなか可愛らしかった。あたしは自分が原因だということも忘れて、もっと困らせてみたい衝動に駆られた。もっと彼の、いろんな表情をみてみたい。
そんな風に、ちょっとわくわくしてきたときだ。
「僕の食事に、何か文句があるのか」
彼は言った。しごく不機嫌そうに言ったので、あたしはその口調に驚いて目を丸くする。強い抵抗も、その内容も。
「は?」
訊ね返すと、彼は慌てた。ものすごい早口になった。
「レイちゃんのごはんは、なんでも美味しい」
そして小さくなった。
「……食べているんだから、邪魔しないでください」
彼は慌ててごはんをかきこんだ。スープの残りを飲むついでに、避けていたはずの黒いものも、つい一緒くたにして口に入れてしまっている。咽そうになって、けれどそのまま飲み込んだ。かなり狼狽していて、自分の言ったことを後悔しているのだとわかった。
そこでやっとあたしは気づいたのだ。ある事実に。数ヶ月も経ってやっと気づいたなんて、あたしは彼の何を見ていたんだろう?
あたしの作った料理を、彼はゆっくり食べていた。
その重要さに、ちゃんとした意味で気づいた。だってクリームパンなんて、虫が入っていたとしても気づかないほどの速度で、飲み込んでいたくせに。
彼なりに食事を味わっていたのだ。わかりづらいんだけど、間違いなかった。
彼は立ち上がった。
「片づけは僕がする……」
あたしを置き去りにして、彼はすべてを食べ終えた。テーブルの上に並んだ皿の、空っぽのものだけを彼が積んでいく。あたしの分はまだ残っている。
あたしは言葉を失くしたまま。
あたしはこんなの絶対に美味しいとは認められないし、事実としてぜんぜん美味しくない。それに、不味いものは不味いってはっきり指摘するほうがお互いのためではないか。良好な関係性というのは、言いたいことを何でも言い合えるものだ。……と思っていた。
でも少し、考えを改める。彼はそもそも、美味しいとか美味しくないとか、そのリングで戦っていなかったのだった。彼はあたしを尊重したのではない。性格がやさしいわけでもない。あたしがこうして作るだけで、本当にそれでいいって思っているらしい。そう伝わってきた。いつもおぼろげな彼にしては、はっきりとした意思だった。味なんて関係ないんだということだった。
……なんか、馬鹿みたいだ。あたし。一人相撲だ。自分が納得しきれなくたって、彼がそういうんだったら評価なんて預けてしまえばよかった。美味しいでいいのか。
いや、よくない。美味しくないってば。
あたしは決意する。次は絶対に失敗したくない。彼が真剣に食べるんだったら、あたしも真剣に作ってみるよ。いや、これまでも真剣に作っていたはずなんだけど。ふざけてなんかない。もう少しだけ成長してみたい。
あたしくらいしか彼に食べ物を用意しない。どうせあたしだって、彼くらいしか食べてくれるひとがいない。
あたしたちは恋人同士じゃない。
ただのクラスメートであり、たまたまお互いのタイミングが合ったから、向かい合わせで晩ごはんを食べていただけだ。そこに必然なんてない。だから何ヶ月もふたりきりで食事をしていたけれど、なんの接触もなかった。それなのに、わずかに心が触れたかと思えば、いきなり何もかもを飛び越えるようなことになるから不思議だ。
彼のとなりで目覚めたとき、真夜中だった。一日中降りつづいた長雨の音が、いまは聞こえなくなっていた。こんな日はどんな悪い出来事が起きたって仕方ないと思うほど陰鬱な一日だったけれど、夜が更けたら晴れてきた。
あたしはそうっと上半身を起こして、すぐ横の窓に掛かるカーテンに指を差し入れて、少しだけ隙間を作る。かぼそい月明かりが洩れる。午前二時の深い藍色の世界で、輪郭の淡い半月がぽかんと浮かんでいる。色彩はたった二種類だけで、やたら澄んでいて、あたしの目に鮮やかに映る。月が永遠みたいにまばゆく光る。上空を渡る風の遠い音、夜の色が涼しくて、まっさらな気分だった。
そうして彼の寝息に耳を澄ませていたら、熱かった身体が冷えてきて、ふしぎでたまらない気分になる。憎悪っていったい何なんだろう。あたしはあたしの家庭不和の原因だった家族を、写真の美少女を、憎んでいた。だから雨の朝、写真をびりびりに破いていたら、楽しくなった。幸せなんて、あたしにもこの子にも辿り着けないんだって。
けれどあたしは今、あのとき足元に散らばった破いた写真の残骸を、心のなかで一片ずつ繋ぎ合わせようとしている。
だってあの子の笑顔が思い出せなくなってしまったんだ。
かつて写真に映っていた笑顔はどこかへ消えて、彼は空気に溶けるように薄い影となっている。別人みたい。蝋燭の火でも吹き消すように、いつかふっと消えてしまうかもしれない。心がひとりぼっちのまま、どこかへ遠ざかってしまう。
振り返って屈んで、こちらに背を向けて眠っている後ろ頭の髪を手櫛で梳いてみる。かいた汗はもう乾いて、柔らかい毛だった。そんなことをしていたら彼は起きた。喉を鳴らして整えて、訝しげにこちらを仰ぐ。眠たげだ。
「レイちゃん?」
彼の声が低く響いた。なつかしい気持ちになる。昔からそんな風に呼ばれていたみたい。
「うん」
ここにいるよっていう意味を込めてあたしが頷くと、彼はあたしを引き寄せた。あっという間に腕のなかに抱きこまれる。肩がすっかり冷えていて、大きな掌に包まれて温かい。
あたしは少し体勢を整え、彼の胸に頬を寄せる。お互いに気持ちがいい具合を模索しながら、ずれてしまった上掛けを羽織りなおした。あたしたちはやっと、もうちょっと近づいて抱き合う。
あたしは彼の背中に腕を回して、指先や、鼻や、額で彼の肌をなぞる。できるだけ優しく触れる。なんだか傷だらけで、疲れはてた鳥に似ていて、可哀相だから。
鋭利なもので刺された痕も、煙草を押しつけられたらしい火傷も、古傷、濃い痣、薄い痣、たくさんある。けっこう新しいものもある。
どうしてこんなにも傷つけられているの?
でも何も訊かなかった。見て見ぬふりをしよう。たぶんいま、この鳥は飛べない。だから鼓動だけに耳を傾ける。飛べなくても、生きている音は確かだ。
彼のことが知りたい。でもほんとうに知りたいのは彼の過去じゃない。どうして傷ついているのかじゃない。かといって事情を知りたくないわけでもない。でもそれを説明させたら、思い出すことによって彼がもう一度傷ついてしまうでしょう。だから、この傷はどう手当てしたら癒えるのかな。そんなことを静かに、ただ闇雲に考えていた。
この状況が幸せかどうかはこの際置いておいて、ここはあたしたちが辿り着いた未来だといえるだろうか。激しい水流に揉まれてやっとの思いで漂着した岸辺だろうか。この、これから先に続いていく道がどういうところかまったく見えない、手探りの、現実のただなかは。
あたしの耳元で彼が静かに呟いた。
「少しだけ、このまま」
じゃあ、あたしはこのままでいてあげるよ。君がそう願うのなら、そのとおりにしてあげる。望むことをしてあげる。そうだ、美味しいものを作ってあげよう。他にもして欲しいことがあるんだったらどんどん言えばいい。あたしでできるのならばなんだって叶えてあげるから。
たとえ見たことも聞いたこともない料理をリクエストされたって、あたしなりに一所懸命作ろう。もちろん、きっと最初は上手く作れない。家庭料理ではなく化学実験かもしれない。けれどもしかしたらカレーから肉じゃがみたいに新しいメニューが爆誕する可能性もあるから、それはまた一興ってことで許してほしい。
何かの約束みたいに、あたしの指を彼の指に絡ませる。そうして、ともすれば夢のように消えてしまいそうに遠い彼を、こうしてちゃんと現実に掴まえておこう。じゃないと、ここにいるのにどこにもいない感じがするもの。
触れた指先から体温が伝わってきて、このままでいさせてほしい。急に。無性に。神様、このひとがいいです。そんな風に。息が詰まる。熱がこみあげてくる。あたしの胸に疼痛が広がっていく。それらはあたしに甘い心地など一切もたらさず、ひたすらに辛い気持ちだ。なのになぜかずっと味わっていたい。息なんかできなくなってもいい。
たとえ馬鹿みたいになったとしても、泣きたいくらい哀しくなったとしても、この身が滅びてしまっても、後戻りはしない。できない。どうなったって構わない。
<了>
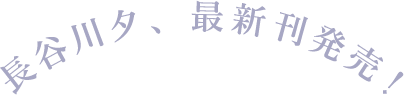
この願いは、誰も聞かなくていい――。

『どうか、天国に届きませんように』
オカルトに憧れる「僕」は、ある日の下校中、自分の指へ絡む黒い糸に導かれ、死体を見つける。特別な力を得た優越感に溺れた「僕」は死体を見つける行為にのめりこんでいくが…? 偶然が偶然を呼び、不幸に魅入られた者たちは巡り合う。そして、彼らが抱く行き場のない願いと孤独は哀しく連鎖していき――。「僕は君を殺せない」の著者が贈る、サスペンス連作短編集。



