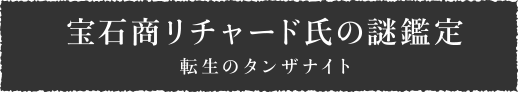
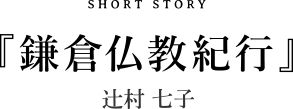
古都・鎌倉を訪れたリチャードと正義。仕事を終えたリチャードは、
突然ある古刹に立ち寄ると言って――!?
突然ある古刹に立ち寄ると言って――!?
『鎌倉仏教紀行』
宝石商のリチャード氏のお得意さまの所在地は、なにも日本には限らない。俺が行ったこともない国の、名前も聞いたことのない地域でも、あの美しい男はしっかりと商売をしている。はずだ。そういう風に想像していた。逆にいうと、近所にそういう場所があるとは考えていなかったわけで、突然の関東地方弾丸旅行を、俺は不思議な感慨と共に体験した。美貌の店主とゆくジャガーの旅だ。
目的地は鎌倉である。
車で二時間、高速道路を走った後、俺はリチャードの後ろから荷物もちになって軽い山登りをした。まかせておけ。こういう時のために男子大学生が宝石屋でアルバイトなんかしているのだ。街並みを一望する山頂に建てられた別荘は、別世界のように静かな日本家屋なのだが、あちこちに防犯用の人感センサーがばっちりあり、床暖房も完備だった。過去と未来が交差している。三時ごろまでお茶室で猫の遊び相手を務めてから、俺は店主とともに異世界のような屋敷を後にした。リチャードを呼んだ和服のおじいさまは、お手伝いさんと一緒に、車いすの上から俺たちに手を振ってくださった。彼には両足の膝から下がなかった。
ジャガーの助手席で外を眺めていると、風情のある古都ですねとリチャードが言った。その言葉のほうに俺は『風情』を感じてしまうが、確かに鎌倉は古い街だ。
「いいくにつくろう鎌倉幕府だもんな。あっ、えーと、いいくにっていうのはな」
「なくようぐいすも存じ上げておりますよ。日本語特有の愉快な詩ですね」
「詩……? あれは詩かなあ……?」
ちょっと寄り道、というリチャードの言葉でたどりついたのは、古刹の駐車場だった。鎌倉名物の大仏さまのおわすところである。中学校の修学旅行生がわんさといた。車から降りたリチャードに気づくと、珍しい動物でも見つけたような笑顔で、津波のように押し寄せてくる。俺はにわか仕立てのボディガードになり、引率の先生が注意しにやってくるまで、麗しの男を無限こども地獄から守った。ちょっと愉快な地獄だったが、際限がなかったので疲れる。
「ちょっと意外だな。わざわざ観光地に来るタイプじゃないと思ってたよ」
「一度シャウルとここに来たことがあります」
答えになっているような、なっていないような言葉だった。日本に来たばかりの頃です、とリチャードは続ける。なるほど、今日のお客さまはシャウルさんのお知り合いだったのかもしれない。
参拝者向けの『大仏』という看板の下には、ビッグ・ブッダというローマ字の解説があった。確かにビッグなブッダである。衆生の話に耳を傾けるように、下を向いて耳を澄ましている大仏さまに一礼すると、リチャードはそのまま境内の右側に歩を進めた。白砂の上をしゃくしゃく進が、他に人気のない場所だ。庭園でもあるのだろうか。
「正義」
リチャードが促したのは、俺の顔くらいの高さの石碑だった。ブッダではなく、ふつうの男性の顔が、青い石にほられている。
「……これ、珍しい石なのか?」
「違います。この人をご存知ですか。スリランカ人ですよ」
男性の顔の下を見ると、確かにシャウルさん風の名前が書かれていた。『ジャヤワルデネ前大統領』。もしかしてこの人か。リチャードが以前言っていた、スリジャヤワルダナプラコッテという、おそろしく長い都市名の語源になった人は。確認すると、リチャード先生のお返事はグッフォーユーだった。当たりらしい。でも解せない。どうしてスリランカの過去の大統領の石碑が、鎌倉の大仏さまのお膝元に?
リチャードは俺の質問を見越したように、解説を始めてくれた。
「スリランカは敬虔な仏教国として知られた国です。もちろんヒンドゥイズムやイスラームに帰依した人々も存在しますが、最大多数派は仏教です。そして親日的な国家でもあります」
親日。ありがたい話だ。ODAとか、そういう理由だろうか。リチャードは首を横に振り、少し残念そうな顔をした。
「あなたはいわゆる『戦後の日本史』をどの程度ご存知ですか?」
一般常識程度、と俺が気まずい顔で告げると、リチャードは少し残念そうな顔で微笑んだ。
「『それほど親しんではこなかった』ということですね。簡単にお話すると、戦後のサンフランシスコ講和条約において、日本がアメリカの支配下を離れる後押しをした国家が、スリランカでした。当時の彼は確か、大統領ではなく蔵相であったと思いますが」
中学校で習った領域の話だ。ポツダム宣言を受け入れた後の日本は、しばらくアメリカの占領下だったが、講和条約を経て独立、国際社会に復帰した。そういう時期の話のはずである。だというのなら。
「それはかなり、恩人っていうか、恩国だな……?」
「ええ。そして彼は死後、自分の右の角膜をスリランカ人に、左の角膜は日本人にという遺言をのこして亡くなりました」
自分の角膜を、別々の国の人間に。
もうそれは親日国とかそういうこと以前に、その人個人が、かなり日本を好きでいてくれたのだろう。九十年代の話だという。そんなに前のことでもないのに、初耳すぎてちょっと驚く。スリジャヤワルダナプラコッテという首都の名前の方が、長すぎるということでまたネタになるくらいだ。
石碑にほりこまれた細面の男性の顔は、迷いのない眼差しで前を見ていた。そしてその下に、三か国語でありがたい言葉が彫り込まれている。『人はただ愛によってのみ 憎しみを超えられる 人は憎しみによっては 憎しみを越えられない』。含蓄のあるお言葉である。これも仏教の言葉らしいが、キリスト教の言葉と言われたら信じてしまいそうな雰囲気もある。汎用性の高そうな語句だ。宗教の理念というのは、行きつくところまで行くと、どれも似通ったりするものなのだろうか。
「……上から日本語、シンハラ語、英語だな」
「グッフォーユー。おや、シンハラ語が読めますか」
「全然読めないよ。読めないけど」
何となく、シンハラ文字だなということだけはわかるようになった。シャウルさんの高速メールザッピングを何度も垣間見ているせいだろう。英語のメールの方が多いが、時々あのかたつむりのような形の文字もあらわれて、そういえばこの人はスリランカの人だったっけなと思い出させてくれる。そうでなければ彼はただの羊羹の好きなダンディなおじさんだ。あの人はいつも俺と流暢な日本語で喋ってくれるのだ。当たり前のように。
「……少しでも読めたらいいなあ。難しそうだけどさ。アルファベットならまだ、何となく想像がつくけどさ、なんて発音するのかもわからない」
すると俺の隣に立っていた男が、魔法のような言葉を口にした。うにゃんうにゃんと歪曲するシンハラ文字にぴったりの、よく響く弦楽器をつまびいたような音を。
涼しい顔をしている美貌の店主を、俺はまじまじと見てしまった。
「今のは、これを、読んだ音……?」
「その通りです。何ですかその顔は」
「いや、お前が美しいのは知ってたけど……言葉まで美しいんだなって……何か空が青いのに感動したような気分だ」
「はあ、左様で、ございますか」
「ごめんって。あのさ、よければもう一回言ってくれないかな」
できればもう少しゆっくり、と俺が繰り返すと、リチャードは苦笑しながらつきあってくれた。俺は全く語学の天才タイプではないのだが、教え上手な先生のおかげで、三回目くらいで聞き取れるようになってきた。
ワイラヤ、ワイラェン、ノワ、マイトリェン、サンシディー。
こういう時には日本語ではなく英語と照らし合わせて考えるのが便利だ。中学高校と品詞分解をひたすらやらされてきたおかげで、英語を分析する能力ならばそこそこ培われている自負がある。
ワイラヤとかワイラェンが『憎しみ』関係で、この『マイトリェン』が『慈しみ』なのではないだろうか。リチャードは頷きながら俺の推理を聴いてくれた。正解らしい。でもグッフォーユーはもらえなかった。そのかわりに、しかし、と補足が入る。
「『マイトリ』という語を単体で考えるのなら、これは『慈しみ』というより『友情』に近い言葉かもしれません。サンスクリット系の語源をもつ言葉ですので、シンハラ語のみならず、南アジアには数多くこの言葉を語彙としてもつ言語が存在しますが、『親しみ深さ』あるいは『無条件の友情』のようなニュアンスを持つ言葉ですよ」
憎しみは憎しみによっては克服できない。たが無条件の、親しみ深い、友情のようなものがあれば、克服できると、仏教の経典には書いてあるということか。
「……うーん。深い。深いなあ」
「お腹でも減ったのですか。いきなり投げやりな顔になりましたよ」
「そうじゃないけどさ。仏教の言葉とは別のところに、ちょっと感動した」
この鎌倉の大仏さまは、もう一千年近くここにお座りになって、下界を見下ろしているはずだ。いろいろな物事が目に入ることだろう。だが。
この境内の中でイギリス人にシンハラ語を教えてもらった日本人は、俺が初めてなのではないだろうかと。
そんなことを考えて感動した、と俺が告げると、リチャードは呆れたように嘆息した。
「ここは国際的な観光地ですよ。あなたが思っているよりも、祈るためにここへやってくる仏教国の方は多いのです。シャウルがこの場所を知っていたのも、過去に来日した顧客の案内人をつとめたからでしょう。あなたで三十人目ですと、あちらにおわすビッグ・ブッダは仰せになるかもしれませんよ」
言われてみれば、確かにその通りだ。ただ俺は、ちょっと珍しいところにやってきて、自分の上司が母国語ではない不思議な言葉を教えてくれたのが、特別な体験のようでとても嬉しかったのだ。本当に初めての人だったかどうかは、正直どっちでもいい。でも俺は嬉しかった。リチャードが俺をここに連れてきてくれたことも含めて。
それだけの話だと俺が告げると、リチャードはちょっと硬直した後、大仏の方にむかって高速さかさか歩きで去ってしまった。観光でもしたかったのだろうか。あいつは自分の存在が『動く観光地』みたいなものだとちゃんと認識しているのだろうか。案の定大仏さまの真下でわいわいしていた小学生たちが、野生のパンダでも見つけたように集い、身動きが取れなくなっていたので、俺は再び適当に人払いをし、駐車場に向かって上司を先導した。
「気をつけろよ。子どもってパワフルだぞ。ああ、勝手に出てきちゃったけど大丈夫か」
「……結構です。今日は急に、大仏の顔が見たくなっただけですので」
「へえ、そういうこともあるんだな。そうだ、おみやげ買って帰らないか? 鎌倉って言ったら、お茶請けの定番で有名なバターサブレの老舗が」
食い気味の「では行きましょう」というお返事に、俺は笑いをかみ殺した。
その後、俺は戦時中のスリランカはまだイギリス領だったことを思い出した。あれからまだ百年も経っていなのに、俺はイギリス人の上司とスリランカの話をして、和気あいあいと過ごしている。
ばあちゃんが今の俺を目にしたら、きっと俺には想像もつかないような理由でびっくりすることがたくさんあるに違いない。もう俺が勝手に想像するしかない事柄ではあるのだが、今でも変わらず彼女は俺の大事な人だから、そういうのもありだろう。
そんなことを思いながら、俺は町田の実家に顔を出したついでに、かわいらしい鳩の形のビスケットをお供えして、鈴を鳴らした。いいくにつくろう鎌倉幕府は千年近く前の話だが、できれば世界中の国が『いいくに』で、仲良しであってくれたらと願うのは、世界中、いつの時代のどの国の人でも同じだろう。
目的地は鎌倉である。
車で二時間、高速道路を走った後、俺はリチャードの後ろから荷物もちになって軽い山登りをした。まかせておけ。こういう時のために男子大学生が宝石屋でアルバイトなんかしているのだ。街並みを一望する山頂に建てられた別荘は、別世界のように静かな日本家屋なのだが、あちこちに防犯用の人感センサーがばっちりあり、床暖房も完備だった。過去と未来が交差している。三時ごろまでお茶室で猫の遊び相手を務めてから、俺は店主とともに異世界のような屋敷を後にした。リチャードを呼んだ和服のおじいさまは、お手伝いさんと一緒に、車いすの上から俺たちに手を振ってくださった。彼には両足の膝から下がなかった。
ジャガーの助手席で外を眺めていると、風情のある古都ですねとリチャードが言った。その言葉のほうに俺は『風情』を感じてしまうが、確かに鎌倉は古い街だ。
「いいくにつくろう鎌倉幕府だもんな。あっ、えーと、いいくにっていうのはな」
「なくようぐいすも存じ上げておりますよ。日本語特有の愉快な詩ですね」
「詩……? あれは詩かなあ……?」
ちょっと寄り道、というリチャードの言葉でたどりついたのは、古刹の駐車場だった。鎌倉名物の大仏さまのおわすところである。中学校の修学旅行生がわんさといた。車から降りたリチャードに気づくと、珍しい動物でも見つけたような笑顔で、津波のように押し寄せてくる。俺はにわか仕立てのボディガードになり、引率の先生が注意しにやってくるまで、麗しの男を無限こども地獄から守った。ちょっと愉快な地獄だったが、際限がなかったので疲れる。
「ちょっと意外だな。わざわざ観光地に来るタイプじゃないと思ってたよ」
「一度シャウルとここに来たことがあります」
答えになっているような、なっていないような言葉だった。日本に来たばかりの頃です、とリチャードは続ける。なるほど、今日のお客さまはシャウルさんのお知り合いだったのかもしれない。
参拝者向けの『大仏』という看板の下には、ビッグ・ブッダというローマ字の解説があった。確かにビッグなブッダである。衆生の話に耳を傾けるように、下を向いて耳を澄ましている大仏さまに一礼すると、リチャードはそのまま境内の右側に歩を進めた。白砂の上をしゃくしゃく進が、他に人気のない場所だ。庭園でもあるのだろうか。
「正義」
リチャードが促したのは、俺の顔くらいの高さの石碑だった。ブッダではなく、ふつうの男性の顔が、青い石にほられている。
「……これ、珍しい石なのか?」
「違います。この人をご存知ですか。スリランカ人ですよ」
男性の顔の下を見ると、確かにシャウルさん風の名前が書かれていた。『ジャヤワルデネ前大統領』。もしかしてこの人か。リチャードが以前言っていた、スリジャヤワルダナプラコッテという、おそろしく長い都市名の語源になった人は。確認すると、リチャード先生のお返事はグッフォーユーだった。当たりらしい。でも解せない。どうしてスリランカの過去の大統領の石碑が、鎌倉の大仏さまのお膝元に?
リチャードは俺の質問を見越したように、解説を始めてくれた。
「スリランカは敬虔な仏教国として知られた国です。もちろんヒンドゥイズムやイスラームに帰依した人々も存在しますが、最大多数派は仏教です。そして親日的な国家でもあります」
親日。ありがたい話だ。ODAとか、そういう理由だろうか。リチャードは首を横に振り、少し残念そうな顔をした。
「あなたはいわゆる『戦後の日本史』をどの程度ご存知ですか?」
一般常識程度、と俺が気まずい顔で告げると、リチャードは少し残念そうな顔で微笑んだ。
「『それほど親しんではこなかった』ということですね。簡単にお話すると、戦後のサンフランシスコ講和条約において、日本がアメリカの支配下を離れる後押しをした国家が、スリランカでした。当時の彼は確か、大統領ではなく蔵相であったと思いますが」
中学校で習った領域の話だ。ポツダム宣言を受け入れた後の日本は、しばらくアメリカの占領下だったが、講和条約を経て独立、国際社会に復帰した。そういう時期の話のはずである。だというのなら。
「それはかなり、恩人っていうか、恩国だな……?」
「ええ。そして彼は死後、自分の右の角膜をスリランカ人に、左の角膜は日本人にという遺言をのこして亡くなりました」
自分の角膜を、別々の国の人間に。
もうそれは親日国とかそういうこと以前に、その人個人が、かなり日本を好きでいてくれたのだろう。九十年代の話だという。そんなに前のことでもないのに、初耳すぎてちょっと驚く。スリジャヤワルダナプラコッテという首都の名前の方が、長すぎるということでまたネタになるくらいだ。
石碑にほりこまれた細面の男性の顔は、迷いのない眼差しで前を見ていた。そしてその下に、三か国語でありがたい言葉が彫り込まれている。『人はただ愛によってのみ 憎しみを超えられる 人は憎しみによっては 憎しみを越えられない』。含蓄のあるお言葉である。これも仏教の言葉らしいが、キリスト教の言葉と言われたら信じてしまいそうな雰囲気もある。汎用性の高そうな語句だ。宗教の理念というのは、行きつくところまで行くと、どれも似通ったりするものなのだろうか。
「……上から日本語、シンハラ語、英語だな」
「グッフォーユー。おや、シンハラ語が読めますか」
「全然読めないよ。読めないけど」
何となく、シンハラ文字だなということだけはわかるようになった。シャウルさんの高速メールザッピングを何度も垣間見ているせいだろう。英語のメールの方が多いが、時々あのかたつむりのような形の文字もあらわれて、そういえばこの人はスリランカの人だったっけなと思い出させてくれる。そうでなければ彼はただの羊羹の好きなダンディなおじさんだ。あの人はいつも俺と流暢な日本語で喋ってくれるのだ。当たり前のように。
「……少しでも読めたらいいなあ。難しそうだけどさ。アルファベットならまだ、何となく想像がつくけどさ、なんて発音するのかもわからない」
すると俺の隣に立っていた男が、魔法のような言葉を口にした。うにゃんうにゃんと歪曲するシンハラ文字にぴったりの、よく響く弦楽器をつまびいたような音を。
涼しい顔をしている美貌の店主を、俺はまじまじと見てしまった。
「今のは、これを、読んだ音……?」
「その通りです。何ですかその顔は」
「いや、お前が美しいのは知ってたけど……言葉まで美しいんだなって……何か空が青いのに感動したような気分だ」
「はあ、左様で、ございますか」
「ごめんって。あのさ、よければもう一回言ってくれないかな」
できればもう少しゆっくり、と俺が繰り返すと、リチャードは苦笑しながらつきあってくれた。俺は全く語学の天才タイプではないのだが、教え上手な先生のおかげで、三回目くらいで聞き取れるようになってきた。
ワイラヤ、ワイラェン、ノワ、マイトリェン、サンシディー。
こういう時には日本語ではなく英語と照らし合わせて考えるのが便利だ。中学高校と品詞分解をひたすらやらされてきたおかげで、英語を分析する能力ならばそこそこ培われている自負がある。
ワイラヤとかワイラェンが『憎しみ』関係で、この『マイトリェン』が『慈しみ』なのではないだろうか。リチャードは頷きながら俺の推理を聴いてくれた。正解らしい。でもグッフォーユーはもらえなかった。そのかわりに、しかし、と補足が入る。
「『マイトリ』という語を単体で考えるのなら、これは『慈しみ』というより『友情』に近い言葉かもしれません。サンスクリット系の語源をもつ言葉ですので、シンハラ語のみならず、南アジアには数多くこの言葉を語彙としてもつ言語が存在しますが、『親しみ深さ』あるいは『無条件の友情』のようなニュアンスを持つ言葉ですよ」
憎しみは憎しみによっては克服できない。たが無条件の、親しみ深い、友情のようなものがあれば、克服できると、仏教の経典には書いてあるということか。
「……うーん。深い。深いなあ」
「お腹でも減ったのですか。いきなり投げやりな顔になりましたよ」
「そうじゃないけどさ。仏教の言葉とは別のところに、ちょっと感動した」
この鎌倉の大仏さまは、もう一千年近くここにお座りになって、下界を見下ろしているはずだ。いろいろな物事が目に入ることだろう。だが。
この境内の中でイギリス人にシンハラ語を教えてもらった日本人は、俺が初めてなのではないだろうかと。
そんなことを考えて感動した、と俺が告げると、リチャードは呆れたように嘆息した。
「ここは国際的な観光地ですよ。あなたが思っているよりも、祈るためにここへやってくる仏教国の方は多いのです。シャウルがこの場所を知っていたのも、過去に来日した顧客の案内人をつとめたからでしょう。あなたで三十人目ですと、あちらにおわすビッグ・ブッダは仰せになるかもしれませんよ」
言われてみれば、確かにその通りだ。ただ俺は、ちょっと珍しいところにやってきて、自分の上司が母国語ではない不思議な言葉を教えてくれたのが、特別な体験のようでとても嬉しかったのだ。本当に初めての人だったかどうかは、正直どっちでもいい。でも俺は嬉しかった。リチャードが俺をここに連れてきてくれたことも含めて。
それだけの話だと俺が告げると、リチャードはちょっと硬直した後、大仏の方にむかって高速さかさか歩きで去ってしまった。観光でもしたかったのだろうか。あいつは自分の存在が『動く観光地』みたいなものだとちゃんと認識しているのだろうか。案の定大仏さまの真下でわいわいしていた小学生たちが、野生のパンダでも見つけたように集い、身動きが取れなくなっていたので、俺は再び適当に人払いをし、駐車場に向かって上司を先導した。
「気をつけろよ。子どもってパワフルだぞ。ああ、勝手に出てきちゃったけど大丈夫か」
「……結構です。今日は急に、大仏の顔が見たくなっただけですので」
「へえ、そういうこともあるんだな。そうだ、おみやげ買って帰らないか? 鎌倉って言ったら、お茶請けの定番で有名なバターサブレの老舗が」
食い気味の「では行きましょう」というお返事に、俺は笑いをかみ殺した。
その後、俺は戦時中のスリランカはまだイギリス領だったことを思い出した。あれからまだ百年も経っていなのに、俺はイギリス人の上司とスリランカの話をして、和気あいあいと過ごしている。
ばあちゃんが今の俺を目にしたら、きっと俺には想像もつかないような理由でびっくりすることがたくさんあるに違いない。もう俺が勝手に想像するしかない事柄ではあるのだが、今でも変わらず彼女は俺の大事な人だから、そういうのもありだろう。
そんなことを思いながら、俺は町田の実家に顔を出したついでに、かわいらしい鳩の形のビスケットをお供えして、鈴を鳴らした。いいくにつくろう鎌倉幕府は千年近く前の話だが、できれば世界中の国が『いいくに』で、仲良しであってくれたらと願うのは、世界中、いつの時代のどの国の人でも同じだろう。


