
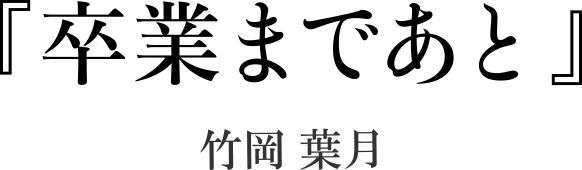
咲良としての人生を歩みだした私。期待、不安、でも、一人じゃない。
『卒業まであと』
シャープペンシルの芯を出して、プリントの名前欄に『二年B組円城咲良』と書く。
(あ、しまった。二年じゃない、三年だ……)
私は心の中で舌を出し、学年の部分を書き直す。
手書きの文書というのは、こういう時に面倒くさい。心の底からWORDが使いたいと思う。
女子高生、円城咲良の中の人として生きていくこととなった私だけど、その咲良も先月めでたく高三となったのだ。
「──どうした円城。一人か?」
私は、プリントから顔を上げた。
教室の出入り口に、白衣姿の若手教師が顔を出していた。
「鹿山先生」
こいつの名前は、いま言った通り鹿山守という。昨年度から持ち上がりで担任となった社会科教師で、私がOL市ノ瀬桜だった頃を知る、貴重な協力者だ。
放課後の鹿山は、生徒を追い出すべく、見回りの最中のようだ。本当に先生のお仕事って多岐にわたる。
「数学の課題が、見事に再提出になりまして」
「最悪だな。お前、国立志望じゃなかったのか」
鹿山が呆れた顔で、居残り中の私のところにやってくる。
「浪人するつもりはないんだろ」
「そんなの当たり前でしょ。理系科目はまだ始めたばっかりなんだから、大目に見てよ」
「間に合えばいいんだけどな。ちょっと見せてみろ」
鹿山は、私が解こうとしていたプリントを手に取る。
「……社会の先生でも、数学は教えられるの?」
「まあ、この程度の基礎レベルならな」
プリントから視線を外さず、鹿山。そういうものなのか。私は卒業してから、仕事に関係ないものはほとんど忘れちゃったわ。
私はそんな鹿山の、賢そうな額のあたりを眺める。
私たちが、現役の高校生だった頃。こいつはそれはもう冴えない読書好きの文系小僧であった。十年の歳月は、奴に人並みの社会性と、そこそこのファッションセンスを与えたもうたようだ。
「好きだよ、鹿山」
鹿山が人のプリントを握りしめて、突き破りそうになった。ちょっとやめてよ。提出するんだからそれ。
「お前、お前……!」
そんなに俺を社会的に殺す気かと、言わんばかりだった。
「いやね、考えたんだけどね、私がこうして好きだなんだ言うのは、女子高生の戯れ言でじゅうぶん許される範囲内だと思うのよ。他の子たちだって、言ってるわけだし」
言ってるよね、実際。この間も新一年の子に呼び出されてるの、知ってるからね。そんな無言のプレッシャーを、かけてみたりもする。
「ようはね、鹿山が相手にしなきゃいいわけよ。簡単な話だったのよ」
「……何をどうすると、そこまで自己中な理論を組み立てられるんだ……」
「だってさあ」
私はシャーペンを持ったまま、机に頬杖をつく。
「……この年で秘めた恋、しかも片思いとなると、錆び付きが心配でね。たまには運転して、エンジンが動くか確認したくなるというか」
その鹿山が、ちらりと私のことを見た。
「……止まりそうなのか?」
「なに、焦ってるの?」
鹿山は、言葉に詰まった感じで目を背ける。あはは、慌ててくれるなら悪くないかも。
向こうが吐くものがため息だったとしても、私はちょっと嬉しかった。
「……女子高生を笠に着るなら、もうちょっと初々しくしてくれ」
「それは無理かもねえ」
何せ二回目なもので。
ゆるりと笑う私の耳に、どこかからトランペットの音出しが響いてくる。
学校という箱庭に音楽はあふれ、教える人、教えられる人がいて。私は今日も生きていく。
(あ、しまった。二年じゃない、三年だ……)
私は心の中で舌を出し、学年の部分を書き直す。
手書きの文書というのは、こういう時に面倒くさい。心の底からWORDが使いたいと思う。
女子高生、円城咲良の中の人として生きていくこととなった私だけど、その咲良も先月めでたく高三となったのだ。
「──どうした円城。一人か?」
私は、プリントから顔を上げた。
教室の出入り口に、白衣姿の若手教師が顔を出していた。
「鹿山先生」
こいつの名前は、いま言った通り鹿山守という。昨年度から持ち上がりで担任となった社会科教師で、私がOL市ノ瀬桜だった頃を知る、貴重な協力者だ。
放課後の鹿山は、生徒を追い出すべく、見回りの最中のようだ。本当に先生のお仕事って多岐にわたる。
「数学の課題が、見事に再提出になりまして」
「最悪だな。お前、国立志望じゃなかったのか」
鹿山が呆れた顔で、居残り中の私のところにやってくる。
「浪人するつもりはないんだろ」
「そんなの当たり前でしょ。理系科目はまだ始めたばっかりなんだから、大目に見てよ」
「間に合えばいいんだけどな。ちょっと見せてみろ」
鹿山は、私が解こうとしていたプリントを手に取る。
「……社会の先生でも、数学は教えられるの?」
「まあ、この程度の基礎レベルならな」
プリントから視線を外さず、鹿山。そういうものなのか。私は卒業してから、仕事に関係ないものはほとんど忘れちゃったわ。
私はそんな鹿山の、賢そうな額のあたりを眺める。
私たちが、現役の高校生だった頃。こいつはそれはもう冴えない読書好きの文系小僧であった。十年の歳月は、奴に人並みの社会性と、そこそこのファッションセンスを与えたもうたようだ。
「好きだよ、鹿山」
鹿山が人のプリントを握りしめて、突き破りそうになった。ちょっとやめてよ。提出するんだからそれ。
「お前、お前……!」
そんなに俺を社会的に殺す気かと、言わんばかりだった。
「いやね、考えたんだけどね、私がこうして好きだなんだ言うのは、女子高生の戯れ言でじゅうぶん許される範囲内だと思うのよ。他の子たちだって、言ってるわけだし」
言ってるよね、実際。この間も新一年の子に呼び出されてるの、知ってるからね。そんな無言のプレッシャーを、かけてみたりもする。
「ようはね、鹿山が相手にしなきゃいいわけよ。簡単な話だったのよ」
「……何をどうすると、そこまで自己中な理論を組み立てられるんだ……」
「だってさあ」
私はシャーペンを持ったまま、机に頬杖をつく。
「……この年で秘めた恋、しかも片思いとなると、錆び付きが心配でね。たまには運転して、エンジンが動くか確認したくなるというか」
その鹿山が、ちらりと私のことを見た。
「……止まりそうなのか?」
「なに、焦ってるの?」
鹿山は、言葉に詰まった感じで目を背ける。あはは、慌ててくれるなら悪くないかも。
向こうが吐くものがため息だったとしても、私はちょっと嬉しかった。
「……女子高生を笠に着るなら、もうちょっと初々しくしてくれ」
「それは無理かもねえ」
何せ二回目なもので。
ゆるりと笑う私の耳に、どこかからトランペットの音出しが響いてくる。
学校という箱庭に音楽はあふれ、教える人、教えられる人がいて。私は今日も生きていく。


