宝石の歌
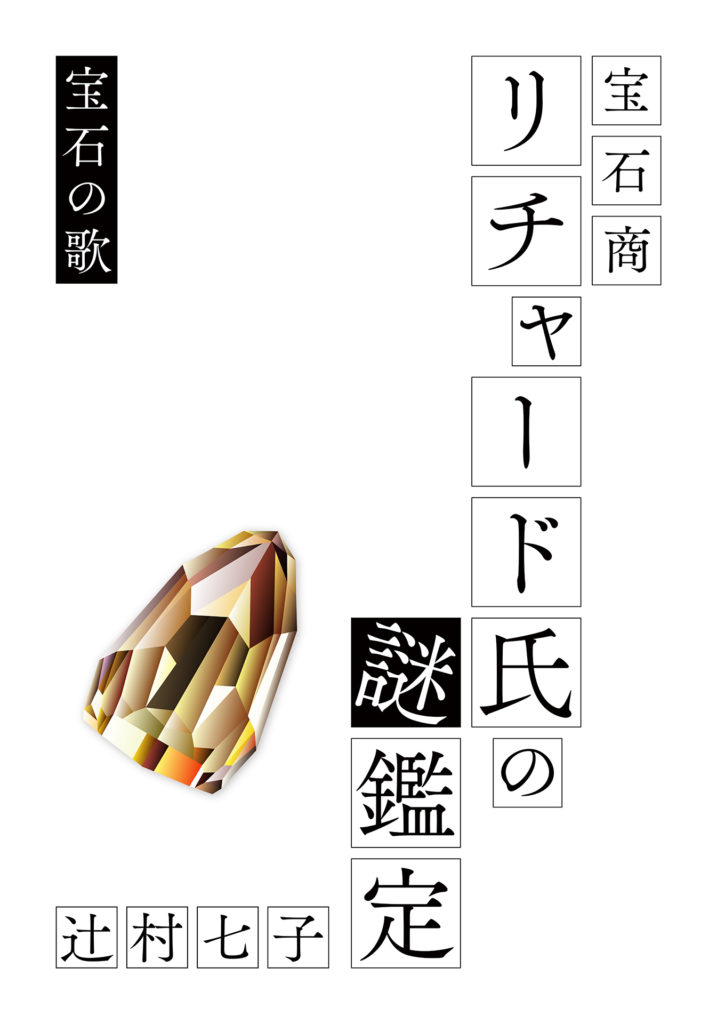
オペラハウスにほど近いホテルに戻り、ベッドに身を投げると笑い声が聞こえた。
「そんなに疲れた?」
「そうでもないけど、ずっと座ってたからお尻がかたくなっちゃった。ストレッチ」
「じゃあ、せめて首飾りは外さないと」
そっと滑り込んできた長い指が、ヨアキムの首から金の金具を外した。
たくさんのトパーズをぶどうの房のようにぶらさげたネックレスは、彼からの贈り物だった。揃いのイヤリングと指輪もついでに外して手渡す。彼は笑った。
「そっちの方が楽そうでいいね」
「昔のお姫さまたちの苦労がわかってきた気がする」
「でも君は宝石が似合うよ。すごく似合う」
カラーを外してジャケットを脱いだ彼は、ベッドの隣に寝そべると、猫のように体を伸ばした。二人で寝そべっても、上下左右どの角度からも手足がはみださない広さのベッドにも、もう慣れて久しい。
長いホリデーみたいなものだからと。
最初に説明された時、何も思わなかった。そういうものかなと感じただけだった。強いていうのなら、嬉しかった。
今までの人生の中で、彼が『ホリデー』と呼べるような休息の日々を得たことがあるようには思えなかったので、その手伝いができるなら、嬉しかった。
今夜のオペラの演目は『ファウスト』。初めて耳にする単語だった。仮にそれが『ファースト』が訛ったものであるなら、続編に『セカンド』や『サード』もあるのか、と尋ねると、実はイレブンスまである、と彼は真面目な顔で答えてくれた。背中を軽くどつくと、まるで学生のようにけらけらと笑った。悪魔からプレゼントされた宝石を、そうとは知らず清純なヒロインが次々と身につけてゆき、「まるでお姫さまよ」と喜びながら歌うアリアが一つの聴かせどころで、ヨアキムはうっとりと目を閉じて聴きほれた。隣に腰かける男に身をもたせかけながら。
その時の写真が、既にSNSにアップされているのは知っていた。帰り道のリムジンで確認済みである。もちろん自分たちで掲載したものではない。
隠し撮りである。
見るべきではないから見ない、と最初は割り切っていたものの、あまりに膨大な分量の情報が投稿され共有され適当なドラマをつけられ消費されてゆくので、そのうちある程度は『仕事』として観測することにした。度を超えたものは、広がる前に「法的な手段を講じる」とアプローチすることで抹消可能だからである。とはいえそこまでのものが広まったことは、幸運なことに一度もなかった。幸運なことに、と声もなく頭の中で繰り返すと、唇にいびつな笑みが浮かんできた。
マットレスの隣に寝そべっている彼が、少しだけ体を起こした。
「そういえばさあ」
さりげない声色だったが、何か大きなことを切り出されるのはすぐにわかった。彼は声のトーンを自在に操れると自負しているし実際にそういう面もあったが、何か月も毎日毎日同じ声を聞き続ければ、微細な違いもわかるようになるものである。
やわらかな茶色の瞳を細め、彼は笑っていた。
「君は何が好き?」
「……何って?」
「宝石とか」
「これ以上もらえないよ。身に着けるところがなくなっちゃう」
「『とか』だから、別に宝石じゃなくてもいいよ」
含みのある言葉だった。
ヨアキムは変化球を投げられるのが好きだったが、それはうまく投げ返す前提の話である。愛撫のように言葉のキャッチボールを愉しめる関係は心地よかったが、今回の球は投げ返す角度を間違えればひどいことになりかねない。彼も、自分も。
しばらく考えているうちに、彼は質問を重ねてきた。
「君は何が好き?」
時間稼ぎのようなキスをした後に、ヨアキムは微笑んだ。好きなもの。そんなものは決まっていた。
「あなたが好き。世界で一番好きだよ、可愛いジェッフィ」
「ありがと。でも知ってる」
「教育の甲斐があったね」
「昔の人の言葉を引こうか。『深淵をのぞきこむ者は、怪物と化さないように注意せよ。なぜなら深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ』」
「どういうこと?」
「君が僕を見つめてるのと同じくらい、僕も君を見つめてるってこと」
「ネットフリックスの見すぎ」
「君の瞳ほどは見てない」
「めんどくさいこと言うー」
「はいはいお互いさま、お互いさま」
それでしばらく、会話は棚上げになった。
二時間後、ヨアキムが跳びはねるように目覚めると、隣でうとうとしていた彼もつられて起きてしまった。嫌な汗で体がびしょびしょになっていて、全力疾走で捕食者から逃げたように息も上がっている。
「どうしたの」
「……何でもない。ちょっと、嫌な夢を見て」
「こっちに来て。ハグさせて」
空耳をしたのかと思ったが、そうではなかった。
彼はいつかの自分そっくりの声で、隣にいる相手を慰めているのだった。
「ルームサービスとる? 飲みに行こうか」
微笑みがあまりにも優しくて、しばらく何も言えなくなった後、口が動いた。
「あなたは……何で平気なの?」
何が? と彼は尋ねなかった。自明のことである。
世界有数の富豪に属する男は、ややあってから朗らかに微笑んだ。
「そうだねえ……生まれた時から『永遠に耳元で雑音が聴こえますが、無視しましょう』って教育を受けてきたせいかな。これでも僕は偉大なるオナラブル・ジェフリーだから、一般人よりは耐性があると思う」
「違う、ごめんなさい。今の質問はひどかった」
「そうでもないと思うけど」
「別の質問をさせて」
どうぞ、と促すと、彼は抱きしめてきた。
本当に、こういうことが自然とできる人が、どうして自分と一緒にいるのか。
考えれば考えるほどわからなくなる迷宮に迷い込みながらも、口は動いた。
「あなたは……どうして私を恨まないの」
多少、間の抜けた沈黙が訪れた。
ブーンという空調機の音が微かに聞こえる中、しばらく経った後、彼は首を傾げた。
「うーん?」
「ジェッフィ、真面目に答えて」
「真面目に答えようとして考えてるよ。でも前提条件がおかしい。何で僕が君を恨むの? 感謝するならまだしも」
「それは」
言葉に詰まっても、彼はそれ以上何も言おうとしなかった。それは。それは。頭の中を無数の言葉がガーランドのように回る。
何とかして絞り出した声は、何故か震えていた。
「……私があなたに、あげられるものと、私があなたから奪ってるものの、種類が全然違うから」
返事は笑い声だった。
真面目に話しているのよ、とむくれた顔をすると、彼はいつものように適切なタイミングで笑いをおさめ、しばらく足をパタパタさせた後、微笑みながら告げた。温和で、理知的な笑みだった。
「君は僕に水と酸素と黄金をくれた。同じタイミングで、もしかしたら僕たちのまわりには雑音が少しだけ増えたかも。でも水と酸素と黄金と、雑音って、そもそも比較可能?」
「……オーバー」
「オーバー? 個人的には全然だね。だから僕は君を恨んでないし、恨もうと思ったこともない。もっといろいろなものをあげたいと思うし、君から与えて欲しいとも思う。強欲だよ、僕は」
「何でもあげるよ。まだあげてないものがあればだけど」
「おやファウスト博士、メフィストフェレスの前でとんでもないことを仰いましたね」
「私はあんなむっつりインテリじいさんとは違うから」
ごろりと寝返りをうってベッドから出ようとすると、誰かの手が柵のように降りてきた。
なあに? と振り向くような形で見上げると、真上に彼の顔があった。
「君の時間をくれない? 僕に。もっと」
寝乱れた姿の彼は、しかしいつになく、真剣な表情をしていた。
言わんとすることを悟るのは簡単だった。受け止めることほど難しくはない。
少し考えたような素振りを見せた後、ヨアキムはぐるりと瞳を回し、大きく笑った。
「そんなもの、幾らでもあげるし、今だってシェアしてる」
彼の返答は沈黙だった。うまくかわせただろうかと思っていると、彼は微笑まず、少し頭をかいた。
「うーん、質問の仕方を間違ったかな」
「ジェッフィ」
「ちゃんと質問しなかった僕がいけなかった。そのままの格好でいいから立ってくれる?」
「ジェッフィ」
「世の中には相手が立ってくれないと言えなかったり、できなかったりすることもあってさ」
「ジェッフィ!」
今度こそ、彼は獲物を逃すつもりはないようだった。
今までにも同じトピックを持ち掛けられたことはあった。だがその都度のらりくらりと逃げていたし、逃げることを許容されてもいた。だがここから先はそうはいかないと、彼は言っているようだった。
うかうかしているとベッドサイドに跪いてしまいそうな男を留め、ヨアキムは何とか告げた。
「……ちょっと私も、時間がほしい。考える時間が」
いいかなと尋ねると、答えは明快な「もちろん」だった。
ホテルのベッドで夢を見た。誰かがオペラハウスで聞いたキンキンする歌をうたっていて、その歌に追い立てられるように、数々のジュエリーを身に着けてゆく自分を俯瞰している夢だった。首飾り。腕輪。イヤリング。ティアラ。そんなに付けたら重くて動けなくなるのではないかというくらいの量があり、それでもまだまだつけるものはある。後から後から盆に盛られて運ばれてくるので決してなくなることがないのである。でもそれは最初からわかっていたことではあった。重くて動けないなどと、今更言う気はなかった。だが。
最後の盆に載っていたのは指輪だった。
たった一つきり、虹色に輝く石のセットされた指輪。
ジュエリー人間のようになった自分はおずおずと後ずさりをし、銃を構えた人間をなだめるように両手を前にかざしていた。ちょっとそれは難しい、ちょっとそれはどうなのかしらと告げても、盆は一人でに近づいてくる。
その奥にはにこにこ顔の青年が立っていた。
無限にも思われる富にまみれ、時に溺れかけ、しかしその中をゆうゆうと渡ってゆくことを選んだ青年が。もう青年って年齢でもないわねと考えると、彼は笑った。
それをあげる、と。
子どものような声で言った。
でもこれを渡したら、あなたはもう別の人には同じものをあげられなくなるんだよと、諭しても青年は聞かなかった。あげるから、と微笑むばかりである。もっと他にいろいろ選択肢があるかもしれないし、私は今もらっているぶんでもう十分だから、と言い聞かせようとすると、彼は少し、悲しそうな顔をした。
欲しくないの? と。
俯瞰のカメラマンと化している意識は、その時ジュエリーの怪物と同化した。下方向ではなく目の前に彼がいて、微笑みと共に盆から指輪を持ち上げ、差し出してくる。
そして自分と彼とを囲む世界に、無数のカメラのレンズが光っているのも見えた。バシャバシャバシャというシャッター音はまるで投げつけられる石礫のようで、果たしてその後ろに人間がいるのかいないのかも判然としない。大きな機械に挟まれているような不快感だった。彼もまた同じ思いを味わっているはずなのに、穏やかな微笑みには、恐れも怒りもまるで滲んでいなかった。
いいんだよ、と言われている気がした。
今までの全てを、彼の前でのみ晒すことができ、誰にも裁かれず、ただありのままでいることを許されている気がした。
こういう人なのだと。
こういう人を好きになったのだと理解した時、夢は醒めた。
二度目のベッドでの覚醒は静かだった。隣では彼が再び眠っている。
両手で顔を覆い、ブツブツと呪文のように呟いた。逃げたらいけない、逃げたらいけない、逃げたらいけない、と。
だがそれにも限界がある。
戦略的撤退、という言葉が続いて脳裏をよぎった。
前に進むために、一度退くということである。
何だかいい響きだった。逃避の別の言い方としてぴったりである。
「…………ごめん」
眠りこける彼の額に一度キスをしてから、ヨアキムは身支度を整え始めた。
行くことのできる場所は少なかったが、全く存在しないわけでもなかった。
コール四回で電話は繋がった。
ハロー、というアメリカで耳にするのとは少し響きの違う言葉に、ジェフリーは目を細めた。
「やあハリー。久しぶり。今は大丈夫? ちょっと相談があるんだけど」
『何なりと、私の可愛い弟』
「恋人が逃げちゃった」
『……GPSは?』
「あはは、初手でそれを言われるとつらいなあ」
もちろん追いかけてるよ、とジェフリーは電話口で笑った。
たった一人残された高級ホテルのベッドの上で、半裸の男は肩をすくめ、枕元のジンを呷った。
「何がいけなかったのかな。すごく愛してるし、愛されてるとも思うんだけど。あれかな? 和製英語で言う所のマリッジブルー? それともオペラ鑑賞って、何かの理由で地雷だったりする? 中田くんに相談しておけばよかったな」
『マリッジ、失礼、何色だと?』
「プレ・ウェディング・ジッターズのこと」
『……ああ、ようやく申し込んだのか。おめでとう』
「いや申し込もうとしたら逃げられたんだよ。おめでたくはないです。まだね」
『しかしあの人は、きっとお前と結婚してくれると思うよ』
「僕もそう思ってる。っていうかそうする」
しばらくの沈黙の後、再び口火を切ったのはジェフリーだった。
「あのさ、『貴族だから』って理由でふられそうになったことってある?」
『……すまない、ジェフ、私にはあまり恋愛の経験がない』
「ごめん。そうだよね。でもこういう話をリッキーに振るほど無神経にはなれなくて」
『私にならいいと思ってくれたところに、お前の信頼を感じる。ありがとう』
「とっても真面目なところを本当に信頼してるよ、ハリー」
皮肉るような言葉を、ヘンリーは「ありがとう」と言って受け取った。そういうリアクションをされるとちょっと罪悪感が湧く、とジェフリーが告げて以来、いつもそうするようになったので、兄なりのジョークの返礼であることを弟はわかっていた。
何かもう一言くらい返したい、と弟が思っている間に、長兄は言葉を紡いだ。
『おそらくあの人は、わかっているのではないかな』
「……何を?」
『お前が自分の人生を、どうでもいいと思っていることが』
「え? どうでもよくはないよ? だって好きな人がいっぱいいるし。自分のことを大切にしましょうねって、ちゃんとキムが教育してくれたしね」
『では言葉を変えよう。全ての重荷をお前が背負うと、勝手に覚悟してしまったことを、怒っているのではないかな』
「…………」
今度の返答は予想外だった。
沈黙を保ち続けるジェフリーに、ヘンリーは言葉を続けた。
『ジェフ、私たちは確かに、高貴な存在に相応しいふるまいをするようにと、非常に時代がかった、ある意味で特殊な教育を受けてきた。それは悪いばかりではなかったと思う。だが、あの人はお前に守られたいとは思っていないのではないかな。たとえ過去、お前があの人にずっと守られていたように感じているからという理由があるとしても、その記憶と引き換えにするように、これからの全てをお前に任せて安穏と過ごしてゆきたいと考えるタイプとは、私は違うと思う』
ジェフリーは何も言えなかった。心の中の、一度も殴られたことのない場所を、優しく撫でられたような感覚だった。
ヘンリーは言葉を継いだ。
『ジェフ、時間をかけた方がいい。そういうことをお前は遂行しようとしている』
「……ハリー、マジで、電話してよかった」
『どういたしまして。これでもお前の不肖の兄だ』
「あっ、でもまだ許してないからね。諸々のこと。ずっと許さないよ」
『ああ……ありがとう、ジェフ。ではそろそろ切っても構わないかな。こちらは朝の四時だ』
「うわーごめん、時差のことを忘れてた。こっちはまだ夜の十一時」
『よい夜を、ジェフ』
「おやすみ、お兄ちゃん」
最後にヘンリーはくすりと笑い、そのまま回線を切った。
背中からベッドにぽーんと身を投げたジェフリーは、携帯端末を握ったまま手足をばたつかせ、あーっと呻いた後、意を決したように叫んだ。
「よーし、待ってろ、僕の愛しい人! 今すぐ重荷を背負わせに行くからね!」
【おわり】